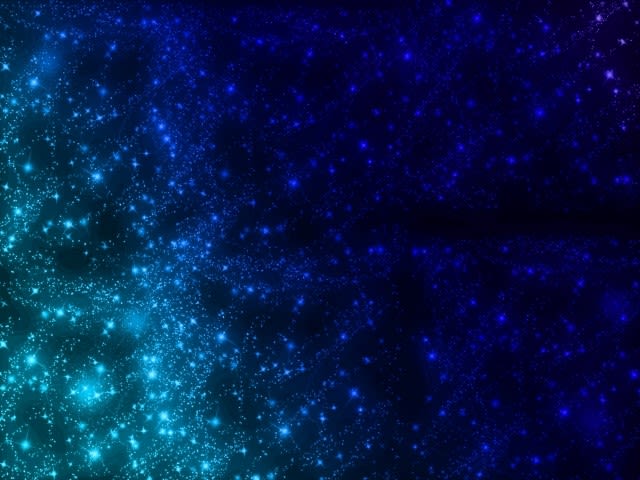1.
るりおが雪山に行ったまま帰ってこない。
道でばったり出会った中学時代の同級生から、そう聞いた。
「るりお」は、中学の時の同級生。
「下山の予定日をずいぶん過ぎても帰ってこないんだって。遭難したみたいよ」
るりおが、るりおが、帰ってこない? 遭難?…………ソウナン? なにそれ。
「そんな」
「おそらく死んじゃったんじゃない。ちょっと変わったやつだったけど、まさかこんなに早く死んじゃうなんてねえ」
「そんな」
同級生は、今から自分は仕事なので急ぐけれど今度ゆっくりみんなで集まろうよ、みたいなことを言って道路の向こうへ消えたようだけれど、わたしの頭はるりおでいっぱいになっていた。
「……そんなそんなそんなそんなそんなそんな」
その場に取り残されたわたしは、どんどん頭の中が真っ白になり、同じ言葉を馬鹿みたいに繰り返していた。
だってるりおが行方不明だなんて。
死んじゃったかもしれないなんて。
そんな……
だめだ。
同じことばかり、ぐるぐるして何も考えられない。
待てよ。
ええと、今からわたしはどこへ行って何をするところだったっけ。
それさえも、もうろうとして忘れかけ……
思い出してみよう。
確か大事なことだったはず。
そう、そう、そうだった。
就職の面接に行くところだったんだ。
え、でも、こんな状態で行けるわけがないじゃない。
普通の状態でも初対面の人とは、緊張してしどろもどろになってしまうわたしが、よりによってこんなときに、普段以上にきちんとしゃべれるわけがないじゃない。
就職はすごくしたいけれど、無理だ。
絶対無理だ。
るりおめ。
こんな大事なときに何てことになってるのよ。
ああ、
頭の中にどんどん雪が降り積もる。
るりおが降らせている。
雪山から帰ってこないるりおがわたしの頭の中を吹雪にしている。
こんなときはこんなときは、どうすればいい。
思い……つかないよ。
……
そうだ。
早く帰って……
寝よう。
それが、いい。
それしか、思いつかない。
2.
中学時代のことを思い出していた。眠りの中で。
ある冬の日の放課後の教室。
わたしはひとり、机につっぷして泣いていた。
悲しくてくやしくてたまらない。
いったい何がそんなに悲しいのだったっけ?
あまり泣きすぎると、涙の原因がどこかへとんでいってしまうのかしら。
ああ。
クラスの女ボスに目をつけられて、ほとんどの女子から「しかと」されているんだ、わたし。
こんなにくやしくて悲しいことなのに、思い出すのに時間がかかるなんて。
馬鹿じゃないの、わたし。
自分の馬鹿さかげんに、また涙。
でも、待てよ。
悲しいことばかりじゃなかったはず。
「しかと」を少しだけ忘れるくらいの何かがあったはず。
そうそう、そうよ。
るりお……
と、呼んでみると、胸がぎゅうっと痛んだ。
いたたた
「どこか痛いの?」
その声につっぷしていた顔をあげると、るりおが隣に座ってわたしを見ていた。
るりおだ。
なんだ。るりお、元気でいるんじゃない。
るりおは中学時代の、たったひとりと言っていい、わたしの「親友」。
男の子なのにどことなく少女っぽくもある優雅なしぐさと話し方のせいか、男子からも女子からも一歩引かれている、ちょっと、いや、かなり変わり者でとおっている、るりお。
口数は少ないわりにどこか気が強く見えるらしく、女ボスににらまれ、現在はぐれ一匹オオカミのわたし。
ういているふたりは気が合った。
るりおとわたしは、よくみんなが帰った後の放課後、話をした。
一緒にどこかへ遊びに行ったり、お互いの家を行き来するような間柄ではなかった。
ただ、放課後しばらくのあいだ一緒にすごして話をするだけなのだ。
るりおは聞き上手だった。
わたしの話をいつも丁寧に聞いてくれた。
わたしはるりおが相手だと、固くならずに話せた。
話す内容といっても、きのうのテレビ番組のことだとか、はやりの芸能人のことだとか、飼っている犬のことだとか、他愛のないことばかりなのだけれど。
でもあの暗い中学時代、るりおがいなかったら、わたしは、本気で自殺行為に及んでいたかもしれないと思う。
3.
「絵を描いたんだ。見てくれる?」
るりおは華奢な白い手を、大きな画材かばんにそっと入れて大事そうに絵を取り出した。
るりおは絵がとても上手だった。
描いた絵をよくわたしに見せてくれた。
パステル、水彩、油絵の具、何でも使いこなした。
画材はいろいろでも、るりおの書く絵は山の絵ばかり。
「また山の絵?」
「そうだよ。これは初夏の山。木々の緑がつやつやしてきれいでしょ」
「なんで山ばかり描くの」
「ふふふ……山にはなんと宝物が埋もれていました、とさ」
おとぎ話を語るような、るりおの言い方にわたしは笑った。
るりおも笑った。
どこから見ても少女のような、るりおの清廉な笑顔ばかりが、どんどんふくらんでいった。
どんどんどんどん、どんどんふくらみ……
そして、突然風船が割れるようにそれは、るりおの笑顔は、弾けた。
そして、消えた。
「るりお! るりお!」
わたしの呼び声がしんとした教室にこだまする。
陽は沈みかけ、あたりは群青色の夕闇に、ものすごいスピードで染まっていった。
窓の外を見ると群青色の空に雪がひらひらと舞っていた。
その向こうに、はるか、はるか、向こうに、雪を頂いた白い山が見えた。
悲しいじゃないの、るりお。
涙があふれてとまらなくなった。
目が覚めると、午後の遅い時間だった。
ずいぶんな時間、眠ってしまった。
涙でぐしょぐしょに濡れた頬をパジャマの袖でごしごしとぬぐう。
のろのろとからだを起こし、ベッドから、すぐ横のコタツへ、立ち上がることなく移動。
一人暮らしのワンルームの部屋はこれだから便利。
大学卒業後に四年間勤めた会社は、この春に倒産。社員は全員解雇された。
それからわたしは短いアルバイトで食いつなぎながら、ずっと職探しをしている。
実家に帰ればいいのだけれど、両親が一昨年離婚して、早速再婚した父親と新しい母親が住んでいる家には帰る気がしない。
4.
大きなあくびをひとつすると、また涙が頬をつたった。
からだがひどくだるくて、熱っぽい。
熱を測ってみると、三十九度近くあった。
レトルトのおかゆをお椀にあけ、レンジでチンして食べたあと、氷枕を頭の上にのせ、コタツに入ったまま、横になった。
また眠りの中で思い出していた。
中学校の卒業式。
体育館に整列した紺色の制服の集団の中に、るりおの姿はない。
式の一ヶ月前にるりおのお母さんが突然、事故で亡くなったのだった。
それからるりおはずっと欠席している。
るりおはお母さんと二人暮しだった。
一度だけ、参観日でるりおのお母さんを見たことがある。どこかはかなげで華奢なところは、るりおととてもよく似ていた。
きれいな人だった。
るりお、きっとものすごいショックを受けて落ち込んでいることだろう。
お葬式は、お母さんの実家のある、ここからずいぶん離れた町で行われたらしい。
高校受験の時期と重なったこともあって、クラスメイトは誰も出席していない。
るりおもずっとそっちへ行っている。
るりおが欠席の間、わたしはるりおと積極的に連絡をとろうとしなかった。
もし連絡がとれたとしても、わたしは何と言って、るりおをなぐさめていいのか……中学生でまだまだ子どものわたしには、わからなかった。
そのくせ、ものすごくるりおのことが気になってしかたなくて、とても会いたかった。
卒業式には会えると思っていたのに、るりおの姿がなくてがっかりした。
でもるりおとわたしは地元の同じ高校に進学の予定だったから、また高校でもたくさん会えるし、そのときゆっくり話せばいいと、楽観していた。
式が終わって、校庭で肩を抱き合って泣いているクラスメートの輪の外にぽつんと立っているわたしの背中に、冷たい手がふわっと当たった。
制服ごしでも、その手の冷え切った感触は感じられた。
るりおだった。
5.
「るりお……」
「まにあわなかった。卒業式にも」
「にも、って?」
「ママの臨終にも」
そう言って、るりおは長いまつげをふせた。
顔色がぬけるように白い。
わたしは消え入りそうなるりおの頬を両方の手のひらで覆った。
手と同様、その頬も氷のように冷たかった。
「冷たいよ。るりお」
「……るりおって、名前、ね、」
「名前?」
「ママがつけたんだ。るりおの『瑠璃』は、宝物のことなの、って、言ってた」
「へえ、いい名前だよね。とても」
校庭の真ん中で、校歌の大合唱が始まった。
「変な名前って、よくみんなにからかわれた」
「わたしは大好き」
わたしはスニーカーの先で、校庭の土の上に「瑠璃」と漢字で書こうとしたのだけれど……あれ?どんな字だっけ?好きだって言ったくせに書けないなんて情けない。きょううちに帰ったら、漢字字典で調べてみよう……なんて考えていると、るりおがわたしの手をとって、手のひらにその漢字を書いてくれた。
ありがたいけれど、画数が多過ぎて何が何だかわからないよ。そのことを言おうとしたら、るりおが先に口を開いた。
「ぼくは高校へ行かないことにした」
「え」
ということは、一緒に高校へ通えないってこと?
お別れってこと?
わたしの考えていることがわかったのか、るりおはうなずいた。
そしてここからとても遠い都会の地名をあげてそこで働くんだと言った。
この一ヶ月で、るりおはきっとわたしなど想像もできないくらい、深い悲しみの中にいたにちがいない。
そして、今も。
こんな重大な決心をさせるくらいの運命の力が今、るりおにふりかかっているんだ。
その証拠に、るりおは、ほら、こんなに、こんなに、白くて、冷たい。
るりおは、小さな声で何か歌っていた。
るりおが好きなジョン・レノンの曲「イマジン」だった。
るりおがときどき「イマジン」のチカラは凄いんだ、と言ってはくちずさんでいたから、わたしも曲のタイトルは知っていた。
「ジョン・レノン? しぶい」
「ママが好きだったんだ。かっこいいと言ってよ」
少しだけ、るりおの顔がゆるんだ。
三月には珍しい雪が、るりおの頭と肩に、さらさらと降りかかっていた。
「名ごり雪」
と、誰かが叫んだ。
6.
「イマジン」の曲が流れている。
待って。
もう少し、るりおと話していたい。
せっかく会えたのに。
また別れなきゃいけないの。
わたしはうつろな頭で重い身体を起こし、コタツの上に置いてある携帯電話に手を伸ばした。
携帯の着メロは、「イマジン」。
「もしもし」
「ええっと、突然で、失礼なんだけど、おたく、るりおくんの友達か彼女かな?」
「るりお」の名前を聞いて、水をかけられたように、一気に目が覚め、わたしは背筋を伸ばした。
「るりおが、るりおが、どうかしたんですか」
「るりおが雪山へ行ったまま行方不明なの、知ってる?」
「あ、はい」
「おれ、るりおが勤めていた店の店長なのね」
「そうなんですか」
「あ、店って、あれよ。まあそのつまり、ホストクラブね。るりおは美少年タイプだからね。けっこう人気だったのよ」
「はあ」
ホストクラブ。るりおだったら、それ、あり、かも。
「まあ、そんなことはともかく、るりおから、おたくに送るものがあるの」
「わ、わ、わたしにですか」
「そう。おたくに。るりおがなかなか帰って来ないから、マンションの管理人に事情を話して、彼の部屋へ入ったの。そうしたら「店長様」っておれあてに手紙が置いてあったわけ。それには、自分がもし、山へ行ったまま、一ヶ月以上も帰ってこなかったら」
「か、か、か、帰ってこなかったら……」
「荷物をおたくに送ってくれって書いてあったのね。荷物ったって、まあ、ほんの身の回りのものだからたいしたことはないんだけどさ」
「ええっと、荷物って、誰の荷物ですか」
「るりおの荷物に決まってるでしょうよ。荷物は几帳面に整理してあったよ。まるで覚悟して出かけたみたいにきれいな部屋だったな。そう、部屋の契約も解約してくれって書いてあったから解約の手続きも済ませたの。そういうわけで荷物も行き場がなくて困ってるのよ」
「はあ……」
「ここに送ってくれって、手紙におたくの電話番号と住所が書いてあったの。で、いきなり送るのもあれだから電話をかけたら女の人が出て、ここは実家だけどあの子は出て行ってもういないし帰る予定もないからって、携帯の電話番号を教えてくれたのね」
るりおとは卒業式以来、会っていなくて、わたしの携帯の番号を知るはずはないから、るりおは、わたしの実家の電話番号を店長に教えたんだ。
父の再婚相手、義母が電話に出たらしい。
7.
「まあ、そういうことだから、おたくの住所、教えてくれるかな? おれ、頼まれたことはきちんとやりたい人なの。それに死んでるかもしれないるりおの最後の願いだよ。叶えてやりたいじゃない」
「あ、はい」
わたしは店長に住所を教えて、電話を切った。
なぜ、なぜ、わたし?
荷物?
荷物って何。
わからない。
何もわからない。
るりおとは何年も会っていないのに。
なぜわたしに……
やめた。
頭ががんがんしてきた。
考えるのは後にしよう。
熱はまだ下がらない。
とりあえず、ヨーグルトを口に入れて、風邪薬を飲み、ベッドにもぐりこんだ。
るりおが「イマジン」を歌っているところから、眠りの中の、るりおは始まった。
どこだろう?
るりおがいるところはどこなのだろう。
るりおは透明な壁に囲まれた部屋で透明な椅子に座っていた。
天井からは青紫色の明かりがぶら下がっている。
るりおは透明なクレヨンを手に、「イマジン」をハミングしながら、透明なスケッチブックに絵を描いていた。
きっと山の絵を描いているにちがいない。
雪山の絵なのかな。
それとも……
宝が埋もれている緑の生い茂った山の絵なのかな。
それにしても、余計なお世話だけど、透明なクレヨンで絵なんて描けるのかな。
ねえ、どこにいるの、るりお。
8.
店長の仕事は早かった。
次の日にはもうその荷物とやらが届いた。
たいしたことはないといっていたわりには、大きな段ボール箱が五個もあった。
段ボール箱は、せまい部屋のほとんどのスペースを占拠してしまった。
まったく、るりおのやつ、なに考えてんだ。
これって全部わたしあてだから、あけていいんだよね。
「あけるよ。るりお」
きょうも熱は下がらなくて、頭も痛くてからだもふらふらするけれど、こんな気になるものが目の前にどかんとあったんじゃ、中身をさっさと確かめないことには、落ち着けない。
ガムテープをばりばりとはがしながら、わたしの心臓は高鳴っていた。
中学のとき以来、会っていない(眠りの中でしか会えなかった)るりおの存在が、急に近くに感じられた。
段ボールの中身は、と言えば……
五個のうち三個は、スケッチブックとキャンバス。ざっと見たところ、やはり、というか、すべて山の絵。
一個は画材道具。油絵の具とか、水彩絵の具とか、パステルとか、筆とか、パレットとか、そういったもの。
残る一個は、洗面道具とか着替えとか貯金通帳とか、いわゆる日常的な身の回りのもの。
これって、どういうこと?
わたしは熱のある頭を思いっきりひねった。
頭を冷やして考えてみようと、氷枕をタオルで頭に固定させた。
可能性としては、るりおはこれを「形見」としてわたしに託したことが考えられる。
理由は中学時代の親友だったわたしのことを今でも信頼できる友人だと思ってくれているから。
形見、ということは、るりおは「死」を覚悟していた?
覚悟したみたいにきれいな部屋だった、と店長は言っていた。
ということは、考えたくないけれど、自殺の可能性もある。
自ら命を絶ったのだろうか?
それとも、いつなんどきふりかかるかわからない遭難事故を想定していたという意味の覚悟なのだろうか?
でも、それならば、着替えのパンツやパジャマや歯ブラシまでが詰まっている、日用品の箱はどう説明するのだ?
ちなみに貯金通帳の残高は極めて少額でお話にならない。
約一ヶ月前にほとんど引き出された記録がある。
「形見」とするならば、そんな日用品グッズをわざわざ送ってくるだろうか。
9.
形見というものは……(今までにもらったことはないけれど)常識的に言って、普通、友人に送る形見としては、この山の絵がせいぜい一、二枚、が妥当な線ではないだろうか。
でも変わり者のるりおのことだから、これらを形見として送ってくることも、考えられないことはない。
るりおの手紙でも入っていないかと、箱の四隅までまんべんなく探したけれど、そんなものは出てこなかった。
もしも、自殺したのなら、遺書くらいはあってよさそうなものを。
だから、自殺の可能性は低い?
いやいや、遺書のない自殺だってあり得るからして、それは何とも言えない。
わたしの頭は爆発しそうだ。
るりおが描いた山の絵をいくつか、箱から取り出して壁に立てかけてみた。
そびえ立つ山々の絵。
雪をかぶっているものもあれば、夕焼けに染まっているものもあり、夜の山なのか、闇の中に濃い紺色のシルエットが浮かび上がったものもある。
美しい。
るりおが本気で描いたのがわかる。
るりおの山の絵はずっと欲しかった。
一度、ちょうだいって頼んだことがある。
そうしたらるりおは「死んだら価値が上がるから形見にあげるよ」って冗談めかして言っていたことがあったっけ。
でもじっくり鑑賞するのはもう少し後にする。
お腹も空いてきたし、からだもだるい。
カップラーメンを食べて、風邪薬を飲んで、またベッドにもぐりこんだ。
「イマジン」の着メロが鳴った。
携帯電話を手に取ると、見覚えのない電話番号が表示されている。
「もしもし」
「もしもし、ぼく、るりおだけど」
「ええええー!」
「そんなに驚かなくても」
「どどど、どうしてこの番号、知ってるの」
10.
「店長に聞いた」
「あ、そうか」
「元気?」
「元気?じゃないよ。るりお、今いったいどこにいるのよ」
「ふふふ。秘密」
「教えなさい。あんたの荷物まで預かってんのよ」
「そうだね。ぼくの荷物、届いたんだ。ありがとう。受け取ってくれて」
「何よ、あれ。形見の品なの」
「ふふふ。どう思う」
「茶化さないで。どこにいるかだけでも教えてよ」
「そうだね。ぼくたち、離れていたけれど、ずっと親友だった」
「だから、どこ?」
「ヒント。その山には宝物がありましたとさ」
「わかった。宝の山だ。埋蔵金でも見つけるつもり」
「埋蔵金もいいけど、ぼくが探しているのは瑠璃」
「瑠璃?」
「瑠璃を見つけたら帰るよ」
「夢みたいなこと言わないで。瑠璃とやらを見つけたら、帰ってくるの?」
「うん。帰るよ。真っ先に、そこへ。だから荷物、預かっていて。ぼく、他に身寄りもないし」
そうか。るりおは「身寄りがない」のか。
だから、昔の親友のわたしなんかのところに荷物を預けたのか。
「わかったわ」
るりおは早口で何か言った。そのあと電話がぷつんと切れた。
最後の言葉、よく聞き取れなかったけれど、とにかくわかったよ、るりお。
るりおは帰る。きっと帰ってくる。
それまで、段ボール箱五個、確かに預かりましょう。
夢だ夢だ、これは夢に違いないと思ったら、やっぱり夢だった。
るりおから電話なんてあるはずがない。
もしかして、万が一、わたしがねぼけているのかも、と思って携帯電話の着信記録を見てみたけれど、今日は一件たりとも、どこからも電話はかかってない。
目が覚めると、わたしはるりおが描いた絵と段ボール箱に囲まれていた。
無性に悲しくなってきた。
るりお。
残酷だよ。
わたしの部屋に、こんなにるりおのにおいをまき散らしておいて、存在を匂わせておいて、行方が知れないなんて。生死さえも知れないなんて。
残酷すぎるよ。
11.
一日中、何もしないで、寝ているだけの日々を続けた。
るりおが行方不明、ということを知って、もう何日になるだろう。
るりおの荷物が届いて、何日になるだろう。
熱は微熱が続き、咳が止まらない。
このままだと死ぬ、と思って、とうとう実家に助けを求めた。
義母と父親がそろってわたしの部屋を訪ねてきた。
家族に、いや、ナマ身の人間に会うのは何日ぶりだろう。
父親の車でわたしは病院へ連れて行かれ、診察を受けた。
肺炎を起こしかけていると医者に言われた。
危ないところだった。
山ほど薬をもらい、部屋に帰ると、義母が掃除と洗濯をしておいてくれていた。
せまい室内に段ボールが五個も転がっているので、さぞかし掃除がしにくかったことだろう。
「この箱はなんだ。引越しでもするのか」
と、父親に聞かれたけれど、「まあ」と言葉を濁して、こぎれいになった部屋を見回した。
「素敵な山の絵ね」
父親の横で、いごごちが悪そうにしていた義母が絵に目を留めた。
「この前、あなたに男の人から電話があったのよ。携帯の番号を教えたのだけど、よかったかしら」
よかったかしらって、もう教えたあとに言われても。まあ別によかったんだけど。
と、そんなふうには義母には言えないから、「まあ…」と曖昧に返事をした。
「この段ボール箱は、あの電話の人が言っていた荷物ね」
そう、なかなかするどい。
わたしは「少し寝るから」と、ベッドにもぐりこんだ。
「たまには帰ってこいよ。就職のこととか、よくなったら話そう」
「そうよ。いつでも帰っていらっしゃい。あなたの家なんだから」
ふたりは、せまい部屋に降参したように、帰っていった。
当座の生活費を少々置いていってくれたから、情けないけれど、助かった。
12.
眠った。
わたしの夢はるりおでできているのだろうか。
夢で会える。
夢でしか会えない。
わたしとるりおは夢でできているのだろうか。
放課後の教室。
机につっぷして泣いているわたしの肩に手を置いたのはるりお。
るりおはわたしの手を取って、
「行こう」
と言った。
顔をあげたら、卒業式が終わった後の校庭にふたり、立っていた。
ずいぶん前に式は終わったようだ。
あたりは薄暗く、誰もいない。
雪が降っている。
雪はるりおに降り積もる。
雪はわたしに降り積もる。
紺色の制服が白く染まっていく。
「ぼくは瑠璃を探しに雪山へ行く」
「行っちゃうの?帰ってこないの」
るりおは返事をしない。
「返事をして、るりお。るりおが言っている瑠璃ってなに。宝物ってなに。なんで山ばかり描くの。なんで山に行ったの。なんでわたしのところに荷物を送ってきたの」
るりおは黙ったまま、空を仰いでいる。
答える気がないのか、わたしの声が聞こえていないのか。
るりおは黙って、紫がかった瑠璃色の空を見上げている。
空からはとめどなく雪が舞い落ちている。
るりおは瑠璃の空を見上げて、「イマジン」を歌い出した。
そうか。
このまえ聞き取れなかった電話の最後のフレーズはイマジンの歌詞の一節だったと気づいた。
「電話をかけて。きっとよ。実家じゃなくてこっちに」
わたしはるりおに携帯電話の番号を教えた。
るりおは、まだ歌っていた。
……may say I’m a dreame……
雪は、るりおとわたしにずんずん降り積もっていく。
校庭を埋め尽くし、町を埋め尽くし、山を埋め尽くし、やがて世界を埋め尽くしていった。
13.
駅で帰りの電車を待っていると、胸のポケットで、携帯電話がぶるぶると震えた。
肺炎を起こしかけて死んだ熊のように冬眠していたのは三ヶ月前。
あれからようやく体調を取り戻し、父親のコネでわたしは何とか就職できた。
つくだ煮を作っている小さな食品会社の事務の仕事だ。
季節は変わり、春が来た。
これもまたいやな季節なのだ。
電話をポケットから出そうとすると、くしゃみが三回続けて出た。
鼻水をずるずるとすすりながら、画面を見ると、見知らぬ番号。
「はい、もしもし」
「もしもし?」
若い男の声。
誰だ。会社の上司や同僚はみなおっさんだし、若い男からかかるあてなどはない。
「どなたですか」
「忘れた? ぼくの声」
「ええええー!」
「そんなに驚かなくても」
る、る、る、るりおだ。
るりおの声だ。
驚きすぎて鼻水がずずっと出てきた。
夢だ。夢だ。これはきっと夢だ。夢に違いない。
確かこんな夢を前にもみたような。
ええと、こんな場合、平凡だけどほっぺをつねるんだっけ。ああ、でも片手は電話、片手はバッグを持っていて、どこもつねられない。ど、どうしよう。
「どどどど、どうしてこの番号を知ってるの。店長さんに聞いたの」
「実家に電話したら、教えてくれた」
またもや義母が無断で教えたのだな。
「るりお、生きてたんだね。まさか幽霊じゃないよね」
「ぼくは死んだことになってるのかな」
るりおがのんびりした声を出した。
「そりゃ思うわよ。雪山へ行ったまま帰って来ないんじゃ、誰だってそう思うでしょう」
「ごめん。いろいろあったんだ。で、荷物、そっちに行っているのかなあ」
そう、荷物。わたしは三ヶ月間もの間、るりおの「形見」とおぼしき五つの段ボール箱に囲まれて暮らしているのだ。
「確かに預かっておりますわよ」
わたしをこんな気持ちにした恨みをこめて、冷たく言い放つ。
「あれ、怒ってる?」
こいつめ。
「怒ってる? じゃないよ」
お詫びに、得意な「イマジン」を今、電話口でフルコーラスで歌うぐらいのサービス、しなさい、とそれは言わなかったけれど。
「会おう」
「え、会うの?」
14.
「荷物のこともあるし」
ああ、荷物ね。
わたしじゃなくて、気になるのは荷物、ね。
それでもるりおに会えるなんて、それって、いつもみている夢みたいで、にわかには信じがたい。
疑い深いわたしはバッグを下に下ろし、あいた手で、慎重に自分のわき腹をつねった。
くすぐったい。
そのショックでまたくしゃみが出た。
二時間後、るりおはわたしのワンルームマンションの部屋にいた。
こんなことなら、片付けておくのだった。
いつもはひとりがようやく座れるくらいの空きスペースしかないところを、無理やり押し広げて、ふたりで一人用のコタツ兼テーブルを囲んだ。
色白で華奢なつくりの、るりおの顔立ちは昔とほとんど変わっていなかった。
これならじゅうぶんホストクラブで稼げるわ、と思った。
るりおは上品な光沢のある生地の群青色の細身のシャツをさらりと着こなし、ボトムはうすいベージュのスリムなカラージーンズをはいていた。さすがホスト。自分の体形に似合う着こなしがわかっていらっしゃる。
店長さんが、るりおはけっこう人気だったと言っていたのがわかる。
変わったのは中学時代よりも背が伸びていることくらい。
あのころは同じくらいの背丈だったのになあ……
「何。ほんとに怒っているの」
黙って遠くを見たまま回想にふけるわたしの表情は、怒っているように見えたらしい。
「……まあね」
怒っていることにしておこう。
だって、ものすごく心配したのだから、少しくらい怒った顔をしてもいい。
「悪い。この荷物。部屋をますますせまくしているね」
「どういたしまして。わたしあてだから、勝手にあけさせてもらいました」
「あ、これ」
るりおは壁にかけてある絵が自分の描いた山の絵を指さした。
「勝手に飾ったから。なんせ、わたしあてだもの。全部もらえるんでしょ。るりおの形見なんでしょ」
るりおは答えないで首をかしげて苦笑した。
「雪山へ登ったのはなんで?」
「う~ん」
るりおは腕組みをし、下を向いた。
「違うの? 瑠璃を探していたんじゃないの」
「瑠璃って?」
「宝のことよ。瑠璃を見つけたら帰るって……」
わたしのところへ真っ先に帰るって……というセリフはのみこんだ。
「なにそれ。夢でもみたの」
ビンゴ。
瑠璃のことは、夢だった。
夢でるりおが言っていたことだった。
15.
「そう夢をみていたの。るりおが行方不明って聞いて、よくるりおの夢みてた」
正確には「よく」ではなくて、「いつも」だけれど。
るりおはすまなさそうな顔をして、頭を下げた。
おでこがこたつのテーブルにごつんと当たった。
「ごめん。雪山なんか登らなかった」
「うそ」
「ほんと。店長にうそを言って姿をくらました。思わせぶりに荷物も整理して。」
「なんでそんな」
「常連客の中にものすごい過激なストーカーがいて、殺されそうになった」
「はあ?」
「それで、逃げた。ぼくはもういない、死んだ、と思わせたかった。身の回りのものは全部処分しよう思ったんだけど、どうしても捨てきれないものだけ、ここに送ってもらったんだ。ここなら、ぜったいアシがつかないと思って」
ストーカーから逃げた、ですって?
死んだと思わせたかった、ですって?
最近付き合いのないわたしのところなら、ストーカーにばれないと思ったのね。
全身から力が抜けた。
鼻がむずむずしてきた。
「くしゅんくしゅんくしゅん」
くしゃみをすると、るりおがわたしのおでこに手を当てて「熱がある」と騒いだ。
まったく、誰のせいで熱が出てきた思ってんのよ。
今度は本当に腹が立ってきた。
「だいたいぼくが山登りしそうに見えるかな?」
鍋物の材料を手際よく切りながら、るりおが言った。
るりおがお詫びに鍋物を作るというから、「好きにしなさい」と、わたしは背を向けてテレビに見入っていた。
その間にるりおは、近所のスーパーで買い物をして材料をそろえ、料理を始めた。
「体力とかなさそうだから全然見えない。でも山を描くのが好きだから、本物の山にも登ったりするのかなって」
振り返ってみると、るりおは勝手にわたしのエプロンを身につけていた。
赤いタータンチェックのエプロンがわたしよりも良く似合う。
「ぼくが描く山は全部、イメージ。イメージの中にある山。写生はしない」
「へえ、イメージであれだけ描けるんだ」
「イメージの力は侮れないよ。ストーカーだって相手へのイメージを膨らませ過ぎちゃっておかしくなるんだ。きっと」
「こわい目にあった?」
「そりゃこわいさ。どこへいても何をしていても、おっかけてくるんだ。見ているんだ。ぼくの行動をすべて。電話だってひっきりなしにかかるから、何度番号をかえたかわからない」
「警察には言わなかったの」
「言おうと思ったけど、店のお得意さんだし、金払いのいい客だから、店は大事にしているんだ。だからことを荒立てるのも店長に悪いと思って、ぼくが姿をくらませばいいんじゃないかと……はい、できました」
16.
湯気の上がった土鍋がテーブルに運ばれてきた。
部屋中がもうもうと上がる白い湯気に包まれた。
最近冷蔵庫に常備している、社員割引で手に入れた最高級昆布のつくだ煮もテーブルにのせた。
「最高なんだから。このつくだ煮」
「うん、たしかにうまい」
誰かと一緒に夕食を食べるなんて、いつ以来だろう。
湯気のあがる夕食も久しぶりだ。
目が覚めると、夢、ってことは、まさか、ないよね?
さむ。
こたつに入ったまま、眠っていたようだ。
春とはいえ、朝方はやはり冬並みに冷える。
そうだ、るりお、るりおは? どこ? るりお?
せまい部屋をぐるり見回しても、人の気配はない。
きのうふたりで食べたあとの鍋と食器は片付けられ、流しできれいに洗われていた。
空いたビールの缶が、流しの下に数本、きちんと並べられている。
るりおの作った鍋物と、最高級の昆布のつくだ煮がおいし過ぎて、ついつい、飲み過ぎてしまった。
お酒にあまり強くないわたしは、つぶれて寝てしまったらしい。
夢もみないくらいに熟睡してしまった。
わたしが寝たあと、るりおが几帳面にこれらを片付けて、それから、出て行った?
出て行ったって、どこへ?
「しまった。今どこに住んでいるのか、住所と連絡先、聞くの、忘れた」
わたしは自分の後頭部を後ろの壁に打ちつけた。
いったい、るりお、何だったのよ。
何しに来たのだ。わたしのところへ。
もしかしてわたし、また夢をみていたのかなあ……
でもこうして洗われた食器もある。
ふたりで飲んだ缶ビールもある。
物的証拠がある。
これは夢じゃない。
わたしは霞がかかったような頭をはっきりさせようと、シャワー室に入った。
シャワー室は濡れていて、誰かが使ったあとがあった。
「あ」
わたしは冷たい床にへばりついた。
「みつけた」
るりおの茶色い髪の毛が落ちていた。
やつめ。
ちゃっかりシャワーまで浴びていくなんて。
段ボール箱の中に、ちゃんと自分の着替えまで入れていただけのことはある。
証拠の髪の毛にしばらく見入る。
「どこ行ったのよ、るりお」
わたしはシャワー室でひとり静かに怒り、熱い湯を浴びて出た。
濡れたからだをふいて着替えたあと、携帯電話の着信記録に残っていた、るりおがかけてきた電話番号にかけてみた。
「はい、もしもし?」
え、女。
女の人の声。
反射的に切った。
なに、これってどういうことよ。
もう二度とかけるものですか。
17.
やはり、というか、るりおからその後も連絡はなかった。
もしかして、るりおがもどってくるかもしれないと、待つ女になるのなんてすごくあほらしいから、わたしはるりおのことなど、忘れることに努めることにした。
雪山のことが嘘だったなんて、荷物だけ一方的に送りつけてくるなんて、中途半端に姿を見せてすぐに消えてしまうなんて、人を馬鹿にするのにもほどがある。
その上、女の電話を借りてわたしに電話をかけてくるなんて。
わたしだったら許すと思っていたのなら、大間違いだわよ。
わたしはるりおの段ボール箱を、再びガムテープでぐるぐる巻いて固く封印した。
でもそれは心のどこかで、るりおがまたここへもどってくると信じていたから。
もどってきたとき、ぐるぐる巻きの段ボール箱を見せて、ほらこんなに怒っていたんだからね、と言ってぷりぷりして見せたあと、るりおの嘘か本当かわからない言いわけを聞き、またふたりで鍋物やつくだ煮を食べられると思っていたから。
だからるりおが、死んだという知らせを聞いてもすぐには信じられなかった。
会社の昼休み、つくだ煮を煮るにおいのする会社の中庭のベンチに座り、わたしはランチのおむすびを食べていた。
秋の小春日和。青空とさわやかな陽気が気持ちいい。
ベンチに置いた携帯電話が「イマジン」のメロディーを奏でた。
見覚えのある番号?
「もしもし」
「もしもし、わたし、あの、るりおさんの」
女の声。
忘れもしない。
やけにしっかりしたこの声は、るりおがうちへ来て、帰っていった朝に、わたしがかけた電話で聞いた声。
「るりおが何か」
なんで女から電話があるのよ、とわたしは少々つっけんどんに答えた。
「るりおさんが入院していた病院で看護師をしているものなんです」
「え、どういうことですか? るりおが入院って……?」
どういうことなのだ。
「それであなたに預かり物が」
まただ。
「何ですか。段ボール箱か何か?」
「いえ、お手紙なんです」
「手紙?」
18.
「はい。るりおさん、一ヶ月前に亡くなられて、それで、ぼくが死んで一ヶ月たったら、ここへ手紙を送ってほしいと預かっていまして」
「……」
声が出なかった。
一ヶ月前に、シンダ? 死んだ?
ですって?
またまた。
荷物のときもそうだった。
同じじゃない。
一ヶ月たったら、これを送ってくれって、近くにいる人に頼むの、るりおの手口。
きっとそうよ。そうに決まっている。
「もしもし、だいじょうぶですか? 聞いていらっしゃいます?」
「……はい」
答えた自分の声が、予想外にかすれていた。
のどがひりひりしてきた。
電話を持つ手が震えている。
震えを止めようと、もう一方の手で、電話を持つ手を押さえたら、おにぎりが足もとに転がり落ちた。
おにぎりを持っていたこと、忘れていた。
「それで、急にそちらにそれを送りましても、驚かれると思いまして」
「……そうですね」
電話にしても手紙にしてもどっちにしても、驚くに決まっている。
「じゃあ、これ送りますから」
「あ、あの、本当なんですか? 本当だったら、るりおはどうして、あの、な、な、亡くなったんですか」
「亡くなった」と言った部分がまたかすれた。
言葉に出してみると、本当にるりおが亡くなった気がした。
「癌で。末期でしたから手術しても助かる見込みはずいぶん低かったせいもありますが、手術は嫌がられていまして。いろんな延命治療がありますが、人間らしく死にたいというご本人の希望で、痛み止めと精神的なケアを中心にさせていただきました。身寄りがないとかで、最期は看護師のわたしと主治医が看取ったんです。眠るように逝かれました」
とてもまじめでしっかり者の看護師さんらしい。
わたしをいたわるような口調だった。
ごめんなさい。
るりおの女だと、一方的に勘違いして、つっけんどんな声出してごめんなさい。
電話を切っても、震えは体中に広がるばかりで、止まらなかった。
病気だったなんて……
わたし……何も気づかなかった。
会社の建物の中から、誰かがわたしを呼ぶ声がした。
昼休みはとっくに終わっていた。
晴れた空は、さっきまでは、明るい青だった。
が、今のわたしの目には、色など映らなかった。
またたく間に、すべてが灰をかぶったような景色になった。
頭の上に浮かぶ、今の今まで白かった雲は、その白さを失い、風に流れ始めた。
流されて西へ西へと走っていき、視界から消えていった。
19.
三日後、手紙が届いた。
晩秋の朝。
雪でも降りそうなくらい冷え込む朝だ。
土曜日だったので、会社は休み。
るりおと鍋を囲んだこたつにまるまり、震える手で、手紙を開いた。
20.
「きみがこの手紙を受け取るころには、ぼくはこの世にいないんだろうな。
なんて文章に書いてみて、すごく寂しくなった。
この前はごめん。黙って帰っちゃって。
あんまりよく寝ていたから、何だか起こすのが悪くて。
寝顔見てたら、むかし授業中、きみがよく居眠りしていたの、思い出した。
いつも、つついても起きないくらい、爆睡してんの。
わき腹とか背中とかよくつついたんだけどなあ。
よっぽどいい夢見てたんだね。
目覚めたくないくらいいい夢みてるんだなあと、きみの寝顔見て、この前もそう思った。
それから、嘘ついてごめん。
雪山のこともだけど、ストーカーのこともうそ。
もう中学生じゃないんだから、少しは人を疑いなさい。
だまされやすいその性格、何とかしないと、いまに悪い人にだまされてひどい目にあうよ。
病院に入るなんて言うと、みんなにかわいそがられて大騒ぎされるに決まってるから、雪山へ行ったことにしようなんて、つい、浅はかなことを思いついた。
で、かっこよくみんなの前から姿を消そうと思ったわけ。
かっこよく消えたかった、んだけど、でも、ぼくも生身の人間、未練とかわいてきちゃって。
まだからだがちゃんと動くうちに、誰かに会いたかった。
病院に入ったらきっとその気持ちが強くなるのだろうなと予想してたら、予想通り。
弱いの。ぼく。
あのころが、あの中学時代がぼくの中でいちばん楽しい時代だった。
きみなら荷物を受け取ってくれると思った。
そうきみの言ったとおり、ずばり形見だよ。あの荷物。
病院へ入る前、荷物を整理しながら、ぼくが死んだら、ぼくはもちろんこの荷物たちも消えてしまうのかなあって、とてもとても寂しくなった。
きみのところへ送りつけたのは、はっきり言ってこの世への未練。
ぼくのことを覚えておいて欲しいという身勝手な未練だよ。
それで店長さんに頼んだ。
さいしょから部屋も荷物も消したんじゃ、雪山のうそがさっそくばれるでしょ。
店長さんはいい人だから、だますのは心苦しかったけれど。
きみは山の絵、すごく欲しがっていたし。
ぼくが死んだら、自動的に形見になるからね。
大事にするように。
ずうずうしいけど、ぼくのこと、好きなんじゃないかと、ずっとうぬぼれもあったんだけど、ちがうかな。
ぼくはきみのこと、大好きだったよ。
でもそんなむかしむかしの中学生のころのことなんてね。
だいたいきみがぼくのことを覚えているかしら、という疑いも少しあったんだ。
けれど、きみの性格上、はたちすぎても、根性はそのままだと信じてた。
会えてよかった。
思っていたとおり。
きみはきみのままだった。
きみのナイーブで、そのくせ頑固なところ、変わっていなかった。
あんまり長いこといっしょにいるとぼろがでそうだから、早々に退散したんだ。
弱ったすがたは、現役美少年系のぼくとしては見せたくなかったから。
元気なぼくを覚えておいてほしかったから。
さっき、大事にするように、なんて書いたけれど、本当は荷物、強引に送りつけて悪かったと思ってる。
じゃまなら捨ててくれていい。
きみにカレシができたとき、男物のグッズが部屋にあったんじゃ、まじでシャレにならないでしょう。
きみがぼくの夢をみたと言ってくれて、もうそれでぼくは十分なような気がした。
だから、ぼくの身勝手な未練や形見は捨ててください。
あの日、きみが言っていたことが病院に帰ってから、ずっと頭の中をぐるぐるしてた。
「瑠璃を探していたんじゃないの」って。
それで子どものころ(今考えるとばかみたいだけど)、山に宝物があると思いこんでいたことを思い出した。
今も、それが、信じられるような気がしてきた。
きみに会ってそんな気がしてきた。
ぼくは瑠璃を探しに山にいってきます。
……なんてセリフを最期の言葉にしたかったんだけれど、
もしかしてぼくはもう瑠璃を見つけているのかもしれない、
と、今気づいた。なーに言ってんの、なんてつっこむなよ。
ぼくの母が言っていたように、宝物のことを「瑠璃」と言うのなら、ぼくの瑠璃はきみだったのかもしれない。
というわけで、眠るのが得意なきみの夢にぼくは時々出かけていくつもりだから。
きみもぼくに会いたくなったら、イメージのチカラでぜひ会いに来てください。
続きはそのときに。
じゃあ、いつかまた
るりおより」
21.
な、な、なにが「じゃあいつかまた」よ。
死んじゃったくせに。
さんざん、わたしに嘘ついて、ふりまわしたくせに。
いないから、反論もつっこみもできないじゃない。
自分勝手に「形見」だけでなく「遺書」なんて送りつけてきて。
瑠璃を見つけに行くなんて、ほかでぜったい言わないのよ。
なにあほな夢みたいなこと言ってんの、って冷たい目でみられるから。
でも、でもね、もしかしたら……もしかしたらだけど、これも大嘘で、どこかからまたひょこり、るりおは現れるかもしれない。
ごめん、嘘だった、なんてね。
中学生じゃないんだから、もっと人を疑えって、るりおもここに書いているじゃない。
何が嘘で何が本当なのかなんて……
嘘も本当も、どっちもあやふや。紙一重。
見方ひとつで、百八十度変わる。
嘘が本当になり、本当が嘘になり。
確かなことなんて、山の中の瑠璃を探すようなもので……
確かを求めて考えていると、あやふやにはまってしまい、不確かに打ち砕かれるから……
涙も鼻水も止まらない。
頭もしくしく痛む。
こんなときは
こんなときは
そう、
眠るのがいい。
夢をみて、夢を見続けて、不確かが確かであることを確かめよう。
イメージの力で。
侮れないイメージの力で。
夢から覚めたあとも、不確かな現実に押しつぶされないように。
窓の外には、いつ降り始めたのか、雪。
……I’m a dreamer.
積もらない雪が眠りの中に白く舞い続けていく。
ねえ、るりお。
今から、会いにいくね。
返事、して。
「君は僕のことを夢想家だと言うだろう」fin.