
さて、第七章の紙面も残り少なくなってきたので、ラストに、80年代の青年向け赤塚ギャグを代表するこの作品を論及しつつ、本章を総括することにしたい。
「平凡パンチ」に連載された『松尾馬蕉』(83年4月4日号~10月3日号)は、キャロル・リード監督の代表作『第三の男』に発想の原点を求めた、ギャグとサスペンスが渾然一体となった不条理ナンセンスで、主人公が一度も顔を出さずに、ドラマが完結するという、通常の漫画のセオリーのみならず、従来の赤塚漫画のスタイルからも完全に乖離した異端作の一本だ。
大学をこの春卒業した小林一茶青年は、先輩の松尾馬蕉から、事業拡張に向け、協力を仰ぎたいとの旨を綴った手紙をもらい、上京する。
一茶は、早速馬蕉のアパートを訪れるが、部屋に馬蕉の姿はなく、そこにはただ、一台のモーターボートが所狭しと置き去りにされていた。
ボートともに残されていた手紙には、「わけあって対馬へ行く このボートで大島旅館へ来い」と書かれており、一茶はボートに乗り込み、対馬へと向かう。
だが、投宿している筈の大島旅館にも、馬蕉はおらず、主人のエイハブの話では、一茶が着いたその前日に、北海道屈斜路湖畔のホテル〝コタン〟へ向かったというのだ。
やっと思いで、ホテル〝コタン〟に辿り着く一茶だったが、ここにも馬蕉はいなった。
だが、フロントの話では、馬蕉は三年も前から〝コタン〟に滞在し、昨日チェックアウトしたばかりだという。
そして、今度は沖縄に来るようにと書かれた俳句もどきのメッセージが、やはり一茶に宛てて、残されていた。
一体、馬蕉は何が目的で、ここまで一茶を振り回すのか……。
この物語のポイントは、毎回、一茶が訪れる先々で、馬蕉の奇っ怪な人物像が浮かび上がってくる点にある。
対馬では、大島旅館の主人・エイハブが白鯨に襲われ、片足を喰いちぎられた時、命からがら助け出し、英雄視されていたかと思えば、突然、テレビのニュース中継に現れ、日本人初の搭乗員として、スペースシャトルに乗り込む姿が報じられたりと、そのベールは二重三重にと連なってゆく。
挙げ句の果てには、その姿形までもが、様々な変貌を遂げ、手の指が八本になったり、尻に尻尾が生えていたりと、生物学上、その正体すらも断定不可能となる有り様で、益々一茶を混乱させてゆくのだ。
連載中盤では、馬蕉の顔を読者から募集したり、突如、本編に出てきたと思ったら、顔が巨大な○印になっていたりと、何処までも読者を煙に巻く悪戯が、ギャグとして描かれるようになる。
つまり、読者に主人公のイメージを喚起させるという試験的なギャグがテーマとなっているのだが、そのテーマも、恐らく見切り発車のまま打ち立てられたものであるため、消化不良の印象は否めず、終盤、矢継ぎ早の展開は、更に箍が外れたかの如く、破綻の一途を辿ってゆく……。
因みに、アイデアブレーンを務めていた長谷邦夫の話によれば、「平凡パンチ」編集部より、連載のオファーを受け、主人公が一回も顔を出さないが、でもやはり主人公であるという漫画を描けないものかと考えていた赤塚に対し、長谷は、それならば、サミュエル・べケットの『ゴドーを待ちながら』のような不条理なシチュエーションが、赤塚が抱いている構想に、最も適しているのではないかと提案したそうな。
即ち、『ゴドーを待ちながら』では、劇中、ウラディミールとエストラゴンの二人が、ゴドーという謎の人物を待ち続けることに対し、この『松尾馬蕉』は、小林一茶が謎の人物・松尾馬蕉を、ひたすら追い続けるという、逆転の発想によって生まれたシリーズと言えるだろう。
ただ、赤塚自身、新機軸を打ち立てようと、意欲的に取り組んだ作品ではあるものの、最終回は、馬蕉の正体が十字架に掛けられたキリストだったという、蛇足のような落ちが付き、着地点を見誤った感は否めない。
結局、謎が謎を残したままという、後味の悪い結末を迎えてしまったため、折角のエクスペリメンタルなギャグも、不発に終わってしまったことが、非常に悔やまれる。
尚、赤塚も、後に自作を振り返るインタビューで、『松尾馬蕉』を印象深い作品であると語りながらも、よりナンセンスを際立たせるには、尤もらしい説明的な落ちではなく、徹底した無責任さを貫くべきだったと、悔恨の念を述べている。
*
少年向けギャグ漫画の世界を開拓し、一時代を築き上げてきたパブリックイメージもあり、「少年サンデー」、「少年マガジン」等の週刊少年誌に発表された一連のシリーズに比べ、漫画マニアの間でも、言及される頻度はないに等しいジャンルであるものの、赤塚自身、大人漫画、時事漫画の世界においても、決して閑却することの出来ない足跡を幾つも遺していることを、本章を通読する中で、お分かり頂けたと思う。
『ギャグゲリラ』を除き、いずれも、赤塚全盛期から断絶した時代に描かれたマイナータイトルであり、パッケージ(絵柄)から漂うロートル感は否めないものの、かつての少年向けギャグ作品で見せた赤塚ならではのアナーキーな破壊性と、軽妙洒脱な笑いのセンスは、シリーズによっては健在であり、現在の観点から捉えても、そのエスプリの利いた諧謔的ナンセンスは十分な読み応えを備えている。
また、80年代の社会風俗を語るうえでの資料的価値も高く、その時事世相を立体感をもってカリカチュアしている点も、特筆に値しよう。
これらのビターテイスト溢れる大人の赤塚ワールドもまた、後期『バカボン』や『レッツラゴン』、『ギャグゲリラ』といった70年代赤塚漫画の延長線上に位置する、猛爆ギャグの終着点として、広く吟味の対象となり、今一度、再評価への見直しが図られることを、一ファンとして、切望せずにはいられない。
そう、赤塚ギャグの先鋭的センスは、媒体を問わず、至るシリーズにおいて炸裂しており、痛烈なイロニーを伴いながら、絶えず、混濁の世の不条理に嘲笑を投げ掛けているのだ。


















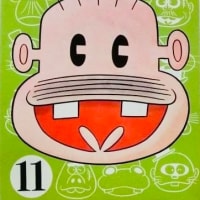

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます