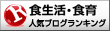・魚類Fishes ぎょるい
魚類(ぎょるい)は、動物界Animalia- 脊索(せきさく)動物門Chordata-脊椎動物亜門 Vertebrataからら四肢動物を除外した脊椎動物の一群で日本語の日常的に魚(さかな、うお)と呼ぶ動物です。これまでの生物分類学の視点では「魚類」なるものを一括りにするのが難しいことが分かり一般的な「魚」は単一の祖先から順次進化してきたものではなく、祖先も進化の過程も多様な変化の過程があることがわかってきています。
鰭(ひれ)があり鰓(えら)で呼吸して多くは、卵生で一生を淡水(いわな、やまめなど)、海水(まぐろ、かじき、とびうお、鮭、鱒、ほっけ等等・・・)の水中で過ごしています。
魚のかぞえ方も複雑で1匹、2匹、又は1本、2本、1尾、2尾、細い魚は条、平たい魚は枚と数えることもあります。
さらに加工品に対しては「枚」や「切れ」や「冊(サク)」や「丁」など、魚の形状や用途によって使い分けは結構複雑です。カニやイカを扱うと1杯、2杯と呼んでいます。
このように、数に添えて、モノの見た目や形状、大きさに加え、食材の用途までを弁別可能にする表現手段が使われています。
地球表面の70%をおおう海、沿岸から沖合、大平洋の真ん中や8000 mの深海までも魚がいます。川、湖、地下水の湧き出るところ、砂漠の水たまりにも魚は棲んでいます。およそ世界で30,000種が知られ、2000種ほどか深海魚として見られ日本とその周辺海域には4000種ほどを確認しています。毎年新種の発見があるのです。東京都中央卸売市場では、ほかの魚に混ってきたものや稀にしか見られない魚も含めると、ここ数年で700種近くが入荷し、このうち、約150種が海外からのもので占められます。
魚類は、軟骨魚類から硬骨魚類に進化したという定説でしたが現在は、サメが誕生する以前に硬骨を持つ祖先がいたことが分かり、進化の過程であえて軟骨魚類になることを選んだのではないか、という説があります。
魚の年齢は、主としてうろこに表われる年輪によって見分けられていますが魚種により年魚(鮎、ワカサギ)といわれ1年から数十年(こい、なまず)生存するものまでいます。現在、魚の種類は3万種以上の魚を分類すると3つの大きなグループに分けられます。脊椎動物の中で最初に地球上に現れたグループです。
1)円口類えんこうるい Cyclostomata(約50種):原生では最も原始的で無顎類は、約5億4,000万年前のカンブリア紀に出現といいます。体の中心には硬い脊椎の代わりに、脊索という柔らかい組織が通って円口類とも呼ばれ、顎がなく口は吸盤状が特徴的です。軟骨魚類や硬骨魚類にある顎あご骨がない魚で、餌は相手に取り付き、口から肉や体液を吸引しているようです。近年に全ての脊椎動物の祖先に当たる動物と同じ特徴があるのではとの仮説があります。
すなわち、ヌタウナギやヤツメウナギを研究することが、全脊椎動物の進化過程を解明する手掛かりとなる可能性があると考えられています。ヤツメウナギ目と2007年1月に日本魚類学会により名称が「ヌタウナギ目(メクラウナギ目)からなります。
2)軟骨魚類(約550種):弾力性のある骨(軟骨)で構成の魚で硬骨魚類よりも原始的な種と考えられ、「エラ穴を複数対持つ」「歯が生え替わる」「浮き袋がない」などの特徴があります。世界中のいたるところに生息しており、住みかは淡水・海水を問わず代表的な魚は、エイやサメ(ギンザメなど)です。エイは500種類以上・サメも500種類以上いるといわれます。
3)、硬骨魚類(2万2000種):
硬骨魚類のほとんどは「条鰭類」に属し胸びれから放射線状に骨の束が伸びており、肩甲骨とつながっているのが特徴です。魚類は最初に誕生した原始的な脊椎動物でサケ・ウナギ・トビウオ・フグ・アンコウ・コイ・フナ・ドジョウ・メダカなど、一般的に「魚」といわれている魚類は、ほぼ条鰭魚類と考えて差し支えありません。シーラカンスや肺魚の仲間で肉鰭類(にくきるい)では胸びれが、一対の骨で肩甲骨部分とつながっています。ヒトや動物のような「四肢動物」に近い骨の構造があり、四肢動物は肉鰭類から進化したと考えるのが一般的です。普通の鰻は硬骨魚類に属します。
海域によって生息している魚の種類が異なり暖流(まぐろ、かじき、とびうお)、寒流(鮭、鱒、ほっけ)を好む魚が水温によって移動し回遊魚となり、冷血動物(変温動物:気温によって体温が変化)でもあり生息している場所の制限があり魚の体温は、基本的に周りの水温とほぼ等しく、その水温が変動すると、それに応じて体温も変化しています。
種別の鮮魚購入数量をみると、昭和40年にはアジ、イカ、サバが上位3種類を占めていましたが、平成22年は、サケ、イカ、マグロへと変化が見られます。
魚は、時期によって脂肪含有量に差があって旨みが異なり美味しく食べられる旬の時期のものを選ぶのがよいのです。一般的に、脂ののっている産卵前の魚を旬としていますが、白身で脂の少ない魚では、淡白なほうがより好まれ産卵後の脂ののりがより少なくなった魚を旬としています。
寄生虫がいることがあるので真水でよく洗浄してから振り塩で滅菌をしてから調理するようにします。筋肉中まで入り込んでいるものは、加熱調理します。素材そのものの味を重視することから刺身、焼き魚、煮魚のように単純な料理が好まれています。
最近は、冷凍技術の発達により遠洋漁業によって多くの種類の魚を季節を問わず水揚げするようになって季節感が失われる傾向にあります。
蓄肉類と異なり魚肉は、筋繊維が短く、組織が柔らかいことから生きた活魚(かつぎょ)、または死後硬直期間中のものを用いた方が歯切れ、味がよいようです。
魚肉の成分組成は、およそ水分60~86%(標準71~79%)、タンパク質10~27%(17~23%)、脂質0.5~20%(1~6%)、炭水化物0.1~1.8%(0.1~0.8%)、灰分0.6~3%(1.0~1.5%)、ナトリウム30~150mg(60mg)%、カリウム250~500mg(400mg)%、カルシウム5~200mg(30mg)%、マグネシウム10~60mg(30mg)%、リン100~400mg(220mg)%、鉄0.4~5mg(1mg)%、銅0.04~0.6mg(0.35mg)%、イオウ100~300mg(200mg)%、ヨード0.01~0.2mg(0.17mg)%、ビタミンA3μg~8,500μg(30μg)%、ビタミンD0~35μg、ビタミンB1:0.01~0.85mg(0.1~0.2mg)%、ビタミンB2:0.01~6mg(0.01~0.44mg)%であり、ビタミンCは殆ど含みません。
魚油に含む脂肪は、常温で液体で血清コレステロールを抑制、さらに油の多い鮭、サバを日常的に食べていると喘息を患う率が低いことがいわれます。脂肪酸がアルツハイマー病を防ぐことも知られています。
近年では一般的には「魚のように見えるもの」を魚類と呼んでいますが学術的に分類学上は分類する際は「脊椎動物で四肢動物以外」という分け方をしています。
習慣的な呼び方としての魚類であり、四肢動物とは、両生類・爬虫類・哺乳類・鳥類などの生物としています。脊椎動物の中でこれらの生き物を除いたものは、習慣的な呼び方としての魚類に分けられているということのようです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
魚類(ぎょるい)は、動物界Animalia- 脊索(せきさく)動物門Chordata-脊椎動物亜門 Vertebrataからら四肢動物を除外した脊椎動物の一群で日本語の日常的に魚(さかな、うお)と呼ぶ動物です。これまでの生物分類学の視点では「魚類」なるものを一括りにするのが難しいことが分かり一般的な「魚」は単一の祖先から順次進化してきたものではなく、祖先も進化の過程も多様な変化の過程があることがわかってきています。
鰭(ひれ)があり鰓(えら)で呼吸して多くは、卵生で一生を淡水(いわな、やまめなど)、海水(まぐろ、かじき、とびうお、鮭、鱒、ほっけ等等・・・)の水中で過ごしています。
魚のかぞえ方も複雑で1匹、2匹、又は1本、2本、1尾、2尾、細い魚は条、平たい魚は枚と数えることもあります。
さらに加工品に対しては「枚」や「切れ」や「冊(サク)」や「丁」など、魚の形状や用途によって使い分けは結構複雑です。カニやイカを扱うと1杯、2杯と呼んでいます。
このように、数に添えて、モノの見た目や形状、大きさに加え、食材の用途までを弁別可能にする表現手段が使われています。
地球表面の70%をおおう海、沿岸から沖合、大平洋の真ん中や8000 mの深海までも魚がいます。川、湖、地下水の湧き出るところ、砂漠の水たまりにも魚は棲んでいます。およそ世界で30,000種が知られ、2000種ほどか深海魚として見られ日本とその周辺海域には4000種ほどを確認しています。毎年新種の発見があるのです。東京都中央卸売市場では、ほかの魚に混ってきたものや稀にしか見られない魚も含めると、ここ数年で700種近くが入荷し、このうち、約150種が海外からのもので占められます。
魚類は、軟骨魚類から硬骨魚類に進化したという定説でしたが現在は、サメが誕生する以前に硬骨を持つ祖先がいたことが分かり、進化の過程であえて軟骨魚類になることを選んだのではないか、という説があります。
魚の年齢は、主としてうろこに表われる年輪によって見分けられていますが魚種により年魚(鮎、ワカサギ)といわれ1年から数十年(こい、なまず)生存するものまでいます。現在、魚の種類は3万種以上の魚を分類すると3つの大きなグループに分けられます。脊椎動物の中で最初に地球上に現れたグループです。
1)円口類えんこうるい Cyclostomata(約50種):原生では最も原始的で無顎類は、約5億4,000万年前のカンブリア紀に出現といいます。体の中心には硬い脊椎の代わりに、脊索という柔らかい組織が通って円口類とも呼ばれ、顎がなく口は吸盤状が特徴的です。軟骨魚類や硬骨魚類にある顎あご骨がない魚で、餌は相手に取り付き、口から肉や体液を吸引しているようです。近年に全ての脊椎動物の祖先に当たる動物と同じ特徴があるのではとの仮説があります。
すなわち、ヌタウナギやヤツメウナギを研究することが、全脊椎動物の進化過程を解明する手掛かりとなる可能性があると考えられています。ヤツメウナギ目と2007年1月に日本魚類学会により名称が「ヌタウナギ目(メクラウナギ目)からなります。
2)軟骨魚類(約550種):弾力性のある骨(軟骨)で構成の魚で硬骨魚類よりも原始的な種と考えられ、「エラ穴を複数対持つ」「歯が生え替わる」「浮き袋がない」などの特徴があります。世界中のいたるところに生息しており、住みかは淡水・海水を問わず代表的な魚は、エイやサメ(ギンザメなど)です。エイは500種類以上・サメも500種類以上いるといわれます。
3)、硬骨魚類(2万2000種):
硬骨魚類のほとんどは「条鰭類」に属し胸びれから放射線状に骨の束が伸びており、肩甲骨とつながっているのが特徴です。魚類は最初に誕生した原始的な脊椎動物でサケ・ウナギ・トビウオ・フグ・アンコウ・コイ・フナ・ドジョウ・メダカなど、一般的に「魚」といわれている魚類は、ほぼ条鰭魚類と考えて差し支えありません。シーラカンスや肺魚の仲間で肉鰭類(にくきるい)では胸びれが、一対の骨で肩甲骨部分とつながっています。ヒトや動物のような「四肢動物」に近い骨の構造があり、四肢動物は肉鰭類から進化したと考えるのが一般的です。普通の鰻は硬骨魚類に属します。
海域によって生息している魚の種類が異なり暖流(まぐろ、かじき、とびうお)、寒流(鮭、鱒、ほっけ)を好む魚が水温によって移動し回遊魚となり、冷血動物(変温動物:気温によって体温が変化)でもあり生息している場所の制限があり魚の体温は、基本的に周りの水温とほぼ等しく、その水温が変動すると、それに応じて体温も変化しています。
種別の鮮魚購入数量をみると、昭和40年にはアジ、イカ、サバが上位3種類を占めていましたが、平成22年は、サケ、イカ、マグロへと変化が見られます。
魚は、時期によって脂肪含有量に差があって旨みが異なり美味しく食べられる旬の時期のものを選ぶのがよいのです。一般的に、脂ののっている産卵前の魚を旬としていますが、白身で脂の少ない魚では、淡白なほうがより好まれ産卵後の脂ののりがより少なくなった魚を旬としています。
寄生虫がいることがあるので真水でよく洗浄してから振り塩で滅菌をしてから調理するようにします。筋肉中まで入り込んでいるものは、加熱調理します。素材そのものの味を重視することから刺身、焼き魚、煮魚のように単純な料理が好まれています。
最近は、冷凍技術の発達により遠洋漁業によって多くの種類の魚を季節を問わず水揚げするようになって季節感が失われる傾向にあります。
蓄肉類と異なり魚肉は、筋繊維が短く、組織が柔らかいことから生きた活魚(かつぎょ)、または死後硬直期間中のものを用いた方が歯切れ、味がよいようです。
魚肉の成分組成は、およそ水分60~86%(標準71~79%)、タンパク質10~27%(17~23%)、脂質0.5~20%(1~6%)、炭水化物0.1~1.8%(0.1~0.8%)、灰分0.6~3%(1.0~1.5%)、ナトリウム30~150mg(60mg)%、カリウム250~500mg(400mg)%、カルシウム5~200mg(30mg)%、マグネシウム10~60mg(30mg)%、リン100~400mg(220mg)%、鉄0.4~5mg(1mg)%、銅0.04~0.6mg(0.35mg)%、イオウ100~300mg(200mg)%、ヨード0.01~0.2mg(0.17mg)%、ビタミンA3μg~8,500μg(30μg)%、ビタミンD0~35μg、ビタミンB1:0.01~0.85mg(0.1~0.2mg)%、ビタミンB2:0.01~6mg(0.01~0.44mg)%であり、ビタミンCは殆ど含みません。
魚油に含む脂肪は、常温で液体で血清コレステロールを抑制、さらに油の多い鮭、サバを日常的に食べていると喘息を患う率が低いことがいわれます。脂肪酸がアルツハイマー病を防ぐことも知られています。
近年では一般的には「魚のように見えるもの」を魚類と呼んでいますが学術的に分類学上は分類する際は「脊椎動物で四肢動物以外」という分け方をしています。
習慣的な呼び方としての魚類であり、四肢動物とは、両生類・爬虫類・哺乳類・鳥類などの生物としています。脊椎動物の中でこれらの生き物を除いたものは、習慣的な呼び方としての魚類に分けられているということのようです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。