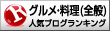・水無月 みなづき
6月は、梅雨の時期なのに水の無い月と命名しています。本来は、稲作を中心とした農作業を、し尽した月の、皆尽月(みなづき)、であったといわれます。
水無月は、陰暦6月の異称で炎暑のため水源も涸(か)れ果てて水が無い月、の意味ともなりますが、田植えに多くの水を必要とする月の意味です。
水の月で田に水を引く必要のある月「水の月」という説もあります。
他にも田植えの終わった田圃に水を湛(たた)えるので水月(みなづき)と、雅(みやび)な夏の呼び名の、蝉羽月(せみのはづき)、風待月(かぜまちづき)、涼暮月(すずくれづき)、常夏月(とこなつづき)、松風月(まつかぜづき)、夏越月(なごしのつき)、などともいわれます。
梅雨どきの日本の六月は、国民の祝日も無い月でもあります。
旧暦の水無月は、真夏の暑い太陽が照り付ける現在の新暦での七月に相当し、つまり、夏の日照りのせいで水が枯れてしまい、水が無い月だったために「水無月」という字があてられたのではないか、といわれています。新暦の2020/6/1は旧暦2020年04月10日、旧暦 2018/6/1 に対応する新暦は2020年07月21日です。
約三十日間の梅雨の時期を含むいまの新暦六月に、旧暦の情緒のある月名を当てるのは不向きといえるでしょう。
雷が鳴るとともに稲の生育を助ける夕立が来るので、鳴神月(なるかみづき)とも言います。古代にあっては、稲妻(いなづま)は稲の夫(つま)を表わし神格化され、稲は稲妻をうけて結実すると信じられていました。
電光が稲に当たることにより稲が妊娠して子を孕(はら)む、電光は稲の夫であると考えられていました。
気象学的には雷が多いとき降水量や日照が多い、気温が高いなどで 稲の生育に都合がよく 神話の時代から稲作をもっとも重要視していた私たちの先祖が、農耕に関わる水や天候を気遣っていたことがうかがわれます。
旧暦(太陰暦)では、月の満ち欠けのサイクル(大の月を30日、小の月を29日として)を基準にしています。ひと月は必ず新月(朔・一日)から始まり、上弦の月(8日頃)、満月(15日ごろ)、下弦の月(23日ごろ)を経て、再び新月に戻ります。
月齢が0の月が、「新月(しんげつ)」です。朔(さく)ともいいます。月が太陽と地球の間になり、地球からは全く見えません。月のはじめの「一日(ついたち)」のことを「朔日(さくじつ)」と呼ぶのは、もともと新月のことを指していました。
月齢3日目の月が、三日月(みかづき)です。若月(わかづき)、初月(ういづき)、眉月(まゆづき)などさまざまな呼び名があります。ようやく月が見えはじめるのはこの月からです。
月齢15日目の月は、満月(まんげつ)です。望月(もちづき)、十五夜(じゅうごや)とも呼ばれ、英語ではフルムーン。月がちょうど太陽の反対側に来るため、日没ともに月が出ます。もっとも美しく見える月で、古来より月見の宴が行われました。
満月以降はおよそ50分ずつ、月の出が遅くなっていきます。月齢30日は、三十日月(みそかづき)です。晦(つごもり)とも言います。太陽とほぼ同時に出てくるので、月の姿は見えません。月が満ち欠けが一周して、新月に戻ります。月の昇る時刻は季節によって違います。
太陰暦は、月の満ち欠けを基にした暦で、月が新月(朔)から次の新月になるまでの期間を1ヵ月(29日または30日)とし、1年を12ヵ月とした暦です。 三月朔日と言えば三月一日を表します。朔から次の朔まで、月が満ち欠けをひとめぐりする周期は平均約29.5日です。29.5日×12ヶ月=354日で、1年が太陽暦(365.2422日)より11日ほど短くなります。
このまま毎年経過していくと実際の季節と暦はどんどんズレ、そのズレは3年で1か月ほどまで拡大してしまうことになります。 これを解消するのが閏月(うるうづき)です。
閏(うるう)といってもグレゴリオ暦(太陽暦)で採用されている4年ごとに1日を加算する閏年(うるうどし)とは大きく異なり、旧暦では約3年に1度、1年を13ヶ月とします。
太陰暦(太陰太陽暦・旧暦)では、30年を1周期とし、1年354日の年が19回、355日のうるう年が11回 と一年が十三ヶ月の年もあるのです。つまり約3年に1度は13ヶ月の年が現れます。
最近では2012年の旧暦3月と4月の間に余分な1ヶ月、閏3月(うるうさんがつ)が、2014年旧暦9月と10月のあいだに閏9月が挿入で挿入位置は一定のルールにもとづかれ、年により異なります。2017年は、旧暦(太陰太陽暦)では閏月のある年で五月の皐月の次に閏皐月が来た年でした。
具体的には、昨年、現在用いているいまの暦(太陽暦)の六月二十三日から閏皐月となり、七月二十一日まで続きます。
そして旧暦の水無月は七月二十二日から八月十九日までとなります。旧暦といまの暦のずれ、違いがよく分かります。旧暦では、暦の上では四ヶ月の長い夏が続いたことになります。
旧暦は6月の次が7月ではなくてもう一度6月だったり、その月の末日(晦日:みそか)が29日であるか30日であるかは暦がないと一般の人々には判らないものだったのです。
西洋にはジューン・ブライトJune brideという言葉があります。 直訳すると6月の結婚で、6月に結婚式を挙げることをいいます。6月に結婚した花嫁は幸せになれるというヨーロッパの言い伝えに由来しています。諸説ありますが、有名なものとして3つが挙げられます。
1)女神「JUNO」説:6月の月名である「JUNE」と、ローマ神話で結婚をつかさどる女神JUNOに由来し、6月は結婚や女性の権利を守護する「JUNO」の月です。この月に結婚する花嫁は幸せになるという言い伝えです。
2)気候・季節説:ヨーロッパの6月は1年の中で最も雨が少ない月で、気候なども適し、復活祭が行われる月でもあることから、全体がお祝いムードとなるので、多くの人から祝福を受ける6月の花嫁は幸せになると伝えられます。
3)結婚解禁説:3月、4月、5月の3ヶ月間は農作業の妨げとなることから、ヨーロッパでは結婚が禁じられていたことによるものです。結婚が解禁となる6月に結婚式を挙げるカップルが多く、その分祝福も多く、6月の花嫁は幸せになれるだろうということです。
京都の和菓子「水無月」がありました。その昔、6月1日(旧歴)に口にすると夏バテしないと言われていたことから、室町時代の宮中では氷の節句の行事として、氷室(ひむろ/京都府衣笠山)から氷を取り寄せて暑気払いをしていました。
しかし、氷は庶民には手に入れることができない貴重なものだったため、氷に似せて作ったお菓子を食べ、夏の暑さを乗り切ろうとしたのです。
そのお菓子が水無月になります。外郎(ういろう)の上に小豆がのっています。
水無月が三角形にカットされているのは、氷のかけらを表現していて、上に乗っている小豆には悪魔払いの意味合いがあります。
水無月を食べることで夏の暑さを乗り切り、自身の厄除けも兼ねた縁起の良いお菓子ということです。
水無月は、現代人には、そのままの漢字では理解しがたい感じがありますが、その意味を深く辿(たど)ると納得させられることであることが分かります。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。