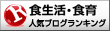・旬の食材の語源(春)
そのものを指す言葉として名前があります。食材にもそれぞれに名前が付けられていますが、どのような経緯で付けられていったのか、少し知りたくなりました。今季の旬の食材の語源を少し探索してみることと致します。
魚貝類
石斑魚・鮎魚女・鮎並 あいなめ
アイナメの肌が、落ち鮎の肌がざらざらしてくるのに似ていることから鮎並などの字が当てられたとといわれる。英名をfat greenling(油っぽい、緑のタラ:海草のあるところに住む油っぽいタラに似た魚)という。
浅蜊 あさり
古くから採取され食べられておりすぐに砂地で漁り(あさり)出せることからといわれる。
伊佐幾 伊佐木Grunt いさき
磯に棲むことから磯魚(イソキ)、魚岬(イサキ)と呼ばれ、あるいは幼魚の縞模様から班魚(イサキ)、背中の縞文様が5つに分かれることから五裂(イサキ)に由来するという。キは魚を表わす。伊佐幾・伊佐木はこれの当て字としている。「背ビレを広げると鶏冠(とさか)に似ているところから中国では鶏魚の漢字があてられる。
鰹 かつお
古くは生で食べることはなく、干して食用にしたことから、堅い魚の意の「堅魚(かたうお)」が変化した語という。「鰹」の字も身が堅い魚の意であるが、中国ではこの字はウナギのことを指す。
吉備奈仔・黍魚子 きびなご
鹿児島県南部では、帯のことを「きび」ということから、銀色で帯状にあることから帯のある小魚ということで「きびなご」と呼ぶ。漢字については、当て字されただけではないかといわれる。
桜海老Sakura shrimp さくらえび
体色が半透明で赤い色素が透き通って綺麗なピンク色に見えるところから、淡いピンク色をしているえびであることから名付けたという。
栄螺・拳螺 さざえ
和訓栞(わくんのしおり:江戸後期の辞書)には、小さな柄のようなものを多くつけた貝の意とあり古名を細枝家(さざえ)という。栄螺は、巻貝を意味する螺(にな)と、表面の角が、いかにも栄えているように見えることから栄の字を組み合わせたとしている。
拶双魚Japanese Shad さっぱ
大言海による語源で、コノシロに比して味のサッパリしたことよる。
細魚・針魚Halfbeak さより
透き通るような銀白色で細長くスラリとし、下あごが長くとがって先端が赤っぽい。細魚、針魚と当て字しその魚の美しさを表す。
鰆、狭腹、小腹、馬鮫魚Spanish mackerel さわら(さごし)
名前は腹部が狭いという意味の狭腹(さはら)、旬が春で魚偏に春をつけ鰆(さわら)とした説がある。細長く頭の小さい銀白色をした駿足のスマートな魚で4~5月の産卵期が旬。花盛りの頃に獲れるサワラを和歌山では「桜鰆」と呼び、サワラを春の使者ともしている。
田螺 たにし
田んぼに住む巻き貝(ニシ)という意味とされる。 タヌシ(田主)でタニシは田の主であるともいわれる。
蝶鮫 ちょうざめ
大きな菱形の硬い鱗が5列に並び、その鱗が蝶の様な形をしているところからチョウザメといわれる。サメと呼ばれるが、系統が異なり外見ではエラ蓋(ふた)があるのがチョウザメで、エラ蓋がなくエラ孔がむき出しになっているのが一般のサメの類としている。
蛍烏賊 ほたるいか
青緑色に輝く発光器を1000個もち蛍のように光ることから名前がつけられたといわれる。
北寄貝 ほっきかい
北寄りの貝であるから、またアイヌ語(ポッキセイ)からとかが名前の由来とも言う。
鱒 ます
マスの語源で定説となっているものはないが、赤みの強さ、繁殖力旺盛な事から「増す」、味が勝[まさ]ることなどから名付けられたという。韓国では色が松の木の内部の色をしているので「松魚」でマスノイオということに由来する説もある。
出雲国風土記(733年)には鮭とともに麻須(マス)を記載している。天子様にささげる尊い魚という意味あいより聖武天皇の頃(天平15年:743年)にマスを献上した記録があり、皇室との関係が深いといわれる。
鱒の尊は、酉は酒つぼ+寸の手の形であり酒どっくりの、かっこうがよいことをあらわしている。
馬刀貝 まてがい
古語で「真手」といい、片手に対して両手という意味で、左右から水管や足が出ているからという説。馬手・ウマテや馬の爪に似ていることから「ムマツメ→ マテ」という説もあるが定かではない。
さらに短刀の一種で騎馬戦の時に用いる刀で貝の形が長方形の細長い刀に似ている所から馬刀貝(マテガイ)と名付けられたという。
眼張 めばる
目が目立って大きい。目を見張っているということらしい。
水蛸 みずだこ
水っぽい蛸のことで蛸は本来クモのことで「海に棲むクモ」という意味で「海蛸子」と表され、これが省略されたもの。タコはその姿から多股(たこ)で足が多い意味。他に手(足)にはたくさんの吸盤があり、物に凝りつくことから手凝(たこ)の意とする説がある。
海藻
鹿尾菜・羊栖菜 ひじき
古名のヒズキモが転じてヒジキになったと言われる。漢字の鹿尾菜は、形が鹿の黒くて短いしっぽに似ている事が由来という。
野菜・きのこ
独活 うど
諸説あり成長した茎が中空なので宇登呂(うどろ)と呼ばれ、そこからウドに転訛したという説がある。
他に土の中に「うずくまっている」若い芽を食用に用いることから埋(ウゾ)が転じた説、埋所(ウド)の意とする説。葉が大きくなって風もないのに独りで動いているように見えることから「独活」と漢字が当てられている。
陸鹿尾菜 おかひじき
英名Salt wort(塩草)といい針状の緑色をして松葉に、葉の多肉質なのが海草のひじき、ミルに似ことから。別名おかみる、みるな、くさひじき、はたけひじき、陸の海藻などともいわれる。
きゃべつ
ラテン語で「頭」を意味する「Caputカプート」が、フランスのピカール方言に入って「Cabocheカボシュ」となり、英語で「Cabbageキャベッジ」になり、日本で「きゃべつ」に変化している。
日本名、中国語は甘藍(かんらん)、玉菜(たまな)と呼ばれていた。 ドイツ語で「Kohlコール」、フランス語で「Chouシュー」という。
グリンピース
英語でGreen-pea、peaは、えんどう豆のことで、ピースは複数でpeasでしょうか。
未熟の緑色のエンドウ豆でグリーンピースとなったものと思われる。
クレソン
クレソンCressonは、フランス名で、英名Watercressウォータークレス、和名はオランダガラシまたはミズガラシと呼ばれる。クレソンの学名は、Nasturtium officinale ナスチューム・オフェチナリースといい、その語源は「薬効がある」ことを意味する。
萱草 かんぞう
中国の故事でこの花を見ると憂いを忘れられるとの事から萱(かや:茅、すすき類)の字があてられ日本に渡って別名ワスレグサとも言う。
グリーンアスパラガスGreen asparagus ぐりーんあすぱらがす
アスパラとはギリシャ語で「たくさん分かれる」・「激しく裂ける」というアスパラゴスからの意味を持つ、次々と生えてくる若芽を収穫することから新芽を指している。
こごみ
くるんと丸まった芽から、しゃがんだように、屈[こご]んだように、かわいい形が似ていることからかがむ、こごむ、こごみになったといわれる。
山椒 さんしょう
山の薫り高い実であること、「椒」の字の叔は小さい実のことで芳しいの意味があり、木に成り、この一字だけでも山椒のことを言い表す。山に見られることから漢名にならい「山椒」の名が付けられている。
椎茸 しいたけ
自生するものは、春と秋に広葉樹の、くり、くぬぎ、しいの木の枯れ木に生えるが主に椎に生えるきのこから名前の由来としている。
🥔じゃが芋 じゃがいも
ジャガイモは、「ジャガタラ芋(ジャガタラいも)」の略。 ジャガタラとは、インドネシアの首都「ジャカルタ」のことで、日本へは16世紀終頃、オランダ商船により導入している。
芹Water dropwort せり
生命力が強く群がって競り合いながら育つことからの語源という。
薇 ぜんまい
若芽の先がくるくると巻いて丸いお金のように見えるため銭巻・銭舞と呼ばれたのが語源としている。
空豆・蚕豆 そらまめ
空に向かってさやがのびる、蚕(かいこ)を飼っている時期と食べる時期の蚕豆が似ていたとかでこの名がついたともいわれる。別名ナツマメとも言う。
鷹の爪 たかのつめ
ウコギ科、幹、小枝はともに灰褐色で、冬芽がとがり、その先端が曲がっていることから鷹の爪を思わせるため、この名がある。
筍 笋 竹の子、たけのこ
筍は、竹冠に旬の字が当てられ旬は、一月を十日づつ分けた時のそれぞれの十日(上旬、中旬、下旬)になる。このことから十日の間に筍が食べられ旬を過ぎると竹になってしまうこと「旬内に竹の子となり、旬外に竹となる」とする説がある。筍の早い成長を言い当てている。
🧅玉葱 たまねぎ
玉ねぎの英語名「オニオン=onion」の語源は、ラテン語の「真珠」を意味する。
楤芽 たらのめ
辣(トゲ)を表す古語タラに由来し、そのトゲのある木の芽を意味するとネット検索であるが定かではない。
茶 ちゃ
日本語だけでなく、世界中の言語で茶(ちゃ)を表す単語は中国語の茶からきている。お茶は中国から渡来し中国語が語源。 朝鮮半島でも「チャ」と発音する。
ロシア語やチェコ語やアラビア語の「チャイ」も、中国の「チャ」が語源。中国からのお茶の伝播方法によって世界の茶の発音は広東語チャ(cha)系統と福建省テー(te)系統の2つに分類できる。
土筆 つくし
古くはツクヅクシといい、ツクシはそれを略したもの。ツクは「突く」で、地面から突き出ることからと言う。スギナにくっついて出てくる事から、「付く子」、袴の所でついでいる様に見える事から、「継く子」となった説が有力。土筆という漢字は、生える様子を筆に見立て付けられたという。
石蕗 つわぶき
腎臓形の葉の裏に褐色の羽毛をもち濃緑色の葉に光沢がありツヤのある蕗という意味でこの名がある。
韮 にら
古事記に加美良(かみら)、臭韮(かみら)、万葉集では久々美良(くくみら)、正倉院の文書には弥良(みら)として記載がある。韮は地面「一」より草が非のように、常に生えいることより作られた象形文字としている。
野蒜 のびる
野蒜は、野に生える蒜(ひる[にんにく(大蒜)、ねぎ【気:秋葱(あさぎ)】、にら(韮)、ラッキョウの香辛野菜の総称])を意味する。
のびるの古名としてあららぎ(蘭)として登場している。単にひるともいい食べるとひりひりして辛いことからつけられたという説がある。
蕗 ふき
名前の由来が冬葱(ふゆき)で冬にでる葱色の植物、冬黄で冬に黄色の花を咲かせるからとか、道端で道(路)でよくみかけることから蕗ともいわれる。
マッシュルームMushroom まっしゅるーむ
フランス語のmousseronからで、mousseの部分は泡のこと。 マッシュルームはヨーロッパで、地下室で育てられ地面から泡のように生えてくるものという意味になる。
蓬 よもぎ
四方に根茎を伸ばし繁殖するすることから四方草(よもぎ)、よく燃える善燃草(よもぎ)など語源に諸説ある。
レタスLettuce れたす(ちしゃ)
レタスの語源はラテン語の乳を意味するlac(ラク)からlactuca、英語でLettuceに、日本では根元に近い茎の部分を切ると乳白色乳汁がでることから乳草、ちしゃとなった説がある。
山葵 わさび、
平安時代に記された本草和名(10C)によると、深山に生え、銭葵(ぜにあおい)の葉に似ていることから山葵(やまあおい)と書いてワサビと読んでいる。
ワルサハリヒビク(悪戯疼)、ワルサワヒビク(悪障疼)の略で、辛い事を示すなどといわれているが定かではない。
蕨 わらび
万葉集にまでさかのぼる古い名前であるワラビの語源は、これといった説得力ある説がない。加茂百樹著の日本語源(興風館、1943年)は、短期間でワラビの芽が散(わら)くので、散芽(わらめ)の転訛、ないし散風(わらぶる)に由来すると説明している。
他に地中を這う根からの芽が散って「散る・ワラ→芽・メ」のワラメからワラビに転じたとする説、カラ(茎)、メ(芽)の転訛説ほか俗説がある。
果物
苺 いちご
草冠に母で植物が、増えていく、子を産む様子を表す。
野生のキイチゴで日本書紀(伊致寐姑いちびこ)、和名抄(伊知古いちご)、枕草子(いちび)に記載があり魚(いお)の血のある子(いくら・すじこ)のごとしと、いわれたことから魚の[い]、血の[ち]、子のごとしの[こ]をとって、真っ赤であるとの意味からいちごと呼ぶようになったといわれる。
また、1~5月に収穫することからいちごという俗説も知られる。英語のStrawberryは、傷つきやい果実でStraw(麦わら)を敷いて育てるberry(核のない果肉の柔らかな食用小果実)というところからとしている。
グレープフルーツGrapefruit ぐれーぷふる
果実がブドウの房状につくことから名づけられたといわれる。
三宝柑 さんぽうかん
江戸時代、文政年間(1818-1830)に和歌山城内で偶然原木がみつかり殿様に三方(三面に穴のある四角の台)にのせ献上したところ喜ばれたことから三方(宝)柑の名がついたという。
枇杷Loquat びわ
果実の形が楽器の琵琶に似ていたところから名前の由来としている。
メロンMelon めろん
ギリシャ語のMelopepon(りんごのようなうり)を語源としている。
国語辞書の大言海(だいげんかい)は、1932~37年(昭和7~12年)に約8万語が収録、刊行した語源解釈書。
語源を知ることは、言葉の意味や使い方を正しく知るうえで、興味深くなり、より理解力を高めるのに役立ちます。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。