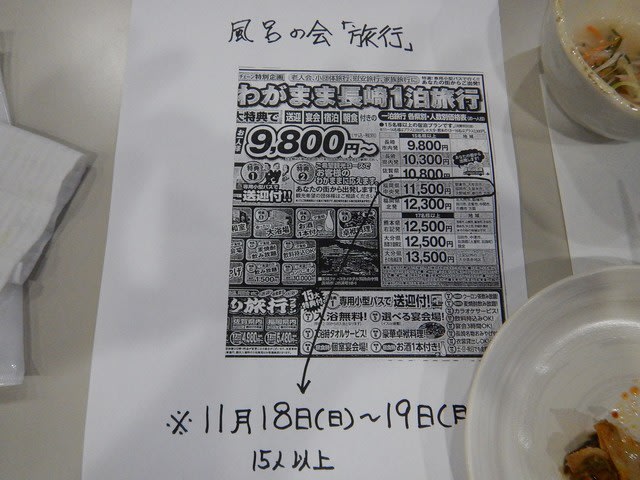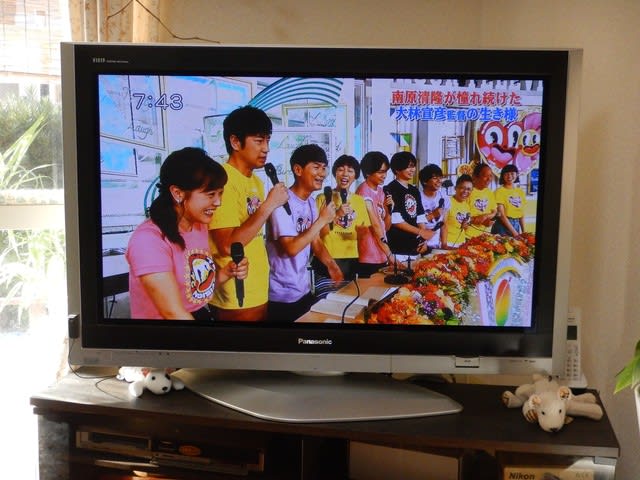先月末から昨日まで、定年後かつてないほどの忙殺の日々でした。メインは友人の子息が福岡市議会議員選挙へチャレンジするとのことで、近所に住むわたしが12日間お手伝いに行きました。新人でおまけに地元出身でないという、大きなハンディを背負っての立候補でしたが、昨年からの選挙区内への自転車での訴えを一貫して行い、R党からの公認などが功を奏し見事当選しました。今後は本人の言う「まっとうな政治」で、たくさんのご支援をいただいた皆さんに応えていってほしいと思います。たかしくん当選おめでとう・・・ バンザーイ バンザーイ バンザーイ

当選発表4月7日の夜は雷雨でしたが、本日も好天が続き我が家の庭の花々も元気に咲いています。ただ、少し寂しいのは毎年我が家のビオラに卵を産み付け、たくさんの蝶が巣立っていく「ツマグロヒョウモン」がまだ訪れていないように思います。勿論可愛い幼虫たちも見えません。

先月の3月26日、日曜大工の師匠中園さんの工房にやってきました。十数年前に私自身が一日がかりで作った、庭の園芸用品置き場のボックスですが、永年の劣化でゆがみが生じているために、補強と小物を置く棚と扉を作りにやってきました。

また新しい工具が増えているようです。工具入れの小屋はありますが、どうやらこの小屋の整理の棚づくりも始まりそうです。


まずは買ってきた杉材の面取りです。便利な機械もあるもんだ‥‥

電気鋸で切断していきます。

扉を作っています。この電動ドライバーもインパクトやドライバードリルと2種類あるのですが、私にはもう一つ違いが判りません。

中園さんが手直ししている間、私は家から持ってきた包丁とカスタムナイフを電動砥石と仕上砥石で研いでいきます。刃物を切れ味鋭く正確に美しい形を保ったまま研ぐことはは大変難しいことですが、この電動砥石であれば、研ぐ力を押さえすぎず均一にして、研ぐ角度を注意することで失敗することなく切れ味鋭い美しい研ぎができます。わたしは鉄工所の息子・・・・今は大変危険なことですが、父ちゃんの工場で金切り鋸の折れたものをグラインダーを使って、手裏剣やナイフを使って作って遊んでいました。写真は五十年前三本松の宇都鉄工所と五十代のとうちゃん

補強して棚や扉の取り付けも見事に終わりました。防腐と美装のための塗料缶を買ってきているものの、忙しさにかまけてまだ塗っていません。

「とうちゃんのしんだといもこえっ おかげさんで なごいきしてきもした こんといになっせぇ しんだ とうちゃん、かあちゃん、あんちゃんと こんといやっからこそでくっ はなぃをしたかぁ」
親父の死んだ年も超え お陰さまで 長生きしていました この年になって 亡くなった お父さん、お母さん、兄貴と この年だからこそできる 話をしたいなぁ