「中国語は楽しい 華語から世界を眺める」
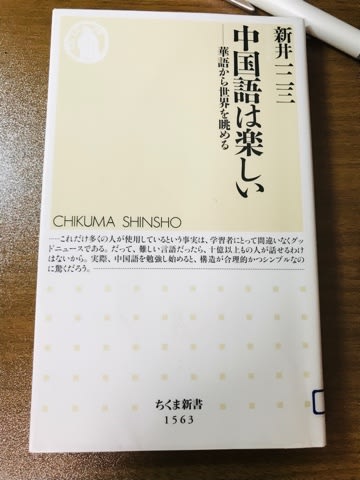
中国語での著書もある作家として活躍する新井一二三氏が、“中国語” の歴史や移り変わり、台湾、香港、海外に散らばる華人のアイデンティティーなどを、中国愛たっぷりに語っている。
中国は広大な国土で多民族国家ゆえ、多くの方言が存在する。
北京語、満州語、広東語、上海語、長沙語、台湾語・・・まだまだたくさんある。
中国人同士でも、地方の方言を使うとまったく通じないというのはよく聞く。
王朝時代には公用語が形成され、やがて科挙制度で全国からやってきた官吏が言葉が通じないのでは困るので、官話という標準語が設けられた。
そのうちの北京官話が中心となり、普通話(Pǔtōnghuà)が人工的に整備されたのは最近(1950年から60年にかけて)のこと。
おかげで中国語を母語としないわたしたちは、それを “中国語” として学ぶことができ、そして中国の各民族もまた、普通話を学ぶようになった。
ひとつの国としては当然のことながら、中国という国は大きすぎるのだ。
権力により母語ではなく普通話を標準語として強制教育されることを思うと、複雑な気持ちになる。
香港の中国返還後の変化と、母語(広東語)への愛についても書かれている。
それで思い出したのが、最近の中国映画では方言を採用することが多くなっている。何か関係あるのだろうか。
著者は大学で中国語を教えているので、本書には学習に役立つ章もある。
中国での親族まわりの呼び名は、それはそれは細かく決まっていて、とても覚えられるものではないので私は覚えないのだがw
(興味のある方は、こちらを参照→中国語の家族・親族の呼び方)
正月に親戚を訪ねて、親戚のひとりひとりにその複雑な敬称(大伯、四叔、舅舅だとか)で挨拶をして紅包(お年玉袋)をもらうことが、中国語圏の子どもが人生で最初に出会う試練だ、と書いてあって笑った。
よそのおじさん、おばさんに挨拶するときの言い方も、年上年下で違うのでややこしい。
そういえば、年齢を聞くときも、子供に聞くのと年上に尋ねるのは違うと習ったなあ。
全て儒教に根差す「長幼の序」の観念からくるのだから、言語としては面白いけど大変だ。
中国語は楽しいかと聞かれたら、楽しい。
難しかったり覚えが悪かったりでなかなか上達しないが、楽しいから学び続けている。
また、外国の言葉を学ぶということは、文化や習慣を知ることだと思っている。
ドラマが入口だったが、歴史についてももっと知りたいと思うし、文学や食や漢方についてもますます興味がわいてくる。
ただ、中国語クラスの同学(同級生)とも話していた。
「中国の歴史や文化は素晴らしくて好きだが……」
中国をめぐる状況は、言わずもがな、ということで。
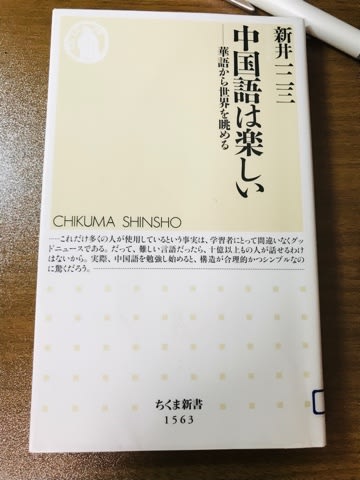
中国語での著書もある作家として活躍する新井一二三氏が、“中国語” の歴史や移り変わり、台湾、香港、海外に散らばる華人のアイデンティティーなどを、中国愛たっぷりに語っている。
中国は広大な国土で多民族国家ゆえ、多くの方言が存在する。
北京語、満州語、広東語、上海語、長沙語、台湾語・・・まだまだたくさんある。
中国人同士でも、地方の方言を使うとまったく通じないというのはよく聞く。
王朝時代には公用語が形成され、やがて科挙制度で全国からやってきた官吏が言葉が通じないのでは困るので、官話という標準語が設けられた。
そのうちの北京官話が中心となり、普通話(Pǔtōnghuà)が人工的に整備されたのは最近(1950年から60年にかけて)のこと。
おかげで中国語を母語としないわたしたちは、それを “中国語” として学ぶことができ、そして中国の各民族もまた、普通話を学ぶようになった。
ひとつの国としては当然のことながら、中国という国は大きすぎるのだ。
権力により母語ではなく普通話を標準語として強制教育されることを思うと、複雑な気持ちになる。
香港の中国返還後の変化と、母語(広東語)への愛についても書かれている。
それで思い出したのが、最近の中国映画では方言を採用することが多くなっている。何か関係あるのだろうか。
著者は大学で中国語を教えているので、本書には学習に役立つ章もある。
中国での親族まわりの呼び名は、それはそれは細かく決まっていて、とても覚えられるものではないので私は覚えないのだがw
(興味のある方は、こちらを参照→中国語の家族・親族の呼び方)
正月に親戚を訪ねて、親戚のひとりひとりにその複雑な敬称(大伯、四叔、舅舅だとか)で挨拶をして紅包(お年玉袋)をもらうことが、中国語圏の子どもが人生で最初に出会う試練だ、と書いてあって笑った。
よそのおじさん、おばさんに挨拶するときの言い方も、年上年下で違うのでややこしい。
そういえば、年齢を聞くときも、子供に聞くのと年上に尋ねるのは違うと習ったなあ。
全て儒教に根差す「長幼の序」の観念からくるのだから、言語としては面白いけど大変だ。
中国語は楽しいかと聞かれたら、楽しい。
難しかったり覚えが悪かったりでなかなか上達しないが、楽しいから学び続けている。
また、外国の言葉を学ぶということは、文化や習慣を知ることだと思っている。
ドラマが入口だったが、歴史についてももっと知りたいと思うし、文学や食や漢方についてもますます興味がわいてくる。
ただ、中国語クラスの同学(同級生)とも話していた。
「中国の歴史や文化は素晴らしくて好きだが……」
中国をめぐる状況は、言わずもがな、ということで。




















少ないと文句言われます。。。(泣)
ホント方言の域を超えているので
テレビドラマ見ていると 全てに字幕が 入ってますからねぇ~
田舎に行くと 北京語喋れない人がいっぱい!!
北京語では、通じないタクシーとかもいっぱいです。
ポケットマネーの紅包、辛苦了。
少ないって文句言うの、中国っぽいですねw
>ホント方言の域を超えているので
日本でも沖縄や青森のネイティブの人の会話はわからないですw
でも中国はそもそも民族が違いますもんね。
大陸のドラマって、普通話を喋れない演員さんは吹替えですね。
でも以前見た台湾のドラマは吹き替えじゃなかったみたいで
全然まったくひとつも聞き取れませんでした(泣)
そしてわたしは繁体字がわかりません(汗)
普通話を学んでても、台湾旅行は無理かも(´;ω;`)ウッ…