20カ国・地域(G20)農相会合に先立ち、来日中のパーデュー米農務長官は新潟市内で時事通信などの取材に応じ、11日日米新貿易交渉について「巨額の対日貿易赤字の解消に焦点を当てるべきだ」との考えを明らかにしたと報じられている。
パーデュー氏は「米国は年間700億ドル(約7兆7000億円)規模の対日貿易赤字を抱え続けている」と述べ、問題視する考えを表明。4月に始まった日米交渉に関しては、「赤字が認識されるべきだ」と訴えた上で、「日米は互恵的な協定に合意できるはずだ」と語ったとのこと。
パーデュー氏は「米国は年間700億ドル(約7兆7000億円)規模の対日貿易赤字を抱え続けている」と述べ、問題視する考えを表明。4月に始まった日米交渉に関しては、「赤字が認識されるべきだ」と訴えた上で、「日米は互恵的な協定に合意できるはずだ」と語ったとのこと。
はっきりいわせてもらえば、アメリカの遺伝子組み換え作物(GMO )など安全性が担保されていない農産物を日本人が食べたくないだけのこと。もっといえば、対日貿易赤字は自国の輸出品が日本の消費者にとって魅力がない結果であろう。
米国におけるGMOの栽培面積は、2017年に7,500万ヘクタールにおよび世界最大。内訳は、ダイズ3,405万ヘクタール、トウモロコシ3,384万ヘクタール、ワタ458万ヘクタール、アルファルファ122万ヘクタール、カノーラ87.6万ヘクタール、テンサイ45.8万ヘクタール、ジャガイモ3,000ヘクタールなど。これ以外にもリンゴ、スクオッシュ、パパイヤが栽培され、ダイズ、トウモロコシ、ワタに関しては、94~96%が遺伝子組み換えで、普及はほぼ一巡したのだそうだ。
■EUでのGMOへの厳しい規制
一方、EU ではGMOに係る食品・飼料については,包括的かつ厳 しい法的な規制が敷かれており、GMO に関する法的規制及び政策は、EUで重要視されている予防原則に基づき、環境並びに人及び動物の健康及び安全性への悪影響を防ぐように立案されているそうだ。
つまり、EUでは意識が高くGMOに懐疑的な消費者、農業者、環境保護者によって表明されている懸念 に対処しているそうなのだ。米国が大量に生産しているGMOを安易に受け入れていないのである。
EU ではGMO 及び GMO から製造された食品・飼料はケースバイケース で行われる厳しい審査と安全性に関する評価を経てM承認を受けた場合にのみ、市場に流通 、または輸入することができるのだそうだ。
この承認は,欧州委員会から 10 年間の期限付きで 与えられるものであって,EU 全体に適用される。具体的には,欧州食品安全機関(EFSA) が必要なリスク評価を行い、GMO,GMO から構成されたまたは GMO が含まれる食品・ 飼料は、識別番号を与えられ、表示とトレーサビリティを確保して消費者の選択に資する ようにしているそうだ。
実は 2001 年から EU ではGMO の事実上のモラトリアム(承認手続きの停止措置)を実施し てきたそうなのだが、(米国による圧力のためか)2003 年 9 月にEU の一般裁判所がEUで2001 年から停 止されていたトウモロコシ 1507 の販売に関する承認の申請を再開すべきであると決定し モラトリアムが終了。 これと時期が同じく、1990 年から始まっていた EU の GMO に関する規制につい て,1999 年に欧州理事会から欧州委員会に対して見直すべきことが要請され、2001 年から 2003 年にかけてその法的な枠組みが改定され、 この新たな法的な枠組みのもとで、最近の動向として2015 年 3 月に施行。
①「加盟国単位で GMO の栽培を 拒否できる」という内容の作物環境放出指令 2001/18/EC の改正
②(2015 年4月に欧州委員会から提案された)「加盟国単位で GMO の輸入を拒否できる」という内容の規則 1829/2003 の改正 なのだそうだ。
日本に米国産GMOを押し付けるのか?
世界中の国民にとり、食の安全は国家単位で規制を行ってまもるべきものであり、いくら日米安保体制にある同盟国とはいえ、対日赤字を補填するために日本人が嫌がる米国産GMOを大量輸出しようとする米国にとり、日本は以前からしばしばいわれているように「経済植民地」ということですか?










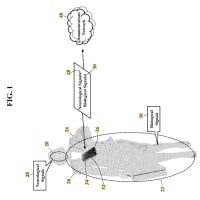


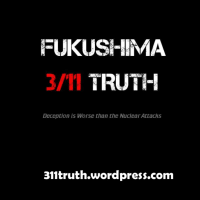
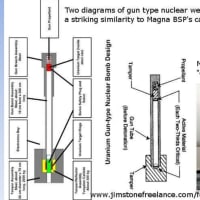

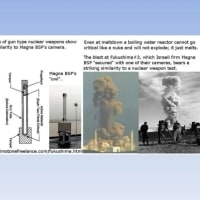
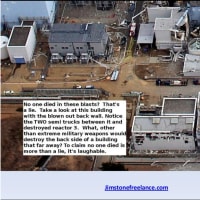
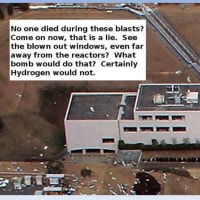
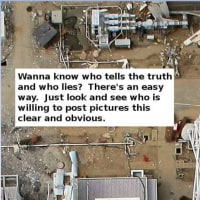
最も使われているGMOはモンサント社が開発した除草剤ラウンドアップに耐性のあるラウンドアップ耐性(Roundup Ready)のものだそうですが、このラウンドアップは土壌の有機成分を破壊してしまうと警告する研究もあり、実際に遺伝子組み換えの集中耕作地域での土壌崩壊問題が問題になりつつあるそうです。その他健康被害については2015年3月20日、国連WHOの外部研究機関国際ガン研究組織(IARC)はラウンドアップを「おそらく発ガン性がある物質」(2A)というグループに分類しています。
日本はずっと全頭検査をしてきたのですから国民の安心・安全のためには輸入条件の緩和に疑問を感じました。
狂牛病と疑われるものは輸入すべきではないと思います。
現実には業者が安全性を確保するために北米から輸入せずタスマニアンやオージービーフに代えたと思います。
ただ、原産地表示がない加工肉には注意が必要です。
遺伝子組み換え作物についても、安心・安全を脅かす点ではBSEと同じ状況ですね。
BSEと同様に米国の圧力に負けて政府としては受け入れる形をとることになるかもしれません。しかし、消費者は遺伝子組み換え作物を購入しませんし、取り扱えば一斉に非難されて商売が成り立ちませんから、業者は遺伝子組み換え作物を取り扱わないでしょう。
これについては、やや楽観的です。
やはり加工品は注意が必要ですね。
ところで遺伝子組み換え作物を使用していないとしていたものの、随分あとになって実は一部混入していたという話が大手食品メーカーから出る恐れはぬぐい切れません。