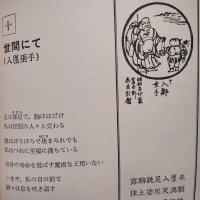2
それから十日ばかりたちました。おみなえしはびっくりしたように叫びました。
「ベゴさん。とうとう、あなたも、かんむりをかぶりましたよ。つまり、あなたの上の苔がみな赤ずきんをかぶりました。おめでとう。」
ベゴ石は、にが笑いをしながら、なにげなく云いました。
「ありがとう。しかしその赤頭巾は、苔のかんむりでしょう。私のではありません。私の冠は、今に野原いちめん、銀色にやって来ます。」
このことばが、もうおみなえしのきもを、つぶしてしまいました。
「それは雪でしょう。大へんだ。大へんだ。」
ベゴ石も気がついて、おどろいておみなえしをなぐさめました。
「おみなえしさん。ごめんなさい。雪が来て、あなたはいやでしょうが、毎年のことで仕方もないのです。その代り、来年雪が消えたら、きっとすぐ又いらっしゃい。」
おみなえしは、もう、へんじをしませんでした。又その次の日のことでした。蚊が一疋くうんくうんとうなってやって来ました。
「どうも、この野原には、むだなものが沢山あっていかんな。たとえば、このベゴ石のようなものだ。ベゴ石のごときは、何のやくにもたたない。むぐらのようにつちをほって、空気をしんせんにするということもしない。草っぱのように露をきらめかして、われわれの目の病をなおすということもない。くううん。くううん。」と云いながら、又向うへ飛んで行きました。
ベゴ石の上の苔は、前からいろいろ悪口を聞いていましたが、ことに、今の蚊の悪口を聞いて、いよいよベゴ石を、馬鹿にしはじめました。
そして、赤い小さな頭巾をかぶったまま、踊りはじめました。
「ベゴ黒助、ベゴ黒助、
黒助どんどん、
あめがふっても黒助、どんどん、
日が照っても、黒助どんどん。
ベゴ黒助、ベゴ黒助、
黒助どんどん、
千年たっても、黒助どんどん、
万年たっても、黒助どんどん。」
ベゴ石は笑いながら、
「うまいよ。なかなかうまいよ。しかしその歌は、僕はかまわないけれど、お前たちには、よくないことになるかも知れないよ。僕が一つ作ってやろう。これからは、そっちをおやり。ね、そら、
お空。お空。お空のちちは、
つめたい雨の ザァザザザ、
かしわのしずくトンテントン、
まっしろきりのポッシャントン。
お空。お空。お空のひかり、
おてんとさまは、カンカンカン、
月のあかりは、ツンツンツン、
ほしのひかりの、ピッカリコ。」
「そんなものだめだ。面白くもなんともないや。」
「そうか。僕は、こんなこと、まずいからね。」
ベゴ石は、しずかに口をつぐみました。
そこで、野原中のものは、みんな口をそろえて、ベゴ石をあざけりました。
「なんだ。あんな、ちっぽけな赤頭巾に、ベゴ石め、へこまされてるんだ。もうおいらは、あいつとは絶交だ。みっともない。黒助め。黒助、どんどん。ベゴどんどん。」
その時、向うから、めがねをかけた、せいの高い立派な四人の人たちが、いろいろなピカピカする器械をもって、野原をよこぎって来ました。その中の一人が、ふとベゴ石を見て云いました。
「あ、あった、あった。すてきだ。実にいい標本だね。火山弾の典型だ。こんなととのったのは、はじめて見たぜ。あの帯の、きちんとしてることね。もうこれだけでも今度の旅行は沢山だよ。」
「うん。実によくととのってるね。こんな立派な火山弾は、大英博物館にだってないぜ。」
みんなは器械を草の上に置いて、ベゴ石をまわってさすったりなでたりしました。
「どこの標本でも、この帯の完全なのはないよ。どうだい。空でぐるぐるやった時の工合が、実によくわかるじゃないか。すてき、すてき。今日すぐ持って行こう。」
みんなは、又、向うの方へ行きました。稜のある石は、だまってため息ばかりついています。そして気のいい火山弾は、だまってわらって居りました。
ひるすぎ、野原の向うから、又キラキラめがねや器械が光って、さっきの四人の学者と、村の人たちと、一台の荷馬車がやって参りました。
そして、柏の木の下にとまりました。
「さあ、大切な標本だから、こわさないようにして呉れ給え。よく包んで呉れ給え。苔なんかむしってしまおう。」
苔は、むしられて泣きました。火山弾はからだを、ていねいに、きれいな藁や、むしろに包まれながら、云いました。
「みなさん。ながながお世話でした。苔さん。さよなら。さっきの歌を、あとで一ぺんでも、うたって下さい。私の行くところは、ここのように明るい楽しいところではありません。けれども、私共は、みんな、自分でできることをしなければなりません。さよなら。みなさん。」
「東京帝国大学校地質学教室行、」と書いた大きな札がつけられました。
そして、みんなは、「よいしょ。よいしょ。」と云いながら包みを、荷馬車へのせました。
「さあ、よし、行こう。」
馬はプルルルと鼻を一つ鳴らして、青い青い向うの野原の方へ、歩き出しました。
・<賢治童話>いかがでしたか。周囲から馬鹿扱いされていた気のいい火山弾ですが、最終的には、東京帝国大学校地質学教室行となりました。まわりの角のある火山弾たちにとっては、いい意味でも悪い意味でも、晴天の霹靂の話だったでしょうか。
気のいい火山弾にとって、死火山のすそ野のかしはの木のかげの自然のなかにいたほうが気が楽だったかとも思ったりするのですが、いい標本として評価されたことは、それはそれとして良かったのではと思う私です・・・・。