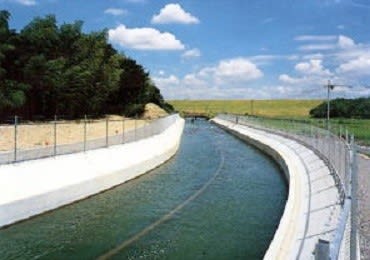旅行先で、実り豊かな水田地帯を目にすることも少なくないと思います。稲穂がどこまでも続く風景は、農村らしいものですが、昔は、水利の便が悪く、畑地や荒れ地になっていたところも少なくなかったのです。そんな土地に水を引いて、水田とすることは、なかなか大変なことで、大規模な灌漑設備を必要としたところも少なくありません。
従って、昔から疎水と呼ばれてきた用水路を苦労して掘削してきた先人たちの功績があって、初めて現在のような水田地帯が形成されたと言っても過言ではないと思います。
そんな中で、農林水産省が関わって、「疏水百選」というのが選定されているのをご存知でしょうか。日本各地にある昔から現代に至るまでに造られてきた、いろいろな疏水(用水)が選ばれていて、なかなか興味深いものです。中には、歴史的価値が認められて、史跡や重要文化財、近代化産業遺産等に選定されている施設も含まれていますので、旅先で立ち寄ってみることをお勧めします。
〇「疏水百選」とは?
疏水は、灌漑・給水・発電などのために、新しく土地を切り開いてつくった水路のことですが、農林水産省と「疏水百選」実施事務局が合同で、2006年(平成18)2月3日に「疏水百選」を決定しました。
これは、全国からの22万票を超える投票を経て、農業・地域振興、歴史・文化・伝統、環境・景観、地域コミュニティの形成といった4つの視点での評価によって選ばれたものです。
日本の農業を支えてきた代表的な用水を選定して、用水によりもたらされる“水・土・里”(みどり)を次世代に伝え、日本伝統の景観として美しい疏水の価値を見直し、その保全を推し進める目的でした。
☆「疏水百選」のお勧め
(1)安積疏水(福島県)
猪苗代湖より取水し、郡山盆地の農業用水・工業用水・上水道に利用され、水力発電にも使用される灌漑用水路です。国家事業として郡山盆地の台地に士族授産と疎水の開削を計画し、明治時代前期の1878年(明治11)にオランダ人の技師ファン・ドールンに設計させ、翌年に国直轄の農業水利事業第1号地区として起工、3年後の1882年(明治15)に完成しました。この工事には、延べ85万人が動員され、総工費40万7千円をかけ、127kmに及ぶ水路を造ったのです。これによって、約9,000haを灌漑して水田面積が増大し、郡山盆地を穀倉地帯に変身させました。1898年(明治31)には、水力発電所が設置され、その電力を利用した製糸業が発達し、1908年(明治41)からは上水道としても利用されます。その後、1951年(昭和26)には、郡山盆地南部を灌漑する新安積疏水が完成しましたが、新疏水路は旧疏水路より一段高位置を流れるようにされました。猪苗代湖周辺の十六橋水門、山潟水門、上戸頭首工、沼上隧道、沼上発電所などを見学すると当時の疎水建設の様子を伺うことが可能ですし、「開成館」(福島県郡山市)に詳しい展示もあります。
(2)見沼代用水(埼玉県)
利根大堰(現在の埼玉県行田市)により利根川から取水し、埼玉県東部から南部の水田地帯を流れる関東平野最大の灌漑用水です。江戸時代中期の1728年(享保13)に、新田開発のために干拓された見沼溜井に代わる用水として、幕府の役人であった井沢弥惣兵衛為永によって掘削されました。幹線水路延長84kmあり、最初は、現在の行田市下中条付近の利根川右岸に取水口をつくり、伏越(サイホンの仕組みの立体交差)で元荒川、綾瀬川と交差し、上尾市瓦葺で東縁用水、西縁用水に分かれていましたが、下流には、その2つを繋ぐ、2段の閘門式の見沼通船堀(国指定史跡)を設け水運にも利用されていたのです。しかし、1968年(昭和43)4月に利根大堰ができてから、旧取水口は閉鎖され、大堰から毎秒45トンの水を供給するようになりました。灌漑面積は1万7000haあり、埼玉県・東京都の葛西用水路、愛知県の明治用水とならび、日本三大農業用水と称されています。
(3)明治用水(愛知県)
矢作川中流にある現在の豊田市今地区から取水し、西三河地方南西部に灌漑用、工業用の水を供給する用水です。豊田市南部で刈谷市へ延びる西井筋を分流し、安城市北部で高浜市,碧南市へ延びる中井筋と西尾市へ向かう東井筋に分かれて碧海台地に至り、幹線水路延長52km、支線水路延長320km、灌漑面積は約1万haで、1975年(昭和50)からは工業用水にも利用されるようになりました。江戸時代後期の1827年(文政10)に、碧海郡和泉村(現,安城市)の酒造家都築弥厚が用水計画を江戸幕府へ出願したのが始まりで、民間資本を元に1879年(明治12)に本流の工事が開始され、1890年(明治23)には完成式典が挙行されます。水に困っていた碧海台地を潤し、みごとな穀倉地帯に変貌させ、大正時代末から昭和時代初期には、「日本のデンマーク」とも呼ばれる多角的農業地域に発展しました。尚、埼玉県・東京都の葛西用水路、埼玉県の見沼代用水とならび、日本三大農業用水と称されています。
(4)愛知用水(愛知県)
愛知用水は、木曾川上流御嶽山麓に建設した牧尾ダム(1961年完成)を水源とし、岐阜県南部の木曽川の兼山取水口から取水し、愛知県の尾張丘陵部から知多半島の先端に及ぶ用水路で、幹線水路(112km)と、幹線水路から分岐して農業用の水を導く支線水路(1,012km)からなります。干ばつに悩まされてきた丘陵地の多い知多半島に引水するという目的で、1951年(昭和26)に、農林省直轄調査事業となり、1955年(昭和30)には愛知用水公団が設けられて、1957年(昭和32)に着工し、1961年(昭和36)9月30日に完成しましたが、総事業費423億円かかりました。工業用水は同年12月から、上水道は翌年1月から、農業用水は翌年10月から通水します。1968年(昭和43)に愛知用水公団は水資源開発公団に統合され、2003年(平成15)10月から独立行政法人水資源機構に管理が引き継がれました。その間、1981年度から2004年度(平成16)まで、水需要量の増大に対応するため、阿木川ダム、味噌川ダムの建設や諸設備の拡充などの第二期事業が行われています。当初は農業用水が主でしたが、現在では、上水道・工業用水・農業用水・水力発電に利用する多目的用水となり、2010年(平成22)には工業用水54%、農業用水20%、上水道用水26%で、工業用水が過半を占めるようになっています。
(5)琵琶湖疏水(滋賀県・京都府)
琵琶湖の南岸(現在の滋賀県大津市三保ヶ崎)から取水し、長等山などをトンネルで抜け、京都市内へ通じる水路で、舟運、発電、上水道、灌漑を目的としてつくられました。田辺朔郎の設計、施工により、1885年(明治18)に工事が始まり、1890年(明治23)に大津から鴨川までの第一疏水(全長17.7km、幅6.4~11.5m、水深1.7m)が完成します。続いて、鴨川から宇治川までの鴨川運河は、1892年(明治25)に工事が始まり、1895年(明治28)に完成しました。さらに、第一疏水の北側に並行し、全水路がトンネル内を走る第二疏水(全長7.4km,幅4m,水深3.1m)が、1908年(明治41)に着工し、1912年(明治45)に完成し、蹴上で第1疏水と合流するようになります。これらの開削工事は、西欧の近代的土木技術を取得した日本人技師による大規模な土木工事であり、明治時代における日本の土木技術水準の高さを示すものでした。そこで、1996年(平成8)に第一疎水の第一・第二・第三隧道の出入り口、第一竪坑、第二竪坑、日本初の鉄筋コンクリート橋、インクライン、疎水分線の水路閣などが国の史跡に指定されたのです。
(6)通潤用水(熊本県)
熊本県上益城郡山都町にあり、笹原川から取水(上井手)と五老ヶ滝川から取水(下井手)し、白糸台地へ通水する灌漑用水です。江戸時代後期の1854年(安政元)に、水不足に悩まされていた白糸台地の村々の要望を受け、矢部手永惣庄屋であった布田保之助が中心となって建設されました。その上井手水路の途中、五老ヶ滝川の谷に架けられた石造水路橋である通潤橋(橋長は78m、幅員は6.3m、高さは20m余、アーチ支間は28m)は、日本最大の石造アーチ水路橋です。この橋は、日本固有の技術が集大成されたものとして評価され、1960年(昭和35)に、国の重要文化財の指定を受けました。農閑期には観光客用に時間を区切って20分程度の大規模な放水を行っていて、観光名所となっています。2008年(平成20)に、「通潤用水と白糸台地の棚田景観」の名称で国の重要文化的景観として選定されていますし、2014年(平成26)、その歴史的背景が評価され国際かんがい排水委員会によるかんがい施設遺産に登録されました。
☆「疏水百選」一覧
<北海道>
・北海幹線用水 (北海道)
・旭川聖台用水 (北海道)
・篠津中央篠津運河用水 (北海道)
<東北>
・稲生川用水 (青森県)
・土淵堰 (青森県)
・岩木川右岸用水 (青森県)
・照井堰用水 (岩手県)
・鹿妻穴堰 (岩手県)
・胆沢平野 (岩手県)
・大堰用水路・立花頭首工 (岩手県)
・奥寺堰 (岩手県)
・愛宕堰 (宮城県)
・大堰(内川) (宮城県)
・上郷温水路群 (秋田県)
・田沢疏水 (秋田県)
・寒河江川用水[二の堰・高松堰] (山形県)
・北楯大堰 (山形県)
・金山大堰 (山形県)
・山形五堰 (山形県)
・安積疏水 (福島県)
・会津大川用水 (福島県)
<関東>
・備前堀用水 (茨城県)
・福岡堰 (茨城県)
・那須野ヶ原用水 (栃木県)
・おだきさん (栃木県)
・渡良瀬川沿岸 (群馬県)
・広瀬用水[広瀬川] (群馬県)
・雄川堰 (群馬県)
・長野堰用水 (群馬県)
・群馬用水 (群馬県)
・見沼代用水 (埼玉県)
・葛西用水 (埼玉県)
・備前渠用水 (埼玉県)
・印旛沼 (千葉県)
・大利根用水 (千葉県)
・両総用水 (千葉県)
・府中用水 (東京都)
・荻窪用水 (神奈川県)
・文命用水 (神奈川県)
・村山六ヶ村堰疏水 (山梨県)
・差出堰 (山梨県)
<中部>
・加治川用水 (新潟県)
・亀田郷 (新潟県)
・十二貫野用水 (富山県)
・常西合口用水 (富山県)
・鷹栖口用水(砺波平野疏水群) (富山県)
・舟倉用水 (富山県)
・辰巳用水 (石川県)
・金沢疏水群[大野庄用水・鞍月用水・長坂用水] (石川県)
・手取川疏水群[手取川七ヶ用水・宮竹用水] (石川県)
・九頭竜川下流 (福井県)
・足羽川用水 (福井県)
・五郎兵衛用水 (長野県)
・塩沢堰 (長野県)
・八ヶ郷用水 (長野県)
・善光寺平用水 (長野県)
・拾ヶ堰 (長野県)
・瀬戸川用水 (岐阜県)
・席田用水 (岐阜県)
・大井川用水[大井川用水・大井川右岸用水] (静岡県)
・源兵衛川 (静岡県)
・深良用水 (静岡県)
・愛知用水 (愛知県)
・豊川用水 (愛知県)
・明治用水 (愛知県)
・濃尾用水 (愛知県)
・枝下用水 (愛知県)
・立梅用水 (三重県)
・南家城川口井水 (三重県)
<近畿>
・愛知川用水 (滋賀県)
・野洲川流域 (滋賀県)
・犬上川沿岸 (滋賀県)
・湖北用水 (滋賀県)
・洛西用水 (京都府)
・琵琶湖疏水 (京都府)
・大和川分水[築留掛かり] (大阪府)
・東播用水 (兵庫県)
・淡山疏水[淡河川疏水・山田川疏水] (兵庫県)
・東条川用水 (兵庫県)
・大和平野 (奈良県)
・小田井用水 (和歌山県)
<中国>
・大井手用水 (鳥取県)
・天川疏水 (島根県)
・高瀬川 (島根県)
・東西用水[高梁川・笠井堰掛] (岡山県)
・西川用水 (岡山県)
・芦田川用水 (広島県)
・寝太郎堰(寝太郎用水) (山口県)
・藍場川(大溝) (山口県)
<四国>
・那賀川用水 (徳島県)
・香川用水 (香川県)
・銅山川疏水 (愛媛県)
・道前道後用水 (愛媛県)
・山田堰井筋 (高知県)
<九州・沖縄>
・大石用水 (福岡県)
・裂田の溝 (福岡県)
・堀川用水 (福岡県)
・柳川の堀割 (福岡県)
・大井手堰[石井樋~多布施川] (佐賀県)
・小野用水 (長崎県)
・上井手用水 (熊本県)
・幸野溝・百太郎溝 (熊本県)
・南阿蘇村疏水群 (熊本県)
・通潤用水 (熊本県)
・緒方疏水 (大分県)
・城原井路[神田頭首工] (大分県)
・杉安堰 (宮崎県)
・清水篠井手用水 (鹿児島県)
・筒羽野の疏水 (鹿児島県)
・宮古用水 (沖縄県)
従って、昔から疎水と呼ばれてきた用水路を苦労して掘削してきた先人たちの功績があって、初めて現在のような水田地帯が形成されたと言っても過言ではないと思います。
そんな中で、農林水産省が関わって、「疏水百選」というのが選定されているのをご存知でしょうか。日本各地にある昔から現代に至るまでに造られてきた、いろいろな疏水(用水)が選ばれていて、なかなか興味深いものです。中には、歴史的価値が認められて、史跡や重要文化財、近代化産業遺産等に選定されている施設も含まれていますので、旅先で立ち寄ってみることをお勧めします。
〇「疏水百選」とは?
疏水は、灌漑・給水・発電などのために、新しく土地を切り開いてつくった水路のことですが、農林水産省と「疏水百選」実施事務局が合同で、2006年(平成18)2月3日に「疏水百選」を決定しました。
これは、全国からの22万票を超える投票を経て、農業・地域振興、歴史・文化・伝統、環境・景観、地域コミュニティの形成といった4つの視点での評価によって選ばれたものです。
日本の農業を支えてきた代表的な用水を選定して、用水によりもたらされる“水・土・里”(みどり)を次世代に伝え、日本伝統の景観として美しい疏水の価値を見直し、その保全を推し進める目的でした。
☆「疏水百選」のお勧め
(1)安積疏水(福島県)
猪苗代湖より取水し、郡山盆地の農業用水・工業用水・上水道に利用され、水力発電にも使用される灌漑用水路です。国家事業として郡山盆地の台地に士族授産と疎水の開削を計画し、明治時代前期の1878年(明治11)にオランダ人の技師ファン・ドールンに設計させ、翌年に国直轄の農業水利事業第1号地区として起工、3年後の1882年(明治15)に完成しました。この工事には、延べ85万人が動員され、総工費40万7千円をかけ、127kmに及ぶ水路を造ったのです。これによって、約9,000haを灌漑して水田面積が増大し、郡山盆地を穀倉地帯に変身させました。1898年(明治31)には、水力発電所が設置され、その電力を利用した製糸業が発達し、1908年(明治41)からは上水道としても利用されます。その後、1951年(昭和26)には、郡山盆地南部を灌漑する新安積疏水が完成しましたが、新疏水路は旧疏水路より一段高位置を流れるようにされました。猪苗代湖周辺の十六橋水門、山潟水門、上戸頭首工、沼上隧道、沼上発電所などを見学すると当時の疎水建設の様子を伺うことが可能ですし、「開成館」(福島県郡山市)に詳しい展示もあります。
(2)見沼代用水(埼玉県)
利根大堰(現在の埼玉県行田市)により利根川から取水し、埼玉県東部から南部の水田地帯を流れる関東平野最大の灌漑用水です。江戸時代中期の1728年(享保13)に、新田開発のために干拓された見沼溜井に代わる用水として、幕府の役人であった井沢弥惣兵衛為永によって掘削されました。幹線水路延長84kmあり、最初は、現在の行田市下中条付近の利根川右岸に取水口をつくり、伏越(サイホンの仕組みの立体交差)で元荒川、綾瀬川と交差し、上尾市瓦葺で東縁用水、西縁用水に分かれていましたが、下流には、その2つを繋ぐ、2段の閘門式の見沼通船堀(国指定史跡)を設け水運にも利用されていたのです。しかし、1968年(昭和43)4月に利根大堰ができてから、旧取水口は閉鎖され、大堰から毎秒45トンの水を供給するようになりました。灌漑面積は1万7000haあり、埼玉県・東京都の葛西用水路、愛知県の明治用水とならび、日本三大農業用水と称されています。
(3)明治用水(愛知県)
矢作川中流にある現在の豊田市今地区から取水し、西三河地方南西部に灌漑用、工業用の水を供給する用水です。豊田市南部で刈谷市へ延びる西井筋を分流し、安城市北部で高浜市,碧南市へ延びる中井筋と西尾市へ向かう東井筋に分かれて碧海台地に至り、幹線水路延長52km、支線水路延長320km、灌漑面積は約1万haで、1975年(昭和50)からは工業用水にも利用されるようになりました。江戸時代後期の1827年(文政10)に、碧海郡和泉村(現,安城市)の酒造家都築弥厚が用水計画を江戸幕府へ出願したのが始まりで、民間資本を元に1879年(明治12)に本流の工事が開始され、1890年(明治23)には完成式典が挙行されます。水に困っていた碧海台地を潤し、みごとな穀倉地帯に変貌させ、大正時代末から昭和時代初期には、「日本のデンマーク」とも呼ばれる多角的農業地域に発展しました。尚、埼玉県・東京都の葛西用水路、埼玉県の見沼代用水とならび、日本三大農業用水と称されています。
(4)愛知用水(愛知県)
愛知用水は、木曾川上流御嶽山麓に建設した牧尾ダム(1961年完成)を水源とし、岐阜県南部の木曽川の兼山取水口から取水し、愛知県の尾張丘陵部から知多半島の先端に及ぶ用水路で、幹線水路(112km)と、幹線水路から分岐して農業用の水を導く支線水路(1,012km)からなります。干ばつに悩まされてきた丘陵地の多い知多半島に引水するという目的で、1951年(昭和26)に、農林省直轄調査事業となり、1955年(昭和30)には愛知用水公団が設けられて、1957年(昭和32)に着工し、1961年(昭和36)9月30日に完成しましたが、総事業費423億円かかりました。工業用水は同年12月から、上水道は翌年1月から、農業用水は翌年10月から通水します。1968年(昭和43)に愛知用水公団は水資源開発公団に統合され、2003年(平成15)10月から独立行政法人水資源機構に管理が引き継がれました。その間、1981年度から2004年度(平成16)まで、水需要量の増大に対応するため、阿木川ダム、味噌川ダムの建設や諸設備の拡充などの第二期事業が行われています。当初は農業用水が主でしたが、現在では、上水道・工業用水・農業用水・水力発電に利用する多目的用水となり、2010年(平成22)には工業用水54%、農業用水20%、上水道用水26%で、工業用水が過半を占めるようになっています。
(5)琵琶湖疏水(滋賀県・京都府)
琵琶湖の南岸(現在の滋賀県大津市三保ヶ崎)から取水し、長等山などをトンネルで抜け、京都市内へ通じる水路で、舟運、発電、上水道、灌漑を目的としてつくられました。田辺朔郎の設計、施工により、1885年(明治18)に工事が始まり、1890年(明治23)に大津から鴨川までの第一疏水(全長17.7km、幅6.4~11.5m、水深1.7m)が完成します。続いて、鴨川から宇治川までの鴨川運河は、1892年(明治25)に工事が始まり、1895年(明治28)に完成しました。さらに、第一疏水の北側に並行し、全水路がトンネル内を走る第二疏水(全長7.4km,幅4m,水深3.1m)が、1908年(明治41)に着工し、1912年(明治45)に完成し、蹴上で第1疏水と合流するようになります。これらの開削工事は、西欧の近代的土木技術を取得した日本人技師による大規模な土木工事であり、明治時代における日本の土木技術水準の高さを示すものでした。そこで、1996年(平成8)に第一疎水の第一・第二・第三隧道の出入り口、第一竪坑、第二竪坑、日本初の鉄筋コンクリート橋、インクライン、疎水分線の水路閣などが国の史跡に指定されたのです。
(6)通潤用水(熊本県)
熊本県上益城郡山都町にあり、笹原川から取水(上井手)と五老ヶ滝川から取水(下井手)し、白糸台地へ通水する灌漑用水です。江戸時代後期の1854年(安政元)に、水不足に悩まされていた白糸台地の村々の要望を受け、矢部手永惣庄屋であった布田保之助が中心となって建設されました。その上井手水路の途中、五老ヶ滝川の谷に架けられた石造水路橋である通潤橋(橋長は78m、幅員は6.3m、高さは20m余、アーチ支間は28m)は、日本最大の石造アーチ水路橋です。この橋は、日本固有の技術が集大成されたものとして評価され、1960年(昭和35)に、国の重要文化財の指定を受けました。農閑期には観光客用に時間を区切って20分程度の大規模な放水を行っていて、観光名所となっています。2008年(平成20)に、「通潤用水と白糸台地の棚田景観」の名称で国の重要文化的景観として選定されていますし、2014年(平成26)、その歴史的背景が評価され国際かんがい排水委員会によるかんがい施設遺産に登録されました。
☆「疏水百選」一覧
<北海道>
・北海幹線用水 (北海道)
・旭川聖台用水 (北海道)
・篠津中央篠津運河用水 (北海道)
<東北>
・稲生川用水 (青森県)
・土淵堰 (青森県)
・岩木川右岸用水 (青森県)
・照井堰用水 (岩手県)
・鹿妻穴堰 (岩手県)
・胆沢平野 (岩手県)
・大堰用水路・立花頭首工 (岩手県)
・奥寺堰 (岩手県)
・愛宕堰 (宮城県)
・大堰(内川) (宮城県)
・上郷温水路群 (秋田県)
・田沢疏水 (秋田県)
・寒河江川用水[二の堰・高松堰] (山形県)
・北楯大堰 (山形県)
・金山大堰 (山形県)
・山形五堰 (山形県)
・安積疏水 (福島県)
・会津大川用水 (福島県)
<関東>
・備前堀用水 (茨城県)
・福岡堰 (茨城県)
・那須野ヶ原用水 (栃木県)
・おだきさん (栃木県)
・渡良瀬川沿岸 (群馬県)
・広瀬用水[広瀬川] (群馬県)
・雄川堰 (群馬県)
・長野堰用水 (群馬県)
・群馬用水 (群馬県)
・見沼代用水 (埼玉県)
・葛西用水 (埼玉県)
・備前渠用水 (埼玉県)
・印旛沼 (千葉県)
・大利根用水 (千葉県)
・両総用水 (千葉県)
・府中用水 (東京都)
・荻窪用水 (神奈川県)
・文命用水 (神奈川県)
・村山六ヶ村堰疏水 (山梨県)
・差出堰 (山梨県)
<中部>
・加治川用水 (新潟県)
・亀田郷 (新潟県)
・十二貫野用水 (富山県)
・常西合口用水 (富山県)
・鷹栖口用水(砺波平野疏水群) (富山県)
・舟倉用水 (富山県)
・辰巳用水 (石川県)
・金沢疏水群[大野庄用水・鞍月用水・長坂用水] (石川県)
・手取川疏水群[手取川七ヶ用水・宮竹用水] (石川県)
・九頭竜川下流 (福井県)
・足羽川用水 (福井県)
・五郎兵衛用水 (長野県)
・塩沢堰 (長野県)
・八ヶ郷用水 (長野県)
・善光寺平用水 (長野県)
・拾ヶ堰 (長野県)
・瀬戸川用水 (岐阜県)
・席田用水 (岐阜県)
・大井川用水[大井川用水・大井川右岸用水] (静岡県)
・源兵衛川 (静岡県)
・深良用水 (静岡県)
・愛知用水 (愛知県)
・豊川用水 (愛知県)
・明治用水 (愛知県)
・濃尾用水 (愛知県)
・枝下用水 (愛知県)
・立梅用水 (三重県)
・南家城川口井水 (三重県)
<近畿>
・愛知川用水 (滋賀県)
・野洲川流域 (滋賀県)
・犬上川沿岸 (滋賀県)
・湖北用水 (滋賀県)
・洛西用水 (京都府)
・琵琶湖疏水 (京都府)
・大和川分水[築留掛かり] (大阪府)
・東播用水 (兵庫県)
・淡山疏水[淡河川疏水・山田川疏水] (兵庫県)
・東条川用水 (兵庫県)
・大和平野 (奈良県)
・小田井用水 (和歌山県)
<中国>
・大井手用水 (鳥取県)
・天川疏水 (島根県)
・高瀬川 (島根県)
・東西用水[高梁川・笠井堰掛] (岡山県)
・西川用水 (岡山県)
・芦田川用水 (広島県)
・寝太郎堰(寝太郎用水) (山口県)
・藍場川(大溝) (山口県)
<四国>
・那賀川用水 (徳島県)
・香川用水 (香川県)
・銅山川疏水 (愛媛県)
・道前道後用水 (愛媛県)
・山田堰井筋 (高知県)
<九州・沖縄>
・大石用水 (福岡県)
・裂田の溝 (福岡県)
・堀川用水 (福岡県)
・柳川の堀割 (福岡県)
・大井手堰[石井樋~多布施川] (佐賀県)
・小野用水 (長崎県)
・上井手用水 (熊本県)
・幸野溝・百太郎溝 (熊本県)
・南阿蘇村疏水群 (熊本県)
・通潤用水 (熊本県)
・緒方疏水 (大分県)
・城原井路[神田頭首工] (大分県)
・杉安堰 (宮崎県)
・清水篠井手用水 (鹿児島県)
・筒羽野の疏水 (鹿児島県)
・宮古用水 (沖縄県)