
昔、親父が存命の頃、貰った品物ばかりで
自分の時代になっても使ったことはない。

朝鮮唐津の徳利と箱書き。
ズシッと重量感のある焼物
日本の唐津とは趣きが異なる。

この盃も日本のものではないように思う。
もう30年も以前に韓国へ行った時に
買い求めた盃とよく似た染付けの模様。
やや、ぼってりとした釉薬が掛かっている。

草の葉徳利は河合卯之助師の手に成るものだが
上の盃でぬるい燗酒を飲むのが夏には合ってるようにも思う。
徳利の口の部分のフレアーと金継ぎが一種の景色となっている。
優しい徳利であり、やはり最初の徳利のような獰猛さとは無縁だ。
:
昔の人たちは暑い夏でもビールなんての
まだ無い時代には
お酒を呑んでたんだよな。
:
近頃、何かの記事で読んだが日本酒で乾杯をする条例を作る自治体が
増えているとか・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それにしても趣味などというものは
誠にその人間一代限りのもので
なかなか親から子へと引き継いでいくのは難しい時代になってきた。
特に核家族だなどと言って世帯が遠く離れてバラバラに暮らす今は
それが益々困難であるように思う。
日本の文化の継承もそんなところから崩壊していく。
ナツメや酒器を眺めてるうちに
しんみりしてきた。












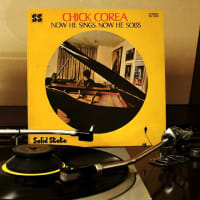







私は幼い頃、祖父母と寝ていたりもしましたので、いろんなことを教えてもらいました。
ウナギカゴのつけかたは、祖父と夕方に川に入り、じっくり丁寧に何度も教えてもらったものです。
私は、盆、正月は、必ず家族で帰省しますが、その一番の目的は、顔をあわせることも重要ですが、実家に受け継がれるさまざまなことを、妻、子供に体験させ、そして、私自身も再確認するためだったりします。
なぜ、お盆過ぎてから川に行くとカッパが出やすいのか?
精霊流しの舟が川に沈んでいて、それに足をとられやすいことを子供に暗に教えることであったり。
地方、家ごとに、いろんなあるでしょうが、こういうことは、繋いでいって欲しいものです。
久しいように思います。
限界集落などの文化は崩落の一途です。
東京一極集中に見られる我が国の経済効率最重視が
新たな文化を生み出す陰で、こうした伝統的な文化は
衰退して行きます。
それが言語にもおよび、いずれは顔付き、体付きまで変化していくのでしょう。
まさに文化とはその国の生き様を表すものと言って過言ではありません。
政治も国民の精神的在り様を色濃く反映したものとなります。
仕方が無いと言えなくもありませんが、なんとか歯止めをしたいものです。
ところで、OH9120-・・・・これ何でしょうか?