
コンピュータが打つ手は、
あらゆる局面で囲碁というゲームの目標である「より広い土地を囲うには?」
という評価関数を計算して
着点を想定し
しかるのちにその手に続く相手の手を予測して
シミュレーションを行う。
そうしておいてから着点を決める。
ま~そういったプロセスを繰り返してるように見えます。
この一点においては
まことに正しい判断であり
人間から見ると囲碁の神様が打つ手のようにも思えました。
でも、非常に繊細な部分のヨミということになると
かなり下手なところがあって人間に虚を突かれることもあります。
この点では神の手とはとても思えない部分も残されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一方、人間には囲碁4000年の歴史から学んだ直感的な
感覚に基づく土地争いへの対処法があります。
いわば師匠から教え込まれた感覚と常識であり
こういう局面では、こう打つ手しか無い!
とするもので、それが囲碁の目標「土地の面積争い」にどれだけ
寄与するのか?を数値的には表しえないものです。
これに基づく着手では評価関数の計算などは一切ありませんから
正確さではAIに遥かに及びませんでした。
つまり
これまで常識とされてきた着手が様々な場面で疑わしいのでは?
と思われる結果を招きました。
これは人間棋士たちにとっては凄い勉強になったに違いありません。
人間側が挙げた貴重な1勝は
まさに上記のAIの盲点を突いたものでした。
おそらく歴史に残るであろう妙手を人間が放ったときに
AIが異様な動作をし始めて悪手を連発した結果によります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
対戦のプロセスが公平でないと言ったのは
コンピュータには疲れといったものや
感情移入などは皆無です。
7日間で真剣勝負を5局打つことが
人間にとってどれほど大変か。
棋士は一局打つと体重が数キロ減るとも言われています。
しかも敗戦の夜は頭の中の碁盤で敗因を探る作業が
延々と続いて眠れないとも言われます。
もし、対局スケジュールが1週間に1局というもので
あったなら・・・と思わずには居られません。
また、対局の持ち時間が人間もコンピュータも2時間づつと
いうのも人間にとっては過酷でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
でも勝負はそういった条件を了承して行われたわけで
後からゴチャゴチャ言っても仕方ありません。
オイラ思うにAIというのは記憶したものを忘れないし
無駄な考えを次々に捨ててより良い戦略を生み出してきます。
囲碁界にとっては「辞書」みたいなものです。
おそらく将来は日本における過去400年に及ぶ
囲碁の名人達の思想も組み込まれて
いくことと思われます。
あの道策、道知、因碩、丈和、秀策、秀甫、秀栄などの
名人上手の打ち碁も取り込まれるでしょう。
そうなった結果を考えればこれはまさしく囲碁歴史Dictionaryです。
そんなものを敵視して戦うなんての
あまり意味がないでしょう。
人間の棋士が最高の状態で囲碁を打てるのは
10代後半から20代のわずか10年しかないのですから。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回の戦いを通じて
やはり人間の素晴らしさ、凄さが
一番目立ったと思います。
疲れを知らないAIを相手に
あそこまで人間らしさを発揮した
イ・セドルの素晴らしさが一番でした。
:
囲碁は何度も申し上げますように囲った土地の広さを
争うゲームですが
双方が土地争いをすれば境界線を巡って
必ず戦いが生じます。
何処へ打てば土地を広く囲うことができるか?と同時に
その結果生ずる戦いを如何に効率よく戦い抜けるか?
という二つの命題を融合して捉える能力が問われています。
そういう点では、AIはまだまだ未熟といわざるを得ません。
例えば
ビジネスへの応用を考えてもビジネスの命題である
利益を最高にするというものと
それに至る様々なコンフリクトと如何に折り合いを付けるか?
という問題を融合して考える必要に迫られるからです。
目標達成と戦略或いは戦術との高度な融合
これが求められるんでしょうね。
いずれにせよAIは面白いですねぇ。












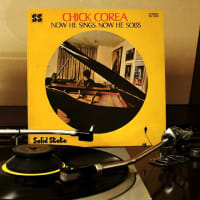







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます