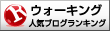苅萱道心(かるかやどうしん)と石童丸(いしどうまる)の話は、悲話として広く知られています。
このお堂は苅萱道心が出家し、実の子である石童丸とともに父子を名乗ることなく仏道修行に明けくれたと伝えられています。

石童丸物語
今から八百有余年前、筑前の守護職、加藤兵衛尉繁昌は跡継ぎがなく、香椎の宮にお祈りし、授かったのがこの物語の主人公である、
加藤左衛門繁氏でありました。

九州の筑前(福岡県)は、刈萱荘博多というところに加藤左衛門尉(かとうさえもんのじょう)藤原の繁氏(しげうじ)という若い領主がいました。
繁氏には、 桂子(かつらこ)御前という美しい妻の他に、千里(ちさと)御前という二番夫人の側室もいました。
加藤家は、こうした夫人達に囲まれて、春には華やかな花 見をもよおすほど、それはそれは優雅な暮らしぶりでした。

憎しみ
桂子と千里との間は、普段は仲良く平静をよそおっていましたが、桂子の方は、心の中で若くて美しい千里を憎んでいました。
ある夜、繁氏は、この二人が囲碁をしているのを薄明かりごしに見ることがありました。
すると、どうでしょう。二匹のヘビが絡みあって戦っているように見えるのでした。

そうこうするうちに、正室である桂子の千里に対する憎しみがあらわとなり、ついには千里殺害の計画がくわだてられます。
しかし家来の計らいにより、他人が身代わることによって千里自身の命は救われ、加藤家を逃れることになりました。

出家
嫉妬(しっと)と憎(にく)しみというものは、時として人の命をも奪い取ってしまいます。繁氏はホトホト嫌気がさしてしまいました。
この事件は繁氏自身をもひどく後悔させ、またそのことで繁氏の妻に対する心はむなしいものへと変化していきました。

やがて、繁氏は誰にも行く先を告げず高野山の安養寺円慶を頼って登山し、出家してしまいます。
その名を円空と改めました。
時に、繁氏21歳でした。
それからというもの、蓮華谷に質素な萱(かや)の屋根の庵(いおり)を結んで一心に修行にはげみ、周囲からは刈萱道心(かるかやどうしん)と呼ばれるようになりました。

父を求めて
一方、千里は加藤家より播磨の国の大山寺に逃れ、観海上人に身を寄せ、やがて男子を産みました。これが石童丸です。
繁氏が出家した折り、すでに身ごもっていたことなど繁氏自身は知る由もありません。
石童丸も大きくなった頃、高野山に刈萱道心というお坊さんがいるという噂(うわさ)が聞こえてきました。
刈萱というのは筑前の刈萱荘にちなんだ名前であることはすぐに想像がつきます。
千里と石童丸は、父、繁氏を求めて高野山へと向かいます。

学文路の宿
千里と石童丸の二人は、高野山の麓(ふもと)、学文路(かむろ)で宿をとりました。
この宿の主人、玉屋の与次兵衛から、高野山は女人禁制で女性は入山できないことを聞かされ、断念します。
それではということで、千里は、父の身体的な特徴を石童丸に伝え、独り高野山へと向かわせます。

独り高野山へ
しかし、なれない足で不動坂まで来た頃には、とっぷりと日は暮れてしまいました。
仕方なく、不動堂(外の不動・清不動)で一夜を明かすことになります。

父との巡り会い
翌日、高野山へ登った石童丸は、あちこち訪ねて歩きます。
しかしなかなか逢うことがかないません。
数日目に、たまたま奥之院の無明(むみょう)の橋まで来たときに、前から花筒を持ったお坊さんとすれ違います。
そこで石童丸は駆け寄って、「刈萱道心という方を探しています。どこにおいでかご存じありませんか?」と尋ねました。
繁氏(円空)は石童丸の身の上を聞いて、たいそう驚くことになります。

伝えられた内容とは
石童丸の話を聞いた繁氏(円空)は、自分が父であることを名乗りませんでした。

しかも、「繁氏という人物は去年の秋に亡くなった。その墓は、ちょうどそこに建っている墓である」と近くにあった適当なお墓を指し示して石童丸に伝えました。
それを聞いた石童丸は、その墓の前で泣き崩れます。

悲しみの下山
繁氏(円空)は出家した修行中で身であることから、今さら石童丸が我が子とわかっても、すでにどうすることも出来なかったのでしょう。
繁氏(円空)は石童丸に「早く母の元に帰ってあげなさい」といいます。
石童丸はしかたなく、トボトボと母の待つ学文路の宿まで帰ります。

学文路で待つ母は
石童丸が学文路の宿まで帰ってみると、なんと、母の千里はこれまでの長旅がたたったのか、発病して急に亡くなっていました。
石童丸の悲しみの程は、察しても余りがあります。しかたなく、この学文路の地で母を葬ることになります。

再び高野山へと
父とも巡り会わず、さらに母にも旅立たれ、ひとりぼっちになってしまった石童丸。
そこに思い浮かぶのは、母から聴いた父の特徴によく似た高野山で遭ったあのお坊さんの事でした。
あの方なら私の相談にのってくれるに違いないと、再び高野山を目指すことになります。
出家
そうして高野山に登った石童丸は、父繁氏(円空)の弟子となり道念と名乗りました。
しかし繁氏(円空)は、生涯、親子であることは石童丸には伝えなかったそうです。
その後30年以上、師弟として一緒に刈萱堂で修行に励んだのだそうです。

親子地蔵
その後、繁氏(円空)は信州の善光寺に赴き、御堂を構えて地蔵菩薩を刻み、建保2年(1214)に没しました。
追って石童丸(道念)も信州に移り、父と同じく地蔵菩薩を彫り上げました。
その地蔵さんは現在も、「親子地蔵」として信仰されているそうです。

この向いに親子地蔵尊が祀られています。
この刈萱堂は、繁氏と石童丸親子が修行した場所と伝えられています。

高野山 刈萱堂