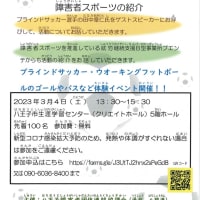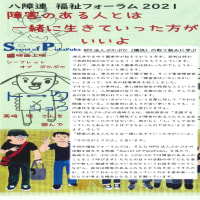八障連通信355号です。
通信号【音声版】はこちらから
ここからは通信本文です。
去る 1 月 14 日、クリエイトホールにおいて「市障害福祉課との懇談会」が開催されました。参加された八障連会員、そして市障害福祉課の皆様大変ご苦労様でした。さて、福祉課との懇談会ですが、今年もまた有意義な懇談会となったと思います。今回は参加できなかった会員の皆様にもぜひ参考にしていただきたく、懇談会の内容をすべて本誌にて掲載いたします。なお、懇談会の司会は鈴木(ハーネス八王子)・立川(わかくさ福祉会・プレワーク)が、書記は有賀(マインドはちおうじ・リサイクルわかくさ)が担当いたしました。市障害福祉
課および八障連の参加者(団体)は以下の通りです。参加者:小池・島村・土方・濱尻・加藤・遠藤・三谷・永松・宮澤(以上八王子市障害者福祉課)/安藤・小林(なみき福祉会)/堀部・酒井・山田・杉山(ほっとスペース八王子)/松井(こあらくらぶ)/百瀬(地域活動支援センターパオ)/松木(IL みなみ tama)/山本(ヒューマンケア協会)/脇田(結の会)/竹沢(八王子精神障害者ピアサポートセンター)/立川・柴田(プレワーク)/秦(ころぼっくる)/宇津木(高尾青年の家福祉会)/有賀(リサイクルわかくさ)/鈴木(八障連副代表)/杉浦(八障連代表)/順不同・敬称略
課および八障連の参加者(団体)は以下の通りです。参加者:小池・島村・土方・濱尻・加藤・遠藤・三谷・永松・宮澤(以上八王子市障害者福祉課)/安藤・小林(なみき福祉会)/堀部・酒井・山田・杉山(ほっとスペース八王子)/松井(こあらくらぶ)/百瀬(地域活動支援センターパオ)/松木(IL みなみ tama)/山本(ヒューマンケア協会)/脇田(結の会)/竹沢(八王子精神障害者ピアサポートセンター)/立川・柴田(プレワーク)/秦(ころぼっくる)/宇津木(高尾青年の家福祉会)/有賀(リサイクルわかくさ)/鈴木(八障連副代表)/杉浦(八障連代表)/順不同・敬称略
杉浦代表挨拶
お集まりいただき、ありがとうございます。この場は陳情などの場ではないですが、レジュメのテーマに沿ってかたくならずに意見交換ができればと思います。
台風 19 号の被災状況など振り返り(18:50~)
昨年の台風 19 号では南浅川の氾濫など市内でも多数の被害がおきました。福祉事業所でも高尾青年寮さんが床上浸水など被災されました。また会員団体の関係者の方々の中でも、一時避難所へ避難された方などのお話もありました。 今回は被災された高尾青年寮の方のお話も聞きつつ、今後につながるような意見交換を行えればと思います。
お集まりいただき、ありがとうございます。この場は陳情などの場ではないですが、レジュメのテーマに沿ってかたくならずに意見交換ができればと思います。
台風 19 号の被災状況など振り返り(18:50~)
昨年の台風 19 号では南浅川の氾濫など市内でも多数の被害がおきました。福祉事業所でも高尾青年寮さんが床上浸水など被災されました。また会員団体の関係者の方々の中でも、一時避難所へ避難された方などのお話もありました。 今回は被災された高尾青年寮の方のお話も聞きつつ、今後につながるような意見交換を行えればと思います。
宇津木氏(NPO 法人高尾青年の家福祉会)
今回はたくさんのご寄付をいただきありがとうございます。高尾青年寮は周りの民家から3M 低い位置に GH が設置してあり、川からも3M 離れた場所。毎年台風で残り数十センチと川の推移は上がっていたが、昨年初めて川が氾濫して被災した。建物の外側で1.4M の浸水があり、建物内は床上被災。女性 7 名の入居者がいたが、前情報があったのであらかじめ避難をしていたので入居者の人的被害はなかった。被災後、入居者は別の寮での相部屋や株式会社マイラ
イフのご協力もあり別の場所で過ごすことになった。最初の 2 週間は消毒の臭いで 2 階も使えなかった。初めの 1 週間は帰省できる方はしてもらったが、とっさに住む家がないという状況はつらいものがあった。年明けには入居者が住めるようになった。来年以降の心配がある。河川対策の優先順位では河口が被害が多いので、河川の対応はだいぶ先になる。来年については今のところ運に任せるしかない状況。避難勧告の仕方が変わったが、1次避難所についてだ、
知的障害の方と避難所へいく選択肢は様々な理由から現実的ではなかった。今後の対策として、ハザードマップにあるグループホームの入居者数や統計などあると良いと思った。
今回はたくさんのご寄付をいただきありがとうございます。高尾青年寮は周りの民家から3M 低い位置に GH が設置してあり、川からも3M 離れた場所。毎年台風で残り数十センチと川の推移は上がっていたが、昨年初めて川が氾濫して被災した。建物の外側で1.4M の浸水があり、建物内は床上被災。女性 7 名の入居者がいたが、前情報があったのであらかじめ避難をしていたので入居者の人的被害はなかった。被災後、入居者は別の寮での相部屋や株式会社マイラ
イフのご協力もあり別の場所で過ごすことになった。最初の 2 週間は消毒の臭いで 2 階も使えなかった。初めの 1 週間は帰省できる方はしてもらったが、とっさに住む家がないという状況はつらいものがあった。年明けには入居者が住めるようになった。来年以降の心配がある。河川対策の優先順位では河口が被害が多いので、河川の対応はだいぶ先になる。来年については今のところ運に任せるしかない状況。避難勧告の仕方が変わったが、1次避難所についてだ、
知的障害の方と避難所へいく選択肢は様々な理由から現実的ではなかった。今後の対策として、ハザードマップにあるグループホームの入居者数や統計などあると良いと思った。
山本氏(ヒューマンケア協会)
重度訪問介護派遣をしているが、半数以上が一人暮らしの方がいらっしゃる。どんな状況でも介護者を派遣しないといけない。被災の中をどう介護者を派遣していくか課題となる。台風 19 号の時も前情報があったので、計画運休等もあったが介護者派遣は工夫しながら乗り切れた。利用者は長沼周辺で住まわれている方が多い。
浸水が警戒される地域の単身生活者については、お昼前から水位が上がっていたので、危険度・必要度を見極めて優先順位をつけて確認をしていった。数名は一時避難所へ避難されていた。数名は危機意識がなく自宅へいらしたので、ヘルパーから避難を呼びかけるが動かれないケースもあった。夕方に避難指示がでた時点でリフト自動車でピストンして 7 名の方を事業所へ避難してもらった。翌日もお昼頃まで状況確認を行った。今回のことで、多くの方は避難所へ避難することをためらっていた。避難所で介助をつけて過ごすのは大変だと感じている。24 時間介助の方が避難所へ避難した際に、避難所に入る際にも数名の介助が必要。一番大変なのはトイレ。専用のトイレはないので皆の前で幕を張ってトイレをされた。障害の方に対応した一時避難所は急務かと感じた。避難の際の情報、避難時に何をもって出たらよいか、準備をしたらよいのかなど、今後の備えとして考えていく必要を感じた。
重度訪問介護派遣をしているが、半数以上が一人暮らしの方がいらっしゃる。どんな状況でも介護者を派遣しないといけない。被災の中をどう介護者を派遣していくか課題となる。台風 19 号の時も前情報があったので、計画運休等もあったが介護者派遣は工夫しながら乗り切れた。利用者は長沼周辺で住まわれている方が多い。
浸水が警戒される地域の単身生活者については、お昼前から水位が上がっていたので、危険度・必要度を見極めて優先順位をつけて確認をしていった。数名は一時避難所へ避難されていた。数名は危機意識がなく自宅へいらしたので、ヘルパーから避難を呼びかけるが動かれないケースもあった。夕方に避難指示がでた時点でリフト自動車でピストンして 7 名の方を事業所へ避難してもらった。翌日もお昼頃まで状況確認を行った。今回のことで、多くの方は避難所へ避難することをためらっていた。避難所で介助をつけて過ごすのは大変だと感じている。24 時間介助の方が避難所へ避難した際に、避難所に入る際にも数名の介助が必要。一番大変なのはトイレ。専用のトイレはないので皆の前で幕を張ってトイレをされた。障害の方に対応した一時避難所は急務かと感じた。避難の際の情報、避難時に何をもって出たらよいか、準備をしたらよいのかなど、今後の備えとして考えていく必要を感じた。
会場からの意見
・人工透析を受けている方は避難所でも衛生面が確保されている必要性がある。そういった避難所は確保されているのか、また電源が確保されているのかなど当事者の方は気にされていた。そういった課題を共有できればと思う。
・山梨県にお住まいで、電車の運休で 1 か月近く通所ができなかったため、体調も崩された方もいた。
・福祉避難所(2 時避難所)は今回機能したのか、いろんな障害の方がいる中で、2 時避難所はどう対応されるのか、課題を共有できればと思う。
・電源と衛生面が確保できる避難所は必要だが、避難すること優先ではなく、避難するべきかどうかは状況によって違う。
状況によって準備することが違うので、公助だけではなく個々が考える部分が大きい。普段から自分で準備しておくことが大事。
・近所にサポートできる人、建物、団体など困ったときに頼れる地盤を作っておくことは必要と考える。
・SNS で避難所がどこが開いているか、動画などの含めて情報があり助かった。避難する判断の役になった。市民センターの和室は横に慣れて助かった。1 次避難所も教室など開放してもらえると助かる。
・2 次避難所は、まず 1 次避難所ありきなので、1 次避難所すらいけない、いかない方は懸念される。
・町会など自身から支援依頼を事前に話しておけると良い。
市からの回答や意見
・透析、人工呼吸器での電源の確保は今のところは対策はできていない。H30 年度から市の保健所では避難所に行けない電源が必要な方へ提供する取り組みはある。問題意識としてはあるが、まだ取り組めていない部分もある。
・ハザードパップないにある事業所は入所施設は調査したが、GH などすべてはまだ把握していない。19 号の時は GH など入所の事業所には状況確認など市として個別に行った。通所までは手が回らなかった。マニュアルの提供も実際にどれだけ活用してもらえているか、そのあたりも今後の課題と考える。
・電源の確保は課題になっている。2 次避難所についても国の予算を活用して自家発電をつけていく事業を予定している。衛生面については課題はまだある。
・一次避難所でも個別対応で教室開放など対応した例があった。今回のいただいた意見など今後も防災課への情報提供して今後につなげていきたい。
・透析、人工呼吸器での電源の確保は今のところは対策はできていない。H30 年度から市の保健所では避難所に行けない電源が必要な方へ提供する取り組みはある。問題意識としてはあるが、まだ取り組めていない部分もある。
・ハザードパップないにある事業所は入所施設は調査したが、GH などすべてはまだ把握していない。19 号の時は GH など入所の事業所には状況確認など市として個別に行った。通所までは手が回らなかった。マニュアルの提供も実際にどれだけ活用してもらえているか、そのあたりも今後の課題と考える。
・電源の確保は課題になっている。2 次避難所についても国の予算を活用して自家発電をつけていく事業を予定している。衛生面については課題はまだある。
・一次避難所でも個別対応で教室開放など対応した例があった。今回のいただいた意見など今後も防災課への情報提供して今後につなげていきたい。
・今回の台風 19 号についての概要は、24 施設 794 名の方が避難した。追加 12 施設で 1038 名、計 8457 名、3732世帯の方が避難した。人的被害は防災課では報告なし。944 件が物的被害あり。2 時避難所は協定先から数施設が受
け入れ可能となり、準備はしていたが台風の影響が弱まり、高齢者施設も含めて開設までには至らなかった。自主避難所として 2 施設の開放をお願いした。一次避難所も教室開放など臨機応変の対応を行った。
・アクセスが集中して市のホームページがダウンした件については防災課が対応を検討している状況。
・2次避難所の協定先は個別の名称は入れていないが防災マニュアルに掲載している。最初からどこが協定先かを明かすのは状況に応じて 2 時避難所は開設することと、今回の台風にように逆に避難しないといけない場所に立地している施設もあるので事前の公表は考えてはいない。2 次避難所は先に開示はしないが、一次避難所で職員に状況を伝えてもらい、市の防災対策本部に情報が集まる。その後に必要に応じて提携先の事業所へ受け入れを要請して、受け入れ
可能であれば 2 次避難所の開設となる。その際には建物の安全性もチェックする。一斉に公表すると多数が集まってしまい、本来、2 時避難所へ避難するべき人が避難できなくなることも懸念されるので、この形体をとっている。
・1 次避難所に避難されない在宅の方への 2 次避難所等の情報提供をどうしていくかは防災課とも課題として認識している。
・要支援者リストは 1 次避難所に配備している。小学校はその地域の、中学校は全市の情報を配備している。情報は一年ごとに更新している。
・福祉政策課が要支援者と自主防災の支援組織とのパッチングも行っている。
地域に住まわれている知的障害者の方の生活への支援について(19:20~)
親の高齢化などの課題を抱える家族同居の知的障害がある方々の今後の生活について、親御さんの立場からの意見を伺いながら、グループホームを初め、どのような支援が可能か、また求められるか意見交換ができればと思います。
け入れ可能となり、準備はしていたが台風の影響が弱まり、高齢者施設も含めて開設までには至らなかった。自主避難所として 2 施設の開放をお願いした。一次避難所も教室開放など臨機応変の対応を行った。
・アクセスが集中して市のホームページがダウンした件については防災課が対応を検討している状況。
・2次避難所の協定先は個別の名称は入れていないが防災マニュアルに掲載している。最初からどこが協定先かを明かすのは状況に応じて 2 時避難所は開設することと、今回の台風にように逆に避難しないといけない場所に立地している施設もあるので事前の公表は考えてはいない。2 次避難所は先に開示はしないが、一次避難所で職員に状況を伝えてもらい、市の防災対策本部に情報が集まる。その後に必要に応じて提携先の事業所へ受け入れを要請して、受け入れ
可能であれば 2 次避難所の開設となる。その際には建物の安全性もチェックする。一斉に公表すると多数が集まってしまい、本来、2 時避難所へ避難するべき人が避難できなくなることも懸念されるので、この形体をとっている。
・1 次避難所に避難されない在宅の方への 2 次避難所等の情報提供をどうしていくかは防災課とも課題として認識している。
・要支援者リストは 1 次避難所に配備している。小学校はその地域の、中学校は全市の情報を配備している。情報は一年ごとに更新している。
・福祉政策課が要支援者と自主防災の支援組織とのパッチングも行っている。
地域に住まわれている知的障害者の方の生活への支援について(19:20~)
親の高齢化などの課題を抱える家族同居の知的障害がある方々の今後の生活について、親御さんの立場からの意見を伺いながら、グループホームを初め、どのような支援が可能か、また求められるか意見交換ができればと思います。
秦氏(ころぼっくる)よりお話あり。
親御さんの高齢化の中でグループホームなど利用したいけど利用できないという意見を以前はよく聞いていた。最近、お話をお聞きする中で、できれば親が元気なうちは一緒にいたいという気持ちが本音ではあるが、準備をしていかないといけない。そのような中で知らない事業所の利用はハードルが高いというお気持ちがある。グループホームは空き情報も含めて情報提供もある。しかし知的と医療の必要な方が利用できるグループホームが少ないという課題がある。本来は親御さん自身に出席願えればと考えたが、残念ながら今回は出席とならなかった。
親御さんの高齢化の中でグループホームなど利用したいけど利用できないという意見を以前はよく聞いていた。最近、お話をお聞きする中で、できれば親が元気なうちは一緒にいたいという気持ちが本音ではあるが、準備をしていかないといけない。そのような中で知らない事業所の利用はハードルが高いというお気持ちがある。グループホームは空き情報も含めて情報提供もある。しかし知的と医療の必要な方が利用できるグループホームが少ないという課題がある。本来は親御さん自身に出席願えればと考えたが、残念ながら今回は出席とならなかった。
安藤さん(なみき福祉会)
親の立場として、70 代の現在 40 歳の障害がある息子を育ててきた。八王子市では高等部を卒業すると行き場がないという現状があり運動を開始し、障害児の学童、作業所、グループホームを作ってきた。一緒に行動してきた親御さんも亡くなられている。40 年前よりかは福祉も改善されてきたが、他市に比べるとまだまだと思える。グループホームについては毎月情報をホームページでアップしてもらって助かっている。障害者計画も第 6 期となる。日中の行き場所がなくなると困るので家賃補助を継続してほしい。作業所は民間が行ってきた。公立の施設(建物)は 30 年前の波多野市長時代に長沼通所センター一か所。駅から徒歩 10 分の作業所は家賃も高い。人件費もあり運営継続が困る。
障害児の移動支援を小学生から対象にしてほしい。通常のお子さんは小学生になると一人通学などできるが、障害児も小さいころから人と接せられる環境が権利保障の観点からも重要。26 市で小学生から適用していないのは稲城市と町田氏のみ。医療的ケアを必要とする高等部卒業後の進路先として、市有地、都有地、国有地を活用して 10 年後を見据えて八王子市療育センターの開設をしてほしい。特別支援学校の 2 年生から行き場所がないと聞いている。
親の立場として、70 代の現在 40 歳の障害がある息子を育ててきた。八王子市では高等部を卒業すると行き場がないという現状があり運動を開始し、障害児の学童、作業所、グループホームを作ってきた。一緒に行動してきた親御さんも亡くなられている。40 年前よりかは福祉も改善されてきたが、他市に比べるとまだまだと思える。グループホームについては毎月情報をホームページでアップしてもらって助かっている。障害者計画も第 6 期となる。日中の行き場所がなくなると困るので家賃補助を継続してほしい。作業所は民間が行ってきた。公立の施設(建物)は 30 年前の波多野市長時代に長沼通所センター一か所。駅から徒歩 10 分の作業所は家賃も高い。人件費もあり運営継続が困る。
障害児の移動支援を小学生から対象にしてほしい。通常のお子さんは小学生になると一人通学などできるが、障害児も小さいころから人と接せられる環境が権利保障の観点からも重要。26 市で小学生から適用していないのは稲城市と町田氏のみ。医療的ケアを必要とする高等部卒業後の進路先として、市有地、都有地、国有地を活用して 10 年後を見据えて八王子市療育センターの開設をしてほしい。特別支援学校の 2 年生から行き場所がないと聞いている。
会場からの意見
・知的の障害の方の今後について、どのような生活が必要か具体的なことも掘り下げる必要がある。
・放課後デイがたくさん出来たが、企業型と草の根でやってきたところと感覚の違いがある。とにかく親を楽にさせることを最優先している事業所が多い。託児所化している。何もない時代は親が頑張るしかないとやってきたが、今の親はどこに預けようかという発想で将来を描けていない。夜まで預かってくれる生活から、通所へ移ると 15 時くらいから子供が家にいる状況に変わることをどう対応するのか心配になる。親の力がどんどんなくなっている状況を感じる。サービスを選ぶ立ち位置にある。
・グループホームでも長く家族同居されていた方が入居した際もいろいろな課題ある。いろんな経験がないまま入居して顕在化する。かといって親御さんに事業所として言うのは難しい面もある。
・障害当事者の立場からも。サービスを選ぶ、利用するという形になって、自分自身についてなど自分で考えずに与えられたサービスを受け入れるという風潮に変化していると感じる。
・グループホームを探すほうの立場として、重度の方が複数いらっしゃると現実として介助時間的に難しく、断られてしまうのは理解できる。すぐには難しいとは思うが、グループホームが受けられるような体制がとれるようなことが検討できればと思う。
・知的の障害の方の今後について、どのような生活が必要か具体的なことも掘り下げる必要がある。
・放課後デイがたくさん出来たが、企業型と草の根でやってきたところと感覚の違いがある。とにかく親を楽にさせることを最優先している事業所が多い。託児所化している。何もない時代は親が頑張るしかないとやってきたが、今の親はどこに預けようかという発想で将来を描けていない。夜まで預かってくれる生活から、通所へ移ると 15 時くらいから子供が家にいる状況に変わることをどう対応するのか心配になる。親の力がどんどんなくなっている状況を感じる。サービスを選ぶ立ち位置にある。
・グループホームでも長く家族同居されていた方が入居した際もいろいろな課題ある。いろんな経験がないまま入居して顕在化する。かといって親御さんに事業所として言うのは難しい面もある。
・障害当事者の立場からも。サービスを選ぶ、利用するという形になって、自分自身についてなど自分で考えずに与えられたサービスを受け入れるという風潮に変化していると感じる。
・グループホームを探すほうの立場として、重度の方が複数いらっしゃると現実として介助時間的に難しく、断られてしまうのは理解できる。すぐには難しいとは思うが、グループホームが受けられるような体制がとれるようなことが検討できればと思う。
市の回答・意見
・施設整備でグループホームの場合に重度の方を受け入れる事業所を優先にしている。必要な方の数より事業所が少ないのが課題としてあるが、出来ることは継続してやっていきたい。
・放課後等デイサービスについては、最近は重度の方を受け入れてくれるところも少しは増えている。共働きの家庭がほとんで、放課後デイを卒業した後についても課題として認識している。グループホーム連絡会でもそうした課題を共有していきたい。
・施設整備でグループホームの場合に重度の方を受け入れる事業所を優先にしている。必要な方の数より事業所が少ないのが課題としてあるが、出来ることは継続してやっていきたい。
・放課後等デイサービスについては、最近は重度の方を受け入れてくれるところも少しは増えている。共働きの家庭がほとんで、放課後デイを卒業した後についても課題として認識している。グループホーム連絡会でもそうした課題を共有していきたい。
杉山さん(ほっとスペース八王子)
私も精神障害の当事者で、当事者として生活支援員の仕事をしている。精神障害者の方がアパートの賃貸借契約更新時に生活保護の理由を執拗に確認があり、精神障害者ということを伝えたら、当事者のご本人を抜きにして、生活保
護担当者と大家さん側で家賃の代理納付が決まってしまった。更に更新料と家賃増額も決まってしまった。これについては生活福祉課へ抗議をして謝罪是正をして頂けたので良かったが、この件でご本人は精神的に参ってしまうこととなった。同様の事例があるのかどうか調査して、あるとすれば是正してもらえればと思う。
私も精神障害の当事者で、当事者として生活支援員の仕事をしている。精神障害者の方がアパートの賃貸借契約更新時に生活保護の理由を執拗に確認があり、精神障害者ということを伝えたら、当事者のご本人を抜きにして、生活保
護担当者と大家さん側で家賃の代理納付が決まってしまった。更に更新料と家賃増額も決まってしまった。これについては生活福祉課へ抗議をして謝罪是正をして頂けたので良かったが、この件でご本人は精神的に参ってしまうこととなった。同様の事例があるのかどうか調査して、あるとすれば是正してもらえればと思う。
会場からの意見
・ご本人抜きにして話が進むことはあってはならないことかと思う。そういうことがないように願いたい。以前に別のケースだが、障害者の方で生活保護世帯の方の場合は必要があれば生活福祉課だけでなく、障害者福祉課も間に入ってもらうということがあったと思う。
・精神障害の方が、ここ数年でアパート等を借りる場合に家主の側から断れるケースを多く聞くが、そういった場合に相談できる手立てはあるか。
・自立支援協議会に不動産の立場の方もいるので、理解が進めればよいかと思う。
・ご本人抜きにして話が進むことはあってはならないことかと思う。そういうことがないように願いたい。以前に別のケースだが、障害者の方で生活保護世帯の方の場合は必要があれば生活福祉課だけでなく、障害者福祉課も間に入ってもらうということがあったと思う。
・精神障害の方が、ここ数年でアパート等を借りる場合に家主の側から断れるケースを多く聞くが、そういった場合に相談できる手立てはあるか。
・自立支援協議会に不動産の立場の方もいるので、理解が進めればよいかと思う。
市の回答・意見
・事例については確認して共有していきたい。同じようなことがあれば対応していきたい。法律的にどこまで代理で行うような権限があるのかどうかも確認できればと思う。また、障害だけを理由に契約を拒むようなことは差別に該当するので、障害者福祉課、委託の 5 か所の相談支援事業所が相談窓口になっているので、相談してほしい。
・事例については確認して共有していきたい。同じようなことがあれば対応していきたい。法律的にどこまで代理で行うような権限があるのかどうかも確認できればと思う。また、障害だけを理由に契約を拒むようなことは差別に該当するので、障害者福祉課、委託の 5 か所の相談支援事業所が相談窓口になっているので、相談してほしい。
障害者福祉課からのお知らせなど(19:50~)
・日中活動系施設等運営安定化事業補助金(家賃補助)について
数年前から見直しの話をお伝えしているが、対象となる 102 事業所へ訪問して調査、意見をお聞きした。その結果、多くの課題が見えてきた。通所実績に影響する給付、人材確保、報酬改定による影響などあった。しかし、障害者計画で優先順位をつけて施策を行っていくためには現行の補助制度では限界があり、改善が必要であると感じている。
一方で通所事業所への影響も考えて令和 2 年度は現行の制度を維持したい。令和 3 年度から家賃補助の引き下げ率を段階的に検討している。引き下げ率については、またご相談させていただければと考えている。
•重度障害児者への施策の充実について
医療的支援が必要な重度障害児者が通所できる事業を検討している。障害者計画でも主要な計画に位置付けている。具体的には重度心身障害児、医療的ケアが必要な障害児の受け入れを事業所へ働きかける、重度重複の障害児を受け入れる放課後デイ等の拡充など記載されている。令和 2 年は計画の最終年度となるが、着手できない状況もある。そのため財源は家賃補助の見直しを考えており、制度設計をして令和 3 年からを予定にしている。決まり次第、報告をできればと考えている。
•2020 年 4 月からの条例改正について
差別禁止条例を東京都が平成 30 年 10 月に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を施行したことを受けて、それに合わせて市条例を改正した。具体的には合理的配慮は行政と指定管理者、外郭団体が義務であったが、すべての事業者について義務化をする。一般市民は努力義務となる。事業者へ従業員への障害者理解促進の努力義務、事業者への勧告に従わない事業者の公表を出来る、難病罹患者の障害者へ含める明記の 4 点となる。令和 2 年 4月 1 日より施行する。障害理解や合理的配慮については事業者、市民へ市としても理解促進を出前講座や障害者サポーター養成講座など活用して進めたい。
•発達障害者への支援として、保護者同士の共有の場を設けるなど支援を考えている。今回、家族への講演会と集いの場を設けることとなった。令和 2 年 2 月 19 日(水)13 時 30 分に冨士森体育館で行う予定。東京都発達支援センタートスカ(TOSCA)に講師依頼している。関心ある方の参加の呼びかけをお願いしたい。
•権利擁護推進部会で令和 2年2月1日(土)に啓発事業を行う。イーアス高尾で障害当事者の方のお話を聞く企画もある。いちょう祭りで行っているようなクイズコーナー、手話点字、ボッチャなども行う予定。
・日中活動系施設等運営安定化事業補助金(家賃補助)について
数年前から見直しの話をお伝えしているが、対象となる 102 事業所へ訪問して調査、意見をお聞きした。その結果、多くの課題が見えてきた。通所実績に影響する給付、人材確保、報酬改定による影響などあった。しかし、障害者計画で優先順位をつけて施策を行っていくためには現行の補助制度では限界があり、改善が必要であると感じている。
一方で通所事業所への影響も考えて令和 2 年度は現行の制度を維持したい。令和 3 年度から家賃補助の引き下げ率を段階的に検討している。引き下げ率については、またご相談させていただければと考えている。
•重度障害児者への施策の充実について
医療的支援が必要な重度障害児者が通所できる事業を検討している。障害者計画でも主要な計画に位置付けている。具体的には重度心身障害児、医療的ケアが必要な障害児の受け入れを事業所へ働きかける、重度重複の障害児を受け入れる放課後デイ等の拡充など記載されている。令和 2 年は計画の最終年度となるが、着手できない状況もある。そのため財源は家賃補助の見直しを考えており、制度設計をして令和 3 年からを予定にしている。決まり次第、報告をできればと考えている。
•2020 年 4 月からの条例改正について
差別禁止条例を東京都が平成 30 年 10 月に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を施行したことを受けて、それに合わせて市条例を改正した。具体的には合理的配慮は行政と指定管理者、外郭団体が義務であったが、すべての事業者について義務化をする。一般市民は努力義務となる。事業者へ従業員への障害者理解促進の努力義務、事業者への勧告に従わない事業者の公表を出来る、難病罹患者の障害者へ含める明記の 4 点となる。令和 2 年 4月 1 日より施行する。障害理解や合理的配慮については事業者、市民へ市としても理解促進を出前講座や障害者サポーター養成講座など活用して進めたい。
•発達障害者への支援として、保護者同士の共有の場を設けるなど支援を考えている。今回、家族への講演会と集いの場を設けることとなった。令和 2 年 2 月 19 日(水)13 時 30 分に冨士森体育館で行う予定。東京都発達支援センタートスカ(TOSCA)に講師依頼している。関心ある方の参加の呼びかけをお願いしたい。
•権利擁護推進部会で令和 2年2月1日(土)に啓発事業を行う。イーアス高尾で障害当事者の方のお話を聞く企画もある。いちょう祭りで行っているようなクイズコーナー、手話点字、ボッチャなども行う予定。
☆質疑応答・意見☆
・家賃補助について、引き下げ率を調整中だが、決定はいつか?
市からの回答): 令和 3 年の予算を組む段階なので令和 2 年の夏または秋頃には固めたいと思っている。その際はもう一度事業所へお話を聞きに行きたいと思っている。
・将来的には補助をなくす予定があるか。
市からの回答):また事業所の皆さんのお話を聞きながら、検討していきたいと思う。今のところなくす決定はしていない。
引き下げ率について、財政状況は影響するか?その場合は厳しい事業所もある。赤字の事業所は赤字になるだけになるので黒字と赤字の事業所とは区別して考えてほしい。
市からの回答): 一律で考えている。
・市長申し立てとは?どのような手続き、公表方法か?障害がある方もできる手続きか?
市からの回答) 障害がある方を対象にしているので、まずは窓口に相談してもらい、お話を聞いて相談しながら進めていく。改善させるために取り組んでいくが、どうしても改善されない場合は調整委員会で検討もして、市長申し立てを行い、市長名義で公表する。市の公示掲示板やホームページでの公表となる。公表だけが目的ではなく、事業者の理解をしてもらうのも目的と考えている。
・家賃補助について、引き下げ率を調整中だが、決定はいつか?
市からの回答): 令和 3 年の予算を組む段階なので令和 2 年の夏または秋頃には固めたいと思っている。その際はもう一度事業所へお話を聞きに行きたいと思っている。
・将来的には補助をなくす予定があるか。
市からの回答):また事業所の皆さんのお話を聞きながら、検討していきたいと思う。今のところなくす決定はしていない。
引き下げ率について、財政状況は影響するか?その場合は厳しい事業所もある。赤字の事業所は赤字になるだけになるので黒字と赤字の事業所とは区別して考えてほしい。
市からの回答): 一律で考えている。
・市長申し立てとは?どのような手続き、公表方法か?障害がある方もできる手続きか?
市からの回答) 障害がある方を対象にしているので、まずは窓口に相談してもらい、お話を聞いて相談しながら進めていく。改善させるために取り組んでいくが、どうしても改善されない場合は調整委員会で検討もして、市長申し立てを行い、市長名義で公表する。市の公示掲示板やホームページでの公表となる。公表だけが目的ではなく、事業者の理解をしてもらうのも目的と考えている。
【編集部より】
今号は 1 月 14 日に開催された、八障連活動の年間活動の柱の一つである「障害福祉課との懇談会」の全記録を一括で本誌に掲載しました(書記を担当された、有賀さんご苦労さまでした)。また 3 月には市議懇談会、福祉フォーラムなどが予定されております。ご参加のほどよろしくお願いいたします。(運営委員会一同/編集部)
通信本文はここまで。