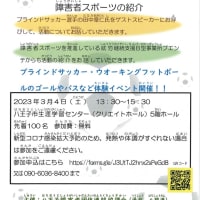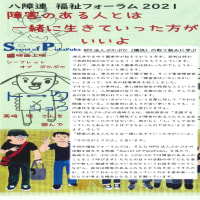八障連通信329号をアップします。
八障連通信329号【PDF版】はこちらから
ここからは通信本文です。
【事務局通信Vol.42】
社会福祉士の方より、現在、国を相手に行われているハンセン病家族の訴訟を支援する公正な判決を求める署名活動への協力依頼がありました。ハンセン病の隔離政策が人権侵害であり、新聞各紙に厚生労働大臣・坂口力(当時)の名前で「ハンセン病患者・元患者に対しては、国が『らい予防法』とこれに基づく隔離政策を継続したために、皆様方に耐え難い苦難と苦痛を与え続けてきました。このことに対し心からお詫び申し上げます」と謝罪広告が掲載されました。前年、小泉純一郎内閣総理大臣(当時)によって、政府はハンセン病国家賠償請求訴訟判決への控訴棄却を決定します。ハンセン病に対して、これまで取ってきた政策は誤りであることを認めました。原因となるらい菌の感染力はとても弱く、日常生活を共にしても感染するような病気ではありませんでしたが、国や医学界は昭和20(1945)年代にその事実を知りながらも、隔離政策を推奨する「らい予防法」を1996年まで存続させてきましたが、1996年に「らい予防法廃止法」が施行され、感染を防止するという名目での隔離政策という名の人権侵害は廃止されました。しかし、当事者のみならず、その家族も大変な人権侵害を受け、苦しい思いをされてきた。その事への国の謝罪はまだありません。バリアフリーによる当たり前に街の中で生活できる権利、施設や病院ではなく、地域で生活できる権利など考えさせられることはまだまだ多く存在します。判決は3月に予定されているようですが、是非多くの署名をお願いできればと思います。また日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の取り組みとして八王子市在住の被爆者の方から核兵器廃絶を求める国際署名活動への協力依頼もありました。核兵器禁止条約が採択されましたが、日本政府の立場も含めて、道のりはまだまだ遠いように思います。私たちの取り組みや営みを一瞬で灰にしてしまう核兵器が必要ない世界は誰もが望むものだと思います。以上、二件の署名協力の依頼が重なりましたが、ご関心ある会員団体の皆様には是非ご協力をお願い致します。(文責/有賀)
【告知板】
11月17日(金)18時30分より、市役所本庁会議室において「市障害福祉課との懇談会」を開催します。通信本号(P2)に市側に提出した「要望書」を掲載しております。当日は必ず通信(本号)をご持参ください。(事務局)
市障害福祉課との懇談会
11月17日(金)
18:00~20:30
八王子市役所本庁
八障連運営委員会
12月14日(木)
18:30~21:00
クリエイト
【市障害福祉課への要望書】
1. 障害福祉課への事前質問に対しての回答と質疑応答(18:45~19:15)
①重症心身障害児を対象とした放課後デイサービスについて
②家賃補助について
③生活保護申請の事前相談における対応と障害者の自立に関する認識のあり方について
2. 生活介護(訓練)を利用している中で就労継続支援B型事業所併用利用について(19:20~19:40)
生活介護と就労継続支援B型との併給が出来ないとステップアップしていけません。生活介護から雇用契約のある、就労継続A型や就労移行支援にはすぐにいけないので、そして、一遍に生活介護から就労移行支援B型に移行すると、その利用者のスキルだけでなく、人間関係がうまく構築できずにダメになるケースも考えられます。それを避ける意味合いでも、併給しながら徐々に慣れて完全に移行するのがベターだと思います。以上の意見が出されています。そのことに対して市の見解や、当事者と支援者の疑問点を意見交換したいと思います。
3. 児童の移動支援に関して(19:35~20:00)
八王子市の利用を15歳以上に限定するのは、保護者の立場からすると非常に使いづらい制度であると思います。障害児を持つ保護者が一番移動支援を使いたいのが7歳から14歳です。以前に立川でヘルパーとして約7年働きましたが、依頼は圧倒的に多いのが児童で7歳から14歳でした。多動・こだわりが強いのもこの年代です。
ヘルパーと移動支援で外出するのは二つメリットがあります。1つは保護者以外の人と外出で他人と接することで世界が広がる。二つ目はその間に保護者が休んだり、自分の用事がこなせるという事です。
4.障害と介護保険の統合に関して(20:00~20:20)
障害当事者が65歳を越えて「障害福祉サービス」から「介護保険サービス」に移行した場合、介護保険に移行した後、受けられるサービスの量や質が低下するのではという問題が、多くの障害当事者の間で懸念されています。
この問題については厚労省から市町村にも通達が降りており、八王子市においても、①一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断。②市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能。③障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能。という考え方を示しいただいているところですが、一方で市として独自に支援できる体力は限られているとのではないかという不安もあり、どこまで従来通りの福祉サービスを継続できるかは、市内に暮らす障害当事者として不透明であると言えます。単に介護の側面だけでなく、余暇活動の支援、当事者が勉強会や講演会に出掛けるなどの文化的活動、社会活動への参加など、障害当事者も単なる受け身の存在としてだけでなく、積極的に他者と関わりを持ち、社会の一員としての顔を持つ人たちがいます。障害の程度や社会参加の程度によって当事者にも様々なニーズがある中、どこまでの利用がサービスとして認められるのか。八王子市としての見解をお聞かせください。
【連載コラム vol.15 『アーナビ』 ハーネス八王子 鈴木 由紀子】
白杖歩行から盲導犬歩行に切り替えてよかったと私が実感していることの一つは、孤立感がなくなったこと。白杖を使って、一歩ずつ足先の様子を確かめながら歩いていたときは、たぶん私の表情も緊張していて、周りの人も近寄りがたかったと思います。狭い道で立ち話をしている人たちのそばにそんな私が近づくと、彼らはすぐに話をやめ、私がそこを通りすぎるまで、黙って私を凝視(ぎょうし)していたように思われます。彼らに何の悪気はないのですが、私にとって、そんな数秒間は、止(や)めてほしいと思いたい時間でした。「彼らにとって、目の見えない私は特別な存在なのではないか」と勝手な思いをめぐらせて、その場にいるのが苦しくなることさえありました。ところが今は、信号を待っているときも、バス停や駅のホームに立っているときも、アーサと一緒にいると、いろいろな人が自然に声をかけてきます。
「自転車もちゃんと避けて、お利口さん!」「お母さんをしっかり守って、いい子ね!」などと、アーサへの褒(ほめ)ことばが続きます。バスや電車に乗り込むと、アーサが空席を見つけて、その椅子に顎(あご)を付けて「ここに座れるよ」と私に教えます。「ありがとう」と言って私がその席に座り、アーサは座席の下に静かに伏せています。
そんなときもアーサが注目の的になり、「うちの犬はね・・・」などと、決まって犬談義が始まり、車内の雰囲気が和(なご)やかになる気がします。それで私もそんな様子に自然に解け込んで、会話もはずみ、まちに出かけることが楽しくなります。 盲導犬アーサの最も特筆すべきすごさは、目的地までの道の特徴をすぐに捉(とら)えて、確実にその場所を探し出すことです。警察犬や救助犬などの活躍ぶりは皆さんよくご存じでしょうし、犬という生き物すべてが、このような素晴らしい能力を備えていると言ってもいいのかもしれません。
私はときどき、新宿区内にあるNPO法人にアーサと出かけます。そこにたどり着くためには、中央線の中野駅まで電車に乗り、駅から少し離れたところにあるバス停から10分ほどバスに乗ります。バス停を下りたら、やはり10分ぐらい歩いて目的の建て物にたどり着きます。中野駅周辺は絶えず通行人がいるので、もし不安になったらどなたかにお願いすると、目的のバス停まで案内してもらえます。しかし、バスを下りたところからは人通りが少ないので、最初のうちは忙しいスタッフを呼び出して、案内してもらっていました。しかし、三度目ぐらいになると、そろそろ一人で行ってみなくてはという気になり、トライしてみたら、アーサのお蔭で、ちゃんと目的の建て物にたどり着くことができたのです。
バス停からの道は、路線バスも通る二車線道路。歩道と車道が白線で区切られただけの狭い道を、車の往来も気にしながら10分ぐらい歩きます。しばらく歩いたら、ある地点でバス通りから左に入る分かれ道を探さなくてはなりません。分かれ道の手前で道が少し下り坂になっているということは私も知っていましたが、その分岐点をうまく見つけ出す自信が、私にはありませんでした。
ところが、ある地点でアーサが私を左側に誘導して「お母さん、ここだよ」と、すいすい進んでいったのです。私たちはそこから更に一度左折してバス通りの裏側の住宅街に入り、ほどなく目的の建て物の門をくぐりました。それまで二回訪ねただけなのに、そこに至る道の特徴をアーサがしっかり覚えて私を誘導してくれたことになります。
私たちは早速、みんなが集まっている室内に入り、ハーネスも外して、アーサをリラックスさせます。ドッグフードも何粒か入れた特製水とリンゴでアーサの労をねぎらうと、アーサも、前足と後ろ足を交互に伸ばして体操をしたり、やがては、おなかを上に向けて寝そべって、周りを見回したり、おなかをなでてもらったりして、みんなの人気者になるのです。
目が見えない私には車が運転できないので、カーナビは必要ありません。しかし盲導犬アーサは私の「アーナビ」として、私にとって無くてはならないもの、私の生活に不可欠な生きものです。雨が降り出したりして急いで歩いていても、路地から急に車が出てきて私たちに近づいたら、アーサは即座に足を踏ん張って止まり、私の動きにブレーキをかけ、危険な状況から守ってくれるほど優秀なナビゲーター。今日もこれからアーサと、電車とバスを乗り継いで出かけて、新たな出会いを楽しむことにします。
【連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小濵 義久】
闘病史 その17
34年間の闘病生活の中で、今年は最大のピンチを迎えた訳だが、お陰様で順調な回復をみ、体重も体調もやっと元に戻ってきた。テニスは続けており、不死鳥と言われたりしている。高尾山には11月5日に登って来た。ツーリング前は行事が重なり、退院後は天候に恵まれなかったこともあり、実に半年振りだった。途中休みはしなかったが、スピードはのろく、心臓破りの階段はやっと登った。
「その16」では、最初の入院生活からやっと退院した処(ところ)までを書いた。私は元々書くことも読むことも人前で喋(しゃべ)ることも苦手だった。小学校の夏休みの宿題の最大の難関は読書感想文だったし、国語の時間に立って本を読まされる時はいつも足が震えていた。じっと座って本を読むことも難しかった。2~3ページ読み進めると目がうつろになった。
読むことは高校時代に小説や哲学書を読み始めてから克服、書くことはずっと苦手のまま過ごし、大学時代のレポートや論文には苦労させられた。この連載を始めてから生まれて初めて書く楽しさというものを味あわせて貰(もら)っている。有り難いことだ。人前で喋(しゃべ)ることは大学で演劇サークルに所属し、少しずつ克服して行った。
そんな背景があり、よもや闘病記を書くようになるとは思いもせず、過去の資料は殆(ほとん)ど捨ててしまっている。手帳と一部残された資料やDrへの問い合わせなどにより、記憶を呼び覚ませながらこの闘病記を実は書き続けている。1983年の手帳を繰(めく)りながら、この年はいろいろな人との出会いがあったのだなぁと懐(なつ)かしく思い出された。2~3のアルバイトをしながらも休職中だったので、時間がたっぷりあったからいろいろ出歩けたのだ。
昨年亡くなった若宮啓文氏とは長野県丸子町(上田市)にあった山小屋へよく一緒に行っているし、彼の自宅にも随分お邪魔している。朝日新聞論説主筆まで上り詰めようとは当時想像もしなかった。草間彌生の当時の主治医のクリニックで出会った看護婦さんが結婚して鬼海と姓が変わった。変わった名前だね、奇怪だねと語呂合わせのように言ったのが昨日のように思い出された。実に失礼な事を言っていたのだが、当時は意味も考えていなかった。その旦那さんの初個展に行ったことはすっかり忘れていた。今では有名になった写真家の鬼海弘雄氏その人である。「断捨離」で一躍有名になった山下英子氏の家には縁があって、一泊させて貰っている。大学の後輩なのだ。在学中に一緒に食事をしたこともあった。
八障連関係で言うと、「わかくさの家」が10月に開所された年である。この当時は病院勤めの傍(かたわ)らまだ外野からお手伝いをしているにすぎなかったが、翌年から本格稼働させようとしていた作業所の職員採用に向け、職員対策委員会に随分足を運んでいる。「わかくさ」と出会う前には福祉には殆(ほとん)ど関心がなかった。精神分裂病(現在は統合失調症と言う)の世界に魅入られ、その世界の謎解きに夢中になっていた。また、精神病院という世界に足を踏み入れてから知った精神医療状況のあまりにもの酷(むご)さに憤(いきどお)りを感じていたので、少しでも良くならないかと精神医療改革運動に参加してもいた。臨床心理学や精神医学の世界から福祉の世界へ大きく舵を切ることになったのは、わかくさとの出会いからである。(次号へ続く)
八障連通信329号【PDF版】はこちらから
ここからは通信本文です。
【事務局通信Vol.42】
社会福祉士の方より、現在、国を相手に行われているハンセン病家族の訴訟を支援する公正な判決を求める署名活動への協力依頼がありました。ハンセン病の隔離政策が人権侵害であり、新聞各紙に厚生労働大臣・坂口力(当時)の名前で「ハンセン病患者・元患者に対しては、国が『らい予防法』とこれに基づく隔離政策を継続したために、皆様方に耐え難い苦難と苦痛を与え続けてきました。このことに対し心からお詫び申し上げます」と謝罪広告が掲載されました。前年、小泉純一郎内閣総理大臣(当時)によって、政府はハンセン病国家賠償請求訴訟判決への控訴棄却を決定します。ハンセン病に対して、これまで取ってきた政策は誤りであることを認めました。原因となるらい菌の感染力はとても弱く、日常生活を共にしても感染するような病気ではありませんでしたが、国や医学界は昭和20(1945)年代にその事実を知りながらも、隔離政策を推奨する「らい予防法」を1996年まで存続させてきましたが、1996年に「らい予防法廃止法」が施行され、感染を防止するという名目での隔離政策という名の人権侵害は廃止されました。しかし、当事者のみならず、その家族も大変な人権侵害を受け、苦しい思いをされてきた。その事への国の謝罪はまだありません。バリアフリーによる当たり前に街の中で生活できる権利、施設や病院ではなく、地域で生活できる権利など考えさせられることはまだまだ多く存在します。判決は3月に予定されているようですが、是非多くの署名をお願いできればと思います。また日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の取り組みとして八王子市在住の被爆者の方から核兵器廃絶を求める国際署名活動への協力依頼もありました。核兵器禁止条約が採択されましたが、日本政府の立場も含めて、道のりはまだまだ遠いように思います。私たちの取り組みや営みを一瞬で灰にしてしまう核兵器が必要ない世界は誰もが望むものだと思います。以上、二件の署名協力の依頼が重なりましたが、ご関心ある会員団体の皆様には是非ご協力をお願い致します。(文責/有賀)
【告知板】
11月17日(金)18時30分より、市役所本庁会議室において「市障害福祉課との懇談会」を開催します。通信本号(P2)に市側に提出した「要望書」を掲載しております。当日は必ず通信(本号)をご持参ください。(事務局)
市障害福祉課との懇談会
11月17日(金)
18:00~20:30
八王子市役所本庁
八障連運営委員会
12月14日(木)
18:30~21:00
クリエイト
【市障害福祉課への要望書】
1. 障害福祉課への事前質問に対しての回答と質疑応答(18:45~19:15)
①重症心身障害児を対象とした放課後デイサービスについて
②家賃補助について
③生活保護申請の事前相談における対応と障害者の自立に関する認識のあり方について
2. 生活介護(訓練)を利用している中で就労継続支援B型事業所併用利用について(19:20~19:40)
生活介護と就労継続支援B型との併給が出来ないとステップアップしていけません。生活介護から雇用契約のある、就労継続A型や就労移行支援にはすぐにいけないので、そして、一遍に生活介護から就労移行支援B型に移行すると、その利用者のスキルだけでなく、人間関係がうまく構築できずにダメになるケースも考えられます。それを避ける意味合いでも、併給しながら徐々に慣れて完全に移行するのがベターだと思います。以上の意見が出されています。そのことに対して市の見解や、当事者と支援者の疑問点を意見交換したいと思います。
3. 児童の移動支援に関して(19:35~20:00)
八王子市の利用を15歳以上に限定するのは、保護者の立場からすると非常に使いづらい制度であると思います。障害児を持つ保護者が一番移動支援を使いたいのが7歳から14歳です。以前に立川でヘルパーとして約7年働きましたが、依頼は圧倒的に多いのが児童で7歳から14歳でした。多動・こだわりが強いのもこの年代です。
ヘルパーと移動支援で外出するのは二つメリットがあります。1つは保護者以外の人と外出で他人と接することで世界が広がる。二つ目はその間に保護者が休んだり、自分の用事がこなせるという事です。
4.障害と介護保険の統合に関して(20:00~20:20)
障害当事者が65歳を越えて「障害福祉サービス」から「介護保険サービス」に移行した場合、介護保険に移行した後、受けられるサービスの量や質が低下するのではという問題が、多くの障害当事者の間で懸念されています。
この問題については厚労省から市町村にも通達が降りており、八王子市においても、①一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断。②市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能。③障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能。という考え方を示しいただいているところですが、一方で市として独自に支援できる体力は限られているとのではないかという不安もあり、どこまで従来通りの福祉サービスを継続できるかは、市内に暮らす障害当事者として不透明であると言えます。単に介護の側面だけでなく、余暇活動の支援、当事者が勉強会や講演会に出掛けるなどの文化的活動、社会活動への参加など、障害当事者も単なる受け身の存在としてだけでなく、積極的に他者と関わりを持ち、社会の一員としての顔を持つ人たちがいます。障害の程度や社会参加の程度によって当事者にも様々なニーズがある中、どこまでの利用がサービスとして認められるのか。八王子市としての見解をお聞かせください。
【連載コラム vol.15 『アーナビ』 ハーネス八王子 鈴木 由紀子】
白杖歩行から盲導犬歩行に切り替えてよかったと私が実感していることの一つは、孤立感がなくなったこと。白杖を使って、一歩ずつ足先の様子を確かめながら歩いていたときは、たぶん私の表情も緊張していて、周りの人も近寄りがたかったと思います。狭い道で立ち話をしている人たちのそばにそんな私が近づくと、彼らはすぐに話をやめ、私がそこを通りすぎるまで、黙って私を凝視(ぎょうし)していたように思われます。彼らに何の悪気はないのですが、私にとって、そんな数秒間は、止(や)めてほしいと思いたい時間でした。「彼らにとって、目の見えない私は特別な存在なのではないか」と勝手な思いをめぐらせて、その場にいるのが苦しくなることさえありました。ところが今は、信号を待っているときも、バス停や駅のホームに立っているときも、アーサと一緒にいると、いろいろな人が自然に声をかけてきます。
「自転車もちゃんと避けて、お利口さん!」「お母さんをしっかり守って、いい子ね!」などと、アーサへの褒(ほめ)ことばが続きます。バスや電車に乗り込むと、アーサが空席を見つけて、その椅子に顎(あご)を付けて「ここに座れるよ」と私に教えます。「ありがとう」と言って私がその席に座り、アーサは座席の下に静かに伏せています。
そんなときもアーサが注目の的になり、「うちの犬はね・・・」などと、決まって犬談義が始まり、車内の雰囲気が和(なご)やかになる気がします。それで私もそんな様子に自然に解け込んで、会話もはずみ、まちに出かけることが楽しくなります。 盲導犬アーサの最も特筆すべきすごさは、目的地までの道の特徴をすぐに捉(とら)えて、確実にその場所を探し出すことです。警察犬や救助犬などの活躍ぶりは皆さんよくご存じでしょうし、犬という生き物すべてが、このような素晴らしい能力を備えていると言ってもいいのかもしれません。
私はときどき、新宿区内にあるNPO法人にアーサと出かけます。そこにたどり着くためには、中央線の中野駅まで電車に乗り、駅から少し離れたところにあるバス停から10分ほどバスに乗ります。バス停を下りたら、やはり10分ぐらい歩いて目的の建て物にたどり着きます。中野駅周辺は絶えず通行人がいるので、もし不安になったらどなたかにお願いすると、目的のバス停まで案内してもらえます。しかし、バスを下りたところからは人通りが少ないので、最初のうちは忙しいスタッフを呼び出して、案内してもらっていました。しかし、三度目ぐらいになると、そろそろ一人で行ってみなくてはという気になり、トライしてみたら、アーサのお蔭で、ちゃんと目的の建て物にたどり着くことができたのです。
バス停からの道は、路線バスも通る二車線道路。歩道と車道が白線で区切られただけの狭い道を、車の往来も気にしながら10分ぐらい歩きます。しばらく歩いたら、ある地点でバス通りから左に入る分かれ道を探さなくてはなりません。分かれ道の手前で道が少し下り坂になっているということは私も知っていましたが、その分岐点をうまく見つけ出す自信が、私にはありませんでした。
ところが、ある地点でアーサが私を左側に誘導して「お母さん、ここだよ」と、すいすい進んでいったのです。私たちはそこから更に一度左折してバス通りの裏側の住宅街に入り、ほどなく目的の建て物の門をくぐりました。それまで二回訪ねただけなのに、そこに至る道の特徴をアーサがしっかり覚えて私を誘導してくれたことになります。
私たちは早速、みんなが集まっている室内に入り、ハーネスも外して、アーサをリラックスさせます。ドッグフードも何粒か入れた特製水とリンゴでアーサの労をねぎらうと、アーサも、前足と後ろ足を交互に伸ばして体操をしたり、やがては、おなかを上に向けて寝そべって、周りを見回したり、おなかをなでてもらったりして、みんなの人気者になるのです。
目が見えない私には車が運転できないので、カーナビは必要ありません。しかし盲導犬アーサは私の「アーナビ」として、私にとって無くてはならないもの、私の生活に不可欠な生きものです。雨が降り出したりして急いで歩いていても、路地から急に車が出てきて私たちに近づいたら、アーサは即座に足を踏ん張って止まり、私の動きにブレーキをかけ、危険な状況から守ってくれるほど優秀なナビゲーター。今日もこれからアーサと、電車とバスを乗り継いで出かけて、新たな出会いを楽しむことにします。
【連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小濵 義久】
闘病史 その17
34年間の闘病生活の中で、今年は最大のピンチを迎えた訳だが、お陰様で順調な回復をみ、体重も体調もやっと元に戻ってきた。テニスは続けており、不死鳥と言われたりしている。高尾山には11月5日に登って来た。ツーリング前は行事が重なり、退院後は天候に恵まれなかったこともあり、実に半年振りだった。途中休みはしなかったが、スピードはのろく、心臓破りの階段はやっと登った。
「その16」では、最初の入院生活からやっと退院した処(ところ)までを書いた。私は元々書くことも読むことも人前で喋(しゃべ)ることも苦手だった。小学校の夏休みの宿題の最大の難関は読書感想文だったし、国語の時間に立って本を読まされる時はいつも足が震えていた。じっと座って本を読むことも難しかった。2~3ページ読み進めると目がうつろになった。
読むことは高校時代に小説や哲学書を読み始めてから克服、書くことはずっと苦手のまま過ごし、大学時代のレポートや論文には苦労させられた。この連載を始めてから生まれて初めて書く楽しさというものを味あわせて貰(もら)っている。有り難いことだ。人前で喋(しゃべ)ることは大学で演劇サークルに所属し、少しずつ克服して行った。
そんな背景があり、よもや闘病記を書くようになるとは思いもせず、過去の資料は殆(ほとん)ど捨ててしまっている。手帳と一部残された資料やDrへの問い合わせなどにより、記憶を呼び覚ませながらこの闘病記を実は書き続けている。1983年の手帳を繰(めく)りながら、この年はいろいろな人との出会いがあったのだなぁと懐(なつ)かしく思い出された。2~3のアルバイトをしながらも休職中だったので、時間がたっぷりあったからいろいろ出歩けたのだ。
昨年亡くなった若宮啓文氏とは長野県丸子町(上田市)にあった山小屋へよく一緒に行っているし、彼の自宅にも随分お邪魔している。朝日新聞論説主筆まで上り詰めようとは当時想像もしなかった。草間彌生の当時の主治医のクリニックで出会った看護婦さんが結婚して鬼海と姓が変わった。変わった名前だね、奇怪だねと語呂合わせのように言ったのが昨日のように思い出された。実に失礼な事を言っていたのだが、当時は意味も考えていなかった。その旦那さんの初個展に行ったことはすっかり忘れていた。今では有名になった写真家の鬼海弘雄氏その人である。「断捨離」で一躍有名になった山下英子氏の家には縁があって、一泊させて貰っている。大学の後輩なのだ。在学中に一緒に食事をしたこともあった。
八障連関係で言うと、「わかくさの家」が10月に開所された年である。この当時は病院勤めの傍(かたわ)らまだ外野からお手伝いをしているにすぎなかったが、翌年から本格稼働させようとしていた作業所の職員採用に向け、職員対策委員会に随分足を運んでいる。「わかくさ」と出会う前には福祉には殆(ほとん)ど関心がなかった。精神分裂病(現在は統合失調症と言う)の世界に魅入られ、その世界の謎解きに夢中になっていた。また、精神病院という世界に足を踏み入れてから知った精神医療状況のあまりにもの酷(むご)さに憤(いきどお)りを感じていたので、少しでも良くならないかと精神医療改革運動に参加してもいた。臨床心理学や精神医学の世界から福祉の世界へ大きく舵を切ることになったのは、わかくさとの出会いからである。(次号へ続く)