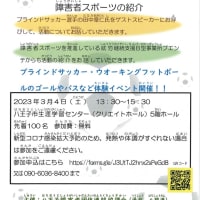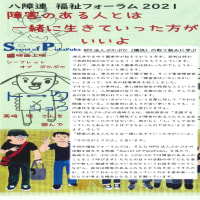八障連通信313です。
八障連通信313号【PDF版はこちら】
八王子腎友会の情報はこちらから。
ここからは通信本文です。
【事務局通信Vol.26】
急な暑さや激しい雷雨に見舞われる季節となりました。九州地方の被災された方々の体調管理が気になります。会員団体の皆様におかれましても熱中症などお気をつけてご自愛をお願いいたします。さて先日の運営委員会で今年度の活動について日程や担当など大まかな役割分担を決めました。市民等への啓発活動となるイベントも単発ではなく、様々な障害の理解について、またライフステージにおける様々な問題をテーマに継続的に取り組めていけないかと意見交換しました。皆様のご意見やアイデアなど多く取り入れいていきたく、運営委員会等へのオブザーバー参加をお願いいたします。
話は変わりますが、いわゆる障害者総合支援法の一部改正が国会で承認され平成30年施行を予定しています。改正ポイントとして、自立生活援助や就労定着、重度訪問介護の訪問先拡大などうたわれています。他にも児童医療や発達支援など児童に対する法改正がみられます。高齢の障害者の方々と介護保険との関係については、障害者サービスでは無料であったサービスが1割負担になる制度上の違いがあり、60歳もしくは65歳以上の方々が利用料が発生する弊害があります。今回の法改正ではこの利用料に着目した改正とサービス提供の事業所が介護保険制度へ事業所として移行しやすいことを謳われています。厚生労働省は当初から少子高齢化の現実を直視して介護保険と障害者分野の制度的統合を進めてきました。高齢化の障害がある方にとっては、サービス提供の考え方の場合によっては介護保険優先という制度が弊害になる恐れがあります。この辺りを懸念して、衆議院厚生労働委員会では付帯決議の二として障害者が高齢になっても障害、高齢者両制度を尊重しつつも、ニーズに即した必要なサービスが円滑に受けられるよう実態を踏まえて検討していくべきことが明記されています。はたして生活の現場ではどのように制度が運用されるのでしょうか。とはいえ少子高齢化の波は押し寄せており、従来の発想では太刀打ちできないことは明らかです。私たち一人ひとりの発想の転換が望まれます。と同時に普遍的に人と人が支え合うために必要なものは何かという価値観が求められる時代だと感じます。
(文責/事務局 有賀)
【今後のスケジュール】
✦ 8月例会より、恒例の「隔月企画」を始めます。今回は、八障連には加盟してませんが、活発に活動している団体さんにお願いしております。現在日程を含め調整中です。ぜひご参加ください。✦ 情報発信したいという会員団体の投稿を引き続き募集しております。投稿先 cxb01672@nifty.com 八障連通信掲載希望とお書きください。(編集部)
八障連運営委員会
7月21日(木) 18:00~20:00 クリエイト試食コーナー
八障連例会・隔月企画
8月25日(木) 18:00~20:00 クリエイト試食コーナー
【「第13回透析サロン」開催さる。~八王子市の障害者災害対策について~】
去る6月26日(日)、クリエイトホールにて、八王子腎友会の総会と第13回透析サロンが開催されました。八障連からも、杉浦代表を含め3名が参加しました。八腎会事務局長の岩崎氏に「透析サロン」のレポートをご執筆いただきましたので、掲載させていただきます。(編集部)
八王子市地域腎友会(以下「八腎会」)は、去る6月26日(日)午後「第13回透析サロン」を開設いたしましたので、今回は「八障連通信」誌上にて、簡単にその報告をさせていただきます。
今回の透析サロンのテーマは、「八王子市における障害者の災害対策」です。私達透析患者は、災害時にライフラインがストップし、電気と水が供給されないと、人工透析治療が不能に陥り、さらにずっと透析ができなければ、できなくなった日からの余命は1週間から10日とされています。このことが、大地震がいつ起きても不思議ではない状況下にあって、「八腎会」が今回本テーマを選定した主な理由です。
障害者の災害対策を考えるときも、また災害が起きたときにも、「自助・共助・公助」の意識が大切と言われています。こうした意識をベースに平成27年度八王子市福祉部障害者福祉課が発行した冊子「障害がある方のための防災マニュアル(自助部分)」と平成26年度同じく障害者福祉課が発行した冊子「災害時障害者サポートマニュアル(共助・公助部分)」について、透析サロン当日参加者全員に本冊子(2冊)を配布し、障害者福祉課所属の担当の方から、二つのマニュアルの概要説明と質疑応答をしていただきました。そしてその前に、八王子市生活安全部防災課所属の担当の方から、「最新の大地震予測とそれぞれの八王子市の被害想定・防災対策」についても、同様の対応をしていただきました。(ここでは具体的内容は割愛)
以上一連の概要説明と質疑応答の中で、浮かび上がってきた問題(課題)がとりあえず二つありました。それは、「二次避難所(福祉避難所)の整備問題」と「災害時要援護者避難支援制度の活用問題」です。以下二つの問題について、整理しておきましょう。
【1】二次避難所(福祉避難所)の整備問題について
①二次避難所(福祉避難所)とは、私達障害者のみならず、介護必要者、高齢者、妊産婦、乳幼児、病者等、一般的な避難所では、生活に支障をきたすいわゆる「災害時要援護者」及びその家族や介護者等のために特別な配慮がされた避難所です。
②八王子市が指定し協定書を取り交わした福祉避難所は、平成27年4月1日現在わずか10箇所に過ぎずもっと増やす必要があり、加えて福祉避難所においては、施設整備(耐震構造化含む)、物資・器材・支援人材・移送手段の確保、医療機関との連携、運営体制の整備等について、あらかじめ事前準備をしておかなければなりませんが、これらの点、八王子市はまだ不十分と言わざるを得ません。
③「八腎会」としては、平成28年4月内閣府(防災担当)発行の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」に基づき、八王子市の福祉避難所の整備問題については、今後しっかりとフォロー・対応をしていきたいと考えています。
【2】災害時要援護者避難支援制度の活用問題について
①大地震等の災害発生時や災害のおそれがあるとき、「災害時要援護者」に対し、災害に関する情報の伝達や避難などの手助けが、地域の中で速やかに安全に行われるための共助・公助の仕組みが本制度の概要です。
②八王子市内の町会・自治会・自主防災組織等が本制度の核となる「地域支援組織」になるためには、市役所に登録し覚書を取り交わさなければなりませんが、平成28年6月現在たったの12箇所しかできておりません。八王子市の町会・自治会等が570存在しますので、「地域支援組織」結成率は、12/570=2.1%と極めてわずかです。これでは八王子市全体として、この組織を中心に要援護者の支援者の募集、決定、支援方法(=避難支援プラン<個別計画>)の策定や八王子市からの要援護者情報の提供といった一連のプロセスが全く前に進めない状況になっています。
③「八腎会」としては、「八腎会」所属の会員に所属する町会・自治会等の会長・役員に対し、まずは「地域支援組織」として市役所へ登録するよう働きかけをお願いすることにしております。「八障連」も同様の対応をお願いいたします。
以上の他、「障害者の災害対策」には、喫緊の課題や足らざるところが多々ありますので、今後も「八腎会」としては、4名の顧問市議の協力を得て市議会への上程や場合によってはしかるべき方法も考えながら、先行き厳しい状況が予想されても、精一杯頑張っていきたいと考えています。
なお、今回の透析サロンに「八障連」三役の方々が傍聴に訪れ、杉浦代表には、冒頭挨拶もしていただ
きましてありがとうございました。今後とも一層のご協力をお願いいたします。(文責:「八腎会」事務局長「岩崎正宏」)
●◎★□◆会場で配布・説明された災害時のマニュアル本です。◆□★◎●福祉関係の事業所へも配布されましたが、みなさんお読みになったことはありますか?障害当事者向けのマニュアルとサポートする側のマニュアルがあります。災害時は障害当事者であってもサポートする側になる場合もあります。そういった意味にでは他障害のことも理解する窓口になるマニュアルです。画像下のアドレスでPDF版がダウンロードできます。是非ご覧になってください。
(編集部注)
災害時 障害者サポートマニュアルhttp://www.city.hachioji.tokyo.jp/moshimo/bosai/051123.html
障害がある方のための防災マニュアルhttp://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/53849/050944.html
【連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小濱 義久】
闘病記 その6
肝臓は血液検査だけでは病態像(肝臓の組織がどれくらいダメになっているか)が掴めない。そこで、まずは腹腔鏡で肝臓の表面を観察する検査を行う。お腹に1㎝くらいの穴をあけ、そこから腹腔鏡を挿入し、お腹を臨月状態くらいに膨らませ、肝臓を肉眼で観察するのである。最後には手元の先に写真機がセットされ、撮影される。我々がたまに食べるレバ刺しのように滑らかであれば問題ないのだが、表面が凸凹しているようなら、肝臓細胞の線維化が進行してきている現れであり、肝硬変が疑われる。写真機のシャッター音が何回もし、意外と原始的だなと感じた(デジカメがまだなかった時代のことである)。
その後、「今から肝生検の針を刺します」と声がかかり、針が刺されたのだが、鈍痛とともに小さな衝撃を感じた。ドスンというような音も聞こえた感じがし、得も言われぬ気色悪い感覚が身体を駆け巡った。「オー、マイゴッド」。全身が硬く硬直し、口も固く閉ざされたままだった。
針の中に取り込まれた肝細胞は顕微鏡でどれだけダメになっているかが調べられる訳だが、組織学的には、CPA、CH2A、CH2B、肝硬変という順番に悪くなっていく。ここに大きな問題がひとつある。
CPAからCH2Bの間は可塑的なのだが、CH2Bと肝硬変の間には大きな溝があり、一旦肝硬変になると元の健康な組織に戻らないと考えられている。先日亡くなった私の大好きな先輩でもある故野坂昭如が、「~間には深くて暗い溝がある」と歌っていたっけ。つまり、肝硬変とは、ほぼ死への片道切符で、肝硬変から肝癌、肝不全になって亡くなるしかないのである。10年というのが一つの目安だろうか。
肝硬変からCH2Bに戻ることを軟化と言うが、最近は軟化する人がたまにはいることが分かってきている。でも、何故、どうしたら軟化するかはまだよく分かっていない。虎の門病院では軟化ケースの統計はないが、5000人位に一人くらいの割合か、もう少し高い確率かもしれないと去年12月に入院した時の担当医が教えてくれた。最初の癌になってから既に21年が過ぎたが、まだ元気いっぱいだ。熊田Drも、地域の家庭医である山田Dr(八王子中央診療所)も吃驚している。ここまで来たら、いっそ軟化まで成し遂げようじゃないかと最近アスリート魂に火が付いた。
「なんかなぁ~」。
通信本文はここまで。
八障連通信313号【PDF版はこちら】
八王子腎友会の情報はこちらから。
ここからは通信本文です。
【事務局通信Vol.26】
急な暑さや激しい雷雨に見舞われる季節となりました。九州地方の被災された方々の体調管理が気になります。会員団体の皆様におかれましても熱中症などお気をつけてご自愛をお願いいたします。さて先日の運営委員会で今年度の活動について日程や担当など大まかな役割分担を決めました。市民等への啓発活動となるイベントも単発ではなく、様々な障害の理解について、またライフステージにおける様々な問題をテーマに継続的に取り組めていけないかと意見交換しました。皆様のご意見やアイデアなど多く取り入れいていきたく、運営委員会等へのオブザーバー参加をお願いいたします。
話は変わりますが、いわゆる障害者総合支援法の一部改正が国会で承認され平成30年施行を予定しています。改正ポイントとして、自立生活援助や就労定着、重度訪問介護の訪問先拡大などうたわれています。他にも児童医療や発達支援など児童に対する法改正がみられます。高齢の障害者の方々と介護保険との関係については、障害者サービスでは無料であったサービスが1割負担になる制度上の違いがあり、60歳もしくは65歳以上の方々が利用料が発生する弊害があります。今回の法改正ではこの利用料に着目した改正とサービス提供の事業所が介護保険制度へ事業所として移行しやすいことを謳われています。厚生労働省は当初から少子高齢化の現実を直視して介護保険と障害者分野の制度的統合を進めてきました。高齢化の障害がある方にとっては、サービス提供の考え方の場合によっては介護保険優先という制度が弊害になる恐れがあります。この辺りを懸念して、衆議院厚生労働委員会では付帯決議の二として障害者が高齢になっても障害、高齢者両制度を尊重しつつも、ニーズに即した必要なサービスが円滑に受けられるよう実態を踏まえて検討していくべきことが明記されています。はたして生活の現場ではどのように制度が運用されるのでしょうか。とはいえ少子高齢化の波は押し寄せており、従来の発想では太刀打ちできないことは明らかです。私たち一人ひとりの発想の転換が望まれます。と同時に普遍的に人と人が支え合うために必要なものは何かという価値観が求められる時代だと感じます。
(文責/事務局 有賀)
【今後のスケジュール】
✦ 8月例会より、恒例の「隔月企画」を始めます。今回は、八障連には加盟してませんが、活発に活動している団体さんにお願いしております。現在日程を含め調整中です。ぜひご参加ください。✦ 情報発信したいという会員団体の投稿を引き続き募集しております。投稿先 cxb01672@nifty.com 八障連通信掲載希望とお書きください。(編集部)
八障連運営委員会
7月21日(木) 18:00~20:00 クリエイト試食コーナー
八障連例会・隔月企画
8月25日(木) 18:00~20:00 クリエイト試食コーナー
【「第13回透析サロン」開催さる。~八王子市の障害者災害対策について~】
去る6月26日(日)、クリエイトホールにて、八王子腎友会の総会と第13回透析サロンが開催されました。八障連からも、杉浦代表を含め3名が参加しました。八腎会事務局長の岩崎氏に「透析サロン」のレポートをご執筆いただきましたので、掲載させていただきます。(編集部)
八王子市地域腎友会(以下「八腎会」)は、去る6月26日(日)午後「第13回透析サロン」を開設いたしましたので、今回は「八障連通信」誌上にて、簡単にその報告をさせていただきます。
今回の透析サロンのテーマは、「八王子市における障害者の災害対策」です。私達透析患者は、災害時にライフラインがストップし、電気と水が供給されないと、人工透析治療が不能に陥り、さらにずっと透析ができなければ、できなくなった日からの余命は1週間から10日とされています。このことが、大地震がいつ起きても不思議ではない状況下にあって、「八腎会」が今回本テーマを選定した主な理由です。
障害者の災害対策を考えるときも、また災害が起きたときにも、「自助・共助・公助」の意識が大切と言われています。こうした意識をベースに平成27年度八王子市福祉部障害者福祉課が発行した冊子「障害がある方のための防災マニュアル(自助部分)」と平成26年度同じく障害者福祉課が発行した冊子「災害時障害者サポートマニュアル(共助・公助部分)」について、透析サロン当日参加者全員に本冊子(2冊)を配布し、障害者福祉課所属の担当の方から、二つのマニュアルの概要説明と質疑応答をしていただきました。そしてその前に、八王子市生活安全部防災課所属の担当の方から、「最新の大地震予測とそれぞれの八王子市の被害想定・防災対策」についても、同様の対応をしていただきました。(ここでは具体的内容は割愛)
以上一連の概要説明と質疑応答の中で、浮かび上がってきた問題(課題)がとりあえず二つありました。それは、「二次避難所(福祉避難所)の整備問題」と「災害時要援護者避難支援制度の活用問題」です。以下二つの問題について、整理しておきましょう。
【1】二次避難所(福祉避難所)の整備問題について
①二次避難所(福祉避難所)とは、私達障害者のみならず、介護必要者、高齢者、妊産婦、乳幼児、病者等、一般的な避難所では、生活に支障をきたすいわゆる「災害時要援護者」及びその家族や介護者等のために特別な配慮がされた避難所です。
②八王子市が指定し協定書を取り交わした福祉避難所は、平成27年4月1日現在わずか10箇所に過ぎずもっと増やす必要があり、加えて福祉避難所においては、施設整備(耐震構造化含む)、物資・器材・支援人材・移送手段の確保、医療機関との連携、運営体制の整備等について、あらかじめ事前準備をしておかなければなりませんが、これらの点、八王子市はまだ不十分と言わざるを得ません。
③「八腎会」としては、平成28年4月内閣府(防災担当)発行の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」に基づき、八王子市の福祉避難所の整備問題については、今後しっかりとフォロー・対応をしていきたいと考えています。
【2】災害時要援護者避難支援制度の活用問題について
①大地震等の災害発生時や災害のおそれがあるとき、「災害時要援護者」に対し、災害に関する情報の伝達や避難などの手助けが、地域の中で速やかに安全に行われるための共助・公助の仕組みが本制度の概要です。
②八王子市内の町会・自治会・自主防災組織等が本制度の核となる「地域支援組織」になるためには、市役所に登録し覚書を取り交わさなければなりませんが、平成28年6月現在たったの12箇所しかできておりません。八王子市の町会・自治会等が570存在しますので、「地域支援組織」結成率は、12/570=2.1%と極めてわずかです。これでは八王子市全体として、この組織を中心に要援護者の支援者の募集、決定、支援方法(=避難支援プラン<個別計画>)の策定や八王子市からの要援護者情報の提供といった一連のプロセスが全く前に進めない状況になっています。
③「八腎会」としては、「八腎会」所属の会員に所属する町会・自治会等の会長・役員に対し、まずは「地域支援組織」として市役所へ登録するよう働きかけをお願いすることにしております。「八障連」も同様の対応をお願いいたします。
以上の他、「障害者の災害対策」には、喫緊の課題や足らざるところが多々ありますので、今後も「八腎会」としては、4名の顧問市議の協力を得て市議会への上程や場合によってはしかるべき方法も考えながら、先行き厳しい状況が予想されても、精一杯頑張っていきたいと考えています。
なお、今回の透析サロンに「八障連」三役の方々が傍聴に訪れ、杉浦代表には、冒頭挨拶もしていただ
きましてありがとうございました。今後とも一層のご協力をお願いいたします。(文責:「八腎会」事務局長「岩崎正宏」)
●◎★□◆会場で配布・説明された災害時のマニュアル本です。◆□★◎●福祉関係の事業所へも配布されましたが、みなさんお読みになったことはありますか?障害当事者向けのマニュアルとサポートする側のマニュアルがあります。災害時は障害当事者であってもサポートする側になる場合もあります。そういった意味にでは他障害のことも理解する窓口になるマニュアルです。画像下のアドレスでPDF版がダウンロードできます。是非ご覧になってください。
(編集部注)
災害時 障害者サポートマニュアルhttp://www.city.hachioji.tokyo.jp/moshimo/bosai/051123.html
障害がある方のための防災マニュアルhttp://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/53849/050944.html
【連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小濱 義久】
闘病記 その6
肝臓は血液検査だけでは病態像(肝臓の組織がどれくらいダメになっているか)が掴めない。そこで、まずは腹腔鏡で肝臓の表面を観察する検査を行う。お腹に1㎝くらいの穴をあけ、そこから腹腔鏡を挿入し、お腹を臨月状態くらいに膨らませ、肝臓を肉眼で観察するのである。最後には手元の先に写真機がセットされ、撮影される。我々がたまに食べるレバ刺しのように滑らかであれば問題ないのだが、表面が凸凹しているようなら、肝臓細胞の線維化が進行してきている現れであり、肝硬変が疑われる。写真機のシャッター音が何回もし、意外と原始的だなと感じた(デジカメがまだなかった時代のことである)。
その後、「今から肝生検の針を刺します」と声がかかり、針が刺されたのだが、鈍痛とともに小さな衝撃を感じた。ドスンというような音も聞こえた感じがし、得も言われぬ気色悪い感覚が身体を駆け巡った。「オー、マイゴッド」。全身が硬く硬直し、口も固く閉ざされたままだった。
針の中に取り込まれた肝細胞は顕微鏡でどれだけダメになっているかが調べられる訳だが、組織学的には、CPA、CH2A、CH2B、肝硬変という順番に悪くなっていく。ここに大きな問題がひとつある。
CPAからCH2Bの間は可塑的なのだが、CH2Bと肝硬変の間には大きな溝があり、一旦肝硬変になると元の健康な組織に戻らないと考えられている。先日亡くなった私の大好きな先輩でもある故野坂昭如が、「~間には深くて暗い溝がある」と歌っていたっけ。つまり、肝硬変とは、ほぼ死への片道切符で、肝硬変から肝癌、肝不全になって亡くなるしかないのである。10年というのが一つの目安だろうか。
肝硬変からCH2Bに戻ることを軟化と言うが、最近は軟化する人がたまにはいることが分かってきている。でも、何故、どうしたら軟化するかはまだよく分かっていない。虎の門病院では軟化ケースの統計はないが、5000人位に一人くらいの割合か、もう少し高い確率かもしれないと去年12月に入院した時の担当医が教えてくれた。最初の癌になってから既に21年が過ぎたが、まだ元気いっぱいだ。熊田Drも、地域の家庭医である山田Dr(八王子中央診療所)も吃驚している。ここまで来たら、いっそ軟化まで成し遂げようじゃないかと最近アスリート魂に火が付いた。
「なんかなぁ~」。
通信本文はここまで。