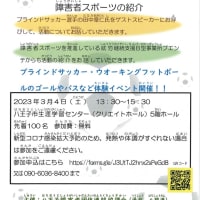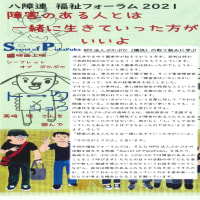こんにちは。ブログ更新が滞っておりました。申し訳ありません。昨年の通信になりますが、八障連通信306号をアップします。
八障連通信306号【PDF版】はこちらから
これより、八障連通信306号本文となります。
八障連通信Vol.306 Hasshoren Tsushin
2015.12.15 八王子障害者団体連絡協議会月刊ニュースレター Tel: 080-3451-8400 E-mail: hasshoren8.zim@softbank.ne.jp
【11 月例会 (八視協 八視協 報告 )・市議 懇談会の 懇談会の報告】
11月17日の例会は、隔月企画として好評の「参加団体からの活動報告として、八視協の福田理事長から、会の発足から現在に至るまでの歩みを中心にお話をいただきました。八視協は今年で70周年を迎える、長い歴史を経て現在に至っています。発足当初は、視覚、聴覚、肢体(したい)の方を中心に「八王子障害者協会」として活動されていましたが、それぞれの当事者が抱える課題の困難さから昭和40年代から50年代にかけて独立した団体へと別れ、視覚障害者の方40名~50名くらいの当事者を中心に八視協として活動を継続されました。平成20年にはNPO法人格を取得して現在に至っています。平成10年までは入会者も多く、会員も120名を超えていましたが、当事者の方の高齢化などで現在は60名前後の会員数となっているそうです。やはり視覚障害者の方の問題として、「行動の自由の確保(外出の困難の克服)とともに、「情報をいかに取得するかが大きな課題であることを強調しておられました(報告の詳細は「八視協活動紹介をご参照ください)。その他の議論として、八障連主催の上映会として「風は生きよという」の上映について議論されました。来年になりますが、3月16日(土)14時より八王子労政会館で行うことが決まりました。詳細は今後の運営委員会で検討することとなりますが、ぜひ多くの会員の参加をお願いしたいと思います。
2月26日の市議との懇談会は、八王子市議会議員6会派11名の方に参加していただきました。八障連側は、10団体15名の参加がありました。テーマは①障害者差別禁止条例施行のその後の状況について、②地域活動支援センターの状況について、③住宅マスタープラン計画から見える地域の障害者支援についてでした。差別禁止条例が施行されても、例えば住んでいる近隣に「グループホーム」ができると、反対運動が起こり、議員さんが地域住民の方とグループホームを進める障害者団体との板挟(いたばさ)みにあい苦悩するケースもあって、必ずしも差別禁止条例の理念が地域住民のレベルに根付いていないなどの指摘もありました。その他職場と家との往復に疲れたり、家に閉じこもる傾向がある当事者の方を、地域につなぎとめる居場所としての「地活Ⅲ型」事業所(パオ、地域活動支援センターわくわく)の重要性や、教育の問題、農業地の利用に関する課題など多岐にわたり、終了が予定時間を大きく超えてしまうほど充実した懇談会となりました。参加された議員の皆様、また八障連参加団体の皆さまご苦労様でした。なお、懇談会の詳細は、レポートを参照ください。(文責/編集部)
【八障連例会隔月企画 八 視 協 の 活 動 紹 介 NPO 法人八王子視覚障害者福祉協会 理事長・福田謹一】
本日はNPO法人八王子視覚障害者福祉協会、略して八視協に貴重な時間を与えていただき、ありがとうございます。名称からもおわかりかと思いますが、この団体は、視覚に障害のある者が自らの意思により集まった会です。それでは簡単に、これまでの歴史からお話しします。
会の発足は昭和18年といいますから、まだ太平洋戦争中でありました。昭和20年代は、現在も私たちの主たる職業となっています三療(あんま・マッサージ・指圧、鍼、灸)の組合と一緒に活動しておりました。それが、30年代に入り、視覚、聴覚、肢体(したい)の3団体が一つの組織を作り、市の補助金も受けて行事を行うようになりました。ところが、40年代に入ると、一緒ではなかなか難しい面が出てきたことで、それぞれの団体に分かれた活動が徐々に増えていきました。そして50年代前半に、とうとう視覚、聴覚、肢体(したい)のそれぞれの団体として、はっきり分かれてしまいました。以後、八視協は独自の団体として市の補助金を受けられるようになるなど、活動を活発化させていきました。会員数も、分かれた当時は40~50人だったものが、平成10年前後には120名余りと、2倍以上になっていました。この会員数の増加には、もちろん、会の活動に活気があったこと、そして糖尿病や網膜色素変性症(もうまくしきそへんせいしょう)などで社会に出てから失明したり、見えにくくなる人が多くなってきたという社会的背景もあったと思います。しかし、その後会員の高齢化が進み、行事に参加できないからと、やめていく人、お亡くなりになる方、路線の違いということもあったようですが、一転して減少傾向になってしまいました。
そんな中でも、平成20年にはNPO法人格を取得し、地域支援事業の「移動支援」、ガイドヘルパー派遣事業を、社協から譲り受ける形でスタートさせました。 八視協がこの事業を行うことを決意したのは、そのことにより、視覚障害当事者の考えをより反映できること、また、それによりガイドヘルパーの質の向上も図れるのではないか、そして、何と言っても、この事業によって収入の増加が期待できるのではないかとの考えからだったと思います。
次に、会員の状況ですが、現在は60数名となっています。入会者がないわけではありませんが、高齢者が多いことで、やめる人、お亡くなりになる方もありますので、なかなか増加傾向とはなっていません。また、会活動に参加できる人も限られていますので、役員への負担がどうしても多くなっています。やはり、若者を含む多くの入会者を迎えるには、多くの会員が目標にできる具体的なものを定めるなど、会の活動を活気あるものにしていく必要があると考えています。
最後に「はなみずき」を含む八視協の経営状況ですが、なかなか苦戦しています。ところで、この「はなみずき」ですが、これは通称であります。正式には、八視協の中に七つある部の一つで「事業部」になります。この事業部(はなみずき)でガイドヘルプ事業を行っていますが、このガイド派遣事業は、発足当時の「移動支援」から、平成24年4月より、国の方針に従い、「同行援護」となりました。国が主管になったことで、この事業を行える条件も厳しくなりました。例えば、この「はなみずき」への視覚障害当事者(利用者)40人に1人の割合で「サービス提供責任者」という資格を有する常勤の職員を置かなければなりません。そんなわけで、現在の八視協の職員は常勤3名(うちサービス提供責任者2名)、パートタイマー1名となっています。そのほか、法人格のため、法律に基づく社会保険等人件費がかなり、かかります。そんなわけで、昨年は赤字決算でした。それでも今年度は、八視協の運動によりガイドヘルパーを利用できる時間が一カ月に30時間から40時間に増えました。これで何とか赤字を出さずに済むのではないかと期待しているところです。
わかりにくい説明になってしまったようですが、八視協の紹介をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
【連載コラム 『日々のなかから 、』 <人生の 価値 > VolVol .38 八障連 代表 杉浦 貢】
前回の続きですが…》
養護学校に通っていた時…一番イヤだったのが…
『杉浦くんはいいね。言葉もしゃべれて身体も元気で…一緒にお話も出来るもんね』
などと、入学からから卒業までずっと言われ続けてきたことでしょうか。その言葉をかけてきたのは…同級生のお父さんやお母さんだったり、先生たちだったり、時によって色々でした。私を持ち上げるために色々と褒(ほ)めた讃(たた)えてくれたのでしょうが…私の気持ちは複雑でした。素直に喜ぶことができませんでした。
考えてみてください…養護学校(特別支援学校)というところは、みなが何らかの障害を抱えながら勉強する場所です。障害の程度…軽度重度の差はあっても、誰もが困難と向き合っていることには差など無いはずだと思うのです。
言語障害かある子も…身体が弱い子も、知能や発達に遅れのある子もたくさんいました。それらが無い方がいい、障害が軽い方がいいというなら、突き詰めていけば障害児に生きる意味が無いということになってしまいます。
普通学校で過ごすうちに疲れ果て…ついに自分の居場所を見つけられなかった私にとって、これは大きなショックでした。障害があってもより良く生きるやり方を学ぶために入ったつもりだったのに…障害が軽ければいい。つまり健常者に近ければいいというのは…とても褒(ほ)められた気分にはなれません。
どんなに重度の障害があっても、それは本人の責任では無いし、障害のある子が産まれたこともまた両親の責任ではありません。私の障害程度が今のようになったのも、私の認識や自覚の及ぶところではありません。自分のあずかり知らぬ運や天の部分を話題にされても、呆然(あぜん)とするばかりで、舞い上がる気にはとてもなりません。
いくら言葉ばかり口先ばかりで褒(ほ)め称(たた)えられていても…、『障害が軽ければいい…いっそ、ない方がいい』 というのが、あるいは社会の本音であるならば、障害と共に産まれてきた子どもたちは…とりわけ重度の障害を持って産まれてきた子は、一体何を誇りにして生きていけばいいのでしょうか。
医学的な障害に関わらず、人間にはそれぞれ持って産まれたものがあります。それは人格としての器の大きさであったり、あるいは運と呼ばれるものかも知れません。それぞれが持って産まれたものを活(い)かし、失敗や挫折を繰り返しながら自分の器量を試して生きるのが、人間の当たり前の姿ではないでしょうか。
たとえ人並みに読み書きそろばんができなくても、寝たきりで、息をするのがやっとの子どもであったとしても、共に過ごし生きられる時間が短かったとしても…それぞれが持てるものを精一杯に使って自分の時間を生きることに、はたしてなんの違いがありましょうや。
障害の有無や、障害の重度軽度に関わらず、成長段階の子どもたちが自分の生き甲斐(がい)を見つけるための手助けをするのも『学校』と名の付く場所の、大切な役割ではないでしょうか。私も競争に負けて挫折した子どもでした。勝ち残り、登り詰めることは素晴らしい行為でしょう。それを否定はしませんが、障害のある子どもたちは他人との競争には弱いかも知れないけれど、誰にも評価されないところで、常に自分自身と戦っているということを、どうか忘れないであげて欲しいのです。
【連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小 義】
闘病史 その2
初めて肝機能値に異常が出現した1982年末以来の検査で(と言ってもわずか2ヶ月振りの事なのだが)、正常値になっていないかと期待したが、GOT、GPT値が40~50を示しており、明らかに無症候性キャリアー(ウイルスを持っていても発病していない状態)ではなくなったことを示していた。10分の1の確率に入ってしまったという複雑な気持ちは、やっぱりなという諦観(ていかん)とないまぜになって狂おしく心をかき乱した。肝硬変、肝がんというシナリオが頭をよぎる。肺結核の為39歳で亡くなった母と同じような運命を辿(たど)るのかと半ば予期していたが故の諦観(ていかん)でもあった。
なんて芝居がかった言い方をせずとも、熊田Drから発病している旨のご宣託(せんたく)を受けた。肝臓がどのような病態にあるかは、入院して腹腔鏡検査をし、肝臓の細胞を採取して組織検査(バイオプシ)をしないと分からないとのことで、帰りに入院の手続きをして帰るよう言われ、待ちくたびれ、疲れ果てた診察が終わったのはもう夕方に近い頃だった。初診の帰りに入院の手続きという事態の進展の速さに面くらいながら、幾分あたふたしていたように思う。どころではなく、しっかり動揺していた。
肝臓の病態と言うのは、正常な肝臓、慢性肝炎(1A、2A、2B)、肝硬変、肝癌(かんがん)の6種類を指す。慢性肝炎である限り、症状がなくなり、炎症が収まれば、2Bから1Aにまで改善し、正常な肝臓まで戻るのだが、肝硬変に至るとそこには大きな溝があり、決して正常な肝臓へは戻らないのだ。男と女の間に深くて暗い溝があるという歌があったが、慢性肝炎と肝硬変は、この男と女の関係のように越えがたい断絶がある。それを調べるのは実際の肝臓の組織を取り出し、顕微鏡で確かめるしかない。
肝 臓に注射針を突き刺して、肝臓組織を採取する訳で、「ウララ、ウララ、ウラウラよ、お前の肝臓狙(ねら)いうち」と山本リンダの声が浮かんできた。入院窓口で申し込みの手続きをしたが、これも大変な混みようで、いつになるか分からないと言う。まあ2ヶ月くらいはお待ちいただくことになるでしょう。病院から電話連絡が行きますので、直ぐ入院できるような態勢を取っておいて下さいと言われ、千鳥足(ちどりあし)のように与太(よた)りながら帰途に就いた。(続く)
【今後の予定】
八障連運営委員会
12月17日(木) 18:00~20:00 クリエイト 第1学習室
映画「風は生きよという」上映会
2016年3月16日(土) 13:30~17:00 労政会館
通信本文はここまで。
八障連通信306号【PDF版】はこちらから
これより、八障連通信306号本文となります。
八障連通信Vol.306 Hasshoren Tsushin
2015.12.15 八王子障害者団体連絡協議会月刊ニュースレター Tel: 080-3451-8400 E-mail: hasshoren8.zim@softbank.ne.jp
【11 月例会 (八視協 八視協 報告 )・市議 懇談会の 懇談会の報告】
11月17日の例会は、隔月企画として好評の「参加団体からの活動報告として、八視協の福田理事長から、会の発足から現在に至るまでの歩みを中心にお話をいただきました。八視協は今年で70周年を迎える、長い歴史を経て現在に至っています。発足当初は、視覚、聴覚、肢体(したい)の方を中心に「八王子障害者協会」として活動されていましたが、それぞれの当事者が抱える課題の困難さから昭和40年代から50年代にかけて独立した団体へと別れ、視覚障害者の方40名~50名くらいの当事者を中心に八視協として活動を継続されました。平成20年にはNPO法人格を取得して現在に至っています。平成10年までは入会者も多く、会員も120名を超えていましたが、当事者の方の高齢化などで現在は60名前後の会員数となっているそうです。やはり視覚障害者の方の問題として、「行動の自由の確保(外出の困難の克服)とともに、「情報をいかに取得するかが大きな課題であることを強調しておられました(報告の詳細は「八視協活動紹介をご参照ください)。その他の議論として、八障連主催の上映会として「風は生きよという」の上映について議論されました。来年になりますが、3月16日(土)14時より八王子労政会館で行うことが決まりました。詳細は今後の運営委員会で検討することとなりますが、ぜひ多くの会員の参加をお願いしたいと思います。
2月26日の市議との懇談会は、八王子市議会議員6会派11名の方に参加していただきました。八障連側は、10団体15名の参加がありました。テーマは①障害者差別禁止条例施行のその後の状況について、②地域活動支援センターの状況について、③住宅マスタープラン計画から見える地域の障害者支援についてでした。差別禁止条例が施行されても、例えば住んでいる近隣に「グループホーム」ができると、反対運動が起こり、議員さんが地域住民の方とグループホームを進める障害者団体との板挟(いたばさ)みにあい苦悩するケースもあって、必ずしも差別禁止条例の理念が地域住民のレベルに根付いていないなどの指摘もありました。その他職場と家との往復に疲れたり、家に閉じこもる傾向がある当事者の方を、地域につなぎとめる居場所としての「地活Ⅲ型」事業所(パオ、地域活動支援センターわくわく)の重要性や、教育の問題、農業地の利用に関する課題など多岐にわたり、終了が予定時間を大きく超えてしまうほど充実した懇談会となりました。参加された議員の皆様、また八障連参加団体の皆さまご苦労様でした。なお、懇談会の詳細は、レポートを参照ください。(文責/編集部)
【八障連例会隔月企画 八 視 協 の 活 動 紹 介 NPO 法人八王子視覚障害者福祉協会 理事長・福田謹一】
本日はNPO法人八王子視覚障害者福祉協会、略して八視協に貴重な時間を与えていただき、ありがとうございます。名称からもおわかりかと思いますが、この団体は、視覚に障害のある者が自らの意思により集まった会です。それでは簡単に、これまでの歴史からお話しします。
会の発足は昭和18年といいますから、まだ太平洋戦争中でありました。昭和20年代は、現在も私たちの主たる職業となっています三療(あんま・マッサージ・指圧、鍼、灸)の組合と一緒に活動しておりました。それが、30年代に入り、視覚、聴覚、肢体(したい)の3団体が一つの組織を作り、市の補助金も受けて行事を行うようになりました。ところが、40年代に入ると、一緒ではなかなか難しい面が出てきたことで、それぞれの団体に分かれた活動が徐々に増えていきました。そして50年代前半に、とうとう視覚、聴覚、肢体(したい)のそれぞれの団体として、はっきり分かれてしまいました。以後、八視協は独自の団体として市の補助金を受けられるようになるなど、活動を活発化させていきました。会員数も、分かれた当時は40~50人だったものが、平成10年前後には120名余りと、2倍以上になっていました。この会員数の増加には、もちろん、会の活動に活気があったこと、そして糖尿病や網膜色素変性症(もうまくしきそへんせいしょう)などで社会に出てから失明したり、見えにくくなる人が多くなってきたという社会的背景もあったと思います。しかし、その後会員の高齢化が進み、行事に参加できないからと、やめていく人、お亡くなりになる方、路線の違いということもあったようですが、一転して減少傾向になってしまいました。
そんな中でも、平成20年にはNPO法人格を取得し、地域支援事業の「移動支援」、ガイドヘルパー派遣事業を、社協から譲り受ける形でスタートさせました。 八視協がこの事業を行うことを決意したのは、そのことにより、視覚障害当事者の考えをより反映できること、また、それによりガイドヘルパーの質の向上も図れるのではないか、そして、何と言っても、この事業によって収入の増加が期待できるのではないかとの考えからだったと思います。
次に、会員の状況ですが、現在は60数名となっています。入会者がないわけではありませんが、高齢者が多いことで、やめる人、お亡くなりになる方もありますので、なかなか増加傾向とはなっていません。また、会活動に参加できる人も限られていますので、役員への負担がどうしても多くなっています。やはり、若者を含む多くの入会者を迎えるには、多くの会員が目標にできる具体的なものを定めるなど、会の活動を活気あるものにしていく必要があると考えています。
最後に「はなみずき」を含む八視協の経営状況ですが、なかなか苦戦しています。ところで、この「はなみずき」ですが、これは通称であります。正式には、八視協の中に七つある部の一つで「事業部」になります。この事業部(はなみずき)でガイドヘルプ事業を行っていますが、このガイド派遣事業は、発足当時の「移動支援」から、平成24年4月より、国の方針に従い、「同行援護」となりました。国が主管になったことで、この事業を行える条件も厳しくなりました。例えば、この「はなみずき」への視覚障害当事者(利用者)40人に1人の割合で「サービス提供責任者」という資格を有する常勤の職員を置かなければなりません。そんなわけで、現在の八視協の職員は常勤3名(うちサービス提供責任者2名)、パートタイマー1名となっています。そのほか、法人格のため、法律に基づく社会保険等人件費がかなり、かかります。そんなわけで、昨年は赤字決算でした。それでも今年度は、八視協の運動によりガイドヘルパーを利用できる時間が一カ月に30時間から40時間に増えました。これで何とか赤字を出さずに済むのではないかと期待しているところです。
わかりにくい説明になってしまったようですが、八視協の紹介をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
【連載コラム 『日々のなかから 、』 <人生の 価値 > VolVol .38 八障連 代表 杉浦 貢】
前回の続きですが…》
養護学校に通っていた時…一番イヤだったのが…
『杉浦くんはいいね。言葉もしゃべれて身体も元気で…一緒にお話も出来るもんね』
などと、入学からから卒業までずっと言われ続けてきたことでしょうか。その言葉をかけてきたのは…同級生のお父さんやお母さんだったり、先生たちだったり、時によって色々でした。私を持ち上げるために色々と褒(ほ)めた讃(たた)えてくれたのでしょうが…私の気持ちは複雑でした。素直に喜ぶことができませんでした。
考えてみてください…養護学校(特別支援学校)というところは、みなが何らかの障害を抱えながら勉強する場所です。障害の程度…軽度重度の差はあっても、誰もが困難と向き合っていることには差など無いはずだと思うのです。
言語障害かある子も…身体が弱い子も、知能や発達に遅れのある子もたくさんいました。それらが無い方がいい、障害が軽い方がいいというなら、突き詰めていけば障害児に生きる意味が無いということになってしまいます。
普通学校で過ごすうちに疲れ果て…ついに自分の居場所を見つけられなかった私にとって、これは大きなショックでした。障害があってもより良く生きるやり方を学ぶために入ったつもりだったのに…障害が軽ければいい。つまり健常者に近ければいいというのは…とても褒(ほ)められた気分にはなれません。
どんなに重度の障害があっても、それは本人の責任では無いし、障害のある子が産まれたこともまた両親の責任ではありません。私の障害程度が今のようになったのも、私の認識や自覚の及ぶところではありません。自分のあずかり知らぬ運や天の部分を話題にされても、呆然(あぜん)とするばかりで、舞い上がる気にはとてもなりません。
いくら言葉ばかり口先ばかりで褒(ほ)め称(たた)えられていても…、『障害が軽ければいい…いっそ、ない方がいい』 というのが、あるいは社会の本音であるならば、障害と共に産まれてきた子どもたちは…とりわけ重度の障害を持って産まれてきた子は、一体何を誇りにして生きていけばいいのでしょうか。
医学的な障害に関わらず、人間にはそれぞれ持って産まれたものがあります。それは人格としての器の大きさであったり、あるいは運と呼ばれるものかも知れません。それぞれが持って産まれたものを活(い)かし、失敗や挫折を繰り返しながら自分の器量を試して生きるのが、人間の当たり前の姿ではないでしょうか。
たとえ人並みに読み書きそろばんができなくても、寝たきりで、息をするのがやっとの子どもであったとしても、共に過ごし生きられる時間が短かったとしても…それぞれが持てるものを精一杯に使って自分の時間を生きることに、はたしてなんの違いがありましょうや。
障害の有無や、障害の重度軽度に関わらず、成長段階の子どもたちが自分の生き甲斐(がい)を見つけるための手助けをするのも『学校』と名の付く場所の、大切な役割ではないでしょうか。私も競争に負けて挫折した子どもでした。勝ち残り、登り詰めることは素晴らしい行為でしょう。それを否定はしませんが、障害のある子どもたちは他人との競争には弱いかも知れないけれど、誰にも評価されないところで、常に自分自身と戦っているということを、どうか忘れないであげて欲しいのです。
【連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小 義】
闘病史 その2
初めて肝機能値に異常が出現した1982年末以来の検査で(と言ってもわずか2ヶ月振りの事なのだが)、正常値になっていないかと期待したが、GOT、GPT値が40~50を示しており、明らかに無症候性キャリアー(ウイルスを持っていても発病していない状態)ではなくなったことを示していた。10分の1の確率に入ってしまったという複雑な気持ちは、やっぱりなという諦観(ていかん)とないまぜになって狂おしく心をかき乱した。肝硬変、肝がんというシナリオが頭をよぎる。肺結核の為39歳で亡くなった母と同じような運命を辿(たど)るのかと半ば予期していたが故の諦観(ていかん)でもあった。
なんて芝居がかった言い方をせずとも、熊田Drから発病している旨のご宣託(せんたく)を受けた。肝臓がどのような病態にあるかは、入院して腹腔鏡検査をし、肝臓の細胞を採取して組織検査(バイオプシ)をしないと分からないとのことで、帰りに入院の手続きをして帰るよう言われ、待ちくたびれ、疲れ果てた診察が終わったのはもう夕方に近い頃だった。初診の帰りに入院の手続きという事態の進展の速さに面くらいながら、幾分あたふたしていたように思う。どころではなく、しっかり動揺していた。
肝臓の病態と言うのは、正常な肝臓、慢性肝炎(1A、2A、2B)、肝硬変、肝癌(かんがん)の6種類を指す。慢性肝炎である限り、症状がなくなり、炎症が収まれば、2Bから1Aにまで改善し、正常な肝臓まで戻るのだが、肝硬変に至るとそこには大きな溝があり、決して正常な肝臓へは戻らないのだ。男と女の間に深くて暗い溝があるという歌があったが、慢性肝炎と肝硬変は、この男と女の関係のように越えがたい断絶がある。それを調べるのは実際の肝臓の組織を取り出し、顕微鏡で確かめるしかない。
肝 臓に注射針を突き刺して、肝臓組織を採取する訳で、「ウララ、ウララ、ウラウラよ、お前の肝臓狙(ねら)いうち」と山本リンダの声が浮かんできた。入院窓口で申し込みの手続きをしたが、これも大変な混みようで、いつになるか分からないと言う。まあ2ヶ月くらいはお待ちいただくことになるでしょう。病院から電話連絡が行きますので、直ぐ入院できるような態勢を取っておいて下さいと言われ、千鳥足(ちどりあし)のように与太(よた)りながら帰途に就いた。(続く)
【今後の予定】
八障連運営委員会
12月17日(木) 18:00~20:00 クリエイト 第1学習室
映画「風は生きよという」上映会
2016年3月16日(土) 13:30~17:00 労政会館
通信本文はここまで。