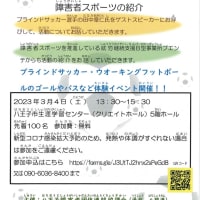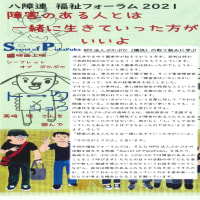八障連319号をアップします。
八障連通信319号【PDF版】はこちらから。
通信本文はここから
【事務局通信 Vol.32】
あけましておめでとうございます。皆様にとって2017年が益々のご健勝の年となりますようお祈り申し上げます。さて、八障連としましては、色々な挑戦と、継続を考えつつ、皆様に情報の提供等を本年も行っていきたいと考えております。まずは、2017年の第一弾として、八王子市内にある「Hachiouji FARMERS Kitchenふぁむ」を運営している「グッドホーム」さんの活動報告を1月26日(木)の例会・隔月企画にて行います。「Hachiouji FARMERS Kitchenふぁむ」は八王子市内の生産者の方と連携して「無農薬野菜」の素材を中心に作った「自然食・薬膳」料理を提供しています。現状と今後の抱負を語っていただきます。ご期待ください。また昨年11月に開催予定であった八王子市議会との懇談会についてですが、2月中に開催を行うこととして調整中です。内容としましては「農福の問題」や「生活保護の課題点」などの課題を議論していきたいと考えております。さらに3月には、恒例となった八障連主催の「福祉フォーラム」として映画上映と講師の方をお迎えしての意見交換など計画中です。また2017年4月以降になりますが法政大学の生徒さんたちと障害体験&意見交換会(イベント名決まってませんが…)を計画中です。そのほかにもイベント等計画をしていることもありますので、ぜひこれを機に八障連の活動に参加したいという方を募集したいと思います。多くの方に参加していただき、より良い方向に進めていきたいと考えていますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。(文責/事務局 立川)
【今後のスケジュール】
✦ 1月26日(木)の八障連例会の隔月企画は、グッドホームさんからの報告となります。グッドホームさんは、無農薬野菜の素材で作った自然食・薬膳料理を提供する「HACHIOJI FARMERS KITCHENふぁむ」を運営しておられます。現状と今後の抱負を語っていただきます。ぜひご参加下さい。
✦ 昨年11月、54年ぶりの雪のため中止となりました「市議会議員との懇談会」は、2月20日(月)18:30よりクリエイトホール第2会議室にて開催します。ぜひご参加ください。
✦八障連主催の福祉フォーラムを3月18日(土)に開催します。映画上映とともにお招きした講師の方との対談形式での意見交換を予定してます。ご期待ください。
八障連例会(隔月企画・グッドホームさんからの報告)
1月26日(木)
18:30~20:30
クリエイト第5学習室
八障連運営委員会
2月16日(木)
18:30~20:30
クリエイト試食コーナー
八障連主催「市議会議員との懇談会」
2月20日(月)
18:30~20:30
クリエイト第2会議室
障害者地域生活支援拠点等事業報告会
2月26日(土)
10:00~12:00
労政会館2階ホール
八障連福祉フォーラム
3月18日(土)
13:30~16:00
クリエイト
【2017年・年頭のご挨拶 八障連代表 杉浦 貢】
あけましておめでとうございます。
さて、2016年を振り返れば、「障害者としてどう生きるのか」、「社会の一員としての障害者とは、どうあるべきか」を問われ続けた一年であったように思います。
昨年4月1日に施行された差別解消法は、我々障害当事者の宿願とも言うべきものだったのですが…問題点も多いのです…。この障害者差別解消法が出来るまではバリアフリー法、(平成18年12月20日施行)などで対応していましたが、民主党が政権を取ったときに自民党政権では批准してこなかった、国連の障害者権利条約を批准しました(先進国では凄く遅いですが)。差別解消法が施行されて、何が変わったのかと言うと…一番大きな点が、合理的配慮が社会の義務になったことです。
合理的配慮とは、日常生活や社会生活を営む中で、障がいの種類やその程度において社会が障害者に対して配慮することを言います。この合理的配慮が社会の義務になったことはいいのですが、配慮する側の負担が大きい場合は合理的配慮を行わなくても良いと書かれているのです。合理的配慮は義務になったと言いますが、民間企業は努力義務なので、たとえ違反しても何の罰則もないのです。厚生労働省の話では3年後に法律を一度見直すことになっています。日本は国連の障害者権利条約を批准したものの、福祉制度が世界の水準に達していないので、3年かけて世の中を変えていこうというのがお役人の思惑のようです。
リオデジャネイロオリンピックの後に開かれたパラリンピックも、それまでの大会にありがちだった『かわいそうな人たちが、一生懸命頑張っています』という扱われ方はあまりされなくなり、本家オリンピックと同等…とまではいかなくとも…一級のアスリートたちが参加する一級のスポーツイベントとして、日本の人々にも認知されるようになったと思います。しかし、障害のある人を社会の一員、市民の一人として受け入れるところまでは、世の中の空気は醸成されませんでした。あくまでも、『すごい人たちが素晴らしい偉業を成し遂げた』という扱いであり、障害のある人と無い人の間にある心の距離を埋めるまでには至らなかった気がします。
そして…何度思い出しても気分が悪くなってくるのが…津久井やまゆり園での事件です。我々障害当事者と一般社会の間にある距離感を、くっきりと浮き彫りにさせる出来事でした。たくさんの犠牲者を出した痛ましい事件であったことはもちろんですが…事件の被害と同じくらいに私の心を暗くしたのが『犯人のしたことはもちろん許されないが、重度の障害者に生きる価値があるとは思えない。手段はともかく意義は認める』と言う声が…主にネットの書き込みを中心に少なからず広まっていった事でした。『たかがネットの書き込みなんぞを鵜呑みにして…』と仰る方もおられると思いますが…顔も名前も晒されないネットの世界だからこそ…人の持つ暗黒面が明るみに出るのだとも思ってしまいます。
何度か自分のコラムにも書いてきたことですが…人の心から差別や偏見を無くすことはできません。幼い頃から大小さまざまな差別や偏見に向き合ってきた私であっても、キライな人間、気の合わない人間に敵意や悪意を持ってしまうことはあります。しかし、個人の差別は無くせなくても、社会のルールを整えていくことで、置き去りにされ、忘れられる人を減らすことはできます。ルールが整えば、その中で暮らす人の心も、ある程度は律していくことができます。
差別や偏見は無くせるものではありませんが…だからこそ間違った行いを間違っていると訴え続けることはとても重要です。八障連の役割とは、より多くの人々に、多様を認める社会の必要性と、他者への寛容の大切さ示し続けることなのではないでしょうか。
お手々繋いでみんな仲良く、とはいかなくても…『キライなヤツとも、一緒に居る』、こんな社会が実現できたら良いかな…と思います。本年もよろしくお願い致します。
【第5回 知的に障害のある人の地域生活を考える学習会報告】
グループホーム連絡会の果たす役割
知的に障害のある人たちの地域での生活の場のファーストステップとして急増するグループホーム。小規模で<地域>にあるという点で、大規模な入所施設よりも地域生活の場としてよりよい場となる可能性をたくさんもっていますが、一方で、小規模であるがゆえの課題もたくさん抱えています。例えば、夜間勤務のため、スタッフが集まりにくく慢性的な人手不足であること。そのため、休みが取りにくく、研修も受けにくいこと。一人勤務が多く負担が大きく虐待の可能性が高くなること…。そんな大変さを抱えながら頑張っているグループホームが集まって、みんなで知恵を出し合い、支え合っていこうと昨年の5月、八王子市でも、自立支援協議会の下部組織として「八王子市障害者グループホーム連絡会」が発足し活動を始めました。
そこで、12月10日土曜日、クリエイトホール視聴覚室で行われた第5回目の学習会では、9年前から自主的に活動されている杉並区グループホーム世話人等連絡会の取り組みについて杉並障害者自立生活支援センターの佐藤弘美さんに、昨年より都内で唯一杉並区が実施している東京都の地域ネットワーク事業について、杉並区障害者施策課の目黒紀美子さんにご報告いただきました。また、八王子市障害者グループホーム連絡会について、事務局の八王子福祉園、相談事業所ポレポレの沢田哲也さんにご報告いただきました。定員70名のところ10名あまりと大変寂しい参加となり、せっかくおいでいただいた報告者の皆さんには申し訳ありませんでした。
《杉並区の主な取り組み》
もともとは、世話人さんの支援を目的にはじまった活動で、さまざまな事例検討や世話人向けの講座開催をおこなったり、実態アンケートやガイドブックの作成をおこなったりしていました。その後ネットワークで生活支援環境を充実させることを目指し、2007年からはGH世話人情報交換会、運営事業者情報交換会、開設支援プロジェクトを、2008年からは障害者ヘルパー交流・事例検討会を、その後移動支援事業者との交流会もおこなっています。また、2009年からは入居者間の交流イベントもはじめました。
2015年から地域ネットワーク事業を開始 ~ 47グループホーム 幹事11名で運営 ~
さらに、2015年からは東京都と杉並区が1/2ずつ負担して地域ネットワーク事業の補助金がついたことで、会報が発行されるようになるなど、さらに一層活動が充実してきました。特にその目玉は、専門的指導支援事業という名称で実施されている保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士、産業カウンセラー、建築士といった専門職の方に支援会議に出席していただいたり、グループホームを訪問していただき、世話人の悩みや相談に応えていただいたりする事業です。
平成28年度の事業計画
(人材育成事業)
・事例検討会、課題検討会の開催、幹事会の開催
6回/年
・研修会の開催
2回/年
(連携を広げる事業)
・会報等の作成・発行
4回/年
・連絡・情報交換会の開催
12回/年
(専門的指導支援事業)
・医療分野等の専門的指導支援事業・巡回含む相談
168回/年
(その他 地域ネットワーク支援事業)
・入居者交流会の開催
1回/年
・災害を想定した避難訓練等の取組
1回/年
・その他の事業
未定
最後に、参加者のアンケートに「普段は<ホーム>で完結している支援を<地域>で支えることの重要性やグループ(集団)になることで得られる強みをあらためて感じました」とあり、少人数ではありましたが、有意義な学習会となったことをうれしく思います。そして、報告者の皆さん、来場者の皆さん、どうもありがとうございました。(文責/土居)
【 連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小濵 義久】
闘病史 その12
検査も一通り終わった頃だったか、親戚筋に肝臓で亡くなった人はいないかと尋ねられた。一人はいる事を知っていると伝えたところ、母系の近親者にB型ウイルスを持っている人がいないか保健所で検査してもらってくれないかと頼まれた。
私自身の感染経路の解明をしようと意図したものだった。感染経路の確定ができれば、それ以上の感染の拡大を防ぐ手立てを考えることができる。と言っても、その頃はまだ確かな対策という程のものは殆どなかった。母親は5人兄弟の2番目で、3人は東京にいた。小岩にいる長男の叔父と千葉の八千代台に住む一番下の叔母は直ぐに協力してくれ、叔父は陰性、叔母は陽性という事が判明した。亀戸に住む3番目の叔父と徳島に住む2番目の叔父は商売をしており、忙しくて行けないとつれない返事だった。事情を説明し、自分の身体を守ることになるとも説明したのだが、元気でぴんぴんしていると取り合ってくれなかった。このことが後々の運命を分けることになるとは当時知る由もなかった。
昔は肝臓をやられるともう駄目だねと陰で囁かれていたものである。そして噂通り早死にして行った。私の発病当時だってそうで、私もそう噂されていたようだ。だが、良い意味で周囲の期待を裏切ることになった。それは何よりも熊田Drと巡り合ったことで、肝炎治療の最先端の恩恵にあずかることができたからである。厚生省(当時)の肝炎研究班に入っていた熊田Drは科学研究費を使って様々な試みに挑戦しており、私もいくつかの治療法の治験者となっている。のちに書くことになるが、インターフェロンを使う治験では確かNo78だったかで特異症例として報告されている。母系の親族で肝臓病を患ったとはっきりしているのは、祖母(母系)の妹である。1950年代半ばに肝臓癌で亡くなっている。50歳代前半だった。私の母親は結核で1964年に39歳で亡くなっており、祖母は原発不明の癌(分かった時にはいろんな臓器が癌で侵されていた)で1980年に76歳で亡くなっている。二人ともB型ウイルスを持っていたかどうか今となっては分からないのだが、母親の兄弟のうち、ウイルスを持っていないのは長兄の叔父だけで、最終的に残りの3人全員が持っていることが分かった。そのことから、どうも祖母がB型ウイ ルスを持っていたようで、母子感染で私の母親に感染したものが私に再び感染したのではないかとかなりの確率で推測できた。
つまり、推定でしかないが、祖母と曾祖母がともにB型ウイルスを持っていたことが疑われ、曾祖母からの母子感染で私や従妹たち(母系)に至るまでウイルスを抱え持つことになったようなのだ。曾祖母自身は98歳まで生きた当時としてはとても長命の人だったところをみると、B型ウイルスのキャリアのまま生き永らえたという事だろう。B型ウイルスキャリアの系統樹で言えば、私は4代目である(もっと古いかもしれない)。血統書付き、ばりばりの江戸っ子ならぬ、ばりばりのB型ウイルサー(私の造語)なのである。
(次号に続く)
通信本文はここまで。
八障連通信319号【PDF版】はこちらから。
通信本文はここから
【事務局通信 Vol.32】
あけましておめでとうございます。皆様にとって2017年が益々のご健勝の年となりますようお祈り申し上げます。さて、八障連としましては、色々な挑戦と、継続を考えつつ、皆様に情報の提供等を本年も行っていきたいと考えております。まずは、2017年の第一弾として、八王子市内にある「Hachiouji FARMERS Kitchenふぁむ」を運営している「グッドホーム」さんの活動報告を1月26日(木)の例会・隔月企画にて行います。「Hachiouji FARMERS Kitchenふぁむ」は八王子市内の生産者の方と連携して「無農薬野菜」の素材を中心に作った「自然食・薬膳」料理を提供しています。現状と今後の抱負を語っていただきます。ご期待ください。また昨年11月に開催予定であった八王子市議会との懇談会についてですが、2月中に開催を行うこととして調整中です。内容としましては「農福の問題」や「生活保護の課題点」などの課題を議論していきたいと考えております。さらに3月には、恒例となった八障連主催の「福祉フォーラム」として映画上映と講師の方をお迎えしての意見交換など計画中です。また2017年4月以降になりますが法政大学の生徒さんたちと障害体験&意見交換会(イベント名決まってませんが…)を計画中です。そのほかにもイベント等計画をしていることもありますので、ぜひこれを機に八障連の活動に参加したいという方を募集したいと思います。多くの方に参加していただき、より良い方向に進めていきたいと考えていますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。(文責/事務局 立川)
【今後のスケジュール】
✦ 1月26日(木)の八障連例会の隔月企画は、グッドホームさんからの報告となります。グッドホームさんは、無農薬野菜の素材で作った自然食・薬膳料理を提供する「HACHIOJI FARMERS KITCHENふぁむ」を運営しておられます。現状と今後の抱負を語っていただきます。ぜひご参加下さい。
✦ 昨年11月、54年ぶりの雪のため中止となりました「市議会議員との懇談会」は、2月20日(月)18:30よりクリエイトホール第2会議室にて開催します。ぜひご参加ください。
✦八障連主催の福祉フォーラムを3月18日(土)に開催します。映画上映とともにお招きした講師の方との対談形式での意見交換を予定してます。ご期待ください。
八障連例会(隔月企画・グッドホームさんからの報告)
1月26日(木)
18:30~20:30
クリエイト第5学習室
八障連運営委員会
2月16日(木)
18:30~20:30
クリエイト試食コーナー
八障連主催「市議会議員との懇談会」
2月20日(月)
18:30~20:30
クリエイト第2会議室
障害者地域生活支援拠点等事業報告会
2月26日(土)
10:00~12:00
労政会館2階ホール
八障連福祉フォーラム
3月18日(土)
13:30~16:00
クリエイト
【2017年・年頭のご挨拶 八障連代表 杉浦 貢】
あけましておめでとうございます。
さて、2016年を振り返れば、「障害者としてどう生きるのか」、「社会の一員としての障害者とは、どうあるべきか」を問われ続けた一年であったように思います。
昨年4月1日に施行された差別解消法は、我々障害当事者の宿願とも言うべきものだったのですが…問題点も多いのです…。この障害者差別解消法が出来るまではバリアフリー法、(平成18年12月20日施行)などで対応していましたが、民主党が政権を取ったときに自民党政権では批准してこなかった、国連の障害者権利条約を批准しました(先進国では凄く遅いですが)。差別解消法が施行されて、何が変わったのかと言うと…一番大きな点が、合理的配慮が社会の義務になったことです。
合理的配慮とは、日常生活や社会生活を営む中で、障がいの種類やその程度において社会が障害者に対して配慮することを言います。この合理的配慮が社会の義務になったことはいいのですが、配慮する側の負担が大きい場合は合理的配慮を行わなくても良いと書かれているのです。合理的配慮は義務になったと言いますが、民間企業は努力義務なので、たとえ違反しても何の罰則もないのです。厚生労働省の話では3年後に法律を一度見直すことになっています。日本は国連の障害者権利条約を批准したものの、福祉制度が世界の水準に達していないので、3年かけて世の中を変えていこうというのがお役人の思惑のようです。
リオデジャネイロオリンピックの後に開かれたパラリンピックも、それまでの大会にありがちだった『かわいそうな人たちが、一生懸命頑張っています』という扱われ方はあまりされなくなり、本家オリンピックと同等…とまではいかなくとも…一級のアスリートたちが参加する一級のスポーツイベントとして、日本の人々にも認知されるようになったと思います。しかし、障害のある人を社会の一員、市民の一人として受け入れるところまでは、世の中の空気は醸成されませんでした。あくまでも、『すごい人たちが素晴らしい偉業を成し遂げた』という扱いであり、障害のある人と無い人の間にある心の距離を埋めるまでには至らなかった気がします。
そして…何度思い出しても気分が悪くなってくるのが…津久井やまゆり園での事件です。我々障害当事者と一般社会の間にある距離感を、くっきりと浮き彫りにさせる出来事でした。たくさんの犠牲者を出した痛ましい事件であったことはもちろんですが…事件の被害と同じくらいに私の心を暗くしたのが『犯人のしたことはもちろん許されないが、重度の障害者に生きる価値があるとは思えない。手段はともかく意義は認める』と言う声が…主にネットの書き込みを中心に少なからず広まっていった事でした。『たかがネットの書き込みなんぞを鵜呑みにして…』と仰る方もおられると思いますが…顔も名前も晒されないネットの世界だからこそ…人の持つ暗黒面が明るみに出るのだとも思ってしまいます。
何度か自分のコラムにも書いてきたことですが…人の心から差別や偏見を無くすことはできません。幼い頃から大小さまざまな差別や偏見に向き合ってきた私であっても、キライな人間、気の合わない人間に敵意や悪意を持ってしまうことはあります。しかし、個人の差別は無くせなくても、社会のルールを整えていくことで、置き去りにされ、忘れられる人を減らすことはできます。ルールが整えば、その中で暮らす人の心も、ある程度は律していくことができます。
差別や偏見は無くせるものではありませんが…だからこそ間違った行いを間違っていると訴え続けることはとても重要です。八障連の役割とは、より多くの人々に、多様を認める社会の必要性と、他者への寛容の大切さ示し続けることなのではないでしょうか。
お手々繋いでみんな仲良く、とはいかなくても…『キライなヤツとも、一緒に居る』、こんな社会が実現できたら良いかな…と思います。本年もよろしくお願い致します。
【第5回 知的に障害のある人の地域生活を考える学習会報告】
グループホーム連絡会の果たす役割
知的に障害のある人たちの地域での生活の場のファーストステップとして急増するグループホーム。小規模で<地域>にあるという点で、大規模な入所施設よりも地域生活の場としてよりよい場となる可能性をたくさんもっていますが、一方で、小規模であるがゆえの課題もたくさん抱えています。例えば、夜間勤務のため、スタッフが集まりにくく慢性的な人手不足であること。そのため、休みが取りにくく、研修も受けにくいこと。一人勤務が多く負担が大きく虐待の可能性が高くなること…。そんな大変さを抱えながら頑張っているグループホームが集まって、みんなで知恵を出し合い、支え合っていこうと昨年の5月、八王子市でも、自立支援協議会の下部組織として「八王子市障害者グループホーム連絡会」が発足し活動を始めました。
そこで、12月10日土曜日、クリエイトホール視聴覚室で行われた第5回目の学習会では、9年前から自主的に活動されている杉並区グループホーム世話人等連絡会の取り組みについて杉並障害者自立生活支援センターの佐藤弘美さんに、昨年より都内で唯一杉並区が実施している東京都の地域ネットワーク事業について、杉並区障害者施策課の目黒紀美子さんにご報告いただきました。また、八王子市障害者グループホーム連絡会について、事務局の八王子福祉園、相談事業所ポレポレの沢田哲也さんにご報告いただきました。定員70名のところ10名あまりと大変寂しい参加となり、せっかくおいでいただいた報告者の皆さんには申し訳ありませんでした。
《杉並区の主な取り組み》
もともとは、世話人さんの支援を目的にはじまった活動で、さまざまな事例検討や世話人向けの講座開催をおこなったり、実態アンケートやガイドブックの作成をおこなったりしていました。その後ネットワークで生活支援環境を充実させることを目指し、2007年からはGH世話人情報交換会、運営事業者情報交換会、開設支援プロジェクトを、2008年からは障害者ヘルパー交流・事例検討会を、その後移動支援事業者との交流会もおこなっています。また、2009年からは入居者間の交流イベントもはじめました。
2015年から地域ネットワーク事業を開始 ~ 47グループホーム 幹事11名で運営 ~
さらに、2015年からは東京都と杉並区が1/2ずつ負担して地域ネットワーク事業の補助金がついたことで、会報が発行されるようになるなど、さらに一層活動が充実してきました。特にその目玉は、専門的指導支援事業という名称で実施されている保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士、産業カウンセラー、建築士といった専門職の方に支援会議に出席していただいたり、グループホームを訪問していただき、世話人の悩みや相談に応えていただいたりする事業です。
平成28年度の事業計画
(人材育成事業)
・事例検討会、課題検討会の開催、幹事会の開催
6回/年
・研修会の開催
2回/年
(連携を広げる事業)
・会報等の作成・発行
4回/年
・連絡・情報交換会の開催
12回/年
(専門的指導支援事業)
・医療分野等の専門的指導支援事業・巡回含む相談
168回/年
(その他 地域ネットワーク支援事業)
・入居者交流会の開催
1回/年
・災害を想定した避難訓練等の取組
1回/年
・その他の事業
未定
最後に、参加者のアンケートに「普段は<ホーム>で完結している支援を<地域>で支えることの重要性やグループ(集団)になることで得られる強みをあらためて感じました」とあり、少人数ではありましたが、有意義な学習会となったことをうれしく思います。そして、報告者の皆さん、来場者の皆さん、どうもありがとうございました。(文責/土居)
【 連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小濵 義久】
闘病史 その12
検査も一通り終わった頃だったか、親戚筋に肝臓で亡くなった人はいないかと尋ねられた。一人はいる事を知っていると伝えたところ、母系の近親者にB型ウイルスを持っている人がいないか保健所で検査してもらってくれないかと頼まれた。
私自身の感染経路の解明をしようと意図したものだった。感染経路の確定ができれば、それ以上の感染の拡大を防ぐ手立てを考えることができる。と言っても、その頃はまだ確かな対策という程のものは殆どなかった。母親は5人兄弟の2番目で、3人は東京にいた。小岩にいる長男の叔父と千葉の八千代台に住む一番下の叔母は直ぐに協力してくれ、叔父は陰性、叔母は陽性という事が判明した。亀戸に住む3番目の叔父と徳島に住む2番目の叔父は商売をしており、忙しくて行けないとつれない返事だった。事情を説明し、自分の身体を守ることになるとも説明したのだが、元気でぴんぴんしていると取り合ってくれなかった。このことが後々の運命を分けることになるとは当時知る由もなかった。
昔は肝臓をやられるともう駄目だねと陰で囁かれていたものである。そして噂通り早死にして行った。私の発病当時だってそうで、私もそう噂されていたようだ。だが、良い意味で周囲の期待を裏切ることになった。それは何よりも熊田Drと巡り合ったことで、肝炎治療の最先端の恩恵にあずかることができたからである。厚生省(当時)の肝炎研究班に入っていた熊田Drは科学研究費を使って様々な試みに挑戦しており、私もいくつかの治療法の治験者となっている。のちに書くことになるが、インターフェロンを使う治験では確かNo78だったかで特異症例として報告されている。母系の親族で肝臓病を患ったとはっきりしているのは、祖母(母系)の妹である。1950年代半ばに肝臓癌で亡くなっている。50歳代前半だった。私の母親は結核で1964年に39歳で亡くなっており、祖母は原発不明の癌(分かった時にはいろんな臓器が癌で侵されていた)で1980年に76歳で亡くなっている。二人ともB型ウイルスを持っていたかどうか今となっては分からないのだが、母親の兄弟のうち、ウイルスを持っていないのは長兄の叔父だけで、最終的に残りの3人全員が持っていることが分かった。そのことから、どうも祖母がB型ウイ ルスを持っていたようで、母子感染で私の母親に感染したものが私に再び感染したのではないかとかなりの確率で推測できた。
つまり、推定でしかないが、祖母と曾祖母がともにB型ウイルスを持っていたことが疑われ、曾祖母からの母子感染で私や従妹たち(母系)に至るまでウイルスを抱え持つことになったようなのだ。曾祖母自身は98歳まで生きた当時としてはとても長命の人だったところをみると、B型ウイルスのキャリアのまま生き永らえたという事だろう。B型ウイルスキャリアの系統樹で言えば、私は4代目である(もっと古いかもしれない)。血統書付き、ばりばりの江戸っ子ならぬ、ばりばりのB型ウイルサー(私の造語)なのである。
(次号に続く)
通信本文はここまで。