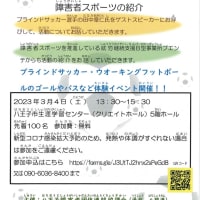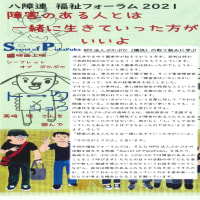八障連通信371号をアップします。
八障連通信371号【音声版はこちら】
ここからは通信本文です。
【連載コラム vol.27 『最初の盲導犬修行』 ハーネス八王子 鈴木 由紀子】
今年の 2 月初旬、私は 2 頭目の盲導犬・レジーナと歩き始めました。レジー
ナと私とは、息がぴったり合うというところまではいきません。しかし、まちの中で、一度立ち寄ったお店の特徴をすぐに覚えて、次に同じ場所を通ると「きょうも、ここに寄るの?」と問いたげに歩をゆるめるので、そのかわいい仕草に、私も思わず、にこっとしてしまいます。
さて、盲導犬のお仕事をアーサからバトンタッチさせるに当たって、レジーナに是非体得してほしいことがありました。それはレジーナのトイレワークに関することです。
飼い犬のフンや尿は飼い主が責任を持って処理することが、自治体の条例などで義務づけられており、補助犬の一種である盲導犬の飼主も、その規制の枠の中にあります。
私が盲導犬と歩きたいと思い始めたのは、いまから 30 年ほど前ですが、様々な心配事の中で最大の容因も、盲導犬のトイレ環境のことでした。
あるとき、盲導犬訓練施設の指導員にそんな思いを打ち明けたところ、「大事なことは、あなたが盲導犬と歩きたいかどうかだけです。トイレのことは、排泄物をきちんと処理すればよいので、何も心配することはありません」という答えを即座に返されました。専門家にそう言われると、「そうか、そんなに気にすることでもないのかな」と気持ちを切り替えて、10 年前にアーサを迎えました。生き物である盲導犬と暮らすのに、常設のトイレ場所を確保することは必須条件なのですが、私たちの住まいには庭もなく、まして、この辺りは市街地なので、犬のトイレ場所として適当な場所も少ないのです。そして、毎日数回ずつ同じ場所を使うことになると、「ここで犬にトイレをさせないでくださいね」などと周りの人に咎められることもありました。また、都心の街並みでは、植え込みにむやみに近づけないようになっているところも増えて、盲導犬とのお出かけには、トイレ探しのことでいつ
も苦労していました。
盲導犬に室内でトイレをさせる手段として、20 年以上前ユーザーや指導員がアイディアを出し合って「ワンツーベルト」という道具が構案され、日本の大部分の盲導犬訓練施設でユーザーに紹介しています。それは小さなベルトを犬の腰に付け、その先にビニール袋を提げて、それで犬のワン(おしっこ)やツー(うんち)を処理するというもので、災害時の非常時用トイレと同じものです。目が見えない私たちにとって、土地勘のない外出先で犬のトイレ場所を探したり、ワンやツーをスムーズに処理するのは、なかなか難しいことなので、いまやワンツーベルトは盲導犬ユーザーにとっての「お助けグッズ」の一つとも言われているほどです。あいにく、私とレジーナが卒業した施設では、ワンツーベルトの使い方は訓練に取り入れていません。環境の美化に配慮することが求められる現代の都市社会で、そのような行為は時代錯誤なのかもしれません。とにかく自力で何とか対処するしかありません。事実、その施設の出身者の間でも、特に大都市で仕事その他の社会活動をするのに、ワンツーベルトは必須アイテムであると認識されています。そして、ワンツーベルトの使用経験者から、使い方のノウハウやコツを聞きながら、自力で練習を重ねて使えるようにする人が年々増えているのです。私も 10 年前、アーサに同じトレーニングを試みたのですが、アーサがことごとく嫌がったので根負けして、そのときは、やめてしまいました。しかし、その結果、やむなく屋外のトイレ場所を探すのに苦労しながら「その日暮らし」をすることになり、周りの人たちに気兼ねして過ごさなくてはなりませんでした。そのような経緯から、今度は是非、そのような煩わしさから解放されたかったわけです。
さて、ワンツーベルトを付けて室内でトイレをするというレジーナの盲導犬修行、言い換えれば、レジーナにそのことを教え込むという私の飼主修行は、今年の 3 月、レジーナが八王子に来て 3 週間ほど経ったころから始めました。私は、何人かの先輩ユーザーのアドバイスをもとに、大まかに 3 段階に分けて、レジーナのトイレ・トレーニングを始めました。
最初の段階では、彼女がトイレをする草地で、ワンツーベルトだけを付け、その状態に慣れてもらいました。はじめのうちは違和感があったようですが、やがて「ワンツー、ワンツー」と声をかけると、その状態でトイレをしてくれるようになりました。
次の段階では、同じ草地で、ベルトの先に袋を付けてみました。レジーナが違和感から嫌がってトイレをしないときは、そのまま引き上げて、しばらく時間を置いて同じことを繰り返すという、半ば過酷なことをしました。それは人間がおむつを付けられるのを嫌がる気持ちと似ていて、「何でこんなこと、しなくちゃいけないのよ!」という声も聴こえそうです。
しかし、ある程度時間が経つと、やがて我慢できなくなってワンやツーをしてくれますので、そのタイミングをつかまえて「グッド!グッド!」と言いながら体をなでたり、思いっきり抱きしめたりして褒めちぎるのです。人間の子どもと同じように、自分の行動や、その出来映えを褒められると、犬もよい気分を味わって、「こうしたら、また褒めてもらえるよね」と、同じように振る舞うので、その習性を利用して、しつけができるというわけです。
さて、次の段階は、いよいよ室内でのトイレ・トレーニングです。手順は同じですが、この段階が最も重要です。単なるコンクリートやタイルが張られた床の上でレジーナにトイレワークをさせようとしても、全く手ごたえがなく、私がワンツーベルトを付けてトイレに誘っても、レジーナは動こうとしません。そんなとき私は、数時間は我慢させましたが、膀胱炎のような病気を起こしてもいけないし、やむなくレジーナを屋外に連れ出してトイレをさせていました。ところが、先輩ユーザーの一人にそんな様子を話したら、「犬が自然に覚えることはないんだから、あなたが本気で頑張らなくては駄目。必ずできるようになるから、根気づよく頑張れ!!」とまさに叱咤激励されました。その励ましをテコに、私はそれから 1 週間思考錯誤を重ねて、ついに目標達成!!レジーナが人間用のトイレの隣りのシートの上でトイレをしてくれたのです。
具体的には、ホームセンターで柔らかい感触の人工芝を買ってきて、それをトイレ内に敷いてみました。人工芝は犬の足に草と同じ感触を与えるので、あちらこちらに出来始めた補助犬用のトイレで使われています。我が家の場合も、この方法が効果がありました。レジーナは私の指示を徐々に理解し、「はいはい、わかりました」と言わんばかりに、その上でクルクル回り出し、やがてスムーズにワンやツーをするようになったのです。レジーナの足が汚れることもありません。そして最近では、人工芝でなくペットシーツでもオーケーとわかって大収穫。それなら外出先にも手軽に持っていけるので安心なのです。
室内でトイレを済ませることができると、お出かけの準備もスムーズになります。また、時間を気にする必要がなくて、真夜中や早朝、また、炎天下や豪雨や台風など悪天候のときに無理に外に出なくて済むので、飼い主としては楽ちんで、大助かりなのです。
室内でのトイレワークのお勉強は、レジーナにとって最初の盲導犬修行です。この先長い年月の間には、新たにお勉強してもらうことが、ほかにもあるでしょう。そのようなときに、しばらくやってみて、「できないからし方がない」とすぐにあきらめてはいけない、本気で取り組んだら、必ず望ましい結果を出してくれるのだということを、レジーナが実証してくれました。そして、これから数年間、レジーナとのさらに楽しい日々が待っているのかなと思うと、ワクワクする日々です。
ナと私とは、息がぴったり合うというところまではいきません。しかし、まちの中で、一度立ち寄ったお店の特徴をすぐに覚えて、次に同じ場所を通ると「きょうも、ここに寄るの?」と問いたげに歩をゆるめるので、そのかわいい仕草に、私も思わず、にこっとしてしまいます。
さて、盲導犬のお仕事をアーサからバトンタッチさせるに当たって、レジーナに是非体得してほしいことがありました。それはレジーナのトイレワークに関することです。
飼い犬のフンや尿は飼い主が責任を持って処理することが、自治体の条例などで義務づけられており、補助犬の一種である盲導犬の飼主も、その規制の枠の中にあります。
私が盲導犬と歩きたいと思い始めたのは、いまから 30 年ほど前ですが、様々な心配事の中で最大の容因も、盲導犬のトイレ環境のことでした。
あるとき、盲導犬訓練施設の指導員にそんな思いを打ち明けたところ、「大事なことは、あなたが盲導犬と歩きたいかどうかだけです。トイレのことは、排泄物をきちんと処理すればよいので、何も心配することはありません」という答えを即座に返されました。専門家にそう言われると、「そうか、そんなに気にすることでもないのかな」と気持ちを切り替えて、10 年前にアーサを迎えました。生き物である盲導犬と暮らすのに、常設のトイレ場所を確保することは必須条件なのですが、私たちの住まいには庭もなく、まして、この辺りは市街地なので、犬のトイレ場所として適当な場所も少ないのです。そして、毎日数回ずつ同じ場所を使うことになると、「ここで犬にトイレをさせないでくださいね」などと周りの人に咎められることもありました。また、都心の街並みでは、植え込みにむやみに近づけないようになっているところも増えて、盲導犬とのお出かけには、トイレ探しのことでいつ
も苦労していました。
盲導犬に室内でトイレをさせる手段として、20 年以上前ユーザーや指導員がアイディアを出し合って「ワンツーベルト」という道具が構案され、日本の大部分の盲導犬訓練施設でユーザーに紹介しています。それは小さなベルトを犬の腰に付け、その先にビニール袋を提げて、それで犬のワン(おしっこ)やツー(うんち)を処理するというもので、災害時の非常時用トイレと同じものです。目が見えない私たちにとって、土地勘のない外出先で犬のトイレ場所を探したり、ワンやツーをスムーズに処理するのは、なかなか難しいことなので、いまやワンツーベルトは盲導犬ユーザーにとっての「お助けグッズ」の一つとも言われているほどです。あいにく、私とレジーナが卒業した施設では、ワンツーベルトの使い方は訓練に取り入れていません。環境の美化に配慮することが求められる現代の都市社会で、そのような行為は時代錯誤なのかもしれません。とにかく自力で何とか対処するしかありません。事実、その施設の出身者の間でも、特に大都市で仕事その他の社会活動をするのに、ワンツーベルトは必須アイテムであると認識されています。そして、ワンツーベルトの使用経験者から、使い方のノウハウやコツを聞きながら、自力で練習を重ねて使えるようにする人が年々増えているのです。私も 10 年前、アーサに同じトレーニングを試みたのですが、アーサがことごとく嫌がったので根負けして、そのときは、やめてしまいました。しかし、その結果、やむなく屋外のトイレ場所を探すのに苦労しながら「その日暮らし」をすることになり、周りの人たちに気兼ねして過ごさなくてはなりませんでした。そのような経緯から、今度は是非、そのような煩わしさから解放されたかったわけです。
さて、ワンツーベルトを付けて室内でトイレをするというレジーナの盲導犬修行、言い換えれば、レジーナにそのことを教え込むという私の飼主修行は、今年の 3 月、レジーナが八王子に来て 3 週間ほど経ったころから始めました。私は、何人かの先輩ユーザーのアドバイスをもとに、大まかに 3 段階に分けて、レジーナのトイレ・トレーニングを始めました。
最初の段階では、彼女がトイレをする草地で、ワンツーベルトだけを付け、その状態に慣れてもらいました。はじめのうちは違和感があったようですが、やがて「ワンツー、ワンツー」と声をかけると、その状態でトイレをしてくれるようになりました。
次の段階では、同じ草地で、ベルトの先に袋を付けてみました。レジーナが違和感から嫌がってトイレをしないときは、そのまま引き上げて、しばらく時間を置いて同じことを繰り返すという、半ば過酷なことをしました。それは人間がおむつを付けられるのを嫌がる気持ちと似ていて、「何でこんなこと、しなくちゃいけないのよ!」という声も聴こえそうです。
しかし、ある程度時間が経つと、やがて我慢できなくなってワンやツーをしてくれますので、そのタイミングをつかまえて「グッド!グッド!」と言いながら体をなでたり、思いっきり抱きしめたりして褒めちぎるのです。人間の子どもと同じように、自分の行動や、その出来映えを褒められると、犬もよい気分を味わって、「こうしたら、また褒めてもらえるよね」と、同じように振る舞うので、その習性を利用して、しつけができるというわけです。
さて、次の段階は、いよいよ室内でのトイレ・トレーニングです。手順は同じですが、この段階が最も重要です。単なるコンクリートやタイルが張られた床の上でレジーナにトイレワークをさせようとしても、全く手ごたえがなく、私がワンツーベルトを付けてトイレに誘っても、レジーナは動こうとしません。そんなとき私は、数時間は我慢させましたが、膀胱炎のような病気を起こしてもいけないし、やむなくレジーナを屋外に連れ出してトイレをさせていました。ところが、先輩ユーザーの一人にそんな様子を話したら、「犬が自然に覚えることはないんだから、あなたが本気で頑張らなくては駄目。必ずできるようになるから、根気づよく頑張れ!!」とまさに叱咤激励されました。その励ましをテコに、私はそれから 1 週間思考錯誤を重ねて、ついに目標達成!!レジーナが人間用のトイレの隣りのシートの上でトイレをしてくれたのです。
具体的には、ホームセンターで柔らかい感触の人工芝を買ってきて、それをトイレ内に敷いてみました。人工芝は犬の足に草と同じ感触を与えるので、あちらこちらに出来始めた補助犬用のトイレで使われています。我が家の場合も、この方法が効果がありました。レジーナは私の指示を徐々に理解し、「はいはい、わかりました」と言わんばかりに、その上でクルクル回り出し、やがてスムーズにワンやツーをするようになったのです。レジーナの足が汚れることもありません。そして最近では、人工芝でなくペットシーツでもオーケーとわかって大収穫。それなら外出先にも手軽に持っていけるので安心なのです。
室内でトイレを済ませることができると、お出かけの準備もスムーズになります。また、時間を気にする必要がなくて、真夜中や早朝、また、炎天下や豪雨や台風など悪天候のときに無理に外に出なくて済むので、飼い主としては楽ちんで、大助かりなのです。
室内でのトイレワークのお勉強は、レジーナにとって最初の盲導犬修行です。この先長い年月の間には、新たにお勉強してもらうことが、ほかにもあるでしょう。そのようなときに、しばらくやってみて、「できないからし方がない」とすぐにあきらめてはいけない、本気で取り組んだら、必ず望ましい結果を出してくれるのだということを、レジーナが実証してくれました。そして、これから数年間、レジーナとのさらに楽しい日々が待っているのかなと思うと、ワクワクする日々です。
【連載コラム Vol.57 『感謝の言葉と心のゆとり』 八障連代表 杉浦 貢】
インターネットの書き込みなどでは、ずっと以前から、『障害者は感謝が足りない』であるとか...、『困っている障害者を助けたのに、礼の 1 つも言われなかった』、または『助けよう、手伝おうとしたのに酷い言葉で拒絶された、障害者に傷つけられた』などの書き込みがあとを断ちません。私はこれについて、障害当事者のひとりとして深く心を痛めています。
まず第一に、障害者に否定的な意見を述べる人たちの言葉によって暗い気分になる、というだけでなく障害者の側にも、『誰かから手助けを受ける、支えてもらう』ということに不慣れであるが故に...せっかく善意や厚意を寄せてくれた人にも、間違った対応をしてしまう障害者が少なからずいるからです。たしかに、人が人を支えて助けるということは、当然の行為です。人間
の社会はそうやって拡大発展し、今日までの歴史を刻んできた訳ですし...、福祉や医療の制度としてもまず困り事のある人を助ける。わけても困り事の多い人から先に助けていく、ということが社会の規範になっています。
もっとも理念や理想を実際の社会で運用していくにあたっては様々な問題が多々あり、必ずしも理想どおりに行かないというのが世の常ではありますが...それでも、社会の仕組みがまったくないところから原始人とほぼ同等な生活をするよりは、いくらかは快適です。とくに、私のような車いす使用者...重度障害者は...自然に囲まれた生活に憧れはあったとしても...医療と福祉、何より文明の手助けなしには生きられません。いつでも自分が必要とした時、どこでも自分が望んだ場所に...助けの手、支えの手がすぐ近くにあるという環境を考えた時に...仮に...『支援が絶えた状態、援助が尽きた状態』を想像すれば...いつも、あたりまえにそこにあると思っていたものが、いかに貴重で得がたいものかということにも、いつしか思いが及ぼうと言うものです。
また、人が人を助けて支える...ということが倫理や道徳に規定され、社会制度に組み込まれたとしても...それを実践し、目に見える形に表していくのは、地域に生きる人の営みです。
八王子の街にヘルパーの派遣制度があり、市役所から委託を受けた派遣事務所のバックアップがあるにせよ...現実に、目の前で私の手助けをしてくれるのは、たとえばヘルパーのタナカさん(仮名)やイトウさん(仮名)という、一人ひとりの個人であったりするわけです。
こういう場合...たとえ福祉や医療のサービスを受けて生活することが、利用者たる障害者...つまり私に与えられた当然の権利であるのだとしても...目の前で一生懸命働いてくれるタナカさんやイトウさんに対して、一言の感謝も述べない、ありがとうございますの、あの字も言わないというのは障害者として、サービス利用者として、何よりも人間として間違ったことだと思います。(もちろん知的や発達、精神などの障害に起因して、他者とのコミュニケーションに困難の伴う人に感謝を無理強いする意図はないです。感謝というものはできる人ができる範囲でやるものですから) 障害者だから支援者より偉い、また逆に、どんなに不満があっても、支援の制度があるだけ...よほどありがたいのだから...障害者は何があっても、何をされても黙って耐えなければならないということでもありません。
ただ...私が思うのは...ヘルパーのタナカさんにしろ、イトウさんにしろ、わざわざ私の支援に入らなくても、他のことをして収入を得る自由と権利があるはずです。私の支援に入れるだけの時間があったなら、自分の生活のために、その時間を使うこともできたはずなのです。どんなに自分と気の合わない相性の悪い支援者であったにせよ...『他のことを脇に置いても私の支援に入ってくれた』という点では、やはり感謝をするべきです。
もうひとつ考えるのは、人に感謝して生きるということは、何も障害者だけが考えなくてはいけない話ではないなあということなのです。人間...誰でも、おぎゃあと生まれて一人前になるまでには...親や家族、大人の庇護を受けて生活しています。成長して、どうにか社会に出られたにせよ...毎日生きていくためには、たくさんの人との繋がりが必要になってきます。
『障害者は感謝が足りない』などと、文句を言う人たちに、私が言って聞かせたいのは、『ではそういうあなたは、これまでちゃんと...周りにいる全ての人々に、その都度きちんと感謝を述べてきたのか...、本来なら、自分のことは自分でやるのが理想であるべきはずのところを、つい都合よく、お人好しの誰かに甘えて、人任せにしておきながら...それでもなお、自分のために行
動してくれた人に対して、感謝を述べるタイミングを外してしまったことはなかったか』ということなのです。あるいは...自分がまったく気が付きもしないところで、誰かに庇ってもらっていたり、見えない部分で誰かに助けてもらっていたり、常に誰かに気にかけてもらうようなことが...どんな人の人生にも、必ずありうるはずです。生きていて一度も他人に甘えたことがない人など、いないのです。
日々...自分が周りからどれだけの支援を受けて、自由で快適な生活が送れているかを考えるなら...いちいち他人の行状をとやかく言うよりも、まず自分の身の周りに感謝するべきだ、とも思うのです。また、『当然ながら感謝するべきところで、感謝の言葉が上手く出せない』ということも、日常にはよくあることです。人が人に感謝する、という行為には、心のゆとりが欠かせませ
ん。しかし、人が本当に悩んで苦しんでいる時には、まずこのゆとりから失われていくものです。心にゆとりがない状態だと、せっかく自分に向けられた善意や厚意も、それを正しく認識することができません。それどころか、自分に優しくしてくれた人、親身に応じてくれた人に、悪口雑言をぶつけることもしばしばです。人に対して感謝の気持ちが持てない人...というのは、まず心にゆとりが無い人であることがほとんどです。
『障害者は感謝がない』などと言う人こそ、他人に感謝する心のゆとり、他人の過ちを赦す心のゆとりのない人だと、私は思うのです。そして...人が人に対するにゆとりを持つということは...言葉で言うほど容易なことではないのです。
障害者を非難する書き込みをネットで見かける度に...社会の中からどんどんと、心のゆとりが奪われているのを感じずにはいられません。
まず第一に、障害者に否定的な意見を述べる人たちの言葉によって暗い気分になる、というだけでなく障害者の側にも、『誰かから手助けを受ける、支えてもらう』ということに不慣れであるが故に...せっかく善意や厚意を寄せてくれた人にも、間違った対応をしてしまう障害者が少なからずいるからです。たしかに、人が人を支えて助けるということは、当然の行為です。人間
の社会はそうやって拡大発展し、今日までの歴史を刻んできた訳ですし...、福祉や医療の制度としてもまず困り事のある人を助ける。わけても困り事の多い人から先に助けていく、ということが社会の規範になっています。
もっとも理念や理想を実際の社会で運用していくにあたっては様々な問題が多々あり、必ずしも理想どおりに行かないというのが世の常ではありますが...それでも、社会の仕組みがまったくないところから原始人とほぼ同等な生活をするよりは、いくらかは快適です。とくに、私のような車いす使用者...重度障害者は...自然に囲まれた生活に憧れはあったとしても...医療と福祉、何より文明の手助けなしには生きられません。いつでも自分が必要とした時、どこでも自分が望んだ場所に...助けの手、支えの手がすぐ近くにあるという環境を考えた時に...仮に...『支援が絶えた状態、援助が尽きた状態』を想像すれば...いつも、あたりまえにそこにあると思っていたものが、いかに貴重で得がたいものかということにも、いつしか思いが及ぼうと言うものです。
また、人が人を助けて支える...ということが倫理や道徳に規定され、社会制度に組み込まれたとしても...それを実践し、目に見える形に表していくのは、地域に生きる人の営みです。
八王子の街にヘルパーの派遣制度があり、市役所から委託を受けた派遣事務所のバックアップがあるにせよ...現実に、目の前で私の手助けをしてくれるのは、たとえばヘルパーのタナカさん(仮名)やイトウさん(仮名)という、一人ひとりの個人であったりするわけです。
こういう場合...たとえ福祉や医療のサービスを受けて生活することが、利用者たる障害者...つまり私に与えられた当然の権利であるのだとしても...目の前で一生懸命働いてくれるタナカさんやイトウさんに対して、一言の感謝も述べない、ありがとうございますの、あの字も言わないというのは障害者として、サービス利用者として、何よりも人間として間違ったことだと思います。(もちろん知的や発達、精神などの障害に起因して、他者とのコミュニケーションに困難の伴う人に感謝を無理強いする意図はないです。感謝というものはできる人ができる範囲でやるものですから) 障害者だから支援者より偉い、また逆に、どんなに不満があっても、支援の制度があるだけ...よほどありがたいのだから...障害者は何があっても、何をされても黙って耐えなければならないということでもありません。
ただ...私が思うのは...ヘルパーのタナカさんにしろ、イトウさんにしろ、わざわざ私の支援に入らなくても、他のことをして収入を得る自由と権利があるはずです。私の支援に入れるだけの時間があったなら、自分の生活のために、その時間を使うこともできたはずなのです。どんなに自分と気の合わない相性の悪い支援者であったにせよ...『他のことを脇に置いても私の支援に入ってくれた』という点では、やはり感謝をするべきです。
もうひとつ考えるのは、人に感謝して生きるということは、何も障害者だけが考えなくてはいけない話ではないなあということなのです。人間...誰でも、おぎゃあと生まれて一人前になるまでには...親や家族、大人の庇護を受けて生活しています。成長して、どうにか社会に出られたにせよ...毎日生きていくためには、たくさんの人との繋がりが必要になってきます。
『障害者は感謝が足りない』などと、文句を言う人たちに、私が言って聞かせたいのは、『ではそういうあなたは、これまでちゃんと...周りにいる全ての人々に、その都度きちんと感謝を述べてきたのか...、本来なら、自分のことは自分でやるのが理想であるべきはずのところを、つい都合よく、お人好しの誰かに甘えて、人任せにしておきながら...それでもなお、自分のために行
動してくれた人に対して、感謝を述べるタイミングを外してしまったことはなかったか』ということなのです。あるいは...自分がまったく気が付きもしないところで、誰かに庇ってもらっていたり、見えない部分で誰かに助けてもらっていたり、常に誰かに気にかけてもらうようなことが...どんな人の人生にも、必ずありうるはずです。生きていて一度も他人に甘えたことがない人など、いないのです。
日々...自分が周りからどれだけの支援を受けて、自由で快適な生活が送れているかを考えるなら...いちいち他人の行状をとやかく言うよりも、まず自分の身の周りに感謝するべきだ、とも思うのです。また、『当然ながら感謝するべきところで、感謝の言葉が上手く出せない』ということも、日常にはよくあることです。人が人に感謝する、という行為には、心のゆとりが欠かせませ
ん。しかし、人が本当に悩んで苦しんでいる時には、まずこのゆとりから失われていくものです。心にゆとりがない状態だと、せっかく自分に向けられた善意や厚意も、それを正しく認識することができません。それどころか、自分に優しくしてくれた人、親身に応じてくれた人に、悪口雑言をぶつけることもしばしばです。人に対して感謝の気持ちが持てない人...というのは、まず心にゆとりが無い人であることがほとんどです。
『障害者は感謝がない』などと言う人こそ、他人に感謝する心のゆとり、他人の過ちを赦す心のゆとりのない人だと、私は思うのです。そして...人が人に対するにゆとりを持つということは...言葉で言うほど容易なことではないのです。
障害者を非難する書き込みをネットで見かける度に...社会の中からどんどんと、心のゆとりが奪われているのを感じずにはいられません。
【お知らせ掲示板】
✦八障連の 2021 年度定期総会は 7 月 3 日(土)AM10 時30 分からの Zoom 開催となります。詳細は同封の「八障連定期総会リモート開催」のご案内でご確認ください。(運営委員会)
【連載コラム B 型肝炎闘病記 パオ 小濵 義久 闘病史 その 54】
ナダ旅行はとてもリフレッシュできたし、どこかに置き忘れてきた自分に出会えた感じもした。また、いろんな意味で大きな転機となった。誰もが明日死ぬかもしれないという可能性を秘めて生きているのだが、私にとってその蓋然性の高さが確実なこと、だから長らく抱え持って来た貧乏性をそろそろ手放し、もう少し自分の好きな事、やりたい事、ライフワークの遂行へエネルギーの転換を図っても罰は当たらないだろうと考えられるようになったの
だ。止むを得ず行っている事を少しずつ誰かに手渡していくことにした。
一番大きなことは自分で起こした事業の継承者を見つける事であり、二番目は日本臨床心理学会の事務局を担える人を見つける事であった。事務局は、身近に適任者がいることが分かり、年が明けた 2005 年 2 月から引継ぎを始めた。
精神障害者の通所事業を担える後継者を探すのは難しいだろうなと設立当初から考えていたが、こちらもタイミングよく見つかり、2005 年 4 月から常勤職員になって貰えた。ある種のシンクロニシティと言えるのか、私の気持ちが整理された時に相次いで事態は進展した。ありがたいことである。こう
いう時に人は本当に生かされているのだなぁと感じる。そういう風に事態が進展すると自然に新しい風が吹き始める。事業所には 30 年来の付き合いのあるメンバーがいた。若い頃ファッション界に身を置いていただけあって、そのセンスはただならぬものがあった。古着屋を廻って掘り出し物を探すのは趣味のひとつで、有り余る衣類があるのに買い続けてもいた。実家の自分の部屋には何箱もの衣類の入った段ボールが山積みされていると言っていた。靴の数も半端じゃないらしい。リサイクル店が自分の持ち物だけで開けそうと言う。自ら買い物依存症と称し、十八番は自分が作った「買い物依存症」という歌を唄うシンガーソングライターでもあった。彼はお風呂に入って一日中過ごせる健康ランドをこよなく愛していた。時に青春 18 切符を買って結構遠くの健康ランドまで出掛けると聞かされた時には吃驚した。私の温泉好きを知っていた彼は、八王子市内に良い温泉ができた事を教えてくれ、一緒に行きませんかと誘ってくれた。「いこいの湯」の寝転び湯を最も気に入っていた。たまたま空いていると、隣同士で入ることもあり、横たわっている時の彼の表情は満足感一杯で、仏様のようでもあった。今は閉鎖されてしまったのだが、2004 年から 2005 年末まで 13 回も通った。若い頃ギターを弾いていた事を知った彼は、一緒に演奏しましょうと誘ってくれた。八王子市営施設の中にあるスタジオを借りて練習したのだが、私の腕が彼ほど上手でなかった事や音楽の好みが少し違った事もあり、9 回で終わった。その後も彼は歌を作り続け、ライブをやらせてくれる喫茶店で何度かライブをやった。スタジオで思い切って歌を唄うなんてことは彼と出会わなければ、一生体験できないことであった。働き者であった彼は、障害者というハンディを背負っても働くことにチャレンジし続けた。しかし、30 年前に出会った頃には軽いと見えていた病気が意外に根深いものらしく、段々いろんな症状に悩まされることとなり、年齢と共に働くことも適わなくなった。その先に待つのは障害年金と生活保護という生活であった。
ある日折り入って相談があるというので話を聞くと、まだ貯金が残っている間に小さい頃からの夢であるハワイに連れて行って欲しいという事だった。2005 年 2 月にハワイへ 2 人で旅立った。格安のフリープランを探して、レンタカーを借りて島内を半周した。その話を聞き及んだ仲間が何処でも良いから僕たちも連れて行ってというので選んだのが格安のグアム旅行。コンドミニアムでの自炊、島内巡りはレンタカーという 4 人での旅行となった。
ファッションリーダーだった彼は、2016 年に 62 歳で亡くなった。何時も話していたピンコロを見事成し遂げた。寂しがり屋の彼は毎日煙草の喫えるファミレスで数時間過ごしていたが、ある日椅子から崩れ落ちそのまま帰らぬ人となった。あの盆踊りの輪の中でハワイを思い出してくれているだろうか?(次号に続く)
だ。止むを得ず行っている事を少しずつ誰かに手渡していくことにした。
一番大きなことは自分で起こした事業の継承者を見つける事であり、二番目は日本臨床心理学会の事務局を担える人を見つける事であった。事務局は、身近に適任者がいることが分かり、年が明けた 2005 年 2 月から引継ぎを始めた。
精神障害者の通所事業を担える後継者を探すのは難しいだろうなと設立当初から考えていたが、こちらもタイミングよく見つかり、2005 年 4 月から常勤職員になって貰えた。ある種のシンクロニシティと言えるのか、私の気持ちが整理された時に相次いで事態は進展した。ありがたいことである。こう
いう時に人は本当に生かされているのだなぁと感じる。そういう風に事態が進展すると自然に新しい風が吹き始める。事業所には 30 年来の付き合いのあるメンバーがいた。若い頃ファッション界に身を置いていただけあって、そのセンスはただならぬものがあった。古着屋を廻って掘り出し物を探すのは趣味のひとつで、有り余る衣類があるのに買い続けてもいた。実家の自分の部屋には何箱もの衣類の入った段ボールが山積みされていると言っていた。靴の数も半端じゃないらしい。リサイクル店が自分の持ち物だけで開けそうと言う。自ら買い物依存症と称し、十八番は自分が作った「買い物依存症」という歌を唄うシンガーソングライターでもあった。彼はお風呂に入って一日中過ごせる健康ランドをこよなく愛していた。時に青春 18 切符を買って結構遠くの健康ランドまで出掛けると聞かされた時には吃驚した。私の温泉好きを知っていた彼は、八王子市内に良い温泉ができた事を教えてくれ、一緒に行きませんかと誘ってくれた。「いこいの湯」の寝転び湯を最も気に入っていた。たまたま空いていると、隣同士で入ることもあり、横たわっている時の彼の表情は満足感一杯で、仏様のようでもあった。今は閉鎖されてしまったのだが、2004 年から 2005 年末まで 13 回も通った。若い頃ギターを弾いていた事を知った彼は、一緒に演奏しましょうと誘ってくれた。八王子市営施設の中にあるスタジオを借りて練習したのだが、私の腕が彼ほど上手でなかった事や音楽の好みが少し違った事もあり、9 回で終わった。その後も彼は歌を作り続け、ライブをやらせてくれる喫茶店で何度かライブをやった。スタジオで思い切って歌を唄うなんてことは彼と出会わなければ、一生体験できないことであった。働き者であった彼は、障害者というハンディを背負っても働くことにチャレンジし続けた。しかし、30 年前に出会った頃には軽いと見えていた病気が意外に根深いものらしく、段々いろんな症状に悩まされることとなり、年齢と共に働くことも適わなくなった。その先に待つのは障害年金と生活保護という生活であった。
ある日折り入って相談があるというので話を聞くと、まだ貯金が残っている間に小さい頃からの夢であるハワイに連れて行って欲しいという事だった。2005 年 2 月にハワイへ 2 人で旅立った。格安のフリープランを探して、レンタカーを借りて島内を半周した。その話を聞き及んだ仲間が何処でも良いから僕たちも連れて行ってというので選んだのが格安のグアム旅行。コンドミニアムでの自炊、島内巡りはレンタカーという 4 人での旅行となった。
ファッションリーダーだった彼は、2016 年に 62 歳で亡くなった。何時も話していたピンコロを見事成し遂げた。寂しがり屋の彼は毎日煙草の喫えるファミレスで数時間過ごしていたが、ある日椅子から崩れ落ちそのまま帰らぬ人となった。あの盆踊りの輪の中でハワイを思い出してくれているだろうか?(次号に続く)