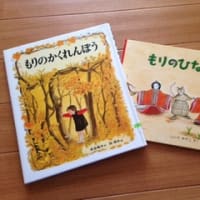毎日あわただしく、スタッフ同士でも情報がきちんと伝わらなくてあわてることがあります。
仕事でも、家族でもともかく話さなくてはだめですね。
ずっとそんなことを思って暮らして来ましたし、現在もそのおもいは強いです。
そして個人的には特に夫との会話に一番気を使っています。(笑)
ヘルシーカフェのらの広場も人と話をする場所、ゆったりしていただき、おいでいただいた方々が自然に交流していただければいいなぁ、というおもいでつくりました。
お友だち同士、知り合い同士で来ていただいてもちろん大丈夫なのですが、のらでの新たな出会い、知らない人との出会いはちょっと面白いと思うのですよ。
「フュチャーーセンターをつくろう」という本を読み終えました。
この本には「対話」という言葉がしきりに出てきます。
背景の違う人たちが寄ってたかって未来の話をして、そしてそれを実現できるようにする。
自分の夢を語って、それを実現するためにほかの人たちも一緒になって考えてくれて、その案を実現するために行動する。
参加している人たちは、どの人も主体的になって今ある話がさらに夢広がるものになるように対話する。
自分だけの利益になる話ではなく、世の中の人たちがハッピーになる企画を作る。
今までの世の中の価値観からすれば「無理」とか「でもねぇ」とか言われるようなことかもしれません。
でもすでに世の中が変わってきているんだから、新たな仕組みがはじまってもいいよなぁ、と私などは思います。
のらをはじめ、隣のババラボ、3月末にでかけてお世話なった富山県高岡市の「ひとの間」、さいたま市のパパたちのネットワークをみていても、新たな仕組み作りが始まっている感じはします。
本人たちは仕組みを作っている意識はないのかもしれませんけど・・・・
それは組織だけではないと思います。
若い人たちの働きぶりを見ていると、今までの価値観では測れないような働き方をしている人たちが存在していて、私は興味を抱きます。
日本全国でその芽はたくさんあります。
まだまだマスメディアでは取り上げられないだけで、ものすごい勢いで変わっているのではないのか、と私は感じています。
変わらないのは政治、行政、大きな会社?
過激な言い方をしましたが、行政職員も政治家も会社も若い人たちは意識のある人たちはたくさんいるかもしれません。
でも、残念だけど彼らにはまだ決定権がないので、なかなかその組織では決定まではいかないのが現状かもしれません。
だからこそ様々な組織、個人がネットワークをつくり、行動していくことは大事なことなのだとも思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それと同時期に朝日新聞(7月5日)に劇作家・演出家平田オリザさんのインタビュー記事を読みました。
オリザさんは「会話は等しい人同士のおしゃべりで対話は異なる価値観などをすり合わせる行為」と言います。
「ディベートは自分の価値観と倫理によって相手を説得し、勝つことが最終目的で、負けたほうは全面的に変わらないといけない。勝ったほうの価値観はそのまま。対話は勝ち負けではなく、価値観のすり合わせによってお互いが変わり、新しい第三の価値観とでも呼ぶものをつくりあげることを目標にする」
「価値観が多様化した成熟社会では討論よりも対話が重要」
と考えていくと、異質な価値観の出会いこそが新たな価値観を産む源であって、仲良しのグループだけでは発展性がなく、組織は(関係性は)壊れていく、ことになりかねません。
ある時期から
私は何を言っても許される同じような価値観の人たちとの会話は気が楽で大事な場所である、と思うと同時に全くの異質、時には激論するほどの存在の有用性を感じていたのですが、平田さんの記事に出会って、膝を叩くおもいがしました。
私は9月にある大学の社会教育関連の授業で話すことになっているのですが、その時の話の中にこのことを入れていこうとおもった次第。
仲間内でハッピーにしていることはいいかもしえないけれど、やはり広がりがなく、深みもありません。
もう少し広い視点でとらえていくことが自分も含めて社会が変わっていくことにつながるのではないか、と考えるのでした。
「対話は勝ち負けではなく、価値観のすり合わせによってお互いが変わり、新しい第三の価値観とでも呼ぶものをつくりあげることを目標にする」という考え方のもと(表現はちょっと違っていましたが)私自身もヘルシーカフェのらの立ち上げは全く違う価値観人たちと組んで立ち上げた経緯があります。
この頃日常業務に多忙で、集中して本を読んだり、考えたり、文章で表現することがなかったのですが、ちょっと考えさせられる本、新聞記事と出会って、メモ程度ですが書いておきたくなりました。
新井 純子