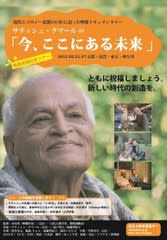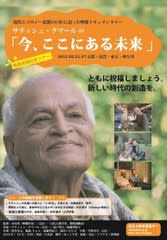
インド出身の思想家であり環境平和運動家のサティシュ・クマールさんのドキュメント映画上映会と講演に行く。350人の定員に対し、立ち見も出るほどの大盛況。これからの社会をどう生きてゆけばよいのかとうことについての人々の関心の高さがうかがえる。
サティシュさんは75歳。しかし、とても情熱的であと50年くらい生きそうなパワーがあった。それでいて、彼が生み出す空気はとても穏やかで優しい。ユーモアも豊富だ。見せる笑顔に大きく包まれると同時にいたずら好きの少年のような無邪気さが覗く。
ドキュメント映画が70分。講演と質疑で約90分。ボリュームたっぷりの3時間だった。その中で印象に残る事柄がいくつかある。
●どんなことも、プロセスと結果に分かれるのではなくてすべてがプロセスのつながり
今の世の中は結果ばかり求めると批判される。私自身もプロセスを大切にしたいと思っている。でも、結果を求めることを悪いことだとは思っていない。むしろ求めたい。「結果ばかりを求める」と批判する人は、実は結果=ゴールと思っている「貧しい」人ではないだろうか。結果をもプロセスの一つととらえれば、こんなに楽しいことはない。
サティシュさんはパン作りに喩えていた。パンを作るには小麦を育て、挽き、捏ね、焼く。焼くことばかりを重視する。しかし、パンを焼いたあとは食べ、消化する。排泄もする。焼いて終わるわけではない。おっしゃるとおり。しかし、だからすべてはプロセスのつながり、結果などないとするのはいかがなものか。
小麦を育てて収穫すれば嬉しい。苦労して挽きあがったら充実感もある。パンが焼ければ食べる楽しさが生まれる。そういった「結果」があるからプロセスにも光が当たるのだ。結果はどんどん求めて良いと思う。
私が喩えるなら雪だるま。最初は手のひらで丸められる玉を次第に大きくしていく。新雪を使うのかちょっと固まった雪を使うのか、考えながら大きくしなければ途中で割れたりいびつな形になっていったりする。そういったプロセスを経て「おお、ここまで大きくなった」と結果を喜び、「もう少し大きくしてみよう」とさらにプロセスを踏む。おかげさまで立派な雪だるまができても、それは永遠ではない。一晩経てば溶けているか、車の泥で汚れてみるも無残な姿になっているか。そこがいいのだ。大きな結果を得たとしても、それは永遠ではない。それをプロセスに変えて次の力に練りこんでゆくのだ。結果を得た!とトロフィーのように誇示していたら泥にまみれた雪だるまと同じ、誰もみたくない。・・・いかがでしょうか。
結果とプロセスは実は二人三脚の関係、とても仲良しなのだ。
●just enough
世界がこれほどまでに原油を大量に消費し自然を破壊し、社会から自然を締め出した背景には人々の「もっと」と思う欲望がある。手があり足があり心がある。これで十分、という気持ちがあれば自然ともっと上手くつきあえる。コンクリートジャングルからも解放される。
共感する。高層ビル、タワーマンション合戦。何を訴えたいのかイマイチ分からない映像プロモーション。確かにすごい!と思わなくはないが、そこまで必要?と思うものも多い。例えば大阪駅周辺のデパート合戦には閉口する。結局入っているテナントにそこまでの差はない気もするし、大型化したといってそれぞれの力をみせつけあっているだけの気がしなくもない。そうでなければ、たまたまこれまでなかったコラボで斬新さをアピールする。どうだ、このアイデアすごいだろう、と。そんなふうに大量の資源を浪費しておいて、子どもたちにワクチンをなどと言ってペットボトルのキャップを集めたり。その資源の浪費が、遠い国の子どもたちの生活環境を破壊し発病の原因となっているかもしれないよ、と思う。
銀座で、サティシュさんが幾何学模様の何かが画面の奥から次々と流れ出てくる映像を目を丸くしてみていた姿が印象的だった。「この世のものとも思えない」というその表情と、サティシュさんとその映像の画がいかにも不釣合いだった。あまりにもアンバランスで会場から笑いも起こったほどだ。今世の中にあるものがいかに人間の素(そ)の営みとかけ離れたものであるかを端的に表しているようだった。
もう、十分でしょ。
●サステイナブルソサエティー
英語で書けよっ!
これはあの有名なE.Hシューマッハも提唱する考え方、彼の本は今でも読者が多い。持続可能な社会を作っていかねばならない。資源は有限なのだ。スモールイズビューティフル。それなのに、人々はそのことに目を向けずにEメールを打つことや飛行機・新幹線を使って(エネルギーを使って)旅行に忙しい。社会を世界をリデザインしなくてはいけない。
これも分からなくはない。しかし、持続可能な社会の実現は昔から言われつつも実現されない。その兆しがあるのかどうかも、私は実感できない。社会は「発展」してゆくばかりだ。もちろん、彼らの言うことはとても素敵だ。人類がそんな生活を送れれば心はもっと穏やかに、人に対しても優しくなれるように思う。共感する人が多いのに、どうして実現されないのだろう。彼らの提唱する持続可能な社会はもはや理想郷と化しているようにも思う。ダイエットと同じだ。「痩せたいよねぇ」と言いながらケーキを食べる。「太陽とか木とか良いよねぇ」と良いながらipadで読書。
さらに現実を見回せば
「身体に優しい自然食を食べよう!というイベントを東京丸の内ビルの地下1階で開催します。」という告知をtwitterで行なう。
「環境負荷を与えない自然農法を体験しましょう。場所は○○。集合場所は○○駅北口。大型バスを用意します。(駅周辺にコンビニあり)」
「植林ボランティアに参加しませんか?木を増やし守りましょう。参加者には仕出し弁当とペットボトルのお茶を用意します」
・・・それが妥当なところではないだろうか。先日のニュースでこんなのもあった。「デジタル時代に何でもすぐに手書きできるアナログなノートが人気です。高級ノートのほかこんなのもあります。書いた内容をiphoneで撮影できるように四隅に印があります。書いた内容をブログにのせたり・・・」結局デジタル?
理想郷が現実になれば、これほど良いことはない。さりとて今のシステムをリセットしてリデザインすることは到底出来ないように思うのだ。サティシュさんが提唱する事柄はもちろん頭の片隅に置きつつ、私たちがこれから考えるべきは、「Re」ではなくて、この社会を生かしたまま、この社会と上手く付き合いながら次世代を考えていくことではなかろうか。「これまでの営みが間違っているからこんな社会になった。だから、元に戻そう。原点に帰ろう」ではなくて、今ここをスタートとする。今の現状から、次にどんな良い社会を作れるか。過去の過ちを糧として考えるのだ。個人は欲望に振り回されない。企業は個人の欲望をむやみやたらに掘り起こさない。社会は現状をよく見極める。要らないものは削げばいい、要るものは足せばいい。守るものは守っていけばいい。そんな新しい「持続可能な社会」を考えるべきではないだろうか。
だって・・・確かに足があるといっても、この来日公演のために、あなたはお国から歩いて日本まで来たのですか?コンクリートジャングルと揶揄しながら、ではホテルではなく山の中に宿泊滞在しているのですか?サティシュさん。
とイジワルな疑問を投げかけてみたくなるのだ。
あぁ、学生時代にこれだけ書けば論文の宿題がひとつ片付いたのに・・・。イジワルな疑問は勉強不足の証左かもしれません。学者の皆様、乱文かつ言いたい放題ご容赦ください。