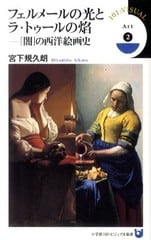
「フェルメールの光とラ・トゥールの焔」 宮下 規久朗 著
先述の「岩田 規久男」さんと「宮下 規久朗」さん。どちらも好んでいる著者なものだから、よく手に取るだけにややこしい(笑)
こちらは宮下さんのほう。この方の解説は、描かれている事実をまず分かりやすく述べて読者を惹きつけ納得させたあとに、私見を含む分析を試みるという構成なので、読みやすいのです。
随所に私見を入れられると「絵を美術的観点から」見たいと思う読者は読みにくい。かと言って、解説が詳細・専門的すぎても、また読みにくい。バランスが、私にはちょうど良いのです。
フェルメールについては特に、光と闇を焦点に当てて書かれますが、これはフェルメールだけでなくて、その光と闇を確立するまでの歴史を追うかたちで進みます。
「ラ・トゥールやレンブラント、フェルメールなどの巨匠たちの魅力は、精神性の高い、静謐で幽玄な光と闇の描写にあります。本書では、ルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチが確立した革新的な「闇」の表現が、バロック絵画の先駆者カラヴァッジョによる光と闇のドラマを経て、いかにして静謐で精神的な絵画へと成熟していったのか、西洋名画を育んだ「闇」の歴史を、西洋美術史界屈指の「語り部」である著者が、美麗な図版とともにわかりやすく解説します。」とあります。だから、副題に「闇」の西洋絵画史とも。
読後、もう一度読み返して各々の絵画への理解を深めたいと思ったのはもちろんですが、同時に「光と闇」。ふたつの関係性について、なぜか深く思いを馳せていました。
闇があるから光は光として現れる。光があるから闇は闇として佇む。ならば、このふたつは助け合っているのか?むしろ、対峙しているのか?
初期の絵画のなかには光源が不明確なものが多いのですが、それに伴って闇の存在も亡羊としているものもあれば、闇ばかりが目立つものも。
光への意識が強くなれば光源はいよいよはっきりして、闇は光を支える「道具」のような存在へと変わってゆきます。
歴史は進むほどに、光と闇はお互いの主張が強くなり、絵画はずいぶんと厚みと力強さと、怪しさを帯びます。
静謐で精神的な絵画へと成熟する頃、絵画には、光が闇を溶かすような闇は光に委ねるような温かさが生まれています。
光と闇をそんなふうに捉えたとき、ふと気づきました。
私が光と闇から感じたのは、人の心であり愛なのだと。
お互いの心を各々持っている、というところからスタートして、相手の存在が自分の中にあることを何となく意識し、その意識が強くなったとき、自分の心で相手の心に影響を与えたいと、自分の心も見てほしいと主張が強くなる。そうした対峙の時期を超えた心たちは、お互いが交わえるところと交わえないところの微妙な融点を悟り、優しく溶け合って、支え合ってひとつになる。
私の好きなフェルメールの絵には、そんな優しさに溢れています。









