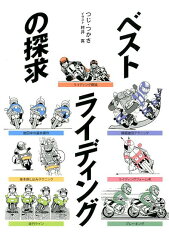先日リヤスタビリンクの試作1号について書きましたが、そのときちょっと予告した試作2号について紹介したいと思います。目的はフロントと同様、車高を下げたことによるスタビリンクの角度を直すために長さを調整することです(スタビリンクのうんちくはこちら)。フロントではその効果をすごく体感できたのでリヤも作ってみたのですが、試作1号ではほとんど体感できませんでした。で今回、懲りずに新たに試作2号を作ったというわけです。で、これがその試作2号です。
アーム側は試作1号と同じストレート型のリンクボールですが、スタビ側はコの字型のブラケットを介してピロボールのロッドエンドで接続します。ロッドエンドのねじで全長を調整できます。ブラケットを作るのにさすがに手作業でt3.2の鋼板を曲げるのはあきらめ、図面を書いてプロに依頼してしまいましたので今回は「自作」とは言いがたいのですが、ついでにメッキもしてもらったおかげで製品っぽいものが出来たと思います。
リンクの長さを調整する理由はスタビの角度(支点とリンク接続点の高さの差)を補正するためだというのは以前書いたとおりです。純正の串ダンゴブッシュの場合は明確な接続点はありませんが2個のブッシュの真ん中くらいが接続点ということになると思います。それに対しこのリンクのようにブラケットを介して取り付ける場合、接続点の位置はロッドエンドの軸になりますので、パッと見では延長しすぎ?のように見えるかも知れません。
また、車高ダウン量を考慮してリンク長を補正してみたところ、支点よりもロッドエンドの接続点が下がっているようです。これはおそらくスタビの設計によるもので、リヤのスタビは「うで」の部分がかなり短いために角度変化に敏感です。そのため1Gで水平にするとストロークに伴いどんどん分力が減ってしまうのを防ぐために純正も水平より少し下向きになっているのだと思います。まあでもリンクの長さは後から調整できるので、とりあえずそのまま様子見です(^-^)
で、効果のほどはというと…これがなかなかいい感じ!コーナー後半でアクセルを開けていくような場面で、効いてる感を実感できます。やっぱりピロ化が効いているのかな?今まで、立ち上がりで一瞬揺り返すような動きがあって気になっていたのですが、それが消えてスムースな感じになったような?。フロントのリンクを変えたときには回頭性がすごく良くなったと思ったのですが、リヤを変えた今回はコーナー後半で効果が感じられます。やはり荷重の移動に伴って、ブレーキング~ターンインは前輪が、後半~立ち上がりは後輪が支配的なんだよなーと改めて考えたりしています。今度は成功かな?なかなか良いものが出来た気がします(^-^)/
ところで、Z32に限らずS13やR32など同時期の日産マルチリンクはみな同じ串だんご型のリンクを使っています。性能的には問題ないのかもしれないのですが、凝ったマルチリンクなのにここだけ前時代的な串だんご…見た目的に今ひとつなので長さの問題とは別に、この部分をピロ化したいなーという不純な動機もありました。
意外にもここのピロリンクって、あんまりアフターパーツがありません。中空スタビで有名なarcはここのリンクも売っています(ただし半ピロ)が、ここくらいじゃないでしょうか(HRD調べ)。海外だとSPL Partsというところが両ピロのリンクを売っているのですが…。
シルビアやスカイラインなど対応車種(たぶん)かなり多いし、これ商品化したら売れるんじゃないか?と密かな野望を抱いています(笑)欲しい方、いますか?
<こっそり追記>
リヤ用のピロスタビリンク、市販は無いみたいって書いたんですが、ナギサオートから出てました。これによるとs13-15,R32-34だけでなくY32,Y33,G50プレジ(!)など当時のマルチリンク車みんな共通みたいです。新商品ってことみたいですが…お値段27825円!高けぇええ!(((;゜Д゜)) あ、でもちょっとコンセプトが違っていて、ロールセンタ補正アーム用でむしろ短くて長さ固定式ってことみたいです。両端ピロのプレート?が専用品っぽいので高いのでしょうね。にしても高いなあ。うちなら半額以下で出せまっせ(笑)
| 試作2号ピロリンク | 装着状態はこんな感じ |
アーム側は試作1号と同じストレート型のリンクボールですが、スタビ側はコの字型のブラケットを介してピロボールのロッドエンドで接続します。ロッドエンドのねじで全長を調整できます。ブラケットを作るのにさすがに手作業でt3.2の鋼板を曲げるのはあきらめ、図面を書いてプロに依頼してしまいましたので今回は「自作」とは言いがたいのですが、ついでにメッキもしてもらったおかげで製品っぽいものが出来たと思います。
リンクの長さを調整する理由はスタビの角度(支点とリンク接続点の高さの差)を補正するためだというのは以前書いたとおりです。純正の串ダンゴブッシュの場合は明確な接続点はありませんが2個のブッシュの真ん中くらいが接続点ということになると思います。それに対しこのリンクのようにブラケットを介して取り付ける場合、接続点の位置はロッドエンドの軸になりますので、パッと見では延長しすぎ?のように見えるかも知れません。
また、車高ダウン量を考慮してリンク長を補正してみたところ、支点よりもロッドエンドの接続点が下がっているようです。これはおそらくスタビの設計によるもので、リヤのスタビは「うで」の部分がかなり短いために角度変化に敏感です。そのため1Gで水平にするとストロークに伴いどんどん分力が減ってしまうのを防ぐために純正も水平より少し下向きになっているのだと思います。まあでもリンクの長さは後から調整できるので、とりあえずそのまま様子見です(^-^)
| 装着状態で長さ調整OKです | 1G状態で覗き込んでみた眺め |
で、効果のほどはというと…これがなかなかいい感じ!コーナー後半でアクセルを開けていくような場面で、効いてる感を実感できます。やっぱりピロ化が効いているのかな?今まで、立ち上がりで一瞬揺り返すような動きがあって気になっていたのですが、それが消えてスムースな感じになったような?。フロントのリンクを変えたときには回頭性がすごく良くなったと思ったのですが、リヤを変えた今回はコーナー後半で効果が感じられます。やはり荷重の移動に伴って、ブレーキング~ターンインは前輪が、後半~立ち上がりは後輪が支配的なんだよなーと改めて考えたりしています。今度は成功かな?なかなか良いものが出来た気がします(^-^)/
ところで、Z32に限らずS13やR32など同時期の日産マルチリンクはみな同じ串だんご型のリンクを使っています。性能的には問題ないのかもしれないのですが、凝ったマルチリンクなのにここだけ前時代的な串だんご…見た目的に今ひとつなので長さの問題とは別に、この部分をピロ化したいなーという不純な動機もありました。
意外にもここのピロリンクって、あんまりアフターパーツがありません。中空スタビで有名なarcはここのリンクも売っています(ただし半ピロ)が、ここくらいじゃないでしょうか(HRD調べ)。海外だとSPL Partsというところが両ピロのリンクを売っているのですが…。
シルビアやスカイラインなど対応車種(たぶん)かなり多いし、これ商品化したら売れるんじゃないか?と密かな野望を抱いています(笑)欲しい方、いますか?
<こっそり追記>
リヤ用のピロスタビリンク、市販は無いみたいって書いたんですが、ナギサオートから出てました。これによるとs13-15,R32-34だけでなくY32,Y33,G50プレジ(!)など当時のマルチリンク車みんな共通みたいです。新商品ってことみたいですが…お値段27825円!高けぇええ!(((;゜Д゜)) あ、でもちょっとコンセプトが違っていて、ロールセンタ補正アーム用でむしろ短くて長さ固定式ってことみたいです。両端ピロのプレート?が専用品っぽいので高いのでしょうね。にしても高いなあ。うちなら半額以下で出せまっせ(笑)