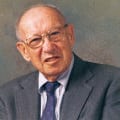2024.2.18のマコなり社長のインサイドストーリーズから
・その言葉を発している人が自覚的であるかどうかはさておき、人はなにかしら意図を持って言葉を発している。
・「なぜこの人はこのような言い方をしたのだろう」「なぜこの言葉を選んだのだろう」「なぜ今このようなことを言っているのだろう」ということを考えながら、コミュニケーションを進めることが大事である。
・上司から部下へのコミュニケーションの7割くらいは、フワっとしたお願いになっていることが多い。
本来であれば、上司の立場にいる人は目的を整理すべきである。「なぜその手段を取るのか?」「その作業の手段を部下にお願いするのか?」「他の選択肢はなにがあるのか?」ということも含めて、論理的に詰め切ったうえでお願いするのが望ましい。
・上司からのオーダーを受けてやってはいけないことは、思考停止でとりあえずデータ整理の作業を始めることと、勝手に思いはかって作業することである。いちばん良いのは「なぜそれをやるのか」「どのようにやるのか」という前提条件をすり合わせてから作業を開始することである。
・抽象度が高く「本当にこれで合っているのかな?」という不安なものに対してびびってなにも聞かずにいると、お互いに不幸になる。
・抽象的な言葉は、定義がズレているとその後の理由や論理展開の全てが無駄になってしまい、人にも誤解されてしまう。
・自分だけでなにか物事に取り組むよりも、たくさんの能力がある人と一緒に物事に取り組むほうが大きな結果を出すことができる。そのためには、誠実に人に付き合うことであり、それだけで人生で結果が出る。
・直接的かつ短期的に目の前の役に立つことばかりを学んでいると、人は大局観を失う。
・長期的に俯瞰的な目線を持って物事を考えていかなければ、常に目の前のことに取り組むばかりの人生になってしまい、それは企業のマーケティングの思うつぼである。
・短期的な欲求を動かすことで、企業はお金を儲けようとする。人の本能に訴えかけて、劣等感を揺さぶる。
・世の中で価値がある人間になりたいと思うのであれば、人と違う発想をしなければならない。
・一定の常識を踏まえたうえで、自分なりの非常識を作っていかなければならない。自分なりの非常識を作るには、長期的かつ俯瞰的な目線が必要になる。
・今ある歴史の知識は、先人たちが残してきた過去を知るヒントである。
・誰かを悪人にすることで自分を正当化するという短期的な快楽を得ようとしているケースが多々ある。
・なかなか変わらない人をなんとか変えようとすることは誠実に向き合うことではない。仕事であれば、その人と一緒に働かないと決めることもひとつの意思決定である。全ての人を救ったり、変えたりすることはできないという現実を認識しなければならない。しかし、その人の人間性そのものを否定するような態度や「自分が上、あの人が下」という傲慢な態度がセットになってしまってはならない。あくまでもお互いの人生の豊かさを第一に考えて、他者貢献の気持ちを持って嫌われる勇気を発揮しよう。
・自分ができると思える限界まで誠実に向き合うとは「優しくする」「おだてる」「忖度する」「特別扱いする」ということではない。相手を悪者にしていないか、下に見ていないかというところを振り返ろう。そのように自分の心の在り方を見直すということを、自分のできると思える限界までやるべきである。
・「あの人が悪い」と思ったら深呼吸をしよう。その人は敵ではない。そして「これからどうするか」を考えよう。