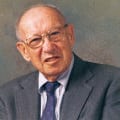今日のマコなり社長のインサイドストーリーズから
・等身大のその人よりも高まり過ぎている期待値はダメである。
・期待値調整のためには、仕組み(情報共有)と教育の両方が必要である。
【教育による2つの期待値調整】
1.どんなに仕組み化(情報共有)していたとしても、結局その人が「今はこれをやっています」と言わなければ、トラブルやネガティブなことについて知ることができない。実務者についてはリスクを感じたら早く上司に共有して期待値調整をする。
2.仮説を持ってアクションプランを握り続けるとは「今はこのように考えているので、このような仮説を持ってまずこれをやってみます。ダメだったらこのようにします」というように、仮説を投げ続ける仕事の仕方により期待値調整をする。
・事前合意は期待値をズラさないために大事である。
【大きな期待値のズレを生む4つのもの】
1.過去の年収(過去の実績)
過去の年収が高すぎたというズレがある場合は、お互いに幸せに働くために「この会社でやっていくのは難しいかもしれない」という健全なプレッシャーをかけるべきである。
2.キャリアや学歴(過去の実績)
キャリアを積んだ人は、めちゃくちゃ大きな錯覚資産を持っている。ピカピカのエリートよりも、体中に矢が刺さってでも前に進み続ける野武士のような人のほうが活躍できる。
3.アピール内容(発する言葉)
4.時間経過(自分の思い込みや期待)
・人と人が一緒に過ごしているだけでも暗黙の了解が増えていくため、期待値は上がっていく。
・自分が長く一緒に過ごしている人たちに対して気づかないうちに貯まってしまっている期待値を、積み下ろさなければならない。それができないと、長く一緒にいる人の行動の全てに対して「なぜこれができないの?なぜ分かってくれないの?前も言ったよね?」というマイナスの期待値に自分が苦しむことになってしまう。
・他者への期待値は気づかないうちに勝手に貯まってしまっているということに気づくだけでも価値がある。
・全ての人を自分だけの力で幸せにする機会を作ることはできない。世の中には、自分と合う人と合わない人がいる。自分の存在や発信、行動、仕事によってプラスの影響力を与えられる人もいれば、難しい人もいる。有限な人生の時間の中で「いかに効率的に自分という有限なリソースを使って社会に貢献していくのか」「貢献感を得ていくのか」を考えるのであれば、付き合う人は選ばざるを得ない。よって、「この人とは価値観が合わないかもしれない」と感じる人とは、(永遠に)保留する。
・私たちが今この瞬間に向き合い続けて、幸せで居続けるためには他者貢献感が必要である。人と比べてしまうという本能が脳の中心部にある以上、役に立っていると思いやすいことをしたほうが良い。そのためには、付き合う人を選ばなければならない。さらに、付き合う人を選んだとしても、時間経過によって期待値は高まって期待値にズレが生まれる。そこにも気をつけなければならない。