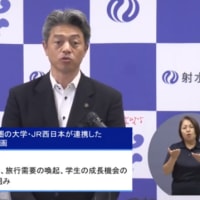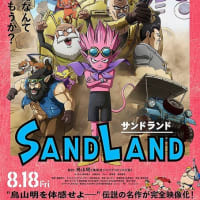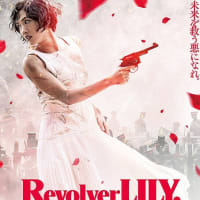朝日新聞 2019年5月28日  https://www.asahi.com/articles/ASM5W566GM5WPUZB00S.html
https://www.asahi.com/articles/ASM5W566GM5WPUZB00S.html
昨年、「手話は言語」と明記された富山県手話言語条例が制定された。だが、かつて聴覚障害者たちにとって、「手話は言語」とは言えない時代があった。県内の聴覚障害者や関係者を取材して、手話を巡る歴史をたどった。
聴覚に障害のある幼稚部から高等部までの18人と、知的障害のある高校生が学ぶ高岡聴覚総合支援学校(富山県高岡市西藤平蔵)。中学部の教室をのぞくと、生徒たちが手話で楽しそうに会話をしていた。幼稚部の教室では、3人の子どもたちが口の動きと聞き取れる音を頼りにしりとりをしていた。
学校では、教師の口の動きを読み取る「口話」教育が行われていた。口の動きを読み取り、健聴者と同じように発話をする訓練が中心。口話の訓練に多くの時間がかけられたため、勉強の進度は3年遅れだったという。
(サイトより引用)