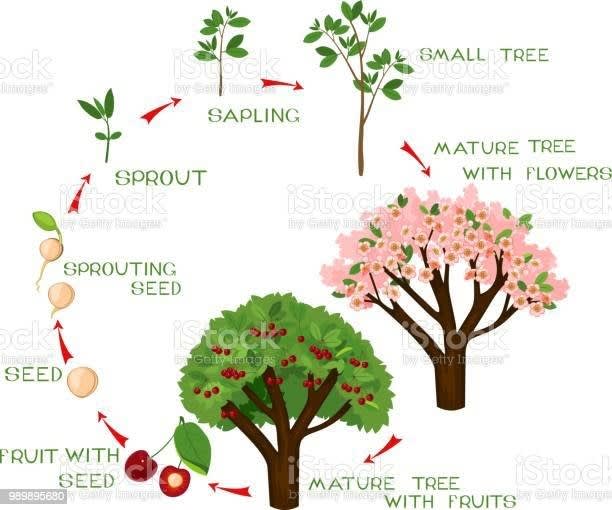ゲーテ(1749~1832)は、ドイツの詩人、劇作家、小説家、自然科学者、政治家、法律家。ドイツを代表する文豪であり、小説『若きウェルテルの悩み』詩劇『ファウスト』など広い分野で重要な作品を残した。
ゲーテ『色彩論』(1810)。ゲーテは自らの色彩論を、いわゆる「色彩環」を用いて論述し、色彩現象の全体的なあり方を明らかにしました。世界には無限に多様な色が存在しますが、色彩にはある種の対立関係も認められるとゲーテは考えます。彼はこれを「分極性」と呼びました。さらにゲーテは「色彩環」の直径の両端が互いを「よび求める」現象にも注目します。色同士の対立関係は、たとえば青と黄が濃くなると赤みがかった輝きをおびるという「高進性」の理論へも展開します。このような「分極性」「よび求め」「高進性」をもつ「色彩環」には、ゲーテによる色彩現象のトータルな把握が示されています。ゲーテの色彩論は、ヘーゲルの哲学にも影響を与えました。
分極性と高進性
あらゆる自然の二大動輪の直観はすなわち分極性と高進性の概念である。
分極性はわれわれが自然を物質的と考える限りにおいて物質の属性であり、高進性はわれわれが自然を精神的と考える限りにおいて自然の属性である。
前者は不断の牽引と反発、後者は絶えず高昇しようとする内的欲求にある。しかし、物質は精神なしには、精神は物質なしにはけっして存在せず、また作用することができないので、物質もまた高進することが可能である。同様に精神もまた牽引し反発することをやめない。結合するために充分に分離し、充分に結合したあと再び分離できる者だけが真に考えることができるのと同じである。
ゲーテ論文「自然」への注釈より
色彩論
色彩は光の行為である。その能動的なはたらきと受動的なはたらきとによって生じ行
たものである。
色彩と光は相互にきわめて厳密な関係を保っている。両者はともに自然の全体に属している。なぜなら、自己を眼という感覚を通して啓示しようとしているのは、自然全体にほかならないからである。
同様に自然の全体は他の感覚に対しても自己の内部を開示する。目を閉じ、耳を開いて傾聴してみるがよい。いともかすかな気息から荒々しい騒音にいたるまで、きわめて簡素な単音から最高の和音にいたるまで、激情の叫びから穏やかな理性の言葉にいたるまで、そこで語っているのは自然そのものである。
自然はこのようにその存在、その力、その生命、その諸関係を啓示しているので、無限の可視的世界を拒まれている盲人も、聴覚の世界の中に無限の生命あるものを捉えることができるのである。
(まえがき)
自然の全体は色彩を通して眼という感覚に自己を啓示する。しかし奇妙に聞こえようとも、眼が形を見ないということである。
明と暗と色彩が合わさって初めて、対象と対象を、また対象の諸部分を相互に眼に対して区別するものを構成するからである。
眼が存在するのは光のおかげである。未決定の動物的補助器官から、光は光と同じなものとなるべき一つの器官を呼び起こし、こうして眼は
光にもとづいて光のために形成される。それは内なる光が外なる光に向かって現われ出るためである。
色彩のエネルギー
物理的色彩、特にプリズムによる色彩は、かつてその特別なすばらしさとエネルギーのために、強烈な色彩とよばれた。しかしさらに考察すると、すべての色彩現象に著しい強烈さを容認することができる。
色彩の暗い本性、その高い飽和性、この性質によってまさに色彩は厳粛であると同時に魅力的な印象をひき起こす。色彩は光が条件をくわえられたものとみなすことができるが、色彩も光なしで済ますことはできない。なぜなら、光は色彩が現れてくるための作用因の一つ、色彩現象の基盤、輝き出て色彩を啓示する強烈な力にほかならないからである。
色彩の決定性
色彩の生成と自己決定は同一である。光が普遍的な未決定のまま現われて対象を提示すると現在の事象がいかにもつまらなく見えるのに対して、色彩はいつでも特殊化されて、特徴的かつ意義深く現われる。
一般的に見て色彩は二つの方向に向かって自己決定を行なう。色彩が提示する対立関係をわれわれは「分極性」と名づけ、プラスとマイナスによってひじょうによく表示することができる。
プラスとマイナス、黄色と青、作用と反作用、光と陰影、明と暗、強と弱、暖と寒、近と遠、反発と牽引•••
この特殊化された対立関係をそれら自身の中で混ぜ合わせても、両側の性質は互いに打ち消されれことはない。しかし、これらの性質が平衡点にもたらされ、両者のいずれをも特に認識できないようにされると、この混合は目に対して再び特殊な性質を帯びる。
すなわち、それは一つの単一のものとして現われ、そのさい、われわれは合成されたということをもはや考えない。この単一なものをわれわれは緑と呼ぶ。
さて、同じ源泉から生ずる二つの相対対立する現象が寄せ合わされても互いに消し合わず、第三の快適に知覚しうるものに結合される場合、この現象はすでに調和というものを示唆している。より完全なものはまだあとに残っている。
赤への高進
青と黄が濃くなると、同時に必ず他の現象が一緒に現われてくる。色彩というものは、その最も明るい状態においてさえ暗いものである。それが濃くされるならばますます暗くなるのは必然的であるが、しかし同時にある輝きを帯びる。これをわれわれは赤味を帯びたという言葉で表わす。
ー以下略ー
「色彩論」ちくま学芸文庫より
ヘーゲル
純粋な光のうちでは純粋な闇の中でと同様、見ることはできない。闇は光の中でも活動しているのだ。闇は光を限定して色にし、それによって光自身に初めて可視性を与えるからである。
可視性は眼の活動であり、あの否定的な闇も、実在的、肯定的なものと見なされる光と同じだけこれに関与しているのである。
ヘーゲル『論理学』第1章「存在注3」より
「色彩論」概要
もしもこの世界に光だけしかなかったら、色彩は成立しない。もちろん闇だけでも成立しない。光と闇の中間にあって、この両極が作用し合う「くもり」の中で色彩は成立する。
色彩は単なる主観でも単なる客観でもなく、人間の眼の感覚と、自然たる光の共同作業によって生成するものである。
音や香りなどの感覚もそうだが、色彩には、ただ客観的な自然を探求しようとする姿勢では捉えられないものがある。色彩は数量的、客観的に分析される光の中に最初から含まれているとすると、客観的に光を分析してゆけば色彩のことが分かるということになる。
しかし、外界の光を分析するだけでは理解できない、眼の働きによる色彩の現象がある。灰色の像を黒地の上に置くと、白地の上の同じ像よりも明るく見える。この像を単独で、客観的に分析するだけでは明るさの違いは説明できない。これには眼の作用が関わってくるからである。
対立するものが呼び求め合うというこのような運動が自然のうちに見いだされる。分極性の働きである。眼はひとつの色彩の状態にとどまらず、明るさと暗さという両極にあるものを呼び求め合うことによって新たなる色彩を生み出す。
このように、静止した対象としてではなく、生成するものとしての色彩を見いだすのである。生きるとは活発に運動し、新たなるものを創造することである。
*
白紙の上に色を付けた紙片を置いてそれをじっと見つめる。しばらくしてから色付きの紙片を取り去ると、白紙の上に紙片の色とは違う色の残像が浮かび上がる。その残像の色こそ対になっている色である。即ち赤は緑、黄は紫、青は橙の残像を出現させるのである。ここにも対立する色が呼び求め合う働き、分極性が見出される。色彩は静止したものではなく、それ自身の内部に力を有して運動するものであり、動きもその色単独のものではなく、他の色と結びついた動きである。色は有機的・生命的に捉えなければならない。
眼は単なる青にも黄にも満足せず、それ以外の色を求める。黄と青は呼び求めあい、結合することによって第三の赤という高度なものを生み出す。赤はただ黄と青が混ざったというわけではなく、黄が橙を、青が紫を経て高みで合一したものである。黄色と青の絵の具はそのまま混ぜれば緑色になる。ここに分極性とならんで自然の中に見いだす力、高昇の働きがある。高昇とは自らを高め、発展させようとする上昇意欲である。赤は高昇の働きを経て合一しはたぶん、エネルギーに充ちた力強い色になっている。
ゲーテ「色彩論」より(wiki)