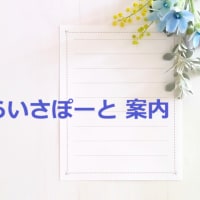療育手帳A判定で重度なASD特性を持っている子どもが成人したときに、
どのような環境でどのようなサポートを受けながらどのような暮らしをしているのか。
それぞれの境遇が異なることから一概には言えませんが、
ASDの特性から何らかの行動障害を伴う当事者はかなり居ると思います。
まわりの状況が理解できないまま、まわりに振り回されながら自分という発信力を持つ機会がないままに安全な個の居場所から放り出されてしまう感覚、
彼らにとって、もしかしたら周りはそのような恐ろしい世界なのかもしれません。
ある問題行動を起こすとその不快さから一時逃れることができる、ある問題行動を起こすことでその反応を得ることを学習する、普遍的な安心を得るためにその問題行動を繰り返す、他の手段を知らない、
まわりが何を求めているのか、自分は何をどう表現したらいいのか、
聴覚や視覚、皮膚感覚などの感覚機能の異常を伴うと更に混乱した世界になってしまう。
そういうしんどさを持った人たちが安心して暮らせる環境とは?
現実はどうかというと、やはり簡単ではありません。
何が難しいのか。混乱を無くそうとすると社会経験をする場面が限定されていってしまい、
ある一定の行動パターンに重きを置くこだわりが強くなるのではないかと思います。
・まわりの状況を理解できるよう構造化された環境で生活の質を保つ
・状況に即した自己発信力を身につける
支援する側としては、特性をよく理解したうえで限定された見方に捕らわれないで、
問題行動の要因、引き金となったものは何かを探り、
では次にどう対処したらよいのかを構築し直し実践を繰り返す、
その場合必ず、親を含めた複数の支援者の共有理解が必要となってきます。
しかし、問題行動とか行動障害とか、冷静に考えてみると実に理不尽極まりない言い方です。
私たちはちゃんとその子の有りのままを理解するという視点を持っていないから、
彼らがまわりから間違った関わり方をされている、言わば、本当は犠牲者なのではないかと、
自らの反省も込めてふと思ったりします。
手帳A判定でしかも重度ASDでも、必要な支援を共有できる環境であれば、
まわりの社会に順応しながら生き生きと自律した生活を送ることができる、送っているのです。
7月31日に強度行動障害のある人の地域での暮らしに関する講演会が高槻市で開催されます↓
【シンポジウムの開催案内】強度行動障がいのある人の地域での暮らしを考えるin高槻 ~当事者の立場を通して~ - 社会福祉法人北摂杉の子会 (suginokokai.com)