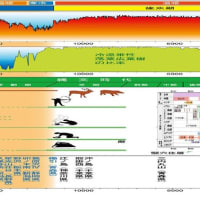アズキ栽培種
伴野原遺跡出土深鉢片
伴野原遺跡33号住居址埋甕 破片展開 会田 進 他
土器の外側と内側あわせて160個のアズキが混入していたのですから、いたるところ穴だらけです。
製作する段階からすでに日用品としての実用性は低かったと考えられます。という土器である
ダイズも混じっているという

 出土状況
出土状況
タイズ栽培種
山梨県北杜市 酒呑場遺跡の181号土坑から出土した縄文中期の蛇体把手付土器[3]の把手部分から栽培ダイズの圧痕が発見され、レプリカ・セム法による観察で栽培植物であると確認された。
また、同様の手法で山梨県都留市の中谷遺跡から出土した縄文晩期前半の土器からは穀物害虫であるコクゾウムシが検出されている。図は探せませんでした

縄文時代の太陽暦と作物の進化
原種からのヒエ、マメ類の栽培種成立
図を参照

小麦やヒエ類は採取に編み籠の容器で穂を採集できた
土器はマメ類の細かい種の採集のための容器として開発されたと考える
ツルマメ ダイズの原種とされている

太陽暦の進化


供献土器の歴史的経緯

縄文草創期に農耕の起源があることは疑いないのでは無かろうか
文明の歴史対比

図はお借りしました
引用ーーーーーーーーーーーーーー
縄文文化を紹介し、研究支援活動を行う「NPO法人国際縄文学協会」によれば、縄文時代の定義は「土器を持った狩猟採集文化」。そのはじまりは17,000年ほど前とされており、当時は氷河期の真っ最中でした。約11,000年前に氷河期が終わり、いわゆる「森と海の時代」に入ります。この頃の日本国内には、ドングリやクリ・クルミが実る豊かな落葉広葉樹の森が広がり、海面上昇や土砂の堆積によって、魚介類が豊富に育つ環境が形成されていたといいます。
ーーーーーーーーーーーーーー
復元されずに土器片としてそのまま残っていたことが、レプリカ法を駆使しての圧痕の解明に繋がったのである。おかげで破片一つ一つの表裏、そして断面の圧痕を調べられる。これがもしも復元されていたら、断面を付き合わせてのシリコン注入は難しい。
明治大学研究・知財戦略機構客員研究員の会田進氏が代表である科研(B)「中部山岳地域縄文時代マメ栽培化過程の解明」グループは、総合研究大学院大学先導科学研究科助教の那須浩郎氏、(株)パレオラボ統括部長の佐々木由香さんの指導のもとに活動しており、主に筆者が所属する「縄文阿久友の会」会員で構成されている。同会会員の牛山、神尾、赤羽、新村、丹野、黒田、斎藤とともに、筆者も圧痕にシリコン(歯科で使われるもの)を注入して型取りをし、その型を実体顕微鏡、さらには走査顕微鏡で調べ、その圧痕が何であるかを確認する作業にあたった。この科研の作業は2013年6月から始まっていたが、2014年12月13日(土)に南信州豊丘村資料館へ出かけ、その土器片と対面した。私たちは大きなマメ圧痕がクッキリはっきり無数に見えることに興奮した。これはただならぬ遺物だとみんなが感じた。そしてその土器片入り木箱を拝借し、大切に原村に持ち帰った。こうして他のどの作業にも優先して、伴野原遺跡出土深鉢片のレプリカ採りが始まったのである。
レプリカ採りは、2015年3月までを目処に行われた。土器片の表裏、目で見える圧痕は185ヶ所で、佐々木由香さんの同定では146個がアズキ亜属種子(ヘソあり16個ヘソなし130個)で、大きさは7.2?9.6mm、その他はダイズなどの種子であった。さらにこの土器片75個をX線写真撮影したところ、圧痕の数は約300個に増えた。内部の圧痕119個はレプリカ採りができないので、アズキか何か分からないが、1個体分の土器片から判明した圧痕の数は日本最多の数であることは間違いない。
ところで、縄文時代中期中葉4500年前の土器から出たマメ圧痕は、何を物語るのだろうか。土器に数個程度のマメ圧痕があるなら、土器を捏ねている間に紛れこんだと言える。しかし、数百個となると、紛れ込んだとは思えない。ここ数年、私たちはマメ入り土器を焼いている。土を捏ねて形を作り、そこにマメを押し込んで焼くと、破裂してしまう。最初から粘土に混ぜ込んで練り入れると圧痕も美しく仕上がって焼けた。この実験から、縄文人は粘土を捏ねるときにマメを混ぜ込んでいたことが断定できる。しかも、マメは土器全体に均一に入り、偏ることもない。ではなぜ、土器にマメを混ぜ込んだのだろう。私たちが考える一番安易な理由は、祭祀に使われたということである。翌年の豊穣を祈るマツリに使ったのか、何に使ったのかは分からないが、縄文人が意図的にマメを入れたことは間違いないと思う。大切な食料としてのマメ、彼らがマメを大切な命の糧としていたのだと考えられる。近年、縄文人の植物利用が解明されてきているが、クリ林を育て、ウルシの木を植栽していたことが分かっている。これまでマメの栽培は大陸からもたらされたと考えられていたが、北東アジアでも栽培化されていたことが分かってきているので、この300個のマメ、特に広義のアズキ146個は、これからの縄文時代の生業解明に大きな一歩を踏み出すきっかけとなりそうである。
文責: 山本郁子
ーーーーーーーーーーーーーー
小林達雄 『縄文人の世界』
食料資源の多様な利用
縄文の文化・社会を支えるのは、いうまでもなく生業経済である。縄文時代の生業は、狩猟と漁撈、採集の三本柱からなっていた。狩猟・漁撈・採集は、四〇〇万年以上にもわたる長い人類史の基本であったが、これは二段階に区別される。
第一の段階は、空腹になったら食べ、満腹になったら休むというものである。旧石器時代や白人文化との接触以前の北アメリカの先住民の一部やオーストラリアのアボリジニなどの生活様式である。第二段階は、食料の確保が計画的になり、その場しのぎに空腹を満たすためだけでなく、種類によっては大量に獲得して、貯蔵しながら長期的に食料事情の安定が図られる。また生のままでは腐敗しやすいので、穴蔵などの貯蔵用施設や保存加工法が工夫されることにもなる。縄文人や北アメリカ北西海岸の先住民諸族は、この第二段階を極めた典型である。
縄文時代が相当規模の定着的な集落を維持しえたのは、まさに狩猟・漁撈・採集経済の第二段階にあり、食料事情の計画性を背景としたからである。とくに縄文文化においては、それを可能にし、大きく前身させたのが、土器の働きである。
縄文時代の貝塚や洞窟、低湿地の遺跡で発見される食料を数え上げていくと、哺乳動物六〇種以上、貝類三五〇種以上、魚類七〇種以上、鳥類三五種以上、植物性食料五五種以上にのぼる。とくに植物性食料は遺存しにくく、当然食べたと思われるワラビ・ゼンマイ・タラの芽・カタクリ・ウド・キノコの類の多くが出土リストから抜けているので、これも加えられねばならない。
・・・・・かつて白井光太郎は『救荒植物』を著し、山野に自生する可食植物を要領よくまとめ、総計四三五種について、芽・若葉・葉・茎・根・苗・花・実などの可食部分の区別とその調理法を明らかにした。これにキノコ類も加えて斟酌すると、かつて概算した三〇〇種をはるかに凌駕する五〇〇種の大台こそが縄文人の植物食の実態に近いのではないかと考えられる。ただ、食料とされたそれぞれの種類を調べあげることも重要であるが、ここではなによりも資源の多種多様な利用が注目されねばならない。
縄文時代の生業の特色は、この多種多様な食料の利用にこそあり、これが「縄文姿勢方針」なのだ。そして、ここに次のような二つの意味を知る。
まず第一に、多種多様な天然資源を食料としたことにより、食料事情の盤石な安定性が保障された。少数の種類に限定しないことで、季節の変化につれて常にそれなりの自然の恵みにあずかることができたのである。また、異常気象などでいくつかの種類の食料が枯渇、あるいは不作となったとしても、他のいくつかは影響を免れ、食いつなぐことができた。また不足気味の一時期を耐え忍びさえすれば、まもなく食べられる新しい食料資源の時期が必ずやってくるのである。
多種多様な利用とは、少数のものに偏しない、集中しないということである。この縄文人と自然との関係は、おのずから自然の生態学的な安定維持につながった。これが、第二の意義である。興味深いのは、ウサギ・タヌキからオオカミ・ヤマネコ、そしてムササビ・オコジョやテン・ネズミまで狩猟の対象となっていたことだ。また多くの民族例からみても、狩猟民は自分と姿形が似ているサルは食べ物から除外するのが普通だが、縄文人は頓着しない。実際、好んで獲っている節さえ見受けられるのである。
また、彼らは、肉のまずい動物まで獲って食べている。・・・・・哺乳動物六〇種の中には、縄文人の舌にもまずいと思えるものがあったに違いない。それでも忌避せずになんでも食べているのである。
たしかに動物の肉、とくにシカやイノシシは美味であり、一頭仕留めさえすれば大量の肉が確保できる。もっとも山岳部ではこれがクマとカモシカになり、北海道ではイノシシがいないのでエゾシカとクマに代わる。けれどもこうした狙い目の動物ばかり獲っていたら、獲物はたちまちムラの周りから逃げて姿を見せなくなるだろう。そうなれば、しだいに狩場への距離が延びて、やがては日帰りでは間に合わないほどの遠征となり、ついにはシカやイノシシの群れを求めて、あの旧石器時代のような遊動的生活に戻らなくてはならなくなる。こうした容易に予測できる弊害は、美味で効率的であるからといってもシカやイノシシにのみ集中せず、多種多様な動物を食べることで回避されたのである。
シカやイノシシだけにこだわらず、他の動物を食べながら頃合いを見計らってゆくこの縄文姿勢方針は、あたかも柵のない牧場経営ともいうべき巧みな仕組みとなっていたのである。
堅果が主食
全国各地の縄文遺跡から発見される植物遺存体の中で、最も普遍的に見られるものは、クリ・クルミ・トチ・ドングリの堅果類である。
・・・・・縄文人が冬を越すための大切な食料だった堅果類は、地下に掘り込んだ貯蔵穴などに保存されたのだ。貯蔵穴は、長期的な食料計画のための施設である。
・・・・・堅果類こそが植物食の重鎮であるばかりでなく、いわば縄文人の主食を構成するものであった・・・・・。
「自然の人工化」
ところで堅果類には、そのまま食べられるものもあるが、アクを抜かなければ食用にならないものもある。アク抜きなしで食べられるのは、ブナ・クリ・シイ・マテバシイ・イチイガシの実だ。簡単な水さらしを必要とするのは、アカガシ・アラカシ・シラカシなどの類、そして水さらしに熱処理を加えて初めて食用となるクヌギ・コナラ・ミズナラ・カシワ・トチなどの類が区別される。また、アク抜きや渋味を軽減するには、油を使用する調理も有効であり、アイヌの人びとは、そのために獣類や魚類の油を活用していた。
なかでも、最も粒の大きなトチは、アク抜きをして食用に供するまで1ヵ月近くもかかるぐらい厄介なものである。このように、自然の野性の状態に特別な手を加えて利用しやすい性質に変化させることは重要であり、軽視してはならない。私はこれを縄文人による「自然の人工化」として評価していこうと考えているところである。
アク抜き法の開発で、広範囲の堅果類が一挙に食料資源化したことがこれで分かるだろう。これにより、縄文人の食料事情の安定性は飛躍的に発展した。縄文文化が、狩猟採集社会としては世界でも一級の水準に達した背景は、ここにこそあったのである。・・・・・
堅果類は、石皿と磨石を使って、砕いて製粉され、団子状にされた。それを縄文人は、魚介類や獣肉のスープの中に、スイトンのように落として食べることもあったであろう。あるいは直接火にかざしたり、灰の中に埋めたりして焼いて食べたのであろう。・・・・・
ところで堅果類の中でも、クリは、アク抜き不要で、しかも天然の甘味を味わえるので、縄文人の関心がひときわ大きかったものかもしれない。・・・・・たしかにクリは、各地の遺跡から出土しており、早期にまでさかのぽる。また遺跡に残された炭化材には圧倒的にクリの多いことが知られている。・・・・・
縄文人は、クリ以外の利用価値の低い樹木は伐採し、これらを薪として燃やし尽くしたため、結果的にクリの木が保護されて人工的な景観が出来上がった、という筋書きである。これが、さらに縄文人とクリの木との関係を緊密としたのだろう。
栽培という自然の人工化
・・・・・前述のとおり、多種多様な食料資源の利用の効果、すなわち縄文姿勢方針を真に理解する時、縄文文化には弥生時代的な農耕がなくても十分安定した力を備えていたことを知らねばならない。
たしかに縄文時代にも、ヒョウタン・エゴマ・リョクトウなどの栽培種と考えられる種類が存在している。ソバ・ヒエ・ニワトコも利用していた可能性がある。佐々木高明は、早くからこうした栽培種にかかわる農耕の存在に注意を向けている。しかし、これを農耕とみなすのは、縄文的な狩猟・漁撈・採集経済の本質を見間違うおそれがある。いずれの栽培種も多種多様な植物性食料の利用の一環であり、農耕という次元の行為・思想・効果とは明確に区別される。これらを混同することは、歴史を観る意義の放棄につながりかねないであろう。
縄文農耕問題
縄文人の食用をはじめそのほかのための動植物資源の開発は、こうして徹底され、さらに薬草や毒物などの弁別知識に及びながら、生態学的知識が深められていった、と思われる。このような自然の観察を通して具体的な試行錯誤を重ねていく姿勢方針、そして資源の多種多様な利用への傾斜については、前にも触れたが、特定の少数の栽培種の食料資源に収斂しようとする農耕経済とは、断固として相容れるところではなく、むしろまったく反対の極に立つものである。たとえ栽培があったとしても、それは縄文姿勢方針にのっとった多種多様な資源利用の一環であって、基本的な縄文経済の枠組みからはみ出すものではなかった。
一定面積を区画して自然から切り離し、特定種専用の畑・水田に転換する農耕は、その土地面積が多種多様な資源を生み出す潜在的機能を否定し、破壊する。この観点からすれば、今日の自然環境に対する冒?と破壊は、まさに自然を積極的かつ人工的に変更することによって効率を高めようとする弥生時代の農耕経済に遠く由来するものであることが理解される。しかも自然を破壊して、自然の中に無理に割り込ませた少数種の農作物は、きわめて脆弱である。そして、だだっ子のように人の手の助けをしきりに頼み、もはや人の助けなくしてはにっちもさっちもいかなくなってしまう。ちょっとした旱魅や冷害、病害虫によっても、壊滅的な打撃を被るのである。
毎年のようにジャーナリズムが報じる世界各国の飢饉は、農耕経済の脆さと不安定さをあらためて教えてくれているではないか。しかしその対極に立つ縄文自然経済においては、たとえ一部の食料資源に不漁・不作があったとしても――それがドングリであってもー―それを補って余りあるほどの代替物でまかなわれる巧みな仕組みを有しているのである。狩猟採集民には、飢饉は無縁なものであった。
たかが狩猟・漁携・採集社会だと、縄文経済の力をあなどってはならない。・・・・・
そして、さらに自然の人工化の実例として、「縄文クッキー※」と「果実酒作り」と「漆工芸技術」が注目される。・・・・・
※縄文クッキー:材料・形をつくる・焼く<情報処理推進機構教育用画像素材集より引用>
食料の備蓄と保存加工
秋に縄文のムラ人が総出で採集したクルミ・クリ・トチ・ドングリなどの堅果類は、食料としての価値と重要性において別格ともいうべき存在である。女や子供でも容易に、かつ大量に採集でき、縄文人の基礎的食品となっていた。ただ別格のドングリの類といえども、豊作の年ばかり続くわけではなく、周期的に不作の年がある。そして異常気象の影響などで、凶作の年も必ず巡ってくるものであった。それでも縄文人は、多種多様な資源を利用する縄文姿勢方針のゆえに、飢え死にから免れたはずである。そこが、ごく限られた栽培種に依存した農耕民とは根本的に違うところである。そして異常気象などの影響に大打撃をこうむるのは、むしろ農耕民であったことを知るのである。
・・・・・縄文人は、その日の糊口を満たすばかりでなく、将来的な食料備蓄も心がけていた事実が重要である。
すべての食料がそうした備蓄にあてられたわけではなく、それにかなう種類は限定されていた。まず第一に、短期間に、効率よく、大量に確保できるというのが、その必要条件である。その意味で、貝塚に残された二枚貝は、干潟が広く現れる時、すなわち大潮とその前後に、大量に採捕された典型的な備蓄用食料の一つになりえたのである。
さらに秋に採集されたクリ・クルミ・ドングリ各種の堅果類も、短期間に、安全確実に大量の収穫が可能な食料である。・・・・・
備蓄の要件の第二は、保存問題である。せっかくの食料が、後で腐敗や変質してしまっては、食べられなくなる。その防止なり、保存のための特別の加工が必要とされる。乾燥、煉製などのほか、塩漬けや発酵法などが考えられる。それに加えて、保存施設の工夫や、備蓄場所の選定が必要である。・・・・・
かくして食料の大量確保と備蓄こそは、縄文時代の食料資源とその利用を特徴づけるものとして重要であった。そのつどの消費と長期的展望による備蓄との組み合わせが季節ごとの食料資源の過不足を調節したのであり、旧石器時代の狩猟採集経済に比べて、一段と生活を安定させ、定住的な生活を保障したのである。
縄文カレンダー
このように縄文人が食料とした資源は、年間を通じて一定していたわけではない。日本列島の四季の変化ははっきりしたものだから、それにつれて動植物資源の種類と量も変化する。
東京大学の赤澤威は、食用植物約二〇〇種の採集利用時期を分析した。地下茎は、少ないながらも年間を通して平均的な利用が見られ、果実と葉茎となると、季節的に大きな偏りがある。果実は、十月をピークに、九~十一月に集中し、六~八月のほかはきわめて少数種に限られる。一方の葉茎は、年間を通じてほぽ途切れなく継続的に利用されているものの、春三月から種類を増し、四~六月にピークがある。植物の季節的変化に対応した植物性食料採集の季節性が、ここにある。
・・・・・漁撈活動にも、このように厳然たる季節性があった。
陸生獣の狩猟活動もまた、季節的であった。・・・・・マタギのクマやカモシカ猟などと同じく、縄文人の狩猟活動も、とくに冬季が中心であったことが判明している。動物は厳しい冬を乗り切るために、秋に十分に餌を食べて、それを皮下脂肪として蓄積している。だから冬の獲物は、脂がのって美味なのである。さらにまた、落葉した冬枯れの木立は見通しもきき、獲物の発見にも有利であった。
このように縄文時代の多種多様な食料資源の採集獲得は、自然の変化に同調したものであった。しかしここでは、単に受動的に自然の恵みを待つだけでなく、むしろ積極的に自然の流れにのり、計画的に労働を展開していくものであった事実を、読み取らねばならない。言い換えれば、縄文時代は、食料獲得をはじめとしたすべての行動を自然の移り変わりに重ね合わせて計画的に進行させていたのである。
++++そうなのか そんなことで可能なのか 太陽暦がある筈
この秩序こそが、縄文人と自然との共生の基礎をなすものであり、ここに、かつて私か縄文人の計画的な年間行動スケジュールとしての「縄文カレンダー」を提唱した趣旨がある。・・・・・
なおこの縄文カレンダーに関連して土器製作についても、一言付け加えておかねばならない。どうも縄文人は決められた季節に土器作り計画を固定していたらしいのである。遺跡を掘ると、壊れた土器を丁寧に補修してとことん使い込んだ例がある一方、新品同然の土器が惜し気もなく廃棄されている例にぶつかることがある。土器作りが年間スケジュールで固定されていたとすれば、初めてこの謎にも合理的な解決が与えられるのである。
陥し穴と罠猟
資源利用に関連して、遺跡に名残をとどめている遺構が貯蔵穴と陥し穴である。・・・・・
貯蔵穴については、すでに述べた。陥し穴は、縄文時代の狩猟事情をうかがううえで重要である。もちろん狩猟といえば、弓矢がすぐ思い浮かぶ。いささか脱線するが、弓矢について少し触れると、矢柄の先端に石鏃を装着した矢は、縄文時代に日常的に使われた飛び道具である。石鏃の貫通力は後世の鉄鏃と比べてもけっして遜色ないどころか、かえって獣への効果が高かったのだ。
・・・・・陥し穴の活用は、あらかじめ計画的に設置しておきさえすれば、いちいち現場に出なくても複数地点で獲物を獲得できるという特典があり、縄文人の知恵がうかがえるのである。
罠猟も、また同様である。・・・・・
手持ちの武器で獲物をしとめる方法には、直接対決に際しての危険の度合いも多く、あるいは敏捷な小形獣の動きを制する困難さがあるが、陥し穴や罠猟はそうした欠点を補ってあまりあるうえに、家の寝所で高枕しながら夜行性の動物をも罠にはめることができるのである。縄文時代の狩猟用の武器の実態は、前述の弓矢以外は意外と不明瞭なままであるが、それは、手持ちの武器で直接に獲物を倒す方法よりも陥し穴・罠猟が盛んであったことの表れなのかもしれない。
ただしこの方法をとると、幼獣や再生産をになう雌は見逃して、図体の大きな成獣や老獣、あるいは雄だけに狙いを集中するという選択ができない。縄文時代の狩猟法の解明は、さらに遺跡出土の動物遺体の年齢構成や雌雄の比率の分析などを通じて明らかにされるだろう。
狩猟儀礼と呪術
狩猟の成功のためには、まずは適切な狩猟具や仕掛け装置の工夫と作戦の立て方が重要である。そして、それを効果的に働かせるための技量を磨く普段の訓練が必要とされる。さらにもう一つ重要なことは、狩猟の成功を確信するための儀礼・呪術である。つまり狩猟は、獲物を獲得する直接的な行動要素とその行動を保障する観念的な要素との二つの面を併せもっているのだ。言い換えれば、儀礼や呪術だけではいかなる獲物も倒せないのはもちろんだが、同時に縄文人の観念では狩猟具や仕掛けだけでもけっして十分な効果をあげえなかったのである。
世界各地の狩猟民にも、また東日本のマタギの間でも、たとえばクマや夕力の爪などのさまざまな護符・呪符がある。縄文時代においても、イヌやオオカミ、さらにはクマ・サル・カワウソ・イルカ・ウミガメ・オオヤマネコの下顎骨や犬歯その他に穿孔した特殊製品は、単に身を飾る装飾品というよりも、むしろ狩猟呪術にかかわる可能性を考えなくてはならない。
Jyoumonnouchitosoto_2
縄文の「ウチ」と「ソト」そして「アノ世」
竪穴住居は、縄文人の造った、初めての恒久的な人工建造物であった。地面を掘り込んで柱を立てて屋根を葺いた住居は、これまでの仮小屋とはまったく異なり、堂々と自分の存在を主張したものであり、ここにイエの「ウチ」と「ソト」の意味が出てくる。
イエの中には炉がつくられる。この炉によって竪穴住居のウチという特有の空間が認識される。やがて炉の縁に石棒などが立てられるが、縄文中期になると石で組んだ祭壇のようなものがつくられる。このように、自分の竪穴、イエの中の空間を特別な空間に仕立て上げていくことによって、イエのウチとソトの違いがはっきりとしてくる。
イエの外に出るとそこには仲間のイエが数軒ある。実は旧石器時代から、狩猟に必要な人数を確保できる三家族から四家族ぐらいがともに移動生活を続けていたのだが、縄文人が定住を始めた頃もそのぐらいの単位であった。こうした数軒のイエが寄り集まった姿、これが実はムラの始まりなのである。旧石器時代までは、いわば自然の中に下宿していたようなものが、縄文人は自然の一部を切り取って、人工的な自分たちの空間をつくり上げていく。そしてその場所を自然に戻すこともなく、あくまでもヒトたる縄文人固有の土地として専有し、承け継いでいこうとするわけである。
イエの外に出るとムラの世界が広がる。さらにその外は、ハラッぱ、ハラが広がっている。
旧石器人はハラの中にすむサルのように自然の中に溶け込んで生きてきたが、縄文人はムラという人工のスペースを確保することによって、ハラというものを対立的なもの、ムラの内とムラの外、すなわちムラとハラの区別をはっきりとさせたのである。だが一方でハラは対立するばかりではなく、食べ物を于に入れる場所であり、生活に必要な道具をつくる材料を提供してくれる場所でもある。いわばハラは、縄文人の食料庫であり、材料庫なのである。特徴的なことには、こうした生活舞台でもあるハラには名前が付く。川、川の淵、瀬、川の曲がりくねった場所、そしてそこにある大きな石、巨木、みんな名前が付くのである。いわば、そうした自然を自分たちの息がかかった味方に引きずり込んでいくのである。こうしてつくられた景観を「縄文ランドスケープ」と私は呼んでいる。アイヌ民族やアメリカ西海岸の先住民が同じようにそれぞれの場所に名前を付けている事実は興味深い。
このように、ムラとハラは、対立しながらも、ハラは縄文人の生活に組み込まれ、しかも平板的ではない。「ウチ」と「ソト」の関係からイエ、ムラ、そしてハラという一つの構造が出来上がっていったのである。そして時代が下るにつれ、縄文人は、大きな広場をつくったり、ますます人工的ではっきりと自然から切り取ったムラという空間を整備して、ハラとの対立を際立たせていくのである。
さらに、そのハラの外には、何かあるだろうか。そう、ハラの向こうにはヤマがある。ヤマというのは、本当の自然であり、そのヤマの向こうにはソラが広がっている。イエ、ムラ、ハラ、ヤマ、そしてソラ。ヤマの向こうのソラというのは、また彼らにとっては、生きてその場所へ行くことのできない「アノ世」でもある。縄文人の中の他界観の成立にも関係するであろう。イエを抱えるムラは「ヒト」の世界、ムラの外のハラは「人と自然」の共生の世界、そしてハラの向こうのヤマは「自然」一色の世界、さらに天上に広がるソラは、ヒトと自然を超えたいわば「神」の世界に続くのだ。この構造こそ、おそらくは縄文人の世界観の大枠をつくる骨組みとなるものと考えられる。
さて、イエの外に出て眺めてみると、まずムラという近景があり、次にハラという中景があり、そしてヤマという遠景がある。この構図こそ、日本の原風景ではないだろうか。縄文時代とその周りの景観との関係というのは、その後の日本人の中にずっと生きている。たとえば、この遠近の関係は、日本独自の浮世絵の見事な遠近法や日本的な庭づくりの借景にもつながっていくのである。