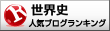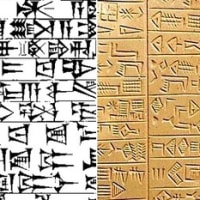それは縄文時代には、半年365日/2 182.5日/2 91日/2 45.5日
四季を知り、季節の始を知ったと思う、必要は発明の母という、それは縄文時代草創、早期から既に存在していた様々な雑穀の栽培暦の為だったのでは無いでしょうか。

これにより暦が春分の91日後からは45日も早く作ることが出来るようになり
栽培暦が早く作れるようになって、栽培生業に大変有利になった。
これは後にチャイナで四立八節の暦と呼ばれるようになったものです。
しかしこれでは太陽暦地域と太陰暦地域の人々が交流するには、暦が違っているため大変困難だった。
約2000年後の縄文時代中期になって、 3波状突起口縁の土器が作られ、
それ以外にも沢山の土器や土偶にも 3が模様として象徴的に作られていた。


何故これほど 3という数字が示され、縄文社会で大盛り上がりとなっていたのか。
それは 45.5日/3 15日という区分暦を作ることが初めて出来て、太陰暦 海の潮の動きを細かく捉えて示す15日 上弦と下弦に区分する 24弦の暦とシンクロすることである。
これが縄文時代に 3に関係する土器などが沢山作られ、社会がその興奮で湧いた理由なのでは無いだろうか。
その後、縄文時代後期、晩期には 5,7波状突起土器が作られていた。
太陽暦では、5日の区分暦 後にチャイナで七十二候の暦と呼ばれることになる暦が作られ
太陰暦では 潮の動きを捉えて、15日/2 7日一週間の暦が作られていた。
縄文社会では地域により異なる生業により、異なった暦が使われながら、
朔旦立春を観測することにより、19年毎に二つの暦を一致させることが出来、
さらに毎年立春観測と同時に朔望を観測することにより、地域で異なる暦の日にちをシンクロさせることが出来ていた。
出土した 5波状突起口縁の土器を見ると、破損してもなお補修して使い続けるというように大変大切にされていたようだ。
現代でも出来ていないような、太陽暦と太陰暦とをシンクロさせて使用するという、思いも掛けないような暦の利用法が存在していた。
地球環境問題など自然の存在の重要性がやっと認識されるようなレベルに人類社会は到達してきたが、それを知り尽くしていたのは縄文時代であり、太陽と月という暦一つでも、宇宙時代と云う現在もまだそのレベルに達することが出来ていないということでは無いでしょうか。
図はお借りしました