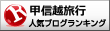縄文晩期には内陸では5日区切りのカレンダーが利用されていたものと考えている

5波状突起口縁の土器についてはどんなものなのか、興味がおありでしたらこちらを参照されることをお薦めします。
グローバル Web アイコン加曽利B2式土器 西根遺跡 補修孔付き5単位波状口縁土器 ...
https://hanamigawa2011.blogspot.com/2019/05/b25.html
2019/05/31 ・ 西根遺跡出土加曽利B2式土器の観察を行っています。. この記事では補修孔付き5単位波状口縁土器を観察します。. 1 377番土器. 377番土器 (千葉県教育委員会所蔵). ・5単位の波状口縁土器です。. 377番土器 部分拡大 (千葉県教育委員会所蔵). ・横走沈線で ...
また海の影響を受ける生業を営む地域では7日区切りのカレンダーを利用していたものと思う

太陽暦では最終的に七十二候のカレンダーに行き着いていたものと考えています。
海の潮の干満を知るためには太陰暦が利用されていたと思うので、その最終形は7日区切りのカレンダーになっていたものと考える。
こうして縄文人が海外からの移民者を受け入れ、彼らのもたらす水田稲作を文化的断絶に戸惑うこと無く、違和感なく受け入れたらしい背景には、暦が存在し定着していたものと考える。
縄文時代を通じて太陽暦を使いこなしていたものだから、稲作文化をさほど大きな抵抗を感じることなく受け入れていた様子からそう考える。
写真はお借りしました