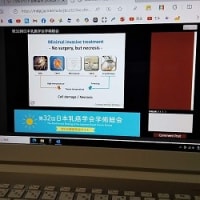抗認知症薬 アデュカヌマブが米国FDAの申請を通ったニュースで
出版社とあわただしくやりとりをしましたが
日本のPMDAの結論が出てから、本格的にいろいろ動くのではないかなと
思っています。
-----------------------------------
6月に入り…
相変わらず、美術館にも工芸館にも
思うように行けず残念に思っていましたが
明日、期間延長している静嘉堂へ行けることになりました

 (何を着て行こうかな…)
(何を着て行こうかな…)
にわか雨がないことを祈って

明石縮に!(こちらはあまり透けない生地なので)
当初はこの、麻地の型絵染を手に取りましたが
ちょっと子どもっぽいかも…と思い直し

ややチャレンジングですが、同系色の首里織 八寸帯に。
この小さな白い花の帯留を、主役にしたかったのです

帯揚げは、昔「銀座もとじ」さんでいただいた、
クリスタルでちょっと天の川をイメージしたような絽縮緬。真っ白です。
半襟は

ホタル、一択です!
------------------------------------
さて、ようやくタイトルについてのお話し。
タイトルを見て興味のある方だけ、読んでいただければ……。
先週末に山本達彦さんのピアノデュオライブを
配信で観て、
ちょっと興味を惹かれる話題があったので、
多少、蘊蓄じみてしまいますが、書いておこうかな、と。

ライブはミディアムテンポが中心で
拍手を挟まないメドレーがときどき入るところや
エンディングがまとまりよくすっと終わっていくところが
心地良く、ヴォーカルも(専門的な言い回しはわかりませんが)
喉が開いているというのか、後半にいくほど声量や太さが感じられて
聴きごたえがありました。
選曲も、穏やかで耽美的なものから快活でエッジが効いたものまで多彩で
……歌詞で常々思うのですが
愛や好きな気持ちを伝えるために、どれほど飾り立てた表現を探しても
「さいごの人」をしのぐパワーワードはない、と。
好きだなあと思う理由は、ここにあるのでしょう。
本題は、カバー曲のことで
私が生まれたころ、米国でヒットした
「花のサンフランシスコ」について。
…私、自分が物心ついた70年代の歌は、
懐かしさから今でもよく聴くのですが、
そういえば60年代って知らないなあ、と新鮮な気持ちで聴きました。
この歌が反戦のニュアンスを含んでいることは、何となく
教養的?に知ってはいたのですが、
実は反戦運動とも深い結びつきがある
カウンターカルチャーについて、約2年半前、
宗教学のたいへん高名な教授に、コメントをいただいたことがあり、
それを今回ふっと思い出して、取材メモを見返した次第。
当時私は、「終末期医療」の取材をしていて、
いわゆる死生観について何人もの識者に話を聞いていました。
その、たいへん高名な教授によると
60年代のカウンターカルチャーは「科学に対する抵抗」なんだそうです。
この時代、米国は目覚ましい経済復興と科学技術の進歩を遂げ
「科学で人は幸せになれる」という空気が強かったそうなのですが
ベトナム戦争勃発が人心を荒廃させ、若者はドラッグに走り
「科学で人は幸せになれない」「自然とともに生きるのが良い」と、
インドやネイティブアメリカンの宗教、
中国の気功などが受け入れられるようになった、とのこと。
このあたりは教授の受け売りですが、
ダスティンホフマンの小さな巨人、ポールマッカートニー、
日本では水木しげる、手塚治虫の世界、……とメモが残っています。
この教授も、他の宗教民俗学の権威の方も
70歳を過ぎたくらいの年代で、
60年代に少年時代を送り、日本の大学紛争を経験しているせいか、
とても気骨がありユニーク。カルチャーにも詳しくて
そうか、死生観の観点でひもとくと、カウンターカルチャーはまた
ちょっと違った解釈になるんだなあ、と
そんなことを期せずして、この歌で思い出してしまいました。