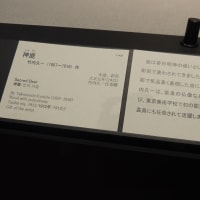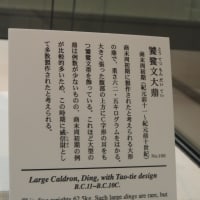奈良国立博物館 青銅器 饕餮文大鼎(とうてつもんだいてい) 商末から周初(BC11C~BC10C)
「中国・晩商~西周初期 紀元前11~紀元前10世紀
饕餐紋
高81.5 口径56.8
1個
商代後期になると、太い柱足を鋳造(ちゅうぞう)欠陥を生じることなく鋳造する技術が発達した。また、実用品ではなく彝器(いき)として装飾が重要視されるようになり、全体に文様を飾るものも現れる。この鼎は商末周初期に相当すると考えられる大型鼎で、重さ62.5キログラムをはかる。当コレクション中でも代表的な資料となっている。大型の鼎は特に商末周初期の例が多いので、この時期に威信材(いしんざい)として多数製作されたらしい。殷墟の大型方鼎鋳造遺構(おおがたほうていちゅうぞういこう)の例では、地面に内型を作りつけ、外型をその上部に組んで鋳造するという大掛かりな仕掛けが見つかっている。内壁に図像記号が鋳込まれている。
坂本コレクション 中国古代青銅器. 奈良国立博物館, 2002, p.37, no.100.」
饕餐紋
高81.5 口径56.8
1個
商代後期になると、太い柱足を鋳造(ちゅうぞう)欠陥を生じることなく鋳造する技術が発達した。また、実用品ではなく彝器(いき)として装飾が重要視されるようになり、全体に文様を飾るものも現れる。この鼎は商末周初期に相当すると考えられる大型鼎で、重さ62.5キログラムをはかる。当コレクション中でも代表的な資料となっている。大型の鼎は特に商末周初期の例が多いので、この時期に威信材(いしんざい)として多数製作されたらしい。殷墟の大型方鼎鋳造遺構(おおがたほうていちゅうぞういこう)の例では、地面に内型を作りつけ、外型をその上部に組んで鋳造するという大掛かりな仕掛けが見つかっている。内壁に図像記号が鋳込まれている。
坂本コレクション 中国古代青銅器. 奈良国立博物館, 2002, p.37, no.100.」
(文化遺産オンラインの解説から)
「 鼎は本来、肉類を煮る器でしたが、次第に料理を盛る器として利用されるようになりました。祭祀(さいし)の儀式では、神や祖先に供物を捧げる器として、最も重要な青銅器と考えられています。 」(岡田美術館HPから)







底をのぞいてみた

上から中を見た