絹張りの主翼中抜き部のDOPE処理方法
ブログ記事内にて 主翼中抜き部分の絹張りのDOPE処理について
ドープサイザー使用部分での説明不足が有りましたので 追加訂正をさせて頂きます
追加訂正
プランク面や 主翼中抜き部分の DOPE処理で
ドープサイザーは 必ずしも入れる必要は有りません
ドープサイザーを使用するかは 機体の組み付け状況にて判断して下さい
理由
主翼中抜き部分に ドープサイザーを入れると
特に 水上機や梅雨時に 緩み傾向が出る場合が有ります
ドープサイザーを使用しない方が 張りは良くなります
主翼や尾翼などの中抜き部分例
その他でのドープサイザー処理方法
1)胴体が骨組のみの機体での 絹張りは 張りによる歪が出る場合が有りますが
ドープサイザー使用は 機体加工状況により 使用判断をして下さい
2)全プランクでの絹張りの場合は プランク材が3mm以上の厚みが有る場合は
ドープサイザーは入れないで張ることが出来ます
3mm以下(2mmなど)の厚みのプランク材の場合は
ドープサイザーの使用は 機体加工状況により判断して下さい
3)一長一短が 有りますので 必ずしも 入れる必要は有りません
4)絹張りの初期 仮張りの作業周囲環境や状況により 一概に言えない部分も有りますので
ご理解下さい
5)主翼の絹張りで 中抜き部のリブ間の絹張り波を出す程度により
主翼の絹上に塗るDOPEクリヤーにドープサイザーの有無か混合率の調整が必要です
仮のテストリブなどで確認されるのをお勧めします
絹を張り始めると修正が出来ません
剥がしても 絹目がずれて再利用出来ない場合が有ります
〔事前に数枚のテスト用リブ組を作って置く 本番と同じ下地処理をして絹張りを見る〕
お詫び
記事や画像内での 説明不足でご迷惑をお掛けしました
お詫び申し上げます
参考
絹張りは 気候(湿度・温度など)や機体張り条件等で
微妙に調整や作業を行う必要が有る場合が有ります
経験されて見える方に聞かれたり 見せて頂く様な事が出来れば より参考に成ります
湿度の高い場所や雨天時は 基本的に 絹張り作業には適しません
対応方法も有りますので 経験された方に伺うのを お勧めします












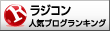














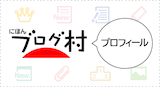




私は油が染みてフィルムがはがれる経験をしてからエンジン機は全て絹張りで仕上げています。
ドープサイザーですが私は窓の部分(私たちは下にバルサがない所を「窓」と言っています。)の絹がベコベコになることを気にせずにドープを買ったらすぐに缶にドープサイザーを入れてそれを使っています。機体を水拭きする段階ですでにベコベコします。
THCのドープが入手不能になりました。手持ちの500mℓ缶を使い終わったらどうしようかと思います。行きつけの模型屋さんにパクトラのガラス瓶詰のドープがありますが殺人的な高さです。
Kikicocoさんはどのような対策を考えていますか。私はアメリカンフラワーの溶液や釣り具屋さんで手に入る「セルロース」を試そうかと考えています。絹の代替は薄手のポリエステルを考えています。