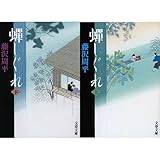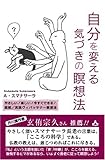中央公論を読んでいたら、「物価と金利」という時評である経済学者が
「物価は変わらないもの」という通念を日本国民が持っているので、
この思い込みは簡単に変わるものではない。
そしてその通念は、それが通用する期間が長いほど強さを増す。
その例えとして、
値上げをした店Aに、ある消費者が訪れた状況を考えてみよう。
もしその消費者が「物価は変わらないもの」との通念をもつ
ならば、店Aは値上げをする例外的な店なので、店Aを出て、
わざわざ移動コストを払ってでも店Bに向かう。
ー中央公論4月号 「物価と金利」坂井豊貴氏ー
諸外国がインフレに対して、金利引き締め策を進めようとしている。
日本はどうか、金利を引き締めるつもりはなさそうで、緩和政策を
今後も続けるようだ。
インフレに対する、諸外国との感性の違いかもしれないが、
諸外国ではどんどん物価があがり、アメリカなどではガソリン価格が
上がることで猛烈に国民から政府が批判を受けている。
日本はどうか、まあ政府も対策を打っているが、ガソリン価格が
上がるのは嫌だけど、それだけで強烈な政府、政治批判には
ならない。
遠出を減らしたりしながら、ガソリン高騰に対応する、そのうち
価格が下がるだろうと思っている。
いろいろ4月以降、商品が値上がりする。これも買うものを
減らせばいい。タラバなんか食べなくてもいい。
こんな感覚の人が、私ですが、そんな人が多いように思う。
コロナ感染が広まった時期から、なんとなく、外で買い物をするのは
私の役割になり、生活必需品も含め買い物に行く機会が多くなった。
そうすると同じ商品なのに価格がお店によって違う、日によっても
違う。こんなに価格がいい加減なのかというものがある。
商品名はさておき、150円の定価のあるものが大体、
120円から130円で売られている、しかし安い時は
88円だ、これは面白いと思います。私はとてもこの商品を
定価で買う気持ちにはなりません。
しかも最近近くにできた超激安店はなかなかの価格破壊力である。
そんなことも手伝って、価格に少し興味を持っている。
ニュースによれば大手メーカーの商品を扱わないスーパーが
ある。価格が合わないからでしょう。それに価格指示があり
定価で売るように圧力がかかるのを嫌がってとのことでしょうね。
ほとほと商品とは売れるから成り立つのである。
そんな中、面白い発見をした。あるところである食材を3割程度
値上げをした、そしたら、その商品がいつも余っている。
そのうちその商品がお店から無くなってしまった。
まさにこのような
「物価は上がらないもの」「物価は変わらないもの」という
通念が日本にまん延している。
値上げしても販売数量が落ちて、消費者離れを起こすものも
出てくるのでしょうね。値上げする側もおっかなびっくりでしょう。
値上げが本当に企業業績にとっていいのかどうか?
最近お店の紹介番組でもこの安い値段で提供しているんだという
低価格=善=庶民の見方 的な番組が増えたようなきもする。
このことは
庶民にとってはいい反面、給与が上がらないとか、働く人に
とっては厳しい面もある。だから物価をあげれない。
日本も本格的なインフレに見舞われるのか、それとも
庶民の通念が勝つのか、勝負の行方は?
本当は経済が成長して、給与があがり、物価があがり
するのがいいのですが、そのためには企業が頑張らなくては
いけませんが、そのパワーを持っている企業が少なすぎます。