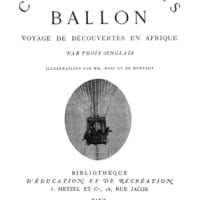『森は生きている』はロシアの詩人であり、作家、翻訳家、児童文学作家であるサムイル・マルシャークが書いた児童劇である。1943年に発表。マルシャークはこのとき56歳。
『森は生きている』はロシアの詩人であり、作家、翻訳家、児童文学作家であるサムイル・マルシャークが書いた児童劇である。1943年に発表。マルシャークはこのとき56歳。
劇の脚本が、そのままの形で児童本として出版された珍しいケース。
ノベライズされずに、なぜ脚本のままかというと、大人になってわかったのだが、ト書きの部分の言葉までが詩であり、美しい世界を作り出しているからだ。
言葉一つ、場面一つムダはない。
研ぎ澄まされた感性と、揺るぎない構成力でシンプルに展開する十二の月と少女の物語。脚本という形で、十二分にその面白さを満喫できる。
はじまりはリスとウサギの会話。
森の中で鬼ごっこをしていたリスが木にのぼり、ウサギに「ピョンとはねてごらん、ピョンと」とからかう場面に出くわし、少女が「クスリッ」と笑う導入が新鮮だ。
動物の言葉が少女にわかる?
しかし、その後に出会った老兵士が言うには、それもそのはず、今日は大晦日。十二の月たちが残らず揃って新年を迎える特別の日。そういうことが起きても、何の不思議もないという。
この劇は、もちろん実際に上演されたのを見ても面白いに違いないけれど、人が演出したものではなく、脚本を読んで作り上げた自分のイメージのほうがずっといいような気がする。
劇場の空間に限定されず、ロシアの雪に埋もれた深い森を背景として、イメージを膨らませたいものである。
つまり、詩的空間を自分の中でこしらえるのだ。
少年期を抜け出したばかりの若者、四月の月が少女に「婚約の指輪」を贈るところが素敵だ。
スラブ地方につたわる十二の月の民話には、この部分はない。たぶんマルシャークの創作。
四月の月は少女にとって王子様なのだ。だけど、王子様よりは身近で、溌剌としている。
もう、食べるもの、着るものに困ることはない。いつでも守ってくれる。
継母にいじめられた美少女が、やがて王子に救われるシンデレラストーリーである。
女の子も男の子もこのタイプの話が好きだ。「いつか王子様が」現れて、人生一発逆転の幸運に恵まれるのだ。
その逆転の鮮やかさ、スピード感が、この物語を何度でも読み返したくなる特別のものにしている。
マルシャークは、日本では、とにかく『森は生きている』の作者として有名である。
「マルシャーク? ああ、あの『森は生きている』の作者か。あの本は、子どものときに読んだよ。あなたも読んだ? 面白かったねぇ」
とういうようなものである。
例えば欧米の国々でも、“『森は生きている』=マルシャーク”の図式で知られているのだろうか。
それとも、他の業績で有名なのか。
そういうところを知りたいと思う。
そういえば、マルシャークはユダヤ人。早くから詩の才能を発揮し、中学生のときにゴーリキーの後押しを受けたそうである。イギリスのロンドン大学で哲学を学んでいる。
さらに、『森は生きている』の訳者は湯浅芳子さん。マルシャークの詩の世界を、見事に日本語に訳してくれているが、その美しい言葉選びから想像するような人物像とは、少し違っているようだ。
瀬戸内寂聴さんが『孤高の人』で書いているように、作家の宮本百合子と長い間恋愛関係にあった同性愛者。様々な方面で活躍したらしいが、けっこうドロドロした人生を送った人のようである。
とはいえ、いつまでもその名前が残るのは、『森は生きている』の翻訳者としてだろうと、私は思う。
湯浅芳子さんの一番いい面が、この仕事に出ているのではないかと、想像する。