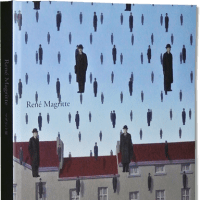□■□■───────────────□■□■
物語の始まり
□■□■───────────────□■□■
そもそもの物語はいつごろ生まれたのか、ずっと疑問に思っていた。
人間が言葉をもったとき?
そりゃそうだろうけど、それはいつだ?
そういう疑問に答えてくれたのが、神話学者の吉田敦彦氏だ。
(僕はまず、神話学者という人たちがいるのに驚いた。
しかし、神話学者は世界各地で、それぞれの神話を研究している。)
吉田氏が言うには、神話というのはいまから3万5000年くらい前、
ネアンデルタール人に代わってクロマニョン人が地球上に登場したときに
生まれたそうだ。
ネアンデルタール人は学名をホモ・サピエンスという。
これは「考える力を持っているヒト」という意味。
クロマニョン人の学名はホモ・サピエンス・サピエンス、
「優れて考える力を持っているヒト」という意味。
クロマニョン人は現在の僕たち人類の祖先だが、
「優れて」考える力があった。
「考える」という行為には、「好奇心」「疑問」「想像」というワードも含まれる。
太古のクロマニョン人がそういうものを持っていたとすると、
当然そこには神話が芽生えたに違いない。
なんたって、不思議だろう。月が満ち欠けすること。
赤く大きな月が出たかと思えば、細く鋭利な銀色の三日月。
(といっても、3万5000年前に月があったとしての話だが。)
太古の人々は地球の自転とか、惑星とか、そういう理屈をまったく知らないのだ。
そもそも地球が円いなんて思うはずもない。
大地はどこまでも真っ平らなんだから。
何日も降り続いた雨の後に太陽が顔を出す。
どんなに歓喜に満ちた気持ちで陽の光を見ただろうか?
彼らは狩猟によって生きていた。
獲物がたくさん獲れれば飢えることもない。
獲物が獲れなければ死は隣あわせである。
太古の人々にとって、きっと大いなるものへの畏怖、
畏敬の念が自分の存在よりも膨らんでいただろう。
その大いなるものとは自然。
クロマニョン人たちが生きた後期旧石器文化の時代に、
かれらが畏怖したのは大地母神だった。
母なる大地こそは、自分たちも動物も植物もはぐくんでくれる大いなるもの。
だから、ひたすら畏怖し崇拝し、祈った。
クロマニョン人たちは、その畏怖する気持ちを表現するために、
乳房と腰とお腹と臀部を極端に強調した独特の形の
「先史時代のヴィーナス像」を石灰石やマンモスの牙などでつくった。
また、洞窟に獲物であるサイや野牛、馬、マンモスなどの絵を描き、
数多くの洞窟画を残している。
吉田氏は「ヴィーナス像は、彼らが尊崇していた母神の姿を表した
神像の意味を持っていたに違いない」という。
また、洞窟は大地母神の子宮。
母なる大地の子宮から、人間も獲物となる動物も、
全てが生み出されるという信仰の表現が、
南フランスなどヨーロッパ各地に残された洞窟画だそうだ。
洞窟画の中には、入り口から迷路のような狭い穴をたどっていった先の、
やっと行きついた広間のような場所に動物の絵が描かれていたりする。
その狭い穴というのが、産道を意味するものらしい。
吉田氏が本の中で1929年にそういう地中の洞窟の一つ、
トロア・フレール洞窟を探査した先史学者キューンの述懐を紹介している。
こんな話だ。
「…広く折れ曲がった廊下を過ぎると、その先はとても細い坑道になっていた。
……その坑道の幅は、わたしの肩幅とほとんど変わらず、高さもそれと同じくらいだった。
……そこを通り抜けるためには、両腕を脇腹にぴったり密着させて、腹ばいになり、
蛇のように身をくねらせて進まねばならなかった。
この通路の高さは、ところどころでかろうじて1フィート(30センチあまり)ほどしかなく、
通るには顔を地面に密着せねばならなかった。
まるで棺の中を這っているような気がした。頭を上げることもできず、呼吸することすら難しかった。
そのあとで穴の高さがいくらか増大し、前腕部で身体を支えられるようになった。
だがそれも長く続かず、通路はじきにまた狭くなった。
……頭のこれほど近くに天井があるということは、本当に恐ろしい。
それはまたきわめて困難なことであり、そのせいでわたしは何度も頭を強くぶつけた。
この苦労には終わりがけっしてないのではないかと思えたとき、
とつぜんその坑道をすっかり通り抜けていた。」
そんな苦労をして通り抜けた先の、光もささない地中で、
どうやって絵を描いたのか、疑問が膨らんでしまうが、
ともかく太古の絵が現実に残されているからには、
そうすることが可能だったに違いない。
どれほど大変なことだったろう?
きっとその大変さは、僕たちの想像を遥かにしのぐのではないだろうか。
それでも、日常の生活とは違う時間を使って、
表現することに多大な労力を注いだ。
その行為には信仰という意味づけがあっただろうし、
意味づけがあるところには物語が生まれる。
だから物語は、神話という形で始まった。
神話とは祈りの対象を神格化したときに生まれる物語だ。
不安を払拭し、生きつづけるための祈り。
太古のクロマニョン人は3万5000年も前、
気の遠くなるような、想像もつかない昔に、物語ることを始めたのである。
吉田氏はあるインタビューに答えて、このように語っている。
「そもそも人間は、いつの時代どの時代でも、
物事がどうやって始まったのか、なぜ存在するのか、
どういう仕組みなのか、神話によって説明してきました。
社会システムから死生観、自分たちの行動、物の起源、価値、
社会のアイデンティティーまでも、神話で説明しています。」
「人間の生き方は、反自然的です。集団ごとに異なる文化が形成されており、
自分の文化の中で当たり前なことが他からは野蛮に見えたりします。
ですから、その文化で行われている一つひとつの習俗、システム、
その文化が持っている価値観などをきちんと説明、定義しておかないと、
自分の行動に迷い、ためらいが生じてしまいます。
そうなると文化は解体してしまいますからね。
…神話のない文化はあり得ない、
つまり人間は、神話がなくては生きられないといってよいでしょう。」
(アットホーム株式会社大学教授対談シリーズ/
機関紙『at home time』2000年10月号より)
そう言えば、上橋菜穂子さんも著書『精霊の守り人』の中で
年老いた女呪術師にこんなことを言わせている。
「わしは、よその国の神話だからといって、それを頭から馬鹿にするほど、
馬鹿じゃない。どこの国の人でも、みな、気が遠くなるほど長い年月をかけて、
この世のほんとうの姿となりたちを知ろうとしてきた」
物語は「気が遠くなるほど長い年月をかけて」語り継がれてきた。
物語なしに、人は生きてはいけないのだろうと、僕は思う。
<参考文献>
*『探求するファンタジー──神話からメアリー・ポピンズまで』(成蹊大学文学部学会/風間書房)・第一章「神話とファンタジーの始まり」(吉田敦彦)
この本は成蹊大学で2008年と2009年の後期に行われた「歴史に学ぶ(神話と中世のファンタジー)」の講義をまとめたもの。
*『神話のはなし』(吉田敦彦著/青土社)
★おまけ
思い出したのはアメリカの作家ジーン・アウルの
『大地の子エイラ』のシリーズ。
新訳を出している出版社によると、29カ国で翻訳され、
全世界で3500万部が出ているヒットシリーズなのだそうである。
3万5000年前、クロマニョン人の少女が、ネアンデルタールの一族に
拾われるところから始まる、太古を舞台にした壮大な物語。
この物語も、あり得ることかもしれないと、現実味を帯びてくる。
【見つけたこと】物語は「意味づけ」である。
───────────────────────
レディバードが言ったこと
───────────────────────
「ということはさ、きみが言う“物語の島”は、
3万5000年よりもずっと後にできたんだろうね」
と僕はレディバードに聞いた。
(レディバードは物語の島の住人。レディバードによると、
亡くなった僕の姉は物語の島にいる。その姉に遣わされて、
僕のところに姿を現すのだという話だ。)
レディバードは、曖昧な笑みを浮かべてこう言った。
「その考え方は、そもそも違うかもね。
物語の島には『時間』はないんだから。
あなたたち人間の難題は、『時間の流れから逃れられない』ことと、
『自分の意識の中から外に出られない』ということでしょ?
物語の島には、『時間』の枠組みはないわ。
つまり、3万5000年前と計ることはできないってわけ」
「ふうん。不老不死ってこと?」
「だから、不老不死という考えが、そもそも時間の枠組みをもとにしてるでしょ。
不老不死も何も、時間の枠組みがないということは、ただそこにあるということなの」
「じゃあ、物が生まれたり、滅びたりもしない?」
「だから、生まれたと物語られたら、生まれる。
死んだと物語られたら、死ぬ。
だけど、そこにあるのは、『生まれる』ということ、『死ぬ』ということ。
始まりでも終わりでもなく、語られるままに、そこにあるのよ。
生まれる前からそこにあり、死んでもそこにある。
悪もそこにあり、善もそこにある。
喜びも悲しみも、すべての思いがそこにある。
そういうところなの」
レディバードは、巫女のように見えないものを見据え、
体を微妙に揺すりながら、こう話した。
3万5000年という、気の遠くなるような時の流れのことを思うと、
レディバードの言うことも、あながちウソに聞こえない。
つまり、こういうことだろうか…。
人々は物語を語らずにはいられなかった。
自分の存在を物語に託すことで、
「時間」や「個という意識」の枠組みをはずそうとした。
もし、それが成功したとして、「個」である肉体は滅びてしまう。
それでも、物語が残るなら、それはそれでいい。
そういう葛藤の中で、物語は語り継がれてきたのかもしれない。
レディバードが鈴のような声で、美しくはあっても、
聞いたことのないようなメロディを口ずさみ始めた。
僕は時のパノラマを見るような不思議な感覚に満たされ、黙り込んだ。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
メルマガ配信しています。購読料は無料。
ご登録はこちらへ。

↑「『赤毛のアン』のキーワードBOOK」をご希望の方は
marupippo1222@gmail.com までお申し込みください。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆