派遣先の宿舎でDVDをみる。
元ナチス戦犯であるクラウス・バルビーがなぜ長年裁かれることなく自由の身でいられたのか?
ドキュメンタリー映画「敵こそ、わが友」は、大変興味深い映画だ。
ナチスが人民の最大の敵であった第二次大戦が終わり、東西冷戦期に入ると、かつての連合国、ソ連が西側諸国の仮想敵国となった。この列強パワーゲームの緊張関係のなかにナチスの残党が暗躍する隙間が生まれた。
反共という旗印のもとに、西側諸国はひそかにナチスの残党と手を組み、ナチスが培ってきたさまざまなノウハウを生かして、共産勢力の掃討作戦を開始する。彼らに対する拷問や暗殺の遂行をはじめとし、挙句の果てには、南米にナチスまがいの極右軍事政権を誕生させたりもした。
ヨーロッパのナチス狩りから逃れ南米に渡ったクラウス・バルビーも、CIAに対して左翼ゲリラ弾圧のためのさまざま手法を伝授し、彼らの反共政策推進に協力した。また、その見返りとしてアメリカ政府からの手厚い保護を受けた。コロンビアでチェゲバラの暗殺を指揮したのも、クラウス・バルビーだったというから驚きだ。
まさに「敵の敵は味方」なのであり、この映画のタイトルが「敵こそ、わが友」である理由もそこにある。
しかし、この映画の真骨頂はさらにその先にある。
バルビーはいかにして捕らえられ、そして、いかにして裁かれたか?
この顛末が皮肉に満ちていて非常に興味深いのだ。
散々CIAに協力したバルビーは、やがて、強まる世論の批判をかわすためにCIAと、かつてナチス占領時代にバルビーが権力を振るったフランス政府の手によってリヨンに移送され裁判にかけられる。人民裁判さながらの法廷でバルビーに対する怒号が続く。バルビーが巨悪としてつるし上げられるなか、バルビーを利用しつくした西側の国々はまんまと雲隠れに成功する。
この映画を観終わったあと、かつて宮台真司が書いた、「砕け散った瓦礫の政治性」という文章を思い出した。
世界に掃いて捨てるほど転がっているさまざまな不条理。
正直者が馬鹿を見、弱き者が踏みにじられ、心優しき者が虐げられ、狡猾な者が大手を振って闊歩する世界。まさに不条理の極みである。
ところが、正義が達成されることを心待ちにしながら、幾多の不条理に翻弄されているうちに、我々は、やがて半ば諦念のうちに「〈世界〉は確かにそうなっているのだな」という事実に思い至るのだ。宮台の言葉を借りるなら「そもそも世界はデタラメ」だという現実に気がつくのである。
松岡正剛は「フラジャイル」という著書のなかで、世界に存在する民話や昔話の類には不条理極まりない話が非常に多いと指摘している。これは、そもそも、世界なんてはじめからデタラメだという事実を説いているにすぎないのだという。
不条理なものに接したとき、われわれは、諦めとも、悲しみとも、怒りともつかぬ感覚に取り憑かれることがある。昔の人はこの感覚を「もののあはれ」とよんだ。
クラウス・バルビーに強く“もののあはれ”を感じ取ったのは僕だけであろうか?
元ナチス戦犯であるクラウス・バルビーがなぜ長年裁かれることなく自由の身でいられたのか?
ドキュメンタリー映画「敵こそ、わが友」は、大変興味深い映画だ。
ナチスが人民の最大の敵であった第二次大戦が終わり、東西冷戦期に入ると、かつての連合国、ソ連が西側諸国の仮想敵国となった。この列強パワーゲームの緊張関係のなかにナチスの残党が暗躍する隙間が生まれた。
反共という旗印のもとに、西側諸国はひそかにナチスの残党と手を組み、ナチスが培ってきたさまざまなノウハウを生かして、共産勢力の掃討作戦を開始する。彼らに対する拷問や暗殺の遂行をはじめとし、挙句の果てには、南米にナチスまがいの極右軍事政権を誕生させたりもした。
ヨーロッパのナチス狩りから逃れ南米に渡ったクラウス・バルビーも、CIAに対して左翼ゲリラ弾圧のためのさまざま手法を伝授し、彼らの反共政策推進に協力した。また、その見返りとしてアメリカ政府からの手厚い保護を受けた。コロンビアでチェゲバラの暗殺を指揮したのも、クラウス・バルビーだったというから驚きだ。
まさに「敵の敵は味方」なのであり、この映画のタイトルが「敵こそ、わが友」である理由もそこにある。
しかし、この映画の真骨頂はさらにその先にある。
バルビーはいかにして捕らえられ、そして、いかにして裁かれたか?
この顛末が皮肉に満ちていて非常に興味深いのだ。
散々CIAに協力したバルビーは、やがて、強まる世論の批判をかわすためにCIAと、かつてナチス占領時代にバルビーが権力を振るったフランス政府の手によってリヨンに移送され裁判にかけられる。人民裁判さながらの法廷でバルビーに対する怒号が続く。バルビーが巨悪としてつるし上げられるなか、バルビーを利用しつくした西側の国々はまんまと雲隠れに成功する。
この映画を観終わったあと、かつて宮台真司が書いた、「砕け散った瓦礫の政治性」という文章を思い出した。
世界に掃いて捨てるほど転がっているさまざまな不条理。
正直者が馬鹿を見、弱き者が踏みにじられ、心優しき者が虐げられ、狡猾な者が大手を振って闊歩する世界。まさに不条理の極みである。
ところが、正義が達成されることを心待ちにしながら、幾多の不条理に翻弄されているうちに、我々は、やがて半ば諦念のうちに「〈世界〉は確かにそうなっているのだな」という事実に思い至るのだ。宮台の言葉を借りるなら「そもそも世界はデタラメ」だという現実に気がつくのである。
松岡正剛は「フラジャイル」という著書のなかで、世界に存在する民話や昔話の類には不条理極まりない話が非常に多いと指摘している。これは、そもそも、世界なんてはじめからデタラメだという事実を説いているにすぎないのだという。
不条理なものに接したとき、われわれは、諦めとも、悲しみとも、怒りともつかぬ感覚に取り憑かれることがある。昔の人はこの感覚を「もののあはれ」とよんだ。
クラウス・バルビーに強く“もののあはれ”を感じ取ったのは僕だけであろうか?















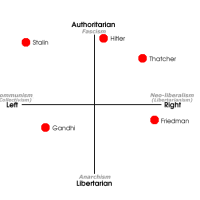
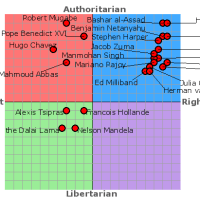
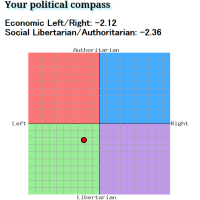
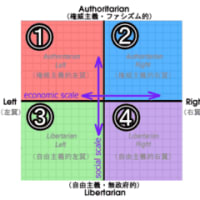






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます