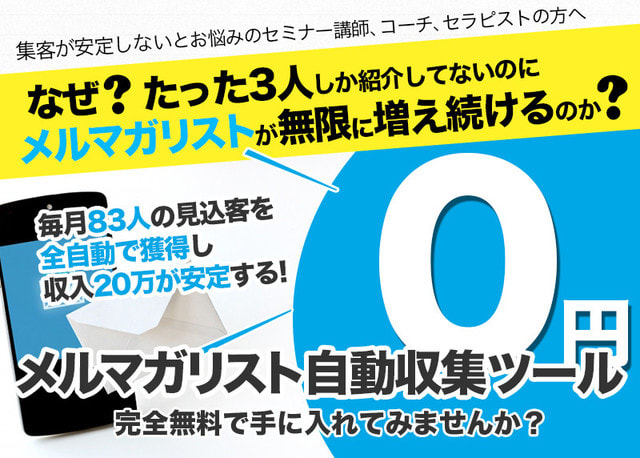Youtube版もご覧くださいませm(__)m
男の動画をどうぞ!

かつて地球上には「干し首」を作る部族や集落が数多く存在していたとされている。干し首は装飾用に加工された人間の頭部である。
だが、記録に残っているのは極めて限られたごく僅かな部族のみで、エクアドルやペルーなど、南アメリカのヒバロー族やシュアール族の干し首「ツァンツァ」が知られている。
当時干し首は、敵を打ち取った強さの象徴や部族内でのランクを示すだけではなく、敵を恐怖させる意味でも非常に有効な手段だったのだ。
19世紀にヨーロッパの探検家が記録した干し首に関する記録によれば、干し首には作る上で3つの重要な段階が存在するという。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
一般的なユダヤ人は平均18歳で経済的な自由を達成し、働かなくても生活することができます。
一方、一般的な日本人の老後は貧困か破産です。
この違いがもたらされる恐るべき秘密が暴露されています。
詳しくは説明文を確認してください。
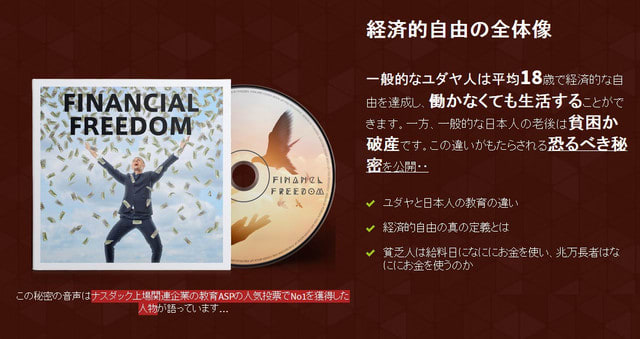
↑ クリックしてね m(__)m
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
敵を倒した後、まず行うのは頭皮や顔全体を剥ぎ取る作業だ。
戦場の近くにキャンプを設営し、そこで戦士たちは打ち首にした敵の首の後ろから耳に沿って皮に切り込みを入れる。
次に切り込みを入れた場所から頭のてっぺん、そして顔に至るまでの頭皮部分を剥いでいく。そこから木材かナイフを使い顔面の皮膚を丁寧にそぎ落とし、耳や鼻の余分な軟骨なども剥ぎ取っていくという。
最後に瞼(まぶた)に糸を通して目を閉じさせ、唇を木製の棒で固定する。この棒は後に糸を通すための穴になるそうだ。
頭から皮膚が完全に剥ぎ取られたら、今度はツァンツァ(干し首)を茹でる。
およそ1時間から2時間ほど茹でるという。この段階は時間との勝負であり、2時間をこえると頭皮から髪の毛が抜け始めるため、注意が必要だそうだ。
鍋からあげるとツァンツァは熱湯に茹でられたことで元の3分の1ほどの大きさになっているという。その後、ツァンツァは裏返しにされ余分な筋肉・脂肪・軟骨などをそぎ落とされる。
最後に最初に入れた切り込みを糸で縫い直して2段階目の作業は終了する。
最後のステップはツァンツァを更に小型化する方法だ。
この段階ではまず熱々の石が大量に使われ、限界ギリギリまでツァンツァの中に石が流し込まれる。石が一つも入らない状態になったら、今度は熱々の砂を流し込まれる。
この工程は常に熱い焚火の上で行われ、皮膚の変色を防ぐことが肝心だそうだ。
その後、余分な髪の毛をむしり取り、唇を熱したマチェットで焼く。更に硬く、黒くするために火にかけ、唇を3本の糸でふさぐ。
頭部にビーズ、鳥の羽毛、甲虫類の鞘翅などで装飾する場合もある。

干し首一つを作るのにおよそ一週間はかかるそうだ。
お披露目の時は頭のてっぺんから糸を通して数珠繋ぎにする事で戦士としての強さを表すのだという。敵の顔の造形をいかにリアルに残すかがヒバロ族の芸術的センスだったようだ。

干し首の製作には宗教的な意義もあったという。干し首は敵の霊魂を束縛することで、制作者への奉仕を強制するものであると信じられていたという。
ヒバロー族は以下の三つの根本的な霊魂の存在を信じていた。
ヨーロッパ人との交易用に非宗教的な干し首も作られたが、宗教的な干し首と非宗教的な干し首とは明確に区別されていたそうだ。
☆インドの事件を考えると、今もあるかもしれんなぁ!
まずは、資料請求をどうぞ (^O^)
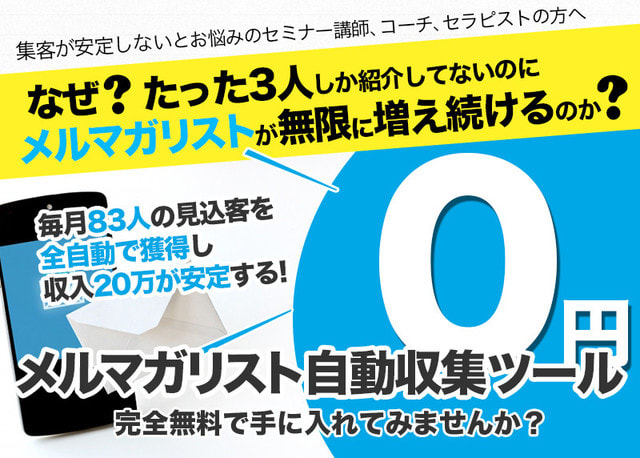
男の動画をどうぞ!

かつて地球上には「干し首」を作る部族や集落が数多く存在していたとされている。干し首は装飾用に加工された人間の頭部である。
だが、記録に残っているのは極めて限られたごく僅かな部族のみで、エクアドルやペルーなど、南アメリカのヒバロー族やシュアール族の干し首「ツァンツァ」が知られている。
当時干し首は、敵を打ち取った強さの象徴や部族内でのランクを示すだけではなく、敵を恐怖させる意味でも非常に有効な手段だったのだ。
19世紀にヨーロッパの探検家が記録した干し首に関する記録によれば、干し首には作る上で3つの重要な段階が存在するという。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
一般的なユダヤ人は平均18歳で経済的な自由を達成し、働かなくても生活することができます。
一方、一般的な日本人の老後は貧困か破産です。
この違いがもたらされる恐るべき秘密が暴露されています。
詳しくは説明文を確認してください。
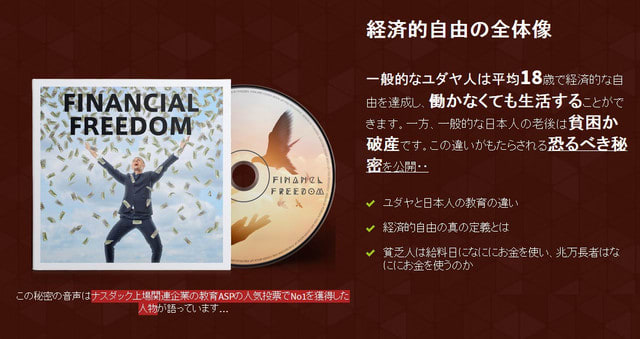
↑ クリックしてね m(__)m
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
ステップ1:頭の皮を剥ぎ取る
敵を倒した後、まず行うのは頭皮や顔全体を剥ぎ取る作業だ。
戦場の近くにキャンプを設営し、そこで戦士たちは打ち首にした敵の首の後ろから耳に沿って皮に切り込みを入れる。
次に切り込みを入れた場所から頭のてっぺん、そして顔に至るまでの頭皮部分を剥いでいく。そこから木材かナイフを使い顔面の皮膚を丁寧にそぎ落とし、耳や鼻の余分な軟骨なども剥ぎ取っていくという。
最後に瞼(まぶた)に糸を通して目を閉じさせ、唇を木製の棒で固定する。この棒は後に糸を通すための穴になるそうだ。
ステップ2:茹でる
頭から皮膚が完全に剥ぎ取られたら、今度はツァンツァ(干し首)を茹でる。
およそ1時間から2時間ほど茹でるという。この段階は時間との勝負であり、2時間をこえると頭皮から髪の毛が抜け始めるため、注意が必要だそうだ。
鍋からあげるとツァンツァは熱湯に茹でられたことで元の3分の1ほどの大きさになっているという。その後、ツァンツァは裏返しにされ余分な筋肉・脂肪・軟骨などをそぎ落とされる。
最後に最初に入れた切り込みを糸で縫い直して2段階目の作業は終了する。
ステップ3:石や砂を流し込む
最後のステップはツァンツァを更に小型化する方法だ。
この段階ではまず熱々の石が大量に使われ、限界ギリギリまでツァンツァの中に石が流し込まれる。石が一つも入らない状態になったら、今度は熱々の砂を流し込まれる。
この工程は常に熱い焚火の上で行われ、皮膚の変色を防ぐことが肝心だそうだ。
その後、余分な髪の毛をむしり取り、唇を熱したマチェットで焼く。更に硬く、黒くするために火にかけ、唇を3本の糸でふさぐ。
頭部にビーズ、鳥の羽毛、甲虫類の鞘翅などで装飾する場合もある。

image credit:Narayan k28/wikimedia
干し首一つを作るのにおよそ一週間はかかるそうだ。
お披露目の時は頭のてっぺんから糸を通して数珠繋ぎにする事で戦士としての強さを表すのだという。敵の顔の造形をいかにリアルに残すかがヒバロ族の芸術的センスだったようだ。

image credit: Jmabel/wikimedia
干し首の宗教的意味合い
干し首の製作には宗教的な意義もあったという。干し首は敵の霊魂を束縛することで、制作者への奉仕を強制するものであると信じられていたという。
ヒバロー族は以下の三つの根本的な霊魂の存在を信じていた。
ワカニ - 死後も蒸気となって存続する、人間固有の霊
アルタム - 「幻影」あるいは「力」の意味。非業の死から人間を保護し、その生存を保障する霊
ムシアク - アルタムによって守られていた人間が殺害された時に現れる、復讐の霊
ヨーロッパ人との交易用に非宗教的な干し首も作られたが、宗教的な干し首と非宗教的な干し首とは明確に区別されていたそうだ。
☆インドの事件を考えると、今もあるかもしれんなぁ!
まずは、資料請求をどうぞ (^O^)