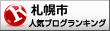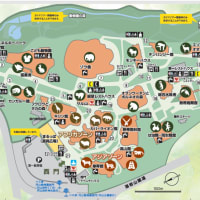カステラ
カステラ
大河ドラマ「龍馬伝」で海援隊の一員である、要潤演じる沢村惣之丞が泡だて器を持って
カステラ作りをしているシーンが確かあったと思います。
へぇー、カステラ作りをしていたのかぁと思い、記憶に残っています。
その後、現在のカステラのように洗練されたものを作ることに成功したのか気になっていたのですが、
「横須賀本」を見たら、なんと海援隊のレシピを再現して作ったお店があることを知り、
ものすごく食べてみたくて買いに行きました。
「御菓子司 精栄軒 本店」。
西叶神社のそばにある和菓子屋さんです。
名は「おりょうと竜馬の愛したかすていら」です。
なんと横須賀市は坂本竜馬の妻、おりょうさんが最後に住んだ街でお墓もあります。
日本最初の新婚旅行と言われている薩摩旅行で、
海援隊が作ったカステラをおりょうさんは食べたと言われています。
興味津々でいただきました。
私たちが普段いただいているカステラとはちょっと食感が異なります。
しかし、思っていたよりしっとりしていて、ちょっと弾力があり、
黒糖の味・香りが口の中豊かに広がって、はっきり言っておいしいです。
これならきっと、おりょうさん、喜んで食べたのではないでしょうか。
ちょっと多めに買って正解でした。
こちらもまた、浦賀散策の良いお土産になると思います。
1つ税抜180円也。
 ウォーキングマップ
ウォーキングマップ
「京急線で行く旅(2) 浦賀・燈明堂への旅 その1」にて参照のこと。
 ウォーキングスタート
ウォーキングスタート
7.愛宕山公園
東福寺を出た後、道を間違えてしまい、愛宕山公園に立ち寄ったのは日も暮れる頃。
なんとかギリギリ写真撮影可能な明るさでした。
(地図を持ってても間違えるのよねえ。涙)



三浦半島ではお決まりの階段をはぁはぁ言いながら上るとまず最初に見る碑が「咸臨丸出港の碑」です。
(実はもう1つあるのですが、何の碑なのか分かりませんでした。)

昭和35年(1960)に日米修好通商条約締結100年を記念して建てられました。
咸臨丸は日本で初めて太平洋を横断した軍艦ですが、その前に浦賀で塗装や修理が行われました。
この碑の裏には勝海舟や福沢諭吉ら乗組員の名が刻まれているそうなのでチェックしてみてください。
(私は疲れ果てて、できませんでした。)
さらに息を切らして階段を上ると与謝野夫妻の文学碑があります。

昭和10年(1935)に日帰り旅行で夫妻が浦賀を訪れた時に詠んだ歌が刻まれています。
文学碑のそばにはもう1つ大きな石碑があります。「中島三郎助の招魂碑」です。

浦賀の地と人をこよなく愛した中島三郎助の死を惜しんだ中島三郎助と生前深く関わりのあった人や、
地元の人達の手によって建てられました。
愛宕山公園そのものも、この碑を建てるために造られたもの。
中島三郎助への敬愛が強く伝わってきます。
この街歩きの最後に足を運ぶ「浦賀ドック」はこの碑の除幕式の時に、
三郎助の業績がある造船を浦賀でやろうという提案があって設立されました。
こうして見てみると、浦賀はペリーよりも中島三郎助の街と言った方が良いような気がします。
8.為朝神社
実は西浦賀に2回、足を運んでおります。
というのも、このシリーズの初回で紹介した資料2つで作ったコースでは、
1つ大事な「鏝絵」を見逃してしまうことが分かったからです。
やはり「三浦の善吉」の作品はちゃんと見ておかなければなりません。
という訳で「為朝神社」に立ち寄ることにしました。


創建 : 文政期(1820年代)
祭神 : 源為朝
源為朝は源頼朝の叔父で強弓で知られ、後に疱瘡除けの神様となったことから、
こちらの神社は航海及びほうそう除けにご利益があるということで信仰を集めました。
また、毎年6月に奉納されるという「虎踊り」は県の民俗文化財に指定されています。
このシリーズの初回で紹介した大平堂のおまんじゅう「虎おどり」はこちらをイメージして作られたものだったのですね。
伊豆下田から伝えられたという「虎踊り」。
見てみたいです。
 お世話になった資料
お世話になった資料
-
横須賀美術館てづくりおさんぽマップ
-
別冊歴史読本54「横須賀歴史読本」
-
「歴史のまち・浦賀 散策の手引き」、「浦賀奉行所と与力・中島三郎助」
(いずれも浦賀コミュニティセンター分館でいただいたもの) -
エイムック3103「横須賀本」
このシリーズ、長期化しそうです。(汗)
次回につづく≫