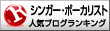今の僕の“ジャズ感”です。
こういう風に思っているのは僕だけかもしれないし、人に強要するつもりもないし、僕と違う価値観の人をリスペクトしますので、あしからずご了承下さい。
長いので、数回に分けて書こうと思っています。
今回は第1回目です。
=古典(1)=

よくお客さんやアマチュアのミュージシャンの方に、
「川島さんは上原ひろみさんをどう思われますか?」
と聴かれるんですね。
で、
「いやー、全然聴いていないんで、何ともお答えできません。でもよくその質問を聴くので、きっとすごい人なんでしょうね」
といつも返事します。ほとんどの場合、質問された方は意外そうな顔をして
「プロで活動されている川島さんが、最新のジャズを聴かないんですか?」
と返される。
「すみません、別に上原さんに限らず、最近のジャズの新譜はほとんど聴かないんです。というか、CDを聴くのならば、過去のジャズの中で聴きたくても聴いてないCDが山ほどあるので、そちらから聴きます。」
と答える様にしています。
もし、僕がCD会社やCD販売店のジャズ担当であれば、当然上原ひろみさんの新譜は聴いていなくてはならないと思いますが、僕はどちらかというと、というかどちらかと言わなくても、格は違えど同じプレイヤーなので、“自分の音楽”を追求したいわけですよ。流行は追いたくないかなぁ~と。
で、僕にとってはジャズというのは、1950年代のハードバップの事を指すんですね。この辺のジャズは『紛れもない』ジャズなんです。で、それは多分、1959年、マイルス・デイビスの出した1枚のアルバム『カインド・オブ・ブルー』でその進化を終えたのではないか…と、思っているんです。
で、もちろんその後も“ジャズとカテゴライズされる音楽”は進化を遂げて、最近では、ノーベル物理学賞でも取れそうなくらい、細かくて、数学的で、現代音楽の様にインテリっぽい音楽になっているのではないかと思います。
進化しないんじゃ、向上心が無いのでは?
と言われるかもしれません。
しかし、僕の興味は、“進化”という意味では、1959年からはソウル音楽の方に向いているのです。
文字でどれだけ伝わるか分かりませんが、『音楽の進化』という意味では、1959年を境に“僕の好きなジャズ”は“ソウル”に名前を変えるんですね。で、本家の“ジャズとカテゴライズされる音楽”の方は、“エンターテイメント”であることを放棄し、“芸術”になっていく訳です。
もちろん言うまでも無いですが、1959年以降に録音されたジャズ・アルバムの中にも好きなアルバムは山ほどあります。しかしそれは“進化”という意味では1959年以前のスタイルの音楽を演奏している訳です。
そういう風にいうと、
「“進化”していないからダメじゃん」
という風に言う方も多いでしょう。
でも、進化はしていませんが“深化している”と思うんです。
ウイスキーとかワインとか、古いほど良いとされるじゃないですか?
それは樽の中で熟成していくからなんです。
ビ・バップやハード・バップを熟成させて演奏するプレイヤーの演奏は、例えばそのプレイヤーの若かったころと比べると、演奏に余裕があるのか、吹きまくっていたプレイヤーも、吹いていない“間”というものを大事にしだすようになったりするわけです。
その点、進化している“ジャズとカテゴライズされる音楽”は、いつの時代も余裕というものが演奏からは感じられず、混沌とした演奏が続きます。前に進まなければならないから、余裕なんて無いんでしょうね。
例えば、ジョン・コルトレーンの1960年代の一連の作品は、『バラード』というアルバムを除くと、常にメンバー全員がff(フォルテッシモ)で演奏を続けており、例えば仕事から疲れて帰って来た時にはあまり聴きたくない演奏ですね。特に、ヴィレッジ・バンガードのライブ盤なんて…。
あ、ただこれは僕だけかもしれませんが、疲れがピークに達したときに、ヴィレッジ・バンガードのライブ盤をヘッドフォンで超大音量で聴くと、ちょっとあちら側にトリップ出来ますね。なんというか、東南アジアのどこかの国の民族音楽を聴いているような、軽いトランスを感じます。
ただ、僕にとっては“いつも聴いていたい”演奏ではないです。
(続く)
という事で、本文とは関係ないですが、本日は、曙橋『フィルイン』に出演します。
崎井蓮歌(vo)さんとの初共演になります。楽しみです。
 new 2014年10月のスケジュール
new 2014年10月のスケジュール
 new プロデュース・ライブ 浅草『SHIZUKAⅡ』
new プロデュース・ライブ 浅草『SHIZUKAⅡ』
 new プロデュース・ライブ 森下『DUMBO2』
new プロデュース・ライブ 森下『DUMBO2』
 12月19日(金) 20:00~ Marie-Style クリスマス・ライブのお知らせ!
12月19日(金) 20:00~ Marie-Style クリスマス・ライブのお知らせ!

 new 新・川島茂ホームページ
new 新・川島茂ホームページ
 Marie-Style2ndアルバム『heartiness』大好評発売中!
Marie-Style2ndアルバム『heartiness』大好評発売中!
 東日本大震災、寄付活動のご報告
東日本大震災、寄付活動のご報告
こういう風に思っているのは僕だけかもしれないし、人に強要するつもりもないし、僕と違う価値観の人をリスペクトしますので、あしからずご了承下さい。
長いので、数回に分けて書こうと思っています。
今回は第1回目です。
=古典(1)=

よくお客さんやアマチュアのミュージシャンの方に、
「川島さんは上原ひろみさんをどう思われますか?」
と聴かれるんですね。
で、
「いやー、全然聴いていないんで、何ともお答えできません。でもよくその質問を聴くので、きっとすごい人なんでしょうね」
といつも返事します。ほとんどの場合、質問された方は意外そうな顔をして
「プロで活動されている川島さんが、最新のジャズを聴かないんですか?」
と返される。
「すみません、別に上原さんに限らず、最近のジャズの新譜はほとんど聴かないんです。というか、CDを聴くのならば、過去のジャズの中で聴きたくても聴いてないCDが山ほどあるので、そちらから聴きます。」
と答える様にしています。
もし、僕がCD会社やCD販売店のジャズ担当であれば、当然上原ひろみさんの新譜は聴いていなくてはならないと思いますが、僕はどちらかというと、というかどちらかと言わなくても、格は違えど同じプレイヤーなので、“自分の音楽”を追求したいわけですよ。流行は追いたくないかなぁ~と。
で、僕にとってはジャズというのは、1950年代のハードバップの事を指すんですね。この辺のジャズは『紛れもない』ジャズなんです。で、それは多分、1959年、マイルス・デイビスの出した1枚のアルバム『カインド・オブ・ブルー』でその進化を終えたのではないか…と、思っているんです。
で、もちろんその後も“ジャズとカテゴライズされる音楽”は進化を遂げて、最近では、ノーベル物理学賞でも取れそうなくらい、細かくて、数学的で、現代音楽の様にインテリっぽい音楽になっているのではないかと思います。
進化しないんじゃ、向上心が無いのでは?
と言われるかもしれません。
しかし、僕の興味は、“進化”という意味では、1959年からはソウル音楽の方に向いているのです。
文字でどれだけ伝わるか分かりませんが、『音楽の進化』という意味では、1959年を境に“僕の好きなジャズ”は“ソウル”に名前を変えるんですね。で、本家の“ジャズとカテゴライズされる音楽”の方は、“エンターテイメント”であることを放棄し、“芸術”になっていく訳です。
もちろん言うまでも無いですが、1959年以降に録音されたジャズ・アルバムの中にも好きなアルバムは山ほどあります。しかしそれは“進化”という意味では1959年以前のスタイルの音楽を演奏している訳です。
そういう風にいうと、
「“進化”していないからダメじゃん」
という風に言う方も多いでしょう。
でも、進化はしていませんが“深化している”と思うんです。
ウイスキーとかワインとか、古いほど良いとされるじゃないですか?
それは樽の中で熟成していくからなんです。
ビ・バップやハード・バップを熟成させて演奏するプレイヤーの演奏は、例えばそのプレイヤーの若かったころと比べると、演奏に余裕があるのか、吹きまくっていたプレイヤーも、吹いていない“間”というものを大事にしだすようになったりするわけです。
その点、進化している“ジャズとカテゴライズされる音楽”は、いつの時代も余裕というものが演奏からは感じられず、混沌とした演奏が続きます。前に進まなければならないから、余裕なんて無いんでしょうね。
例えば、ジョン・コルトレーンの1960年代の一連の作品は、『バラード』というアルバムを除くと、常にメンバー全員がff(フォルテッシモ)で演奏を続けており、例えば仕事から疲れて帰って来た時にはあまり聴きたくない演奏ですね。特に、ヴィレッジ・バンガードのライブ盤なんて…。
あ、ただこれは僕だけかもしれませんが、疲れがピークに達したときに、ヴィレッジ・バンガードのライブ盤をヘッドフォンで超大音量で聴くと、ちょっとあちら側にトリップ出来ますね。なんというか、東南アジアのどこかの国の民族音楽を聴いているような、軽いトランスを感じます。
ただ、僕にとっては“いつも聴いていたい”演奏ではないです。
(続く)
という事で、本文とは関係ないですが、本日は、曙橋『フィルイン』に出演します。
崎井蓮歌(vo)さんとの初共演になります。楽しみです。
 new 2014年10月のスケジュール
new 2014年10月のスケジュール new プロデュース・ライブ 浅草『SHIZUKAⅡ』
new プロデュース・ライブ 浅草『SHIZUKAⅡ』 new プロデュース・ライブ 森下『DUMBO2』
new プロデュース・ライブ 森下『DUMBO2』 12月19日(金) 20:00~ Marie-Style クリスマス・ライブのお知らせ!
12月19日(金) 20:00~ Marie-Style クリスマス・ライブのお知らせ!
 new 新・川島茂ホームページ
new 新・川島茂ホームページ Marie-Style2ndアルバム『heartiness』大好評発売中!
Marie-Style2ndアルバム『heartiness』大好評発売中! 東日本大震災、寄付活動のご報告
東日本大震災、寄付活動のご報告