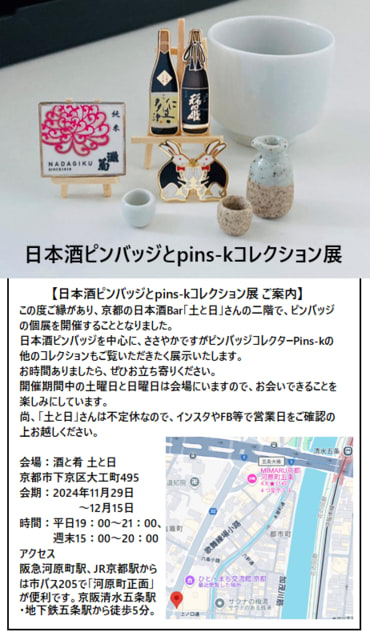『お酒の地理的表示(GI)を知っていますか?』

ようやく確定申告を済ませ、年に一度の面倒な税務署さんとのお付き合いが終わったところだったので「え!」と思ったのですが、実は日本において、酒類行政を管轄しているのは国税庁なんですね。
かつて、日清日露戦争は日本の酒税で行ったといわれるほど日本酒業界は盛んで、税金が多かったんだそうです。その国税庁のお酒に対する取り組みとして、酒類産業の活性化、酒類の表示および品質・安全性のチェック、輸出支援があります。
地理的表示(GI)は、お酒にはその産地ならではの特性があり、産地が要望し、一定の基準をクリアすれば、国税庁長官の指定を受けてその産地名を独占的に名乗ることができる仕組みです。これにより、日本各地のお酒の特色が産地のブランドとして認知され、国内外へ広がっていけばと考えているそうです。
そして、何より「日本酒」が、2015年12月25日に「国内産米のみを使用かつ、日本国内で製造された清酒」として指定されています。「え!最近海外でも蔵ができて日本酒が作られているんじゃないの?」なんて思われる方もいるでしょうが、一般的には「清酒」であり、国内の蔵元も海外米で日本酒を作ると、日本酒ではなく、清酒と定義されるようです。英訳すると日本酒も清酒もsake表記でしたが・・・。

今回、私がKUWANA SAKE SQWAREに参加した時に、国税のブースがあり、GI三重のピンバッジがあると伺ったので、関係者の方にお話ししたところ、身に着けていたものをお譲り頂きました。
「GI三重」は2020年6月19日に国税庁長官の指定を受け、シンボルマークは伊勢内宮から昇る朝日の中に束ね熨斗、その下に神様に捧げるお酒の杯が描かれており、とてもおめでたい図案になっています。

鈴鹿山脈に降り積もった雪や、多雨地帯である紀伊山地に降り蓄えられた雨水が、醸造に適した優良な水となって三重県全体に豊富に供給され、この地の気候と水資源により、酒質は、暖かみがあり芳醇で口に含んだ瞬間から旨味と同時に酸味が鼻に抜けていきます。魚介類等のたんぱくな味わいと合わせることで、酒の旨味との相性が良く、特に貝類や甲殻類の食中酒として楽しめるそうです。
更に三重県酒造協同組合では「GI 三重」の認定酒で、三重県原産あるいは開発された米、三重県内で分離もしくは開発された酵母をつかった純米酒・純米吟醸酒・純米大吟醸酒を「三重」にこだわった製品として、「三重ヘリテイジ(Mie’ Heritage)」の認証を独自で行っています。

「三重 Heritage」マークの形状は、米粒の影(黒色)中に、内張りに金色 の稲穂があり、中央に「Mie’ Heri-tage」と清酒 を醸す酵母がちりばめられています。こちらのピンバッジはまだないようですが、黒字に金のデザインは渋くっていいですね。
三重県酒造協同組合さんのこだわりに敬服いたします。