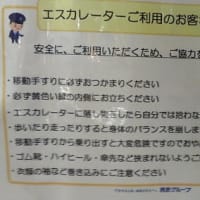12月13日(土) ビーバー“ロザリオ・ソナタ”全曲演奏会
王子ホール
【出演】
パヴロ・ベズノシウク(バロック・ヴァイオリン)/デイヴィッド・ロブロウ(チェンバロ、オルガン)/ポーラ・シャトーネウフ(テオルボ)/リチャード・タニクリフェ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
新井弘順(語り)
全曲演奏に2回の休憩を挟んで4時間も要するビーバーのロザリオ・ソナタ。長大で難曲、しかも名曲ではあるが知名度は決して高くない演目を超一流のプレイヤーを集めて取り上げた王子ホールは偉い!
ロザリオソナタのCDは持ってはいるが、いつも何かしながら聴いていた。こうして演奏会場でじっと聞き入るというのは、そんな普段の「ながら聴き」とは全く違った感動や発見を与えてくれる。バッハがまだ生まれる前に書かれたというビーバーのこの音楽全体を支配する一種独特の緊迫感は、時代を更に遡るジュズアルドの持つただならぬ雰囲気に似ているような…
「ながら聴き」では優雅な旋律が次々と現れ幽玄の世界へと導いてくれるというイメージだった。実際に聴いてもそうした要素は感じるが、実演ではとりわけヴァイオリンの多彩で雄弁な表情にびっくり。バッハより前の時代のとりわけ器楽曲は音楽史的には「前史」として片付けられてしまうこともあるが、バッハやそれ以降の音楽と優るとも劣らない光を放つ音楽がこうしてあるということを改めて認識した。
もちろんこれほどの強い印象を与えるのは演奏者の並々ならぬ力量あってのこと。演奏者には後の時代の音楽とはまた違った難しさが求められる。音楽が、3部形式とかリトルネッロ形式とか、ソナタの走りのような提示と展開による形式というように緊密な構成がはっきりしない分、演奏者はよりファンタジーを膨らませ、即興的な要素も駆使して音楽を魅力的に演奏しなければその曲の良さは伝わらないように思う。
そうした意味で、このロザリオ・ソナタの演奏に集まった4人の奏者の力量は申し分ない。吟遊詩人のようにかっこよくテオルボをかき鳴らすシャトーネフ、柔らかな空気を含んでアンサンブルに常に潤いを与えるガンバのタニクリフェ、オルガンとチェンバロを使い分け人の鼓動のような生きたリズムを与えるロブロウ。
そしてとりわけアンサンブルの主役となるベズノシウクのヴァイオリンは素晴らしかった。細かくめまぐるしく動くパッセージは精神の高揚からくる震えのようにも聴こえ、切々と歌う歌は体の隅々の毛細血管にまで血液が届いているように細やかで熱い。随所に登場する重音奏法の見事さ、これも聞きなれたヴァイオリンの重音とはまた違った魂の訴えを感じる。極めつけが終曲のパッサカリア。単純な4つの音の順次下降の音形が魔法にでもかかったように変幻自在に表情を変え、聴く者を捉え続けた。何しろ4時間に渡って名アンサンブルを聴かせ続けてくれるというのがすごい。
この演奏会で演奏者の他に忘れてはいけない朗読の新井弘順さんはなんと真言宗のお坊さん。黒い法衣を纏い講和を説くようにイエスと聖母マリアの物語を語っていく。「キリスト教の物語をなぜ仏教の坊さんが?」と思うが、これはベズノシウクがプログラムに書いていたように「キリスト教の霊的修練は人が最初想像するよりもずっと強く東洋とつながっている…」という演奏者の信念に基づいている、というのはわかってもどんな意図があるかはよくわからない。
意図はよくわからないのだが、宗教は違っても新井氏の言葉は重く心に伝わり、演奏に神々しい色付けが施されているのを感じた。クリスマスの夜のミサで朗読される聖書の物語などが仏教の坊さんの口から語られるのはしかし不思議な体験だ。でもこれが却ってこの音楽がキリスト教と言う狭義の世界からもっとコスモポリタン的な世界へと解放されているようにさえ感じた。キリスト教の聖職者は仏陀の物語なんて絶対に読んだりしないだろうな。
いろいろな意味で貴重な体験をした素晴らしい演奏会となった。

王子ホール
【出演】
パヴロ・ベズノシウク(バロック・ヴァイオリン)/デイヴィッド・ロブロウ(チェンバロ、オルガン)/ポーラ・シャトーネウフ(テオルボ)/リチャード・タニクリフェ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
新井弘順(語り)
全曲演奏に2回の休憩を挟んで4時間も要するビーバーのロザリオ・ソナタ。長大で難曲、しかも名曲ではあるが知名度は決して高くない演目を超一流のプレイヤーを集めて取り上げた王子ホールは偉い!
ロザリオソナタのCDは持ってはいるが、いつも何かしながら聴いていた。こうして演奏会場でじっと聞き入るというのは、そんな普段の「ながら聴き」とは全く違った感動や発見を与えてくれる。バッハがまだ生まれる前に書かれたというビーバーのこの音楽全体を支配する一種独特の緊迫感は、時代を更に遡るジュズアルドの持つただならぬ雰囲気に似ているような…
「ながら聴き」では優雅な旋律が次々と現れ幽玄の世界へと導いてくれるというイメージだった。実際に聴いてもそうした要素は感じるが、実演ではとりわけヴァイオリンの多彩で雄弁な表情にびっくり。バッハより前の時代のとりわけ器楽曲は音楽史的には「前史」として片付けられてしまうこともあるが、バッハやそれ以降の音楽と優るとも劣らない光を放つ音楽がこうしてあるということを改めて認識した。
もちろんこれほどの強い印象を与えるのは演奏者の並々ならぬ力量あってのこと。演奏者には後の時代の音楽とはまた違った難しさが求められる。音楽が、3部形式とかリトルネッロ形式とか、ソナタの走りのような提示と展開による形式というように緊密な構成がはっきりしない分、演奏者はよりファンタジーを膨らませ、即興的な要素も駆使して音楽を魅力的に演奏しなければその曲の良さは伝わらないように思う。
そうした意味で、このロザリオ・ソナタの演奏に集まった4人の奏者の力量は申し分ない。吟遊詩人のようにかっこよくテオルボをかき鳴らすシャトーネフ、柔らかな空気を含んでアンサンブルに常に潤いを与えるガンバのタニクリフェ、オルガンとチェンバロを使い分け人の鼓動のような生きたリズムを与えるロブロウ。
そしてとりわけアンサンブルの主役となるベズノシウクのヴァイオリンは素晴らしかった。細かくめまぐるしく動くパッセージは精神の高揚からくる震えのようにも聴こえ、切々と歌う歌は体の隅々の毛細血管にまで血液が届いているように細やかで熱い。随所に登場する重音奏法の見事さ、これも聞きなれたヴァイオリンの重音とはまた違った魂の訴えを感じる。極めつけが終曲のパッサカリア。単純な4つの音の順次下降の音形が魔法にでもかかったように変幻自在に表情を変え、聴く者を捉え続けた。何しろ4時間に渡って名アンサンブルを聴かせ続けてくれるというのがすごい。
この演奏会で演奏者の他に忘れてはいけない朗読の新井弘順さんはなんと真言宗のお坊さん。黒い法衣を纏い講和を説くようにイエスと聖母マリアの物語を語っていく。「キリスト教の物語をなぜ仏教の坊さんが?」と思うが、これはベズノシウクがプログラムに書いていたように「キリスト教の霊的修練は人が最初想像するよりもずっと強く東洋とつながっている…」という演奏者の信念に基づいている、というのはわかってもどんな意図があるかはよくわからない。
意図はよくわからないのだが、宗教は違っても新井氏の言葉は重く心に伝わり、演奏に神々しい色付けが施されているのを感じた。クリスマスの夜のミサで朗読される聖書の物語などが仏教の坊さんの口から語られるのはしかし不思議な体験だ。でもこれが却ってこの音楽がキリスト教と言う狭義の世界からもっとコスモポリタン的な世界へと解放されているようにさえ感じた。キリスト教の聖職者は仏陀の物語なんて絶対に読んだりしないだろうな。
いろいろな意味で貴重な体験をした素晴らしい演奏会となった。