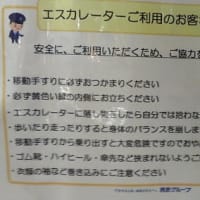「熱狂の日」音楽祭2014 【10回記念 祝祭の日】 東京国際フォーラム 1995年にフランスのナントで始まった型破りの一大クラシック音楽フェスティバル「ラ・フォル・ジュルネ」が2005年に日本に上陸してから今年で10年目を迎えた。2011年は震災の影響で大幅な縮小開催となったが、それでも毎年行われ、昨年までで577万人の来場者を集めてきた。クラシック音楽のイベントがこれほど注目され、人気を集め、しかもそれが足掛け10年も続いているというのは驚くべきことだ。内容や出演者のレベルの高さや多彩さだけでなく、GWの行楽気分で参加できる気軽さや、楽しさが集客力の大きな要因だろう。クラシックの演奏会にいつも通っている僕でも特別なウキウキ気分を感じて、家族と一緒に来たくなる。 今回のテーマはズバリ「10回記念 祝祭の日」。これまでの歩みの総決算的なプログラミングとキャスティングで、魅力的なコンサートが揃った。その中から、初日5月3日の6公演を聴いた。以下、その感想を演奏順に紹介する。 |  |
~5月3日(土)~
 トリオ・レゼスプリ
トリオ・レゼスプリ~Vn:梁美沙/Vc:ヴィクトル・ジュリアン=ラファリエール/Pf:アダム・ラルーム~
ホールD7(ホフマンスタール)
【曲目】
1.ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第6番 イ長調 Op.30-1


2.ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲第5番 ニ長調 Op.70-1「幽霊」


以前、紀尾井ホールで聴いたリサイタルで、まるでダンスを踊っているように大きく体を動かし、その動きと同じような躍動感溢れる瑞々しい演奏が印象に残っている梁美紗、今日も生き生きとした素晴らしいベートーヴェンを聴かせてくれた。攻めるシーンでは迷うことなく果敢に攻め、歌うところは心の底から歌い上げ、隙のないスリリングで若々しい生命力に満ちた演奏を繰り広げる。ピアノのラムールは梁と一緒に呼吸し、敏感に梁のバイオリンに反応する。二人の奏でる音楽はまさに今この瞬間に生まれてきたように新鮮で瑞々しい。ベートーヴェンの命が息づいたような演奏だった。
チェロのラファリエールが加わってのトリオでは更なる火花が散った。3人はガッチリと三つ巴を組んで、まさに当意即妙あうんの呼吸で演奏を進めていく様子に、聴いていてたちまちのめり込んでしまった。それぞれがお互いの様子を感知し合い、相手の呼吸を受け取ってそれに即応する。両端楽章のスリリングな演奏に挟まれた第2楽章の、柔らかな空気を包み込んだデリケートな演奏も素敵。中間部の長いクレッシェンドで膨らんで行くところなんて、神々しい光を感じた。このトリオは音楽的な共感度が高く、エキサイティングな演奏を楽しむことができた。
 ヤーン=エイク・トゥルヴェ指揮 ヴォックス・クラマンティス/Pf:ジャン=クロード・ペヌティエ
ヤーン=エイク・トゥルヴェ指揮 ヴォックス・クラマンティス/Pf:ジャン=クロード・ペヌティエホールB7(ゲーテ)
【曲目】
♪リスト/十字架の道
3年連続で聴くことになった声楽アンサンブルのヴォックス・クラマンティス、今回は12人がステージに乗った。これにピアノが加わって、リストの珍しい宗教作品が演奏された。合唱団からはいつものように無理のないとても自然体な響きが届いてきた。透明感のある柔らかな歌声は、リスト晩年のストイックな作品によく似合っている。
曲はソロと合唱、それにソロ楽曲も受け持つピアノ(オリジナルはオルガン)によって、キリストの受難と、それを嘆き悲しむマリアの姿を描いて行く。抑揚を抑え、静かな祈りを捧げるような音楽で、「マタイ」の受難コラールも入っていたのが印象的。女声のアンサンブルで歌われる「スタバト・マーテル」が清澄な美しい響きを聴かせた。また曲中4つの楽曲で演奏されるピアノソロは、ヴィルトゥオーゾで唸らせるリストのイメージとは対極にあるような静寂に包まれ、それが反って深い痛みを伝えてきた。
 ミシェル・コルボ指揮 ローザンヌ声楽アンサンブル/シンフォニア・ヴァルソヴィア/S:シルヴィ・ヴェルメイユ/Bar:ファブリス・エヨーズ
ミシェル・コルボ指揮 ローザンヌ声楽アンサンブル/シンフォニア・ヴァルソヴィア/S:シルヴィ・ヴェルメイユ/Bar:ファブリス・エヨーズホールC(リルケ)
【曲目】
♪フォーレ/レクイエム Op.48



【アンコール】
♪グノー/十字架上の最期の7つの言葉~終曲

今年もコルボ/ローザンヌ声楽アンサンブルがLFJに来てくれた!LFJのコルボの公演で度々登場するポーランドの室内オーケストラ、シンフォニア・ヴァルソヴィアの共演で、この演奏者達の極め付きとも言えるフォーレのレクイエムを夫婦で聴いた。
何に惑わされることもなく真っ直ぐに捧げられる祈りの光が、心の奥底を仄かに照らすような入祭唱の導入から、会場は深い祈りの空気で包まれた。そして柔らかなオーケストラの前奏に導かれて始まるテノールのユニゾンと弦の織り成す、世にもデリケートな声楽的ポリフォニーの妙はコルボの真骨頂!シンフォニア・ヴァルソヴィアのフレーズの端々まで細やかで柔らかなタッチを大切にした演奏も素晴らしい。
コルボは、主兵のローザンヌ声楽アンサンブルと、この優れたオーケストラ、それにデリケートな声と表情を湛えた2人のソリストを率いて、まさしく極上の音楽を奏でて行った。それはこの上なく甘美で、痛みを優しくいたわる慈愛に溢れて、死者と、死を悼む全ての人々を包み込む。
一方で、近年益々昇華の途をたどり、天上界から神様の声を届けるようになってきたように感じたコルボから、意外なほど熱くて激しいパッションが伝わる場面があったのはちょっとした驚き。この音楽で唯一といえる烈しい「怒りの日」の場面では、大胆に刻んだリズムに乗って、深い苦悩を訴えてきたが、この場面に限らず、あちこちで人間らしい熱い声が聴こえてきた。
聴くたびに世離れしてきたようにも思えたコルボが、80歳を迎えた今、人間らしい姿を見せることに回帰したようにも思えるこの「出来事」に、コルボの生への執着を感じたなどと思うのは考え過ぎだろうか。まだまだ元気な様子のコルボ、大いに生への執着を逞しくして、まだまだ長生きしてこれからも毎年来年元気な姿を見せて欲しい。
 Vn:マリナ・シシュ/Pf:アブデル・ラーマン・エル=バシャ
Vn:マリナ・シシュ/Pf:アブデル・ラーマン・エル=バシャホールB5(カフカ)
【曲目】
1.ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ第9番 ホ長調 Op.14-1
2.ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 「月光」
3. ベートーヴェン/ヴァイオリン・ソナタ第3番 変ホ長調 Op.12-3
エル=バシャのピアノは、以前LFJでショパンを聴いたことがある。端正で上品な演奏だったと記憶しているが、眠くなってしまったことも覚えている。今日はベートーヴェンだったが、やはり端正にソナタの各楽章を綴って行った。語り口は滑らかでとても上品。強弱や濃淡の変化も品がある。お行儀のいい演奏は、しかし言い方は悪いがピアノ学習者のための模範演奏のような印象。聴き心地が良く、たんだんと眠くなってきてしまった。「月光」の第3楽章のような激しいパトスが炸裂する音楽でもエル=バシャは羽目を外すことなく冷静さを保ちつつ、音楽の少し外側から全体を見据えた演奏をする。いい演奏ではあるかも知れないが、やはり面白くない。
マリナ・シシュとのデュオでは、エル=バシャは伴奏者としての人並みならぬ腕前も披露した。シシュのヴァイオリンにピタリと合わせ、ピアノが主体のこの曲でシシュを上手くエスコートする。シシュはきっと安心して演奏できたのではないだろうか。ソロで聴いた時よりも呼吸に躍動を感じたが、どことなく教師然とした姿を感じてしまう。シシュのヴァイオリンは、大きな呼吸で、大胆かつ伸び伸びとした音楽性は感じたが、細やかさや密度では少々物足りない。ピアノを引き立てる伴奏役にまわる場面では、もう少しアンサンブルを分かち合っていることを自らの音で示して欲しがった。
 ヤーン=エイク・トゥルヴェ指揮 ヴォックス・クラマンティス
ヤーン=エイク・トゥルヴェ指揮 ヴォックス・クラマンティス 

ホールB5(カフカ)
【曲目】
♪ケージ/18の春のすてきな未亡人
♪ラング/墓地よ
♪(グレゴリオ聖歌)/昇階曲
♪ラング/イブニング・モーニング・デイ
♪ケージ/花
♪ラング/再び
♪(グレゴリオ聖歌)/アレルヤ
♪ラング/アイ・ウォント・トゥー・リブ
♪ラング/愛は強いから
本日2度目となるヴォックス・クラマンティスの公演は、ジョン・ゲージとラングという現代の作品にグレゴリア聖歌を交えたプログラム。ファンタジー溢れる体験ができそうな予感。
その期待に応えるかのように、まだ誰もいない薄暗いステージに、グレゴリア聖歌風の節を歌いながら合唱隊の男声メンバーがゆっくりと入ってきた。歌と同時にステージ上の蓋が閉じられたピアノを手で叩く音が会場に響き渡る。ケージの作品だ。2曲目のラングの作品では、これに応えるように僕が座っていた席のすぐ後ろに配された女声メンバーのハーモニーが聴こえてきた。一人一人の声が間近で聴こえてきて、この合唱団のメンバーの一人一人が澄みきった美しい声の持ち主であることを身をもって体感した。合唱の響きが澄んでいるわけだ。
演奏は一連の宗教儀式のように、途中で拍手が入ることなく連綿と続いて行く。合唱団は曲によって立ち位置を変え客席フロアも使い、客席は合唱隊に取り囲まれることもある。圧巻は最後のラングの「愛は強いから」。四方八方からの歌声に囲まれ、幻想的なハーモニーと、各パートに与えられた言葉が呪文のように繰り返されるフレーズの渦の中に溶けてしまうような不思議な陶酔感はアルヴォ・ペルトの世界にも繋がる。デッドな響きの会場だが、教会の大聖堂に身を置いている気分を味わった。午前中に聴いたコンサートではボリューム感に乏しいとも思ったが、ここでは清澄なハーモニーがもたらすパワーを思い知った。
 モディリアーニ弦楽四重奏団/Vc:アンリ・ドマルケット
モディリアーニ弦楽四重奏団/Vc:アンリ・ドマルケットホールB7(ゲーテ)
【曲目】
♪シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D956/Op.163


モディリアーニ弦楽四重奏団はLFJの常連。これまでに聴いた演奏でも、柔らかな肌触りと自然な空気感が音楽の優しさを伝えて好印象だったが、これはシューベルト最晩年の奇跡のようなこの名曲でも持ち味を最大限に発揮した。第1チェロとして加わったドマルケットが、モディリアーニ・カルテットのフワリとした響きにしっかりした筆遣いでくっきりと輪郭づけをすることで、硬軟織り交ぜられた曲の魅力を幅広く表現することに成功していた。
それにしてもこの若いメンバーによるアンサンブルから、東欧のベテランカルテットのような味わい深い色合いの響きが聴こえてくるのはとても意外だ。この若さで、気負うことなく自然体で柔らかな表情を生み出すことができるのは、4人の音楽的志向がよほど一致していて、更に1つに束ねられたものをじっくりと熟成させる心と時間のゆとりがあるからに違いない、と思ってしまう。そうでなければ、名曲ではあるが、取り組むには多くの困難を伴いそうな大規模なこの作品をここまで自分たちのものにすることは難しいはず。彼らの演奏からは、心の中の遥か遠い情景を眺めているような深遠な世界や時空を超えた永遠性が伝わってきて、いつまでも浸っていたかった。
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2013
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2012
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2011
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2010
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2009