6月26日(木)東京二期会オペラ劇場公演
【演目】
R.シュトラウス「ナクソス島のアリアドネ」
台本:フーゴー・フォン・ホーフマンスタール
東京文化会館
【配役】
執事長:田辺とおる/音楽教師:加賀清孝/作曲家:谷口睦美/テノール歌手(バッカス):高橋 淳/士官:羽山晃生/舞踏教師:大野光彦/かつら師:大久保光哉/召使:馬場眞二/ツェルビネッタ:幸田浩子/プリマドンナ(アリアドネ):佐々木典子/ハルレキン:青戸 知/スカラムッチョ:加茂下 稔/トゥルファルディン:志村文彦/ブリゲッラ:中原雅彦/ナヤーデ: 木下周子/ドゥリヤーデ:増田弥生/エコー:羽山弘子
【演出】鵜山 仁 【衣装】 原まさみ
【演奏】
ラルフ・ワイケルト指揮 東京交響楽団
オペラの公演というのは僕にとっては「初物」が多い。「アリアドネ」を観るのも今回が初めて。そんなわけでいつにも増して独り言の域を出ない感想、という前置きをした上で正直に言えば、楽しい公演だったが感動するほどではなく、逆にいろいろな疑問を感じる公演だった。
序幕(プロローグ)は良かった。いろんな者達がそれぞれに思惑を抱えて言いたい放題が交錯する喧騒のなか、理想郷の世界を夢想し、俗悪なものを受け入れようとしない作曲家の熱弁に対し、ツェルビネッタがそれまでのオチャラケから本音を語り始め、徐々に作曲家の心を捉えて行くそのやり取りと移り変わりが見事。妖艶で闊達で頭も切れるツェルビネッタの溢れる魅力を、瑞々しく色っぽい歌で存分に表現した幸田浩子は、容姿やしぐさも役になりきっていたし、作曲家を歌った谷口睦美もまっすぐな気性と情熱を歌い上げ、聴き手を引き込んで行った。
さて、問題は本幕の「オペラ」。疑問に思ったことを上げると…
ツェルビネッタの熱弁の真っ最中にアリアドネが中座!?
ツェルビネッタがアリアドネを説き伏せるように歌う有名な長い長いレチタティーヴォとアリア「偉大なる王女さま」、これに耳を傾けようとせずともどこかに思い当たるところもあり、このあとバッカスと結ばれる伏線になっていると思うのだが、アリアドネはツェルビネッタがまだレチタティーヴォを歌っているあたりで退場してしまう。つまり全く物理的にツェルビネッタの歌は耳に入っていないわけだ。どうして?これでは全くツェルビネッタのただの独白でしかなくなってしまうが、それでいいんだろうか?幸田浩子のツェルビネッタが、巧みな歌いまわし、見事な高音のコントロール、お色気ムンムンの表情で、しかもただの遊び女ではない、女の道を説くような筋も一本ピーンと入っていて、これぞスポットライトを一身に浴びるに相応しい歌唱だっただけに(もっともっと拍手喝采を浴びていいと思ったのだが…)なおさらその感を強めた。
茶番劇の道化達
その後ツェルビネッタに言い寄る道化達だが、どれもこんなしたたかで賢い娘を口説き落とせるようなタマではない。ハルレキンがツェルビネッタをものにする場面もいかにも弱い。もっと男の色気をムンムン出し、ツェルビネッタをグッと本気にさせるような「本気のいやらしさ」がないとただの茶番で終わってしまう。これは青戸の歌唱だけの問題じゃあなくて、設定された演技にも問題があるのでは…
へなちょこバッカス
そして出てきたバッカスの威厳のなさ。高所でスポットライトを浴びた登場の場面はそれなりに威光を感じたが、その後ステージに下りてきたバッカスの格好… 言っちゃあ悪いが、へなちょこの若造みたいなイメージしか持てなかった。おまけに高橋淳の歌は、よく声は出ていて美声の部類に入るのかも知れないが、表情は平板で威厳がない(今夜一番の拍手喝采を浴びていたが)。このバッカスでは貫禄さえある気高いアリアドネ(佐々木典子は気高く一途なアリアドネの姿を潤いと包容力のある美声でよく表現していた)は釣り合わない。あれほどまでに一人の男を思い続けていたアリアドネが、結局はバッカスという神と結ばれるに至る脈絡が、演出の面でも、キャスティングの面でも希薄になってしまったような気がしてならない。
劇中劇をどう捉えるか?
ただ、ここで押さえておきたいことは、この「本幕」である「ナクソス島のアリアドネ」は劇中劇であるということ。もし「本幕」だけのオペラだとしたら、とにかくこの物語に観客を引き込めば成功だろう。だが劇中劇となると、どこかに「これはお芝居」という傍観者的な要素が入る余地はあるのかも知れない。それが今回の演出の意図するところだったのだろうか?
しかし…
ホーフマンスタールはシュトラウスがこのオペラの最後に再び作曲家を登場させ、現実に引き戻すというアイディアに猛反発し、
「オペラの結末部の高揚した気分をお考えになって下さい。この気分は、序幕の始めから準備され、次第に高まり、英雄的オペラとなり、やがてバッカスの登場と二重唱の中で、殆ど神秘的な高みまでようやく登りつめているのです…」(中島悠爾先生の訳による「リヒャルト・シュトラウス ホーフマンスタール 往復書簡全集」より)
と書き送り、シュトラウスがこれを尊重したことを考えれば、「アリアドネ」というオペラセリアに劇中劇として道化達が登場し、その対比の面白さを出しつつも、ツェルビネッタの「真面目な」説得などを通して道化達もこの物語の中に取り込まれ、ひとつの「真実」を歌い上げて行く、というのがコンセプトではなかろうか。
そう考えると、この幕の終わりの方で作曲家やら執事長などをステージにしつらえた「客席」に座らせ、劇中劇であることを意識させた演出は、「ドラマ」のクライマックスとは反対の効果をもたらすわけで、演出の鵜山仁は意図的に「お芝居」の面を強調したのかも知れない。簡素な衝立の絵で洞窟を表現したのもそのためかも知れないが、ではどうして最後の最後で大掛かりな洞窟を登場させたのだろうか? そもそも「お芝居」を強調した狙いはどこにあったのだろう?
何分にも今回が「アリアドネ」初体験だったので、全くズレた感想かも知れない。オペラとしても音楽としてもとても面白いので、次は別の演出でまた観てみたい。ちなみに、ラルフ・ワイケルト指揮の東響は、もっと主張するところはどぎついぐらいにやってくれてもいいとは思ったが、細部まで丁寧に表現していて色彩も豊か。柔らかなシュトラウスサウンドを醸し出していた。
これらの疑問や誤解を解く鍵になるようなコメント、TBを歓迎します!
【演目】
R.シュトラウス「ナクソス島のアリアドネ」

台本:フーゴー・フォン・ホーフマンスタール
東京文化会館
【配役】
執事長:田辺とおる/音楽教師:加賀清孝/作曲家:谷口睦美/テノール歌手(バッカス):高橋 淳/士官:羽山晃生/舞踏教師:大野光彦/かつら師:大久保光哉/召使:馬場眞二/ツェルビネッタ:幸田浩子/プリマドンナ(アリアドネ):佐々木典子/ハルレキン:青戸 知/スカラムッチョ:加茂下 稔/トゥルファルディン:志村文彦/ブリゲッラ:中原雅彦/ナヤーデ: 木下周子/ドゥリヤーデ:増田弥生/エコー:羽山弘子
【演出】鵜山 仁 【衣装】 原まさみ
【演奏】
ラルフ・ワイケルト指揮 東京交響楽団
オペラの公演というのは僕にとっては「初物」が多い。「アリアドネ」を観るのも今回が初めて。そんなわけでいつにも増して独り言の域を出ない感想、という前置きをした上で正直に言えば、楽しい公演だったが感動するほどではなく、逆にいろいろな疑問を感じる公演だった。
序幕(プロローグ)は良かった。いろんな者達がそれぞれに思惑を抱えて言いたい放題が交錯する喧騒のなか、理想郷の世界を夢想し、俗悪なものを受け入れようとしない作曲家の熱弁に対し、ツェルビネッタがそれまでのオチャラケから本音を語り始め、徐々に作曲家の心を捉えて行くそのやり取りと移り変わりが見事。妖艶で闊達で頭も切れるツェルビネッタの溢れる魅力を、瑞々しく色っぽい歌で存分に表現した幸田浩子は、容姿やしぐさも役になりきっていたし、作曲家を歌った谷口睦美もまっすぐな気性と情熱を歌い上げ、聴き手を引き込んで行った。
さて、問題は本幕の「オペラ」。疑問に思ったことを上げると…
ツェルビネッタの熱弁の真っ最中にアリアドネが中座!?
ツェルビネッタがアリアドネを説き伏せるように歌う有名な長い長いレチタティーヴォとアリア「偉大なる王女さま」、これに耳を傾けようとせずともどこかに思い当たるところもあり、このあとバッカスと結ばれる伏線になっていると思うのだが、アリアドネはツェルビネッタがまだレチタティーヴォを歌っているあたりで退場してしまう。つまり全く物理的にツェルビネッタの歌は耳に入っていないわけだ。どうして?これでは全くツェルビネッタのただの独白でしかなくなってしまうが、それでいいんだろうか?幸田浩子のツェルビネッタが、巧みな歌いまわし、見事な高音のコントロール、お色気ムンムンの表情で、しかもただの遊び女ではない、女の道を説くような筋も一本ピーンと入っていて、これぞスポットライトを一身に浴びるに相応しい歌唱だっただけに(もっともっと拍手喝采を浴びていいと思ったのだが…)なおさらその感を強めた。
茶番劇の道化達
その後ツェルビネッタに言い寄る道化達だが、どれもこんなしたたかで賢い娘を口説き落とせるようなタマではない。ハルレキンがツェルビネッタをものにする場面もいかにも弱い。もっと男の色気をムンムン出し、ツェルビネッタをグッと本気にさせるような「本気のいやらしさ」がないとただの茶番で終わってしまう。これは青戸の歌唱だけの問題じゃあなくて、設定された演技にも問題があるのでは…
へなちょこバッカス
そして出てきたバッカスの威厳のなさ。高所でスポットライトを浴びた登場の場面はそれなりに威光を感じたが、その後ステージに下りてきたバッカスの格好… 言っちゃあ悪いが、へなちょこの若造みたいなイメージしか持てなかった。おまけに高橋淳の歌は、よく声は出ていて美声の部類に入るのかも知れないが、表情は平板で威厳がない(今夜一番の拍手喝采を浴びていたが)。このバッカスでは貫禄さえある気高いアリアドネ(佐々木典子は気高く一途なアリアドネの姿を潤いと包容力のある美声でよく表現していた)は釣り合わない。あれほどまでに一人の男を思い続けていたアリアドネが、結局はバッカスという神と結ばれるに至る脈絡が、演出の面でも、キャスティングの面でも希薄になってしまったような気がしてならない。
劇中劇をどう捉えるか?
ただ、ここで押さえておきたいことは、この「本幕」である「ナクソス島のアリアドネ」は劇中劇であるということ。もし「本幕」だけのオペラだとしたら、とにかくこの物語に観客を引き込めば成功だろう。だが劇中劇となると、どこかに「これはお芝居」という傍観者的な要素が入る余地はあるのかも知れない。それが今回の演出の意図するところだったのだろうか?
しかし…
ホーフマンスタールはシュトラウスがこのオペラの最後に再び作曲家を登場させ、現実に引き戻すというアイディアに猛反発し、
「オペラの結末部の高揚した気分をお考えになって下さい。この気分は、序幕の始めから準備され、次第に高まり、英雄的オペラとなり、やがてバッカスの登場と二重唱の中で、殆ど神秘的な高みまでようやく登りつめているのです…」(中島悠爾先生の訳による「リヒャルト・シュトラウス ホーフマンスタール 往復書簡全集」より)
と書き送り、シュトラウスがこれを尊重したことを考えれば、「アリアドネ」というオペラセリアに劇中劇として道化達が登場し、その対比の面白さを出しつつも、ツェルビネッタの「真面目な」説得などを通して道化達もこの物語の中に取り込まれ、ひとつの「真実」を歌い上げて行く、というのがコンセプトではなかろうか。
そう考えると、この幕の終わりの方で作曲家やら執事長などをステージにしつらえた「客席」に座らせ、劇中劇であることを意識させた演出は、「ドラマ」のクライマックスとは反対の効果をもたらすわけで、演出の鵜山仁は意図的に「お芝居」の面を強調したのかも知れない。簡素な衝立の絵で洞窟を表現したのもそのためかも知れないが、ではどうして最後の最後で大掛かりな洞窟を登場させたのだろうか? そもそも「お芝居」を強調した狙いはどこにあったのだろう?
何分にも今回が「アリアドネ」初体験だったので、全くズレた感想かも知れない。オペラとしても音楽としてもとても面白いので、次は別の演出でまた観てみたい。ちなみに、ラルフ・ワイケルト指揮の東響は、もっと主張するところはどぎついぐらいにやってくれてもいいとは思ったが、細部まで丁寧に表現していて色彩も豊か。柔らかなシュトラウスサウンドを醸し出していた。
これらの疑問や誤解を解く鍵になるようなコメント、TBを歓迎します!
















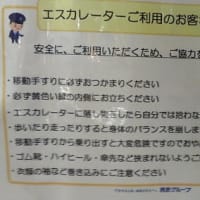









結果的にアリアドネはバッカスと結ばれたのだし。
このオペラはストーリーはハチャメチャで仕方がないのではないか、などと思いながら、同じキャスト28日(土)に観てきました。
以前、新日本フィルで井上道義さん指揮でやった時は、最後音楽が終わると同時に本当に花火(舞台後方に沢山のシュルシュルと上がる火花)が上がったのですよ。どうもその印象が強すぎて、その後「ナクソス島のアリアドネ」を観る度に、花火があるんじゃないかしらと思ってしまいます。
ところで、本当に花火が上がるとすると、それは丁度時刻も9時だったんでしょうか?
ちょっと飲み過ぎてはしゃぎすぎました。
私も気になって、ト書きを調べましたが、アリアドネの所作が明確に書かれてません。
中座せずに、大人しく聴いてから、退出する演出もあるようです。私は、ツェルビネッタの心情告白と捉えたい思いが強いです。アリアドネは、プロローグでは高慢なプリマなのに、オペラでは高尚な人物然となってしまう。
両方通じて変わらないのはツェルビネッタですから。
劇中劇に徹しすぎると何かと矛盾だらけになってしまう難しいオペラですね。