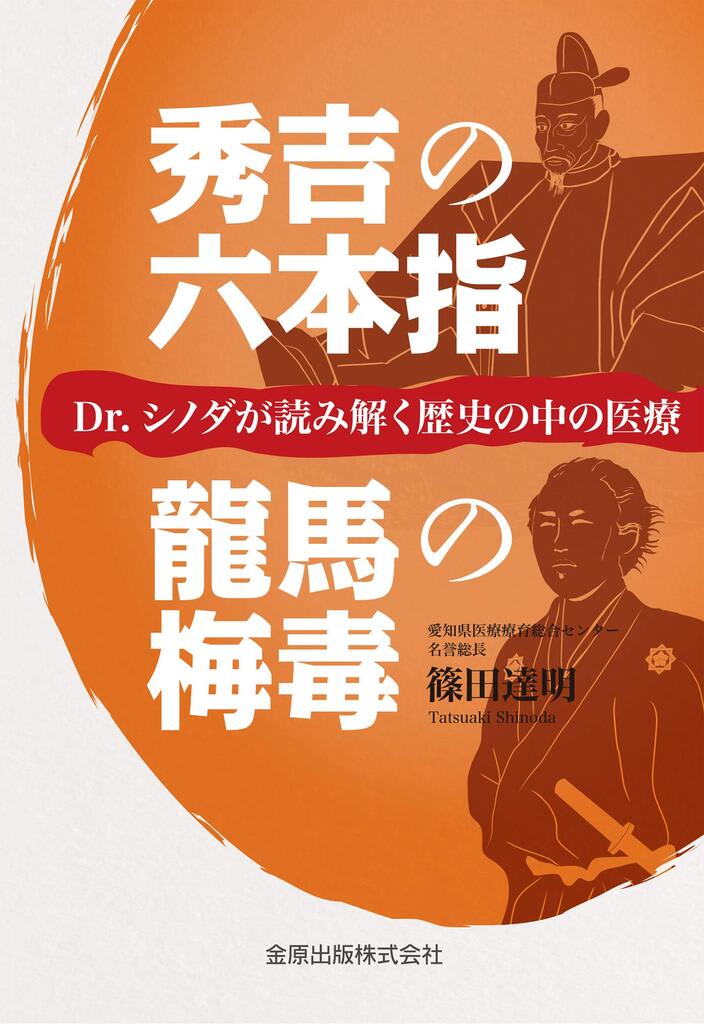ヒト型抗RANKL抗体であるデノスマブは、RANKLと結合してRANKとの結合を競合的に阻害することで骨吸収を抑制し、脆弱性骨折を防止する骨粗鬆症治療薬です。Pivotal studyであるFREEDOM試験では大腿骨近位部骨折を3年間の投与で40%減少させることが報告されています。その効果は主として骨密度増加によるものであるとされていますが、①顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー患者に投与したところ、わずか24時間で握力増加と歩行能力改善が見られた(Lefkowitz SS et al., Am J Case Rep. 2012;13:66-8)②閉経後女性にデノスマブを3年間投与したところ、握力の増加が見られた(Bonnet N et al., J Clin Invest. 2019 May 23;129(8):3214-3223)などの報告もあり、筋に対する直接的な効果があるのではと考えられています。
この論文は5つのプラセボ対照試験のpooled analysisを行い、デノスマブの転倒に対する効果を検討してものです。対象となった研究は骨粗鬆症に対する3つの臨床試験と癌治療関連骨減少症(cancer treatment-induced bone loss, CTIBL) に対する2つの臨床試験です。プールされた症例は10,036例、男性が16.9%です。平均年齢は72歳で半数弱が既存骨折ありでした。6682例が75歳未満、3354例が75歳以上でした。デノスマブ群、プラセボ群の背景に差はなく、全症例の25水酸化ビタミンD3値の中間値は21 ng/mLでした。フォローアップ期間はデノスマブ36.0カ月、プラセボ35.9カ月です。
1度以上の転倒を報告したのはデノスマブ群4.6% vs プラセボ群5.8%(hazard ratio, HR=0.79, 95% CI 0.66-0.93)でデノスマブによる転倒防止効果は21%でした。5つの試験すべてでデノスマブ群で転倒は少なく、傾向は一定でした。Pooled HRはベースラインの年齢、大腿骨近位部骨密度、非椎体骨折の既往歴、地域をそろえても同様でした。デノスマブの効果は年齢と交互作用があり、75歳未満の方が有効性は高く、HRは75歳未満で0.65(95% CI 0.52-0.82)だったのに対し、75歳以上では1.01(95% CI 0.78-1.31)でした。性別との交互作用はありませんでした。
以上の結果からデノスマブが高齢者の転倒を抑制する可能性が示されましたが、この論文に対してはアルファ誤差=0.05(両側)、ベータ誤差=0.20(乗数80%)、相対的リスク低減の予測値20%を想定して推定したところ、登録された参加者数(n = 10,036)が必要な情報量(n = 16,644)を超えていないという批判もあり(Wu X-D et al., J Bone Miner Res. 2020 Jun 3. doi: 10.1002/jbmr.4051)、今後前向きの試験が必要と考えられます。
Chotiyarnwong P et al., J Bone Miner Res. 2020 Jan 30. doi: 10.1002/jbmr.3972. "A Pooled Analysis of Fall Incidence From Placebo-Controlled Trials of Denosumab"