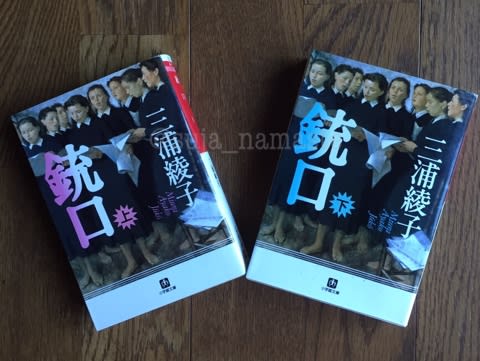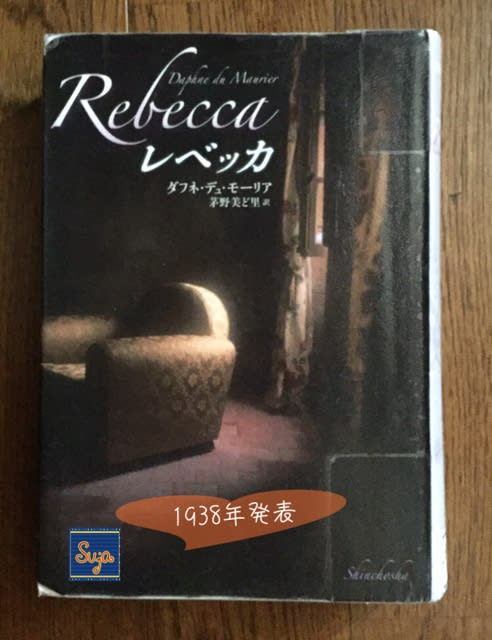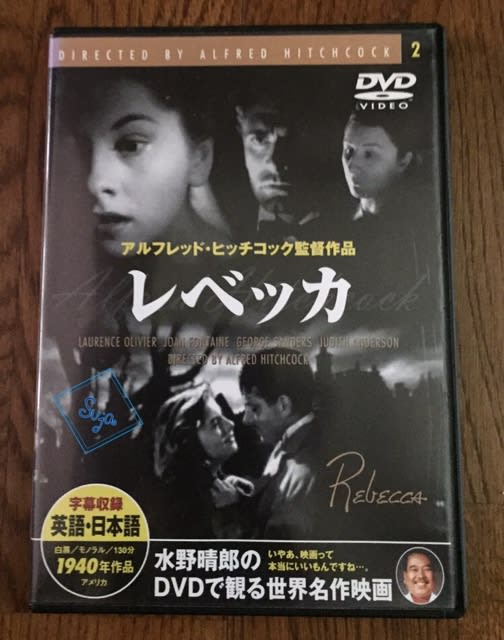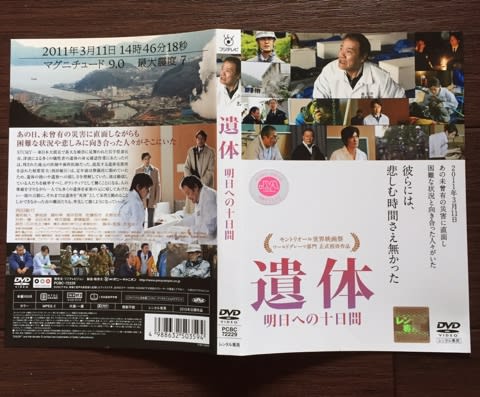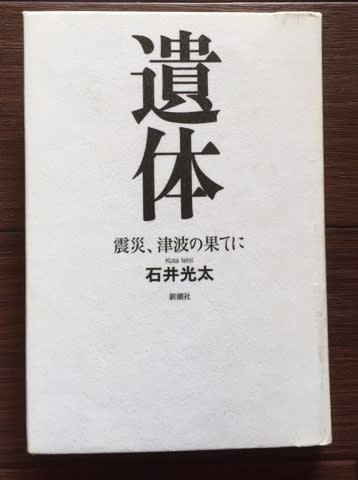こんにちは
Sujaです
時折、相談される内容が深まるなか
精神障害やひきこもりについて勉強しようと
いろんな書物を読み探していたとき
『安心して絶望できる人生』
という本と出会いました

なんてパンチの効いたタイトルなんだろうと思い
思わず手に取り読み始めたのです
著者の向谷地生良(むかいやちいくよし)氏は
北海道の浦河町というところに
『べてるの家』
という精神疾患を抱えた人たちが生活する活動拠点を創設した人で
ソーシャルワーカーとして浦河赤十字病院で働いていた人です
この『べてるの家』では
統合失調症などの精神疾患を抱えた人たちが
自身の悩みや病についてグループで研究するという
『当事者研究』が盛んに行われています
そもそもみんな誰しも
人生に悩みや苦労は常に付いて回るもので
そのうえ精神的な病を抱える中
どうやって人並みで当たり前の苦労を経験しながら
精神疾患と付き合っていくかということが
『べてるの家』ではテーマになっています
日々、ミーティングと研究で自分自身の悩みや病に理解を深めて受け入れながら
自身や周りとバランスよく付き合っていく日々を送っています
この『当事者研究』は
精神疾患を持つ当事者自身が研究者の目を持って
自分自身と社会に目を向け、暮らしやすい場を創っていくことが目標で
当事者が自ら病名を考え研究結果を発表していきます
例えば
小泉元総理大臣の幻聴に恋してしまった人が名づけた自己病名が
『統合失調症ドラマティックタイプ』
実にユニークです
そして
幻聴のことは『幻聴さん』と親しみを込めて呼んでいるそうで
意地悪な事を言う幻聴さんに対し
「丁寧な物言いで丁重にお引き取り頂きましょう」というアドバイス通りに
「幻聴さん、お願いします。今日は疲れているのでもう休ませてください。幻聴さんもお休みください」と伝えると
幻聴さんの頻度が減ったり、優しい幻聴さんになるそうです
この研究やミーティングを重ねるにつれ、当事者にも少しずつ変化が生じ
「自分の行き詰まりに手ごたえを感じる」
「この困り方は良いセンいってるね」
「自分の悩みや不安に誇りを感じる」
「諦め方が上手くなってきた」
「悩みの多さに自信が出て来た」
「病気のスジが良いね」
「最近、落ち方がうまいね」
などと自他ともにそんな感想が出てくるユニークさには魅力に感じます
『悩み事』を『テーマ』に置き換え
「悩みを抱えているのではなく『テーマ』を与えられている」
という発想の転換によって
問題は解決しなくても、自己が損なわれない感覚を覚え
思いつめることなく『行き詰まり』に自信を持つようになるのです
実際に当事者研究をした人の感想が印象的でした
『自己肯定の感覚をつかんだとき、初めて「自分の荷物は自分のものだ」と気付いた。自分が自分の面倒を見て、自分が自分を助けはじめた時、初めて自己否定からくる問題行動で人間関係を壊すというサイクルから少しずつ抜け出しはじめたように思う』
「三度の飯よりミーティング」を合言葉に、何かが生じる度にみんなで話し合う事を大事にしているそうです
所々にユーモアセンスをちりばめる手法はとても魅力的ですね
『苦しいのに笑える』
『絶望してるけど安心』
『泣きながら笑ってる』
そんな印象をうけました
辛い状況下でもユニークさを一滴落とすことで
心や思考が弛緩する効果があり
困難を受け入れるスペースがちょっとだけ出来るような気がします

Sujaです

時折、相談される内容が深まるなか
精神障害やひきこもりについて勉強しようと
いろんな書物を読み探していたとき
『安心して絶望できる人生』
という本と出会いました

なんてパンチの効いたタイトルなんだろうと思い
思わず手に取り読み始めたのです
著者の向谷地生良(むかいやちいくよし)氏は
北海道の浦河町というところに
『べてるの家』
という精神疾患を抱えた人たちが生活する活動拠点を創設した人で
ソーシャルワーカーとして浦河赤十字病院で働いていた人です
この『べてるの家』では
統合失調症などの精神疾患を抱えた人たちが
自身の悩みや病についてグループで研究するという
『当事者研究』が盛んに行われています
そもそもみんな誰しも
人生に悩みや苦労は常に付いて回るもので
そのうえ精神的な病を抱える中
どうやって人並みで当たり前の苦労を経験しながら
精神疾患と付き合っていくかということが
『べてるの家』ではテーマになっています
日々、ミーティングと研究で自分自身の悩みや病に理解を深めて受け入れながら
自身や周りとバランスよく付き合っていく日々を送っています
この『当事者研究』は
精神疾患を持つ当事者自身が研究者の目を持って
自分自身と社会に目を向け、暮らしやすい場を創っていくことが目標で
当事者が自ら病名を考え研究結果を発表していきます
例えば
小泉元総理大臣の幻聴に恋してしまった人が名づけた自己病名が
『統合失調症ドラマティックタイプ』
実にユニークです
そして
幻聴のことは『幻聴さん』と親しみを込めて呼んでいるそうで
意地悪な事を言う幻聴さんに対し
「丁寧な物言いで丁重にお引き取り頂きましょう」というアドバイス通りに
「幻聴さん、お願いします。今日は疲れているのでもう休ませてください。幻聴さんもお休みください」と伝えると
幻聴さんの頻度が減ったり、優しい幻聴さんになるそうです
この研究やミーティングを重ねるにつれ、当事者にも少しずつ変化が生じ
「自分の行き詰まりに手ごたえを感じる」
「この困り方は良いセンいってるね」
「自分の悩みや不安に誇りを感じる」
「諦め方が上手くなってきた」
「悩みの多さに自信が出て来た」
「病気のスジが良いね」
「最近、落ち方がうまいね」
などと自他ともにそんな感想が出てくるユニークさには魅力に感じます
『悩み事』を『テーマ』に置き換え
「悩みを抱えているのではなく『テーマ』を与えられている」
という発想の転換によって
問題は解決しなくても、自己が損なわれない感覚を覚え
思いつめることなく『行き詰まり』に自信を持つようになるのです
実際に当事者研究をした人の感想が印象的でした
『自己肯定の感覚をつかんだとき、初めて「自分の荷物は自分のものだ」と気付いた。自分が自分の面倒を見て、自分が自分を助けはじめた時、初めて自己否定からくる問題行動で人間関係を壊すというサイクルから少しずつ抜け出しはじめたように思う』
「三度の飯よりミーティング」を合言葉に、何かが生じる度にみんなで話し合う事を大事にしているそうです
所々にユーモアセンスをちりばめる手法はとても魅力的ですね
『苦しいのに笑える』
『絶望してるけど安心』
『泣きながら笑ってる』
そんな印象をうけました
辛い状況下でもユニークさを一滴落とすことで
心や思考が弛緩する効果があり
困難を受け入れるスペースがちょっとだけ出来るような気がします