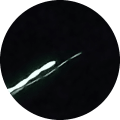「新しい実在論」を提唱して世界的に注目されているドイツの哲学者マルクス・ガブリエル(Markus Gabriel, 1980 - )さんの本の紹介です。
ガブリエルさんにとって「初の芸術論」という触れ込みの『アートの力;美的実在論』という本を読んでみました。実際に読んでみると、これは芸術の本というよりは、やはり哲学の本なので、内容が難しく、私には十分に理解できるものではありません。また、ガブリエルさんの著書としてもわかりやすいものではないでしょう。
ガブリエルさんの著書として有名な『なぜ世界は存在しないのか』や『私は脳ではない』は、ガブリエルさんが私のような素人にもわかるように、順序立てて念入りに書いたものです。それを私なりに読み解いて、blogにも書いてみました。
https://blog.goo.ne.jp/tairanahukami/e/f2a61fa9d7a2aba8c48afecce3fa03a7
https://blog.goo.ne.jp/tairanahukami/e/28606636b896541442b3705c47a7f645
それらに比べると、この『アートの力;美的実在論』はラフな書き方をしています。ですから、「初の芸術論」という謳い文句はちょっと言い過ぎだと思います。この本は、正面から芸術について語ったものではありません。そうではなくて、マルクス・ガブリエルさんという優れた哲学者が、芸術という分野についてどんなふうに考えているのか、ということを、哲学についてある程度の理解を持った人に向けて書かれた本だと言えるでしょう。
それでは、私のような芸術にしか興味がない人間には読む価値のない本なのか、というとそういうわけではありません。私は芸術に関わる人間として、少しは現代思想について知っておきたいと思っている者ですが、ガブリエルさんはそんな私の期待に応えるように、先の二冊の主著をわかりやすく書いてくれました。
そして次に私の思うことは、そんなガブリエルさんが芸術についてどんなことを考えているのか知りたいなあ、ということです。そのことについて、この『アートの力;美的実在論』は十分に応えてくれる本です。
私はガブリエルさんに美術評論家のようにがっつりとアートについて語ってほしいとは思いませんし、仮に彼がそうしたとしても、それほど信頼のおける本にはならないでしょう。何と言っても彼は哲学者ですし、本格的に学問に取り組んできた人なのです。彼が美術好きな人だということは知っていますが、それにしても、もしも美術評論家のように美術について語るのならば、それだけの時間を美術作品を見ることに費やさなければならないでしょう。もちろん、彼にそんな時間があるとは思えません。
私はマルクス・ガブリエルさんに限らず、学問の分野で優れた業績をあげた人が、そのまま美術についても一流の批評ができるとは思っていません。それは美学の分野で優れた仕事をしたイマヌエル・カント(Immanuel Kant 、1724 - 1804)さんであっても、ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831)さんであっても同様です。そもそもカントさんが多くの美術作品を見ることができたとは思えませんし、ヘーゲルさんの趣味もかなり偏ったものでしょう。それでも、彼らの思索に耳を傾けることは必要なことであり、興味深いことなのです。
そもそもカントさんの時代に発展した「美学」は、「美」について考える学問であって、実際の美術作品について批評することとは違っています。そして美学者は「芸術」という概念がどういうものなのか、つまり「芸術とは何か」についてならば語ることができますが、実際の芸術作品について批評することは、彼らの仕事ではないのです。
ガブリエルさんのこの本は、おおよそそのような理解に則ったものです。彼が具体的に語る作品はマルセル・デュシャン(Marcel Duchamp、1887 - 1968)さんやジョセフ・コスース(Joseph Kosuth, 1945 − )さんのようなコンセプチュアル・アートやアンディ・ウォーホル(Andy Warhol、1928 - 1987)さんのポップ・アートですが、いずれもそれが芸術作品なのかどうかという議論の的になるような作品であって、ガブリエルさんは彼らの作品を題材として「アートとは何か」について思慮深い理論を展開しているのです。そして彼らの作品について批評しているわけではありませんが、わずかにガブリエルさんはウォーホルさんよりも、バロック期のオランダの画家、フェルメール(Johannes Vermeer , 1632 - 1675)さんの方が「優れた作品を生み出した」と書いています。
この批評に私は完全に賛成です。
さて、それではこの『アートの力;美的実在論』には、どのようなことが書かれているのでしょうか?
ガブリエルさんの文章を具体的に見ていくことにしましょう。
ガブリエルさんは、私たちがアート作品と向き合うときに、その作品にまつわるさまざまな雑念に侵されていないだろうか、と問いかけます。そして「アートの力」について、例えば私たちは資本主義の商品価値のように何か他の価値観によって惑わされていないだろうか、と問いかけます。そして私たちに、「アートは自律した存在ではない」と考えてはいないだろうかと問いかけているのです。
次の文章を読んでみてください。
アートのこうした偏在とともに、ひとつの懸念が拡がっている。つまり、アートがアートを超える目的のために使用されたり濫用されたりしているのではないか、という懸念だ。私はそうした状況を前にして、本書で次の疑問に取り組むことにした。すなわち、アートはどうしてこれほど強力なーその影響下に置かれていない現実など想像もできないほど強力なー力をもつにいたったのか、という疑問である。
実際、私たちの身のまわりにあるオブジェの世界で、アートはもはや例外的なものであるどころか、むしろ規則そのものとなった。なかには次のように疑う者もいるほどだ。アートがこれほど力をもつのは、その背後により強力な存在がいるからではないか、アートの装いの下で何かがひそかに進行しているのではないか、と。さらにはこんな仮説もある。アートワールドを現在ひそかに支配するその力とは、搾取の構造により生まれた富の蓄積という、マルクス主義的意味における資本(主義)にほかならない、という仮説だ。搾取構造は人の目から隠されることではじめてうまく機能する。アートは物質的な富を美しく見せかけることによって、まさしく生産条件を覆い隠す役割を果たしているのではないか、というわけだ。
(『アートの力;美的実在論』マルクス・ガブリエル著 大池惣太郎訳)
このように、「アート」という言葉は独り歩きしてしまい、何の変哲もない「もの(オブジェ)」がアートワールドの中で巨大な価値を付与されているのではないか、という疑問が生じているのです。
これは金銭的な価値、つまり経済における「アートの力」の問題に限りません。現在のアート市場の問題だけでなく、例えばルネサンスの「宮廷で文芸を庇護するパトロン」の時代から、アートは「権力の顕揚や、公的領域における象徴秩序の構造化に寄与していた」という解釈もある、とガブリエルさんは書いています。
また、ガブリエルさんは、ドイツの美術史家・文化研究者であるヴォルフガング・ウルリッヒ(Wolfgang Ullrich、1967 - )さんの考えを取り上げて、次のように書いています。
ドイツの芸術理論家ヴォルフガング・ウルリッヒによれば、近代のアートはつねに権力と政治に従属していた。それゆえ、アートが純粋な「芸術のための芸術」として受容されることは決してなかったという。ウルリッヒの考えでは、アートそのものよりも、アートを生み出し展示する文脈の方が強力なのであり、したがって、アート自体はどんな自律的本質ももたないことになる。
(『アートの力;美的実在論』マルクス・ガブリエル著 大池惣太郎訳)
これはいささかショッキングな内容です。そして私の実感からは、大きく外れているのです。これを読むと、純粋な芸術は決して受容されないし、アートは「自律的本質」を持たない存在だということになってしまいます。
これに対してガブリエルさんは、「彼は間違っていると思う」と明言しています。そしてそのあとで、次のようなことを書いています。
私はこの問題について、アートこそが権力を支配している、といういくぶん意表をつく考えを主張したい。アート作品はその本性から自律しており、アートワールドと呼ばれるものに支配されることなど決してありえない。アートの自律性によって、アート作品はアートワールドから引き離されているので、アートワールドにはアートの本質についてどんな決定権もない。
(『アートの力;美的実在論』マルクス・ガブリエル著 大池惣太郎訳)
このガブリエルさんの主張は、私たちからすると至極真っ当な考え方です。
例えば私が作品を作るときに「アートワールド」のことなど考えません。アートの関係者にどのように思われるだろうか、などということとは関係なく、日々制作しています。
しかし、現代の芸術哲学においては、このような考え方は「意表をつく」ものとなっているようです。それはどうしてなのでしょうか?
この状況を知るためには、私たちはさらに芸術哲学の現状についてよく知らなくてはなりません。ガブリエルさんの説明をさらに聞きましょう。
アートと権力の関係をめぐる私たちの考えには、根本的に誤った暗黙の前提がある。それを捨て去ることが必要なのだ。
その前提とは、アートの価値が観察者の目に宿るという考えである。この考えを解体するにあたって、まずは名前をつけておこう。これを「美的構築主義」という。美的構築主義とは、アート作品が、それ自体としては全く美的でも芸術的でもないような影響力から生まれる、と信じる立場のことだ。
アメリカの哲学者アーサー・C・ダントー(1923 - 2013)の論考『アートワールド』は、とても大きな反響を呼んだ。ダントーが論文で強調したのは、アート作品が本質的にアートワールドの構成要素であるということだった。アートワールドには、作品以外にも、アーティストやアート批評家、美術館、美術品バイヤー、美術史家、さらにはアーティストが作品に使う原料の生産者までが含まれる。要するに、ダントーはこう考えたのだ。アートはアートワールドの外には存在しない、芸術作品を芸術作品たらしめるのは、アートワールドである、と。
(『アートの力;美的実在論』マルクス・ガブリエル著 大池惣太郎訳)
やれやれ、という感じですね。
ダントーさんの有名な「芸術の終焉論」については、以前にblogで書いたことがあります。ダントーさんは、なかなか人騒がせな方です。基本的に、こういう人は芸術作品に感動したことがないのだと思います。一応、私のblogのリンクを貼っておきますので、ぜひこちらをお読みください。
https://blog.goo.ne.jp/tairanahukami/e/c8bace79581bcc80f5f2c0100cd2c540
そしてガブリエルさんが言っている「アートの価値が観察者の目に宿る」という「美的構築主義」の考え方ですが、これは芸術作品が人との出会いによって価値を発揮する、という意味では半分くらい当たっていると思います。しかし、そもそもアートそのものには価値がない、ということが前提になっているのであれば、これは的外れです。芸術作品の価値は、見る者によっていかようにもなる、という意味で「アートの価値は観察者の目に宿る」というのであれば、これはとんでもない誤解なのです。
確かに芸術の世界には、「これが芸術作品なの?」と聞きたくなるような作品がたくさんあります。マルセル・デュシャンさんの『泉』から始まって、コスースさんのコンセプチュアルな作品や、ポップアートなどの広告のイラストかと見紛うばかりの作品まで、芸術という概念の極限値はどんどん広がっているように見えます。そして頭でっかちの理屈っぽい現代美術愛好家は、それらの極限値の作品を概念化することに夢中になっているのです。さらにタチの悪いことに、そういう人たちは自分たちの興味を理解してもらえないと、「あなたには芸術がわかっていない」と言わんばかりの態度をとるのです。そして、その概念化の果てに「アートワールド」などという狭い世界を作って、そこに関係するものだけが「アート(芸術)」なのだ!とわかりやすい解釈を考えだして、それに同じような輩が飛びつくのです。
このような芸術の極限値について考察する思考は、哲学的な思考とつながるところがある、とガブリエルさんは分析しています。その上でガブリエルさんは、「芸術作品は自律した存在」なのだから、新たな作品との出会いは、その都度新たな出会いであるはずだ、と言っています。つまり作品との出会いは、簡単に概念化できるものではない、ということなのです。
それに芸術作品は完全に概念化できるものではなく、つねに現実の世界と繋がっているものですから、「アートワールド」などという枠の中ですべてが収まるはずはないのです。私たちは芸術作品を私たちの知覚を通して感受するのですが、それも後で見る通り、単純なことではありません。「美的構築主義」の考え方では、この人間の知覚の役割についてあまりに軽視しているようです。
これらに関するガブリエルさんの文章はどれも小気味良くてすべてを引用したいぐらいですが、例えば次の文章を読んでください。
最近の哲学では、新しい種類の実在論が提起されている。その実在論はこう主張する。つまり、概念のなかには、それ自体は概念でできていないような、現実に結びつく概念がある、と。たとえば、知覚するとき、私は概念を使う。意識的な注意に照らして、対象を選り分けるような場合だ。私は自分のコーヒーをじっくり味わい、いつもより美味しくないと判断する。そこで前提となるのは、私が「コーヒーは美味しい時もあれば、美味しくないときもある」というコーヒー概念を用いていることだ。同じように、私は自分のメガネについての概念も抱いているので、たった今、概念に関する基礎的な前提をざっと説明しようとするこの段落で、何か例として役立つ対象を探したときに、メガネをそれとして認識することができた。この新しい実在論の目的は、以下の事実を私たちに思い出させることにある。つまり、概念に依拠することで認識可能なもののすべてが、それ自体ひとつの概念であるとはかぎらない、ということだ。概念は対象をひとつにまとめる。だが概念によってひとつにまとめられたものが、それ自体ひとつの概念であるとはかぎらないのだ。
この意味で、作品もまた概念である。アート作品は、さまざまな意味の場を結びつける概念なのだ。その意味の場には、感覚器官を通じて知覚される場も、その都度含まれるにちがいない。だからといって、感覚器官を通じて知覚されるアート作品の様相を、作品それ自体と決して混同すべきではない。要するに、どんな作品であれ、単に視覚的であることもなければ、単に聴覚的であることもないということだ。私たちがアートと接するとき目にするもの、耳にするものは、アート作品ではなく、ある作品を成り立たせている意味の場や対象の一部なのである。
(『アートの力;美的実在論』マルクス・ガブリエル著 大池惣太郎訳)
いかがでしょうか?
ちょっと難しい文章ですが、コーヒーの味に関する話などはわかりやすいでしょう。私たちはコーヒーについて、あるいはメガネについて、基礎的な概念を持っていますが、実際のコーヒーやメガネが、そのひとつの概念で語り切れるものであるとは限りません。美味しいコーヒーもあれば、美味しくないコーヒーもあり、男性用のゴツい眼鏡もあれば、女性用の繊細なデザインのメガネもあります。また、目で見ればおおよそそれがカップに入ったコーヒーであることはわかりますが、それがどんなコーヒーなのかは飲んでみなければわかりません。また、コーヒー好きの人でなければ、そのコーヒーを飲んだところでそれがどんな味なのか、うまく判断できないでしょう。たった一杯のコーヒーを正確に把握することを考えてみても、このようにさまざまな感覚器官やそれまでの経験が必要となります。このようにいろんな知覚や思考が錯綜する場を、ガブリエルさんは「意味の場」という言い方をしています。
このコーヒーの例は、もちろんアート作品についても当てはまります。ただし、アート作品は芸術として「自律した存在」でもあるので、より事態は複雑です。アート作品は、自然界のもののように、物理的な規則性だけで語ることはできません。
アート作品同士は、何ひとつ共通する実態を持たない。二つの異なる作品に共通する構成は存在しない。メタ作品、構成をめぐる構成というのはありえるが、それもどこかでストップしなければならない。まさにそこで、私たちは作品の還元不可能で、絶対に特異な構成と出会うのだ。
(『アートの力;美的実在論』マルクス・ガブリエル著 大池惣太郎訳)
ガブリエルさんが、何を言いたいのかわかりますか?少し説明しておきましょう。
私たちは、自分ではあまり気づいていませんが、ごく自然に科学的な知見や方法論を身につけています。そして事物を似たもの同士で分類し、必要があればそのものを構成している物質によって還元し、整理してしまうのです。ゴミの分類などは、まさにそういうことを日常的にやっているのです。
ですから芸術作品を鑑賞していても、気づかないうちに作品同士の共通するものを見つけ、無理やり共通項で還元し、作品の特異性を無化してしまうのです。極端な例を言えば、ある種の人たちは、絵画作品は絵画であるということだけですべて同じものとして分類し、内容についてはろくに見ないのです。そういう人たちにとっては、芸術と芸術でないものの境界線にしか興味がなく、そこに新たに概念化したものを付け加えることに喜びを感じているのです。「新しいテクノロジーを駆使した◯◯アートの誕生だ!」というわけです。
しかし常識的に考えてみましょう。ひとつひとつの作品の差異を還元してしまって「これは絵画だからみんな同じだ」という作品の見方をした場合に、芸術作品を見る喜びがそのどこかにあるのでしょうか?作品をすべて概念化してしまって、自分たちの作った「アートワールド」の内側に取り込んでしまうという行為に、どのような価値があるのでしょうか?
ガブリエルさんは、そんな正当な疑問を投げかけているに過ぎないのですが、今の芸術哲学では、その普通のことを言うためには、ガブリエルさんのような卓越した知性が必要なのです。「美的構築主義」にしろ、「アートワールド」にしろ、常識的に考えて偏った考え方によるものだと思うのですが、いざその理論を突き崩すとなると大変です。
ですから、私たちはそのような雑音に取り込まれないように、自分の知性、自分の感性、自分の常識をフル稼働させて、そして自分自身を信じて前へ進みましょう。
最後になりますが、ガブリエルさんは結びの文章で次のように書いています。
私は本論で、アートのラディカルな自律性を擁護した。私の考えでは、アートの自律性はカントやシラーから受け継がれたアートの古典的概念を超えている。カントたちは、アートが道徳に似ており、人間がより良い存在になることに寄与しうると考えた。そうかもしれないし、そうでないかもしれない。いずれにせよ、アートの本性それ自体には、われわれを向上させることも、破壊することも予定されていない。アートにとって、それはどうでもいいことである。
次の注意を繰り返して、本稿を終えよう。アートを存在一般と混同してはならない。存在するものは、ほとんどの場合アート作品ではない。ボース粒子や人間存在は、宇宙がそうでないのと同じく、アート作品ではない。存在するすべてが、普遍的法則に服さない自律的創造物であるわけではない。私たちはニーチェに抗って、世界を美的現象として説明することはできないという事実をはっきりさせる必要がある。なぜなら、世界は美的現象ではないからだ。ロマン主義は間違っている。だからといって、ニヒリズムにも根拠はない。価値、美、真理は、現実それ自体に、実在的に存在する。アートそれ自体は素晴らしい。なぜなら、作品のなかには実際に素晴らしいものがあるからだ。アートが美しいとは、特定のアート作品が自分の構成で定めた基準において高い水準にある、ということだ。その基準を、外から評価することはできない。作品はそれぞれ、自ずと判断される。作品とは、作品自らの美的判断なのだ。アートはわれわれ人間存在に、自分を愛するか尋ねはしない。私たちの方がアート作品に巻き込まれるか、巻き込まれないかのどちらかだ。それがアートの力なのだ。
(『アートの力;美的実在論』マルクス・ガブリエル著 大池惣太郎訳)
最後の数行が、感動的です。
「アートそれ自体は素晴らしい。なぜなら、作品のなかには実際に素晴らしいものがあるからだ。」
このことを忘れてしまった人に、アートを語る資格はありません。すべては、この実感から始めるべきです。
「作品はそれぞれ、自ずと判断される。作品とは、作品自らの美的判断なのだ。」
予め定まった評価などというものはありません。どんな作家の作品であれ、素晴らしいものであるのかどうか、出会ってみないとわからないのです。だから芸術作品を概念で語るのではなく、実際の作品との出会いで語るべきなのです。
「アートはわれわれ人間存在に、自分を愛するか尋ねはしない。私たちの方がアート作品に巻き込まれるか、巻き込まれないかのどちらかだ。」
どんなに素晴らしい作品であっても、あなたが心を開かない限り、好ましい出会いはありません。しかし、あなたが心を開きさえすれば、アート作品はあなたを巻き込むのです。その流れに身を任せれば、あなたには素晴らしい世界が待っています。
「それがアートの力なのだ。」
この「アートの力」には、ロマン主義に惑わされず、ニヒリズムに負けない力が込められています。ガブリエルさんは、そのことを論証したくてこの本を書いたのでしょう。
ガブリエルさんの哲学について、専門家の間ではさまざまな批判もあるようですが、私はガブリエルさんのポジティブな思考にエールを送ります。これは以前にも書いたかもしれませんね・・。
そして、『アートの力;美的実在論』はちょっと難解な本ですが、よかったら皆さんも直接、ガブリエルさんの前向きな姿勢に触れてみてください。