臼杵山に登った後、12月はずっと城攻めばかり注力していたので、ちゃんとした山登りは行けていませんでした。そうこうしている間に12月もあと数日。体力的な不安もあったので、2020年の登り納めとしては比較的楽そうな山ということで、埼玉県寄居町にある鐘撞堂山に登ってきました。
スタートは東武東上線の終点・寄居駅。ここから秩父鉄道に接続するので、長瀞方面の山に登るときにはお世話になります。
鐘撞堂山に行く前に、その少し東にある八幡山に登ります。

寄居駅を出てずっと東の方へ移動し、八幡神社へ。


神社の裏に登山口があります。

しかし登り始めてすぐに、岩の急坂がお出迎え。しかも落ち葉が大量に積もっていてかなり滑ります。手も使ってよじ登らないといけません。なかなか気楽にホイホイとは登らせてくれませんね。

それでも、一登りして尾根筋に出ると、そこからは歩きやすい道になります。


八幡山は標高210m。まだまだ序の口ですね。

眺望はちょこっとだけ。

このまま尾根伝いに鐘撞堂山まで行くつもりだったのですが、その途中で大正池方面に下りるルートがあったので、予定を変更して大正池を見ていくことにしました。
計画段階では、なんとか大正池に寄れないかと思っていたのですが、どうしてもルートが遠回りになっちゃうのでやめたんですよね。でも、ここからショートカットして池の方に下りられるなら、その後の予定も問題なくこなせそうです。

実際、このルートを下りたらすぐに人里まで出られたのですが、この写真のもう少し先で道がかなり細くなって、落ちそうな崖を通らなくてはならず、ちょっと怖かったです。

崖といっても、そのすぐ下にはソーラーパネルが大量に並んでいて、仮に落ちたとしても何とかなりそうではあったんですけどね。

舗装路を進んでいくと大正池が現れました。

まあ、正直なところ、わざわざ見に来るほどのものでもなかったかもしれません。でも、「わざわざ見に来るほどのものでもなかった」ということがわかっただけでも、見に来る価値はあったのだろうと思います(あれ?)。

別角度からもう一枚。

大正池を通り過ぎると、鐘撞堂山への登山口が現れます。

この道をまっすぐ行くと高根山へ向かう道なのですが、行き止まりになっていました。

右に曲がると鐘撞堂山への道になります。

鐘撞堂山への道は割と穏やかで、ホイホイ登って行けます。
印象的だったのは、明らかにハイカーではない、地元のお年寄りみたいな人たちもたくさん登っていたことですね。それだけ登りやすい山なんだろうと思います。
私も歳を取ったら、家から歩いて1時間くらいで登れるお手軽な山の近くに住んで、日課のように山登りを楽しみたいものです。

途中、竹炭工房があります。

やがて、分岐が現れます。右に行くと鐘撞堂山、左に行くと高根山。
今回はあまりハードな山行ではないので、なるべくいろんなところを訪れるべく、高根山へ向かいます。

人通りが少ないせいか、高根山への道はそれまでよりは若干荒れ気味でしたが、それでも大きな問題はありません。傾斜もそんなにキツくはありませんしね。

7、8分ほどで高根山山頂に到着。
高根山は標高284m。道からちょっと外れたところピークがありましたが、特に山頂標識はありませんでした。

眺望はそれほどありません。
高根山をまっすぐ進むと人里に戻っちゃうので、Uターンして鐘撞堂山を目指します。

分岐まで戻り、鐘撞堂山方面へ進みます。
こちらもそんなに大変な道ではありませんね。

長い階段を登れば、山頂まであと少し。

分岐から6、7分ほどで、鐘撞堂山の山頂に到着です。


鐘撞堂山は標高330.2m。ここまで八幡山、高根山と寄り道もしてきましたが、それでも割と楽々登ることができました。

その名の通り、山頂には鐘が設置されています。

山頂には展望台があるのですが……。


展望台に上ると木が邪魔をしてしまいます。


展望台の下からの方が、良い眺望が得られました。

少し休憩したのち、鐘撞堂山から北の方へと下りていきます。

しばらく進むと、道は西へと折れ曲がります。
しかし、実はこの辺りは猪俣城の城跡があったところ。道を外れて、少し探索してみることにします。

道の先に行ってみたのですが、なんとなく曲輪っぽい気もしますが、イマイチ判然としません。

そこから西へ移動してみると、ちょっとした急坂があったので、そこで探索を断念しました。
しかし、後で調べてみたところ、どうもその坂を乗り越えた先が猪俣城だったらしいんですね。ちょっと事前調査が足りませんでした。

ルートに戻り、西へ。

さらに下っていくと、一旦また人里に出ます。

続いて、川沿いに南下していくと、円良田湖に出ます。
ここは灌漑用に作られた人造湖。ヘラブナとかワカサギとかが釣れるそうで、この日も多くの人が釣り糸を垂れていました。

このあたりはずっと舗装路でした。円良田湖の東側を通り、南へ南へと進んでいきます。

釣りが盛んなだけあって、湖のほとりには「へら鮒観世音」なんてのもありました。

へら鮒観音から北の方を眺めて。

ステキなイノシシ。
円良田湖の南側までやってきます。

ここの南側には、少林寺という、拳法でもやっていそうなお寺があります。

少林寺へは、なかなか大変な階段を登っていきます。

ここを左へ進むと、五百羅漢で有名な少林寺へ出ます。

しかし案内板には記されていないのですが、右へ進むと花園御嶽山へ出ます。

で、本当は花園御嶽山へ行った後、引き返して少林寺に行くつもりだったのですが、花園御嶽山への道のりが結構な急坂な上に落ち葉が大量で、結構危なかったんですよね。登りでさえちょっと危なかったのに、ここを下るのは厳しいだろうと思い、少林寺へは戻らずに、そのまま別ルートで下山することにしました。
今考えると、少林寺に行ってから花園御嶽山に登るのが正解だったなぁ……。

山頂に到着。山頂には御嶽神社があります。

ここは全国各地のいろんな神様を勧進しており、多くの石碑が建てられています。

中央に鎮座するのは、もちろん御嶽山の神様。

八海山もあるよ。

他にも、八幡様とか、妙見様とかも。

神社には裏から入ってきたので、表参道を下っていきます。

鳥居に出れば山道も終了。

人里に出ました。

近くに、「西行の戻り橋」というのがありました。

歌の修行の途中で寄居にやってきた西行が、この土地の子供とやりとりをするわけですが、子供の素直な答えを西行が勘違いして、勝手に深い意味を読み取り、自分の不明を恥じてこの橋から戻ってしまったのだそうです。落語の「こんにゃく問答」みたいな話ですね。

秩父鉄道の波久礼駅に着いたところで、この日の山行は終了です。

寄居駅から波久礼駅まで、行動時間は2時間56分、移動距離は10.8㎞、累積上りは565m、累積下りは550m、消費カロリーは1411kcalでした。
鐘撞堂山の周辺は、全体的に歩きやすい道が多かったですね。標高も低く、傾斜もそれほどキツくないので、のんびりマイペースで歩くのに適した山でした。眺望も良いですしね。
でも、この日は欲張っていろんな観光ポイントを回ろうとしたのですが、その結果、舗装路が多めの山登り的には微妙なルートになってしまいました。とはいえ、鐘撞堂山を中心にしてしまうと、どのみち選択肢はそんなにないんですよね。無理やり山道を歩こうとすると、鐘撞堂山に登って下りてを繰り返すとかしないといけなくなっちゃいますしね。
これにて2020年の山登りも終了。しかし、12月はあんまり山に登っていなかったので、1月からはもっと積極的に登りに行こうかなー、なんて思っていたのですが、1月頭に緊急事態宣言が発令してしまい、結局今に至るまできちんとした山には登れないでいます。せいぜいが街中にあるめちゃくちゃ低い山くらいですね。
でもまあ、緊急事態宣言も解除されたことだし、4月からはまた、あちこち出歩きたいですね。去年の夏ほどではないにしても、体力もまたちょっと落ちているでしょうし、また地道に易しめの山から頑張っていこうかと思います。
スタートは東武東上線の終点・寄居駅。ここから秩父鉄道に接続するので、長瀞方面の山に登るときにはお世話になります。
鐘撞堂山に行く前に、その少し東にある八幡山に登ります。

寄居駅を出てずっと東の方へ移動し、八幡神社へ。


神社の裏に登山口があります。

しかし登り始めてすぐに、岩の急坂がお出迎え。しかも落ち葉が大量に積もっていてかなり滑ります。手も使ってよじ登らないといけません。なかなか気楽にホイホイとは登らせてくれませんね。

それでも、一登りして尾根筋に出ると、そこからは歩きやすい道になります。


八幡山は標高210m。まだまだ序の口ですね。

眺望はちょこっとだけ。

このまま尾根伝いに鐘撞堂山まで行くつもりだったのですが、その途中で大正池方面に下りるルートがあったので、予定を変更して大正池を見ていくことにしました。
計画段階では、なんとか大正池に寄れないかと思っていたのですが、どうしてもルートが遠回りになっちゃうのでやめたんですよね。でも、ここからショートカットして池の方に下りられるなら、その後の予定も問題なくこなせそうです。

実際、このルートを下りたらすぐに人里まで出られたのですが、この写真のもう少し先で道がかなり細くなって、落ちそうな崖を通らなくてはならず、ちょっと怖かったです。

崖といっても、そのすぐ下にはソーラーパネルが大量に並んでいて、仮に落ちたとしても何とかなりそうではあったんですけどね。

舗装路を進んでいくと大正池が現れました。

まあ、正直なところ、わざわざ見に来るほどのものでもなかったかもしれません。でも、「わざわざ見に来るほどのものでもなかった」ということがわかっただけでも、見に来る価値はあったのだろうと思います(あれ?)。

別角度からもう一枚。

大正池を通り過ぎると、鐘撞堂山への登山口が現れます。

この道をまっすぐ行くと高根山へ向かう道なのですが、行き止まりになっていました。

右に曲がると鐘撞堂山への道になります。

鐘撞堂山への道は割と穏やかで、ホイホイ登って行けます。
印象的だったのは、明らかにハイカーではない、地元のお年寄りみたいな人たちもたくさん登っていたことですね。それだけ登りやすい山なんだろうと思います。
私も歳を取ったら、家から歩いて1時間くらいで登れるお手軽な山の近くに住んで、日課のように山登りを楽しみたいものです。

途中、竹炭工房があります。

やがて、分岐が現れます。右に行くと鐘撞堂山、左に行くと高根山。
今回はあまりハードな山行ではないので、なるべくいろんなところを訪れるべく、高根山へ向かいます。

人通りが少ないせいか、高根山への道はそれまでよりは若干荒れ気味でしたが、それでも大きな問題はありません。傾斜もそんなにキツくはありませんしね。

7、8分ほどで高根山山頂に到着。
高根山は標高284m。道からちょっと外れたところピークがありましたが、特に山頂標識はありませんでした。

眺望はそれほどありません。
高根山をまっすぐ進むと人里に戻っちゃうので、Uターンして鐘撞堂山を目指します。

分岐まで戻り、鐘撞堂山方面へ進みます。
こちらもそんなに大変な道ではありませんね。

長い階段を登れば、山頂まであと少し。

分岐から6、7分ほどで、鐘撞堂山の山頂に到着です。


鐘撞堂山は標高330.2m。ここまで八幡山、高根山と寄り道もしてきましたが、それでも割と楽々登ることができました。

その名の通り、山頂には鐘が設置されています。

山頂には展望台があるのですが……。


展望台に上ると木が邪魔をしてしまいます。


展望台の下からの方が、良い眺望が得られました。

少し休憩したのち、鐘撞堂山から北の方へと下りていきます。

しばらく進むと、道は西へと折れ曲がります。
しかし、実はこの辺りは猪俣城の城跡があったところ。道を外れて、少し探索してみることにします。

道の先に行ってみたのですが、なんとなく曲輪っぽい気もしますが、イマイチ判然としません。

そこから西へ移動してみると、ちょっとした急坂があったので、そこで探索を断念しました。
しかし、後で調べてみたところ、どうもその坂を乗り越えた先が猪俣城だったらしいんですね。ちょっと事前調査が足りませんでした。

ルートに戻り、西へ。

さらに下っていくと、一旦また人里に出ます。

続いて、川沿いに南下していくと、円良田湖に出ます。
ここは灌漑用に作られた人造湖。ヘラブナとかワカサギとかが釣れるそうで、この日も多くの人が釣り糸を垂れていました。

このあたりはずっと舗装路でした。円良田湖の東側を通り、南へ南へと進んでいきます。

釣りが盛んなだけあって、湖のほとりには「へら鮒観世音」なんてのもありました。

へら鮒観音から北の方を眺めて。

ステキなイノシシ。
円良田湖の南側までやってきます。

ここの南側には、少林寺という、拳法でもやっていそうなお寺があります。

少林寺へは、なかなか大変な階段を登っていきます。

ここを左へ進むと、五百羅漢で有名な少林寺へ出ます。

しかし案内板には記されていないのですが、右へ進むと花園御嶽山へ出ます。

で、本当は花園御嶽山へ行った後、引き返して少林寺に行くつもりだったのですが、花園御嶽山への道のりが結構な急坂な上に落ち葉が大量で、結構危なかったんですよね。登りでさえちょっと危なかったのに、ここを下るのは厳しいだろうと思い、少林寺へは戻らずに、そのまま別ルートで下山することにしました。
今考えると、少林寺に行ってから花園御嶽山に登るのが正解だったなぁ……。

山頂に到着。山頂には御嶽神社があります。

ここは全国各地のいろんな神様を勧進しており、多くの石碑が建てられています。

中央に鎮座するのは、もちろん御嶽山の神様。

八海山もあるよ。

他にも、八幡様とか、妙見様とかも。

神社には裏から入ってきたので、表参道を下っていきます。

鳥居に出れば山道も終了。

人里に出ました。

近くに、「西行の戻り橋」というのがありました。

歌の修行の途中で寄居にやってきた西行が、この土地の子供とやりとりをするわけですが、子供の素直な答えを西行が勘違いして、勝手に深い意味を読み取り、自分の不明を恥じてこの橋から戻ってしまったのだそうです。落語の「こんにゃく問答」みたいな話ですね。

秩父鉄道の波久礼駅に着いたところで、この日の山行は終了です。

寄居駅から波久礼駅まで、行動時間は2時間56分、移動距離は10.8㎞、累積上りは565m、累積下りは550m、消費カロリーは1411kcalでした。
鐘撞堂山の周辺は、全体的に歩きやすい道が多かったですね。標高も低く、傾斜もそれほどキツくないので、のんびりマイペースで歩くのに適した山でした。眺望も良いですしね。
でも、この日は欲張っていろんな観光ポイントを回ろうとしたのですが、その結果、舗装路が多めの山登り的には微妙なルートになってしまいました。とはいえ、鐘撞堂山を中心にしてしまうと、どのみち選択肢はそんなにないんですよね。無理やり山道を歩こうとすると、鐘撞堂山に登って下りてを繰り返すとかしないといけなくなっちゃいますしね。
これにて2020年の山登りも終了。しかし、12月はあんまり山に登っていなかったので、1月からはもっと積極的に登りに行こうかなー、なんて思っていたのですが、1月頭に緊急事態宣言が発令してしまい、結局今に至るまできちんとした山には登れないでいます。せいぜいが街中にあるめちゃくちゃ低い山くらいですね。
でもまあ、緊急事態宣言も解除されたことだし、4月からはまた、あちこち出歩きたいですね。去年の夏ほどではないにしても、体力もまたちょっと落ちているでしょうし、また地道に易しめの山から頑張っていこうかと思います。










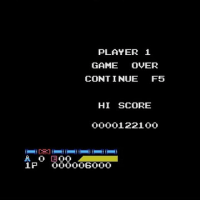

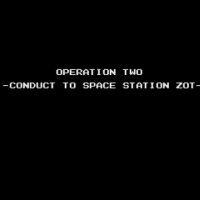












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます