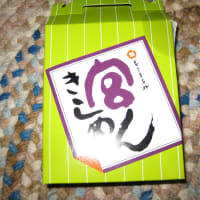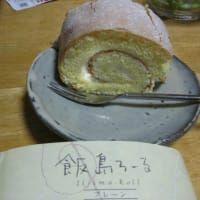公益法人等に贈与税等が課税される場合
(1)概要
持分の定めのない法人に対して財産の贈与又は遺贈(以後贈与等)があった場合において、
その贈与等より、その贈与等をした者の親族等の贈与税等の負担が不当に減少する結果となる
場合には、贈与等を受けた当該法人に贈与税等が課税される。
(2)平成20年12月1日以降の改正点
①改正前は、対象が公益法人等であったが、人格のない社団等及び持分の定めのない法人に
改められた。
②改正前は受贈法人において受贈額が法人税の益金の額に算入される場合には贈与税等は課税
されなかったが、この除外規定がなくなった。
③「贈与税等の負担が負担に減少する結果となる場合」が政令によって明確化された。
(3)贈与税の計算方法(簡易表示です)
贈与者ごとに
①(贈与財産の額-110万円)の額に対する贈与税額
②(贈与財産-翌期控除事業税相当額)を課税対象とした法人税の額、事業税の額、地方税の法人税割
③ 贈与財産のうち益金算入された金額/贈与財産×②
④ ①-③
(4)根拠条文番号
相続税法66条、相続税法施行令33条
(5)根拠条文(他のものは長すぎるので省略)
(人格のない社団又は財団等に対する課税)
第六十六条
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた
場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。こ
の場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当
該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合
計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
4 前三項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、
当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第六十四条第一
項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認
められるときについて準用する。この場合において、第一項中「代表者又は管理者の定めのあ
る人格のない社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と、「当該社団又は財団」
とあるのは「当該法人」と、第二項及び第三項中「社団又は財団」とあるのは「持分の定めの
ない法人」と読み替えるものとする。
(1)概要
持分の定めのない法人に対して財産の贈与又は遺贈(以後贈与等)があった場合において、
その贈与等より、その贈与等をした者の親族等の贈与税等の負担が不当に減少する結果となる
場合には、贈与等を受けた当該法人に贈与税等が課税される。
(2)平成20年12月1日以降の改正点
①改正前は、対象が公益法人等であったが、人格のない社団等及び持分の定めのない法人に
改められた。
②改正前は受贈法人において受贈額が法人税の益金の額に算入される場合には贈与税等は課税
されなかったが、この除外規定がなくなった。
③「贈与税等の負担が負担に減少する結果となる場合」が政令によって明確化された。
(3)贈与税の計算方法(簡易表示です)
贈与者ごとに
①(贈与財産の額-110万円)の額に対する贈与税額
②(贈与財産-翌期控除事業税相当額)を課税対象とした法人税の額、事業税の額、地方税の法人税割
③ 贈与財産のうち益金算入された金額/贈与財産×②
④ ①-③
(4)根拠条文番号
相続税法66条、相続税法施行令33条
(5)根拠条文(他のものは長すぎるので省略)
(人格のない社団又は財団等に対する課税)
第六十六条
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた
場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。こ
の場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当
該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合
計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
4 前三項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、
当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第六十四条第一
項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認
められるときについて準用する。この場合において、第一項中「代表者又は管理者の定めのあ
る人格のない社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と、「当該社団又は財団」
とあるのは「当該法人」と、第二項及び第三項中「社団又は財団」とあるのは「持分の定めの
ない法人」と読み替えるものとする。